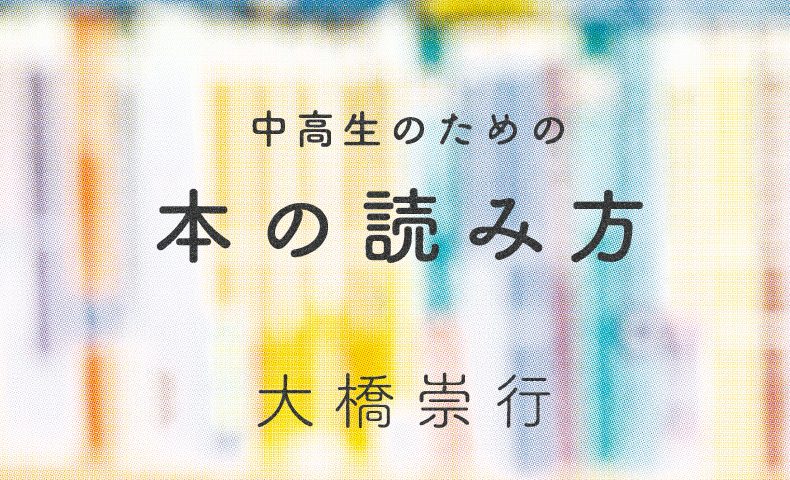甘いものが食べたい!
ちょっと疲れたときや、ストレスがたまっているときには、無性に甘いものが食べたくなります。そんなとき、みなさんは何を食べるでしょうか?
現代の私たちはどうしても、まずは洋菓子を思い浮かべてしまいます。ケーキにチョコレート、クッキー、フィナンシェ。生クリームやバター、砂糖をふんだんに使ったお菓子はとても魅力的です。
一方で、ほんのりと甘い和菓子も捨てがたい。
特に最近は、味だけでなく見た目や形でも、さまざまに工夫を凝らした新しい和菓子が作られています。
もともと和菓子という名前は、単に洋菓子に対して、そのように呼ぶようになったものです。もちろん伝統的なお菓子もその中に多く含まれていますが、けっして型にはまった、堅苦しいものではありません。
今月は、そんな和菓子がつい食べたくなってしまうような本をご紹介していきたいと思います。
和菓子から見る日本史
甘いものへの欲望は、歴史の教科書に出てくるような人たちでも、私たちと変わりませんでした。もちろん、日本の歴史上の人物が食べていたのは、ほとんどの場合が日本の伝統的なお菓子である和菓子になります。
虎屋文庫『和菓子を愛した人たち』(山川出版社、2017年)には、政治家や作家、文化人など、歴史に名前を残した人たちがどんな和菓子を食べていたか、それをどれだけ好んでいたか、物語や文章にどういうお菓子を登場させたのかというエピソードが、当時のお菓子の再現画像とともに実に100編も収められています。
たとえば、高校3年生の古典で扱う『源氏物語』の「若菜上」の巻には、「椿もちひ(椿餅)」というお菓子が出てきます。
これは、室町時代初期に成立した『源氏物語』の注釈書である『河海抄』によると、椿の葉でお餅を挟んだお菓子だそうです。当時は砂糖がとても高価なものだったため、甘葛(ツタの樹液を煮詰めたもの)で甘さを加えていました。
さらに他の資料から、平安貴族が「蹴鞠(けまり)」をして遊ぶときによく出されていたことがわかるとのことです。こうした書物による調査にもとづいて、「椿もちひ」が再現されています。
少し時代を下って、織田信長がポルトガル人の宣教師ルイス・フロイスに日本でのキリスト教の布教を許したとき、信長に献上されたのは、ガラス瓶に入ったコンフェイト(Confeito)でした。これは「金平糖」という名前で、和菓子として定着していますね。
けれども、日本の金平糖よりも砂糖を結晶化させる期間が短いので、形はひとつひとつ違うものになるそうです。
このように、和菓子とはけっして日本で独自に作られたものだけを言うわけではありません。
ヨーロッパや中国から受け入れたものでも、長く日本で作られ、あるいは新しいものに作り替えられていたら和菓子として受け入れてしまう。そういう懐の深さも、和菓子の魅力のひとつだと言えるでしょう。甘いものを求める欲望に、国境は関係ありません。
この本に収められたエッセイは、羊羹(ようかん)などで有名な和菓子の老舗「虎屋(とらや)」が、お菓子の資料室として昭和48年に立ち上げた「虎屋文庫」の学芸員の方たちがさまざまな調査を行って、インターネット上の「虎屋」のホームページで連載していたものです。
ここに掲載された再現画像と同じように、2016年から、国文学研究資料館と国立情報学研究所という2つの研究機関が、書物に書かれた江戸時代のレシピを再現する試みを行っており、現在、料理レシピ投稿・検索サービスの「クックパッド」でそのレシピが公開されています。(https://cookpad.com/recipe/list/14604664)このようにレシピや食の記録も、書物として残されることで、現代において再現することが可能になります。
日本史を勉強するときには、どうしても人名や事件の名前などを覚えることが多くなってしまいます。けれども、ただ名称を覚えるだけでなく、それぞれの歴史上の人物が持っているエピソードに触れてみたり、歴史に残されたより具体的なモノに触れてみたりすることで、歴史をより身近に感じることができます。そのとき歴史は、ただの暗記ではなく、私たちの実感をともなったものとして記憶に残っていくでしょう。
その意味で、コラムなども交えながら”和菓子から見た日本史”を描いたと言える『和菓子を愛した人たち』は、そうした歴史のあり方に触れることができるとともに、紹介されているお菓子までつい食べたくなる、そんな魅力的な一冊になっていると思います。
和菓子を魅力的に描く
作家が物語を書くときに腕の見せどころのひとつとなるのは、作中に出てくる食べ物をどれだけ美味しそうにみせられるか、それを食べたいと読者に思わせることができるかどうかです。
和菓子を題材としてとりあげた小説やマンガは必ずしも多くありませんが、そうした表現にはやはり、さまざまな工夫が見て取られます。
その中で、中高生の皆さんでも読みやすい作品が、坂木司『和菓子のアン』(光文社文庫、文庫版は2012年。シリーズに『アンと青春』、光文社、2016年)です。
高校を卒業したものの、大学に行きたいと思うほど勉強が好きではなく、専門学校にいくほどやりたいことがあるわけでもなく、社員として就職するのもいまいちピンとこなかった梅本杏子(うめもときょうこ)。
彼女はこのままだとニートになってしまうという危機感から、デパートの地下食品売り場にある「和菓子舗・みつ屋」の販売店でアルバイトとして働くことになります。
ふだんは穏やかなのに趣味としている株の投資のことになると過激な人格に変わってしまう店長の椿はるか。イケメンで菓子職人を目指しているけれど乙女男子でつかみどころがない立花早太郎。元ヤンキーの女子大学生・桜井さん。
個性豊かな店員たちに囲まれた杏子が、「杏」の字が「アン」とも読めることから、アンちゃんと呼ばれて可愛がられながら和菓子の奥深い世界に入っていくことになるという、短編連作の日常ミステリ小説になっています。
たとえば第3話に当たる「萩と牡丹」は、アンが売り場にいるところに、坊主頭の一歩手前まで髪の毛を刈り込んでサングラスをかけ、龍と虎を描いた長袖Tシャツを着た、怖い風貌の男性が訊ねてくるという物語。
アンはこの男性から「菓子が泣くぞ」「売り物になんかならない」「腹切りだ」と次々に物騒な言葉を浴びせられます。
はたしてこの男性はいったい何者なのか……。この部分が、ストーリーの核になっています。
少しネタバレになりますが、「萩と牡丹」で謎の男性が使った用語は、すべて和菓子の世界のもの。この他にも、和菓子には俳句の季語のように季節ごとに出すきまったお菓子があったり、名前が駄洒落になっていたりと、多くの遊びが込められています。
特にこの「萩と牡丹」の話では、和菓子そのものが持っている物語が、読みどころのひとつになっています。
たとえば、秋のススキをイメージしたお菓子が「嵯峨野」と呼ばれることについて、アンは立花から、これは『源氏物語』で六条御息所が嫉妬のあまり葵の上を取り殺してしまったあと、葵の上を亡くした後悔のために、光源氏が嵯峨野にこもってしまう場面に由来があると教えます。
「愛すればこその嫉妬。女としての業(ごう)、生きる身の哀しさっていうの? そういうのがさ、風にざわめくススキと重なるわけ。なんかこう、ざあっていう音まで聞こえてきそうじゃない?」
そんな立花の言葉に、アンは、ススキというひとつのきっかけから次々と広がっていくイメージがひとつの和菓子に込められていくことを学び、高校のときには興味を持つことができなかった古典も、読んでみたいと思えるようになっていきます。
このように和菓子についての知識をアンが少しずつ身につけていき、周りの店員たちやお客さんたちからいろいろなことを教えられていくことで、高校卒業までは「食べること」くらいにしか興味がなかった彼女が、少しずつ「和菓子舗・みつ屋」で働きがいを見つけ出していく。そうしたアンの成長物語としての側面を、この小説は持っています。
それと同時に、和菓子がもっているさまざまな意味合いをアンを通して読んでいくことで、思わず読者が和菓子屋さんに足を運んで、ショーケースに並んでいる和菓子を眺めてみたくなる。そんな仕掛けが、この小説には数多く施されています。
和菓子のさまざまな側面
マンガ作品では、浅野りん『であいもん』(単行本既刊4冊、角川コミックス・エース、2017年~。『ヤングエース』(KADOKAWA)で連載中)が、繊細なタッチで和菓子を丁寧に描いています。
父親が入院したという連絡を受け、音楽の夢を捨てて10年ぶりに和菓子屋「御菓子司・緑松(りょくしょう)」を営む京都の実家に帰ってきた納野和(いりの・なごむ)。けれども実家には、一果(いちか)という10歳の見知らぬ女の子がどういうわけか住み込みで働いており、店の主人である父は彼女が店の「跡継ぎ」だと和に告げるというストーリーです。
この作品では、両親に捨てられて身寄りのない一果の面倒を見ることになった和が、父親代わりとして一果との関係を気付いていく様子を、コメディを交えながら描いています。
まだ雑誌連載中なので完結していない作品なのですが、この作品では今のところ、基本的に1話につき1つずつの和菓子をとりあげ、それを軸にしてストーリーを展開しています。
たとえば2巻に収められている「第6話 夏宵囃子」は、東京で和と別れたあと、京都にやってきた元恋人・佳乃子(かのこ)が和と再会し、一果の本当の父親が行方不明だと聞かされるという物語です。
ここで取り上げられているのは、鮎の形をかたどった和菓子「若鮎」。
このお菓子は、餡子を包む関東と、求肥(ぎゅうひ。白玉粉や餅粉に砂糖や水飴を加えて練りあげたもの)を包む関西とで違うだけでなく、京都では鴨川の鮎、たとえば岐阜では長良川の鮎というように、どの川を泳いでいる鮎に見立てるかが違っています。
それを、佳乃子は和菓子がこのように「色んな見方で解釈」されるものとして捉え、和を自分の父親だと「解釈」するように促すことで、なかなか周囲にいる人たちに心を開かない一果と和との関係とを築く手助けをすることになります。
このほかにも、和三盆で作った落雁(らくがん)の食感に注目した「第4話 四葩に響く」(1巻)、工芸菓子のもつ「カンペキ」な美しさをモチーフにした「第14話 秋色に舞う」(3巻)、菅原道真の和歌「東風吹かば匂ひおこせよ梅の花主なしとて春な忘れそ」をもとに梅のつぼみを表現した和菓子「未開紅(みかいこう)」をとりあげた「第19話 春待ち偲ぶ」(4巻)など、和菓子が持っているさまざまな側面をとりこんでいます。
和菓子は、ひとつのモノがただ目の前にあるモノとしてあるだけではなく、そこにはさまざまな歴史や、文化、イメージが折り重なっていることを私たちに示してくれます。このようにモノが持っている多くの意味を読み解いていくことも、本や物語を読むときに、とても重要な発想のひとつなのです。