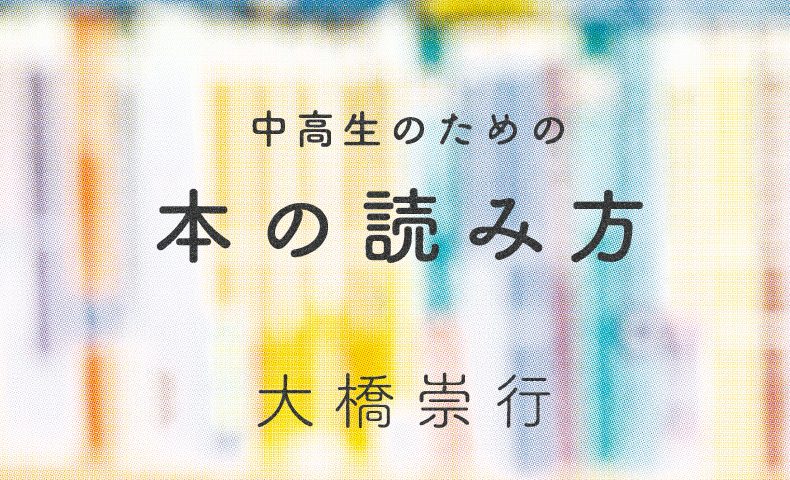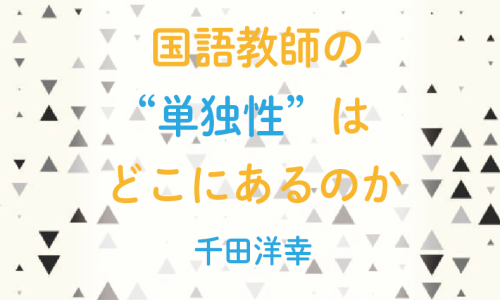美術館に行こう
中高生のみなさんは、美術館に行ったことがあるでしょうか?
もしかしたら、絵や彫刻、写真を観ることが好きで、よく自分で行っているという人もいるかもしれません。
一方で、授業や遠足・修学旅行で行った、家族に連れて行かれたというような人も多いのではないかと思います。特にそういう人の中には、作品が難しかった、退屈だったという感想を持った人も多いかもしれません。
また、美術館に行ったことがないという人の中には、もしかするととても敷居の高い場所のように感じている人もいるのではないでしょうか?
私自身、今では美術館めぐりが趣味の一つで、海外も含めてかなりの場所を回っています。ジャンルも古典から現代まで、洋の東西も問わず、いろいろなものを観ています。
けれども高校生くらいまでは、ほとんど美術館という場所に行ったことがありませんでした。よく行くようになったのは大学生になってからで、それまでは美術の教科書や世界史・日本史の資料集でときどき「名作」の写真をみかけるだけ。自分とは縁遠い世界だと思っていたのです。
とてももったいないことをしたなあ、と思っています。というのは、中高生のときに観るのと大人になってから観るのとでは、たとえ同じ作品を観たとしても、それに対して持つ印象が大きく違ってくるからです。
10代のときに何かを観て感じることは、一生のうちの数年間、その年代にいるあいだにしか得ることができないものだと思います。それを手に入れないまま、いきなり20代に入ってしまっていたわけです。
もちろん、美術の世界には専門的な芸術作品の見方があり、さまざまに研究され、議論が行われています。そうした知識の上に立って観ることも大切です。
一方で、ふらりと美術館に行ってみる、その中から自分の好きな絵や自分とフィーリングの合う作品を、自分の感覚だけで探してみる。そうして美術を気軽に楽しむというのも、一つの見方だろうと思います。そういった見方をするとき、芸術と呼ばれる作品は、私たちにとってぐっと身近なものになっていきます。
そこで今回は、「美術に親しむきっかけになる本」をご紹介していきたいと思います。
まずは入門編
最初におすすめしたいのが、池上英洋(監修)まつおたかこ(イラスト)『マンガでわかる 「西洋絵画」の見かた』(誠文堂新光社、2016年) です。
この本は15世紀にイタリアで始まったルネサンス以降の「西洋絵画」について、「名画」とされている作品に描かれているさまざまな要素にどのような意味があるのか、美術の教科書に出てくるような有名画家がどのような人物なのか、また、それぞれの時期にどういう絵が流行し、どういう絵画の技法が用いられ、それがどのように作品に活かされているのかが、イラストつきで説明されています。
たとえば、日本で人気のある絵画に、19世紀のフランスで起こった「印象派」と呼ばれる画家たちによる作品があります。
一口に「印象派」といっても、実際には時期や画家それぞれによってさまざまな個性があるのですが、ひとことで言えば、現実に目の前にあるものをありのままに描こうとする、何をどう描くべきかについていろいろな制約があり、非常にパターン化されていたそれまでの絵画に対して、画家それぞれが目の前の風景や人物から持ったイメージを、より自由に表現しようとした運動と言えるでしょう。
たとえばこの本では、こうした「印象派」の初期の代表作の一つとして、パリのオルセー美術館が所蔵しているエドゥアール・マネ『草上の食卓』(1863年)が紹介されています。

『草上の食卓』(画像の引用は『マンガでわかる 「西洋絵画」の見かた』より)
まずパッと見て、この絵はおかしいと思いませんか?
ピクニックに行ったらしい二人の男性と、一人の女性。男性は流行の服に身を包んでいますが、女性がなぜか裸です。左下に脱ぎ散らかした服や、食べ散らかした食事が落ちているので、おそらく脱いでしまったのでしょう。
でも、外でわざわざ、服を脱ぎ捨てるでしょうか?
しかも、その女性の肌だけが、異様に白く光っているように見えます。
また、後ろにいる女性に注目してみると、かなり大きく描かれています。この絵が描かれた以前の遠近法から考えるともっと小さくなるはずなのですが、なぜこれほど大きく描かれなくてはならなかったのでしょうか。
こうした疑問について、この本ではとてもわかりやすく解説を加えてくれています。
本の中でも説明されていますが、この『草上の食卓』は発表された当時、大スキャンダルへと発展しました。けれども、それまでの常識をさまざまに覆した描き方が若い画家たちに衝撃を与え、次の世代の新しい絵画を生みだしていくことになります。
著者の池上さんはこの本で、絵画の楽しみ方としてまず「観る」こと、そして「読み解く」こと、そして調べて「掘り下げ」ることを挙げています。
『草上の食卓』について書かれているのは「読み解く」ことですが、いろいろな角度から一枚の絵を見ることができるというのが、この本を通して実感できる作りになっています。また、著者の池上さんが中高生向けに書かれた『西洋美術史入門』(ちくまプリマー新書(筑摩書房)、2012年)と合わせて読んでみるというのもおすすめです。
身近な美術館を探してみよう
けれども、なかなか美術館に行くのも大変です。
スペインのマドリードにあるプラド美術館(6月13日~、兵庫県立美術館で、5月まで上野の国立西洋美術館で開催されていた「プラド美術館展」が開催されます)、パリのルーブル美術館やオルセー美術館、イタリアのフィレンツェにあるウフィツィ美術館に行きたいと思っても、なかなか行くことができません。
東京近郊に住んでいる方であれば、上野の国立西洋美術館や東京都美術館、上野の森美術館、六本木の国立新美術館やサントリー美術館などをはじめ、数多くの大きな美術館があります。
ちなみに、2018年の後半から2019年前半にかけては、近年稀に見る、日本での美術館展示の大規模展示ラッシュとなっています。
今年の5月末から国立新美術館で開催される「ルーブル美術館展 肖像芸術―人は人をどう表現してきたか」、9月から横浜美術館で開催される「モネ展」。10月からの上野はとても大変で、上野の森美術館で始まる「フェルメール展」、東京都美術館でムンク美術館所蔵の『叫び』が観られる「ムンク展」、国立西洋美術館の「ルーベンス展 バロックの誕生」がほぼ同時期に開催となります。
そして2019年4月からは国立新美術館で「ウィーン・モダン クリムト、シーレ世紀末への道」。これは、「世紀末ウィーン」と呼ばれる19世紀末にオーストリアのウィーンを中心に展開した世紀末芸術をまとめて展示するものです。この展示は、絶対に外せません。
このように大規模な展示が次々に日本にやってくる機会は、しばらくないと思います。
けれども、首都圏以外の地域に住んでいる方は、まずはどうやって美術館にアクセスするかが悩ましいところです。(もちろん、現代芸術の所蔵でよく知られている金沢21世紀美術館や、日本の近代美術を数多く持っている「石橋コレクション」で有名な福岡県久留米市にある久留米市美術館をはじめ、全国各地に大きな美術館はあります)
そんなときは、伊藤まさこ『美術館へいこう ときどきおやつ』(新潮社、2018年)を開いてみましょう。
この本は、雑誌『芸術新潮』に連載されていたエッセイをまとめたもので、著者の伊藤まさこさんが旅の途中でふらりと入ったという全国24か所の美術館が写真とあわせて紹介されています。また美術館以外にも、文学館やその地域で買うことができるお土産、カフェなどにも触れられているので、ガイドブックとしても使うことができます。
個人的に、この中で行ってみたい! と思ったのが、静岡県駿東郡長泉町にあるベルナール・ビュフェ美術館と、京都府乙訓郡大山崎町のアサヒビール大山崎山荘美術館。
この本で紹介されている場所以外にも、日本国内にはおよそ1100か所の美術館があるので、ぜひみなさんの家の近くにないか探してみてください。
画家を題材にしたフィクション
よく知られた芸術家やその作品には、さまざまなエピソードや伝説が残されています。そのため、それらはしばしば、フィクションの題材としても使われています。
たとえば穂積『さよならソルシエ』(フラワーコミックスα(小学館)、2012~2013年)は、フィンセント・ファン・ゴッホと、画商として知られるその弟テオドルス・ファン・ゴッホをモデルにしています。
美術アカデミーに認められたものだけが芸術であり、そうして認められた作品が上流階級にだけ受容される時代に、人々が生きる日常を描いた作品をどのように広めるかで苦闘するテオドルス。大きく史実から離れた作品なので好みは分かれるかもしれませんが、フィクションだと割り切って読めば、おもしろく読むことができます。
美術を題材にした小説といえば、まず思い浮かぶのがベストセラーになった原田マハ『楽園のカンヴァス』(新潮文庫、文庫版は2014年)です。1910年に描かれたアンリ・ルソー『夢』にそっくりな絵が本物か、偽物か。先にそれを鑑定した者にその作品が譲られるということで、ニューヨーク近代美術館でキュレーター(博物館や美術館で資料の収集に関する研究や鑑定を行う人)をしているティム・ブラウンと、日本人研究者の早川織絵が争うことになるというストーリーです。
少し冒頭のところが難しくて入りにくいかもしれませんが、文章に慣れてくると一気に読み進められます。また、ルソーの作品を中心にさまざまな名画が登場するので、小説を読んでいるとまるで本当にその絵を見ているような気分になることができます。
一方で、原田さんの作品で、画家のほうに焦点を当てているのが、『ジヴェルニーの食卓』(集英社文庫、文庫版は2015年)です。
この小説は、マティス、ドガ、セザンヌ、モネといった画家に焦点を当て、その周りにいた人たちの視点から、それぞれの画家たちが絵を描くときに抱えていたさまざまな人生を描き出した四つの短編連作です。
もちろんこれらの物語はすべてフィクションなのですが、非常に入念な調査に基づいており、もしかしたら本当にこういうことがあったのではないかと思わせられるほど、それぞれの画家たちの姿がリアリティを伴っています。
たとえば一番目の作品「うつくしい墓」は、晩年のアンリ・マティスの家で花瓶にマグノリアの花を生けたことをきっかけに家政婦となり、マティスの死に衝撃を受けて修道女となった女性・マリアがインタビューに答えて、マティスとの過去を回想するという物語です。
この世の生きとし生けるもの。あふれるものたちに恋をして。
悲しみは描かない。苦しみも、恐れも。重苦しい人間関係も、きなくさい戦争も、ただれた社会も。そんなものは、何ひとつだって。
ただ、生きる喜びだけを描き続けたい。
病魔に冒されても、先生には、確たる決心があった。
マティスといえば、代表作『生きる喜び』に示されるように、自然の彩りにあふれた鮮やかな色づかいと、「喜び」にあふれた絵画で知られています。
そうしたマティスの表現を、この小説では「この世の生きとし生けるもの」に対して向けられたマティスの「恋」だったと捉えています。そうした「恋」の感情を通してマティスとマリアは通じ合いますが、それは「恋愛感情」とも違った、もっと大きな世界へと通じる感情だったのではないか。
「喜び」というキーワードは、マティスとその作品について語られるときに、必ずついてまわるキーワードです。けれどもその言葉を無味乾燥なものではなく、一つの人間が持った活き活きとした実感として描ききったところに、この作品のおもしろさがあると思います。
一つの言葉にこだわって読むというのは小説を読むときの基本的な読み方の一つですが、その言葉をただそのまま受け取るのではなく、そこで使われている言葉の広がりに目を向けることで、小説はまた違った表現の奥行きを見せてくれるようになるのです。
これらの作品を読んで興味を持った人はぜひ、その本を片手に、美術館に足を運んでみましょう。