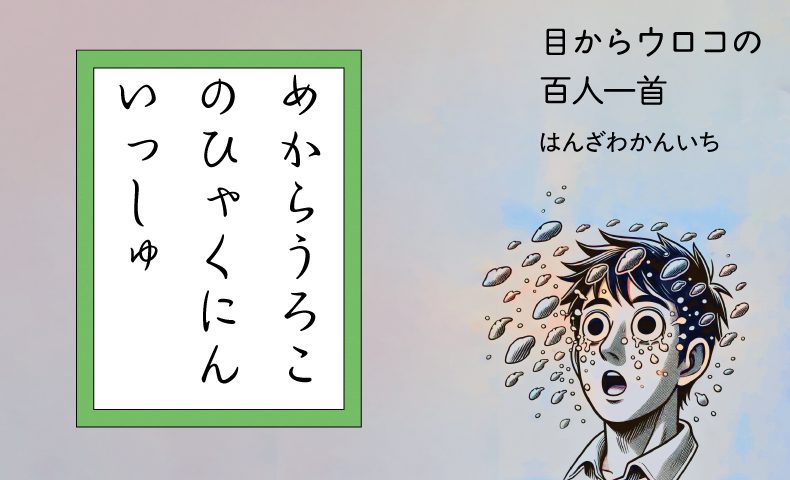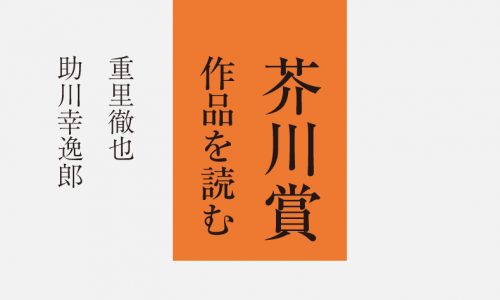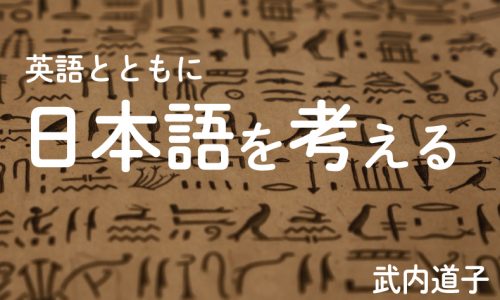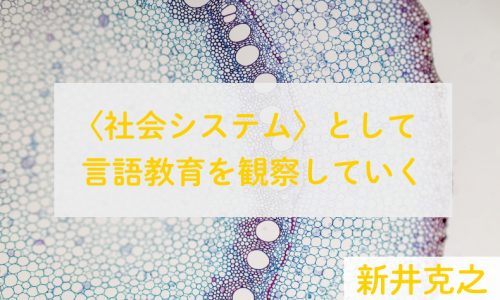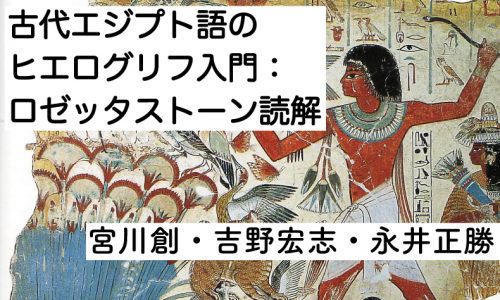あしひきの山鳥の尾のながながし夜をひとりかも寝む
この歌は、拾遺集(巻13・恋三・778番)に柿本人麻呂作として載っているのですが、元歌は作者不明の「思へども思ひもかねつあしひきの山鳥の尾の長きこの夜を(或本:あしひきの山鳥の尾のしだりを尾の長々し夜を一人かも寝む)」(万葉集・巻11・2802番)であり、しかも或本歌のほうが採られているのです。
万葉集における2つの本文を比べると、或本では、初句・第二句の「思へども思ひもかねつ」の代りに、結句に「一人かも寝む」が入り、「この夜」が「夜」に、そして、「長き」が「長々し」に置き換えられています。これらによって、1首として、何がどう変わったのでしょうか。
〔ウロコ1〕「あしひきの山鳥のをのしだり尾の」
この上三句全体が「ながながし」という語を導く序詞つまり前置きになりますから、この前置きの表現には、「あしひきの」という枕詞があり、加えて「尾」と「しだり尾」という反復もありますから、不必要なくらいに表現を長くしているように感じられます。
〔ウロコ2〕「ながながし」
この歌の表現上の要は、「ながながし」です。この言葉は、「ながし」とどのように違うでしょうか。
時間そのものの差ではありません。異なるのは、気持ちを含むか否かです。「ながし」が中立的な言葉であるのに対して、「ながながし」は現代語の「ながったらしい」に似て、いやになるくらいというマイナスの気持ちを含んでいるのです。
この歌の序詞が長いのは、まさにそのような「いやになるくらい」感を醸し出そうとしたためと考えられます。
「ながながし」に関して、もう1つ指摘しておきたいのは、意味の転換です。序詞とのつながりでは、山鳥の尾という空間的な長さですが、続く「夜」とのつながりでは、時間的な長さになります。つまり、「ながながし」の意味が、空間から時間に切り替わっているのです。
ここで、ちょっとひっかかる点があります。そのような意味の転換があったとしても、夜だけでなく、山鳥の尾にも「いやになるくらい」感があることにならないでしょうか。山鳥の尾は、普通の鳥の尾に比べれば、ピンと長く伸びていて、美しいのに。
じつは、尾そのものが問題なのではなく、「山鳥」(キジの一種)は、夫婦別々の場所で寝る鳥と言い伝えられていたのです。序詞にわざわざ「山鳥」を持ち込んだのは、そのイメージを呼び起こすためです。つまり、自分も山鳥と同じ立場になってしまったよー、ということです。
〔ウロコ3〕「かも」
「かも」を1語と見れば、万葉集において歌末に置かれて詠嘆を表わす終助詞になります(古今集以降は「かな」がそれにとって代わります)。しかし、この歌では歌末にも句末にも位置しませんから、本来の、疑問の係助詞「か」に「も」を強意的に添えた形ということになるでしょう。
その疑問は、独り寝をすることに対してです。いつも1人で寝ているのなら、そんな疑問を抱くはずもありません。いつもはそうではない、つまり共寝をしているからこその疑問なのであり、何らかの事情による独り寝という現実を受け止めることができないでいるということです。
そういう夜はやけに長く感じられるものですよね。まさに「いやになるくらいに」。
万葉集の元歌の或本のほうが拾遺集にも百人一首にも採られたのはひとえに、内容としてだけでなく、表現自体としても、独り寝の夜の「ながながし」感がしっかり出ていることにあると言えるでしょう。