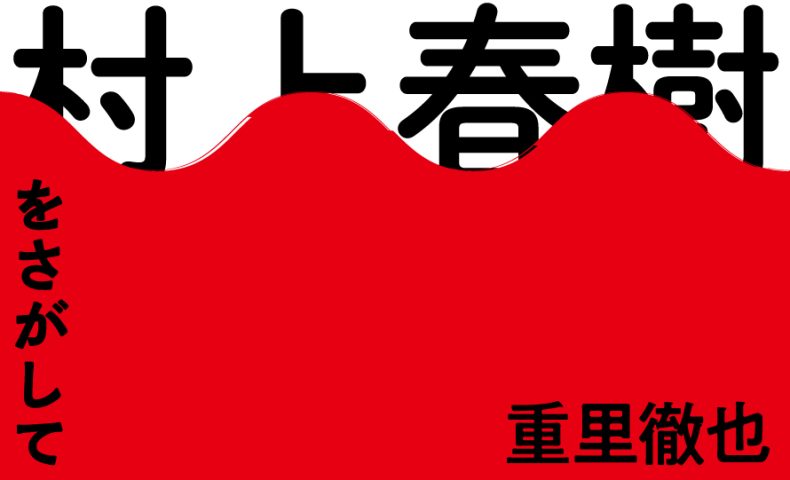「授業には出ない、勉強はしない、力任せに暴れ回って、随分大学に迷惑をかけた。そういう卒業生に名誉博士号を授与するのは、随分太っ腹な大学だな、ととても感心しています」
村上春樹に早稲田大学が名誉博士学位を贈呈した。十二月十七日に同大学の大隈記念講堂で開かれた贈呈式と祝賀イベントに行ってきた。会場は約千人のファンや学生で超満員。ジーンズにスニーカーというカジュアルな格好の上に式服を着て登壇した村上は学位を受けた後、短いスピーチ。笑いを誘いながら、どこか堅苦しかった会場をなごやかで親密な雰囲気に一変させた。
この時、村上はこうも語った。「もし、早稲田大学に来ていなかったら、小説なんて書いていなかったんじゃないかな」。早稲田は今でも、そんな磁場として機能しているのだろうか。今年は村上関連で何度か、この大学を訪れた年だった。
村上が若い頃に、大学の先輩でもある五木寛之と対談していることを最近、知った。教えてくれたのはX(旧ツイッター)のアカウント名「村上春樹的羊男」のポスト(ツイート)だった。
この人のポストはとにかくすごい。ええっ、なんでそんな昔のものを持っているの、という雑誌から、村上関連の記事や写真を紹介してくれる。作家デビュー前のインタビューから、村上がやっていたジャズ喫茶「ピーター・キャット」のスタッフ紹介(陽子夫人も含む)まで、村上の読者にはありがたくてこのうえない。
英語の文献はすぐに訳してくれるし、その日に関連した村上作品の抜粋も楽しい。作品の引用はそれを読んだ記憶を思い起こさせてくれるし、えっ、こんな発言をしていたのか、と驚くこともある。
ちょうど折よく、五木寛之の対談集が今秋、刊行されたので、この五木・村上対談を容易に読むことができた。私が求めたのは『五木寛之傑作対談集 Ⅰ』(平凡社)。「言の世界と葉の世界」と題された対談は、「小説現代」一九八三年二月号に掲載されたものだ。村上は前年に三作目の長編『羊をめぐる冒険』を発表。新しい日本文学の旗手として村上龍と並び、文学界で注目されていた時期だ。
ジャズと映画という共通の話題があるうえに、同窓ということもあって、村上はけっこう素顔で本音を語っているように読める。いくつか列挙してみよう。
「(ジャズ喫茶経営について)店というのはね、閉店しちゃうのが楽しみなんですよね」。五木から「残酷な楽しみだな(笑)」と返されたのに対して、音楽もその周辺もどんどん変わっていく。変わったものを見せられるよりも、なくしちゃったほうが本当の親切と語っている。クールな割り切り方とも、深い無常観とも読めるだろうか。
「六〇年代後期のアジ演説みたいなもの、あれが言葉としては正しくても、何も解放しなかった」。言葉というのは解放するというよりは、かえって閉塞させるんじゃないか、と続ける。しかし、それを積み重ねていくと、その魔術が破れ、究極的には物語を語るということになるんじゃないかな、という。村上の物語論の原点を読む思いがした。
「自分自身が非常に日本的なものに向かっているんじゃないか、という気持ちがものすごくあるんですよね」。その「日本的なもの」が何かは、よくわからないという。日本的浪漫への回帰とか、そういうものではない。ただ、何か日本の固有のものをめざしているんじゃないか、そのためにも、自分が手を触れることができるものに対しては、できるだけ親切でありたいという。
自分の身体が接するものを大切にすれば、自ずと日本的なるものがにじみ出てくるということだろうか。自分の身体が触れるものの重視。観念的なものを嫌い、大言壮語を排して、等身大の世界を大切にすること。初期村上の特質だろう。
この対談では一貫して、五木が鋭い指摘をしている。村上を「この人はわりと東洋っぽいところがあるな」と語り、村上の小説にはコスモポリタンの雰囲気があったとしても、ものすごく日本的な作家だという感じがしたというのだ。これには大いに共感する。
村上の作品に流れる、すべてのものは永遠ではなく、流れていくという態度。敏感に反映される四季の移ろい。絶対的な善悪をすり抜ける多神教的な響き合い。自然と人間は対立するものではなく、調和させるものという姿勢。村上はまさしく日本の伝統的な精神風土に根差した作家といえるのではないか。
五木寛之と村上春樹は意外に相性がいいように感じた。浄土真宗に詳しい五木は、都市風俗に隠された、村上の仏教的な側面に大いに反応しているのだろう。
村上春樹は初期にはさまざまな人と対談をしている。村上龍との対談『ウォーク・ドント・ラン』(講談社)もその一つ。古本はかなりの高額になっている。文庫本で出してもらうわけには、いかないものだろうか。