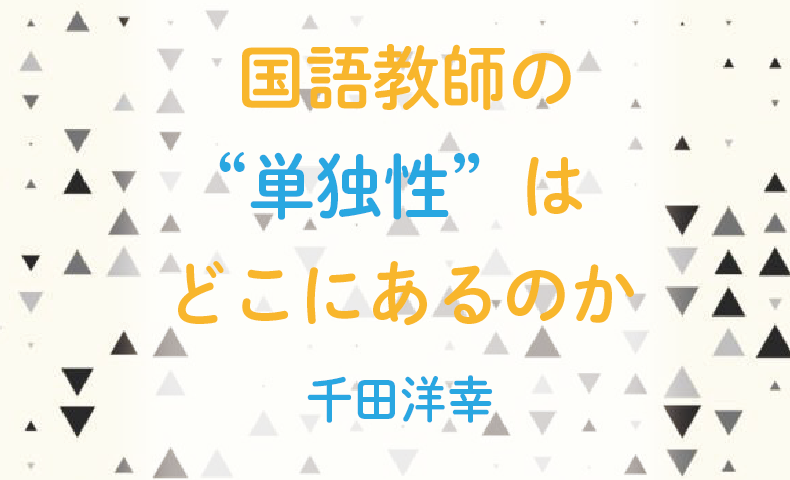十数年ほど前であろうか、出身大学のOB達と飲んでいたとき、メンバーの1人(A氏としておこう)が勤務している重症心身障害児支援施設での出来事が話題となった。A氏は施設での事例検討会の際、同僚の職員達の前で、「障害児を支援することは『賭け』です」と語ったのだという。施設の職員が障害をもつ子どもを懸命に支援し育てていることはいうまでもないが、いわゆる健常者の子どもの場合とおなじように、自分がかけた労力に見あうだけのリターン=報いが――あるいはその実感が――もたらされるかどうかについてはなんの保証もない。だから、「賭け」なのであると。A氏の言によると、その施設では「子ども達は純真で無垢な存在」という観念を強固に保持している職員が多く、彼らからは大いに顰蹙をかってしまったとのことだ。
だが、A氏のこの断言は正しいと私は思う。障害者への支援もふくめ、あらゆる教育は、「賭け」であることからけっして逃れられないはずだからだ。
柄谷行人は、ウィトゲンシュタイン『哲学探究』から「教える―学ぶ」というコミュニケーション関係を抽出し、さらに、「教える」立場はけっして優位にあるのではなく、「「学ぶ」側の合意を必要とし、その恣意に従属せざるをえない弱い立場」であるとのべた(注1)。教える側が優位にあるとはかぎらない、という事態は教師であれば誰でも思い当たるだろう。商品が、売れることによってはじめて「価値」と見なされるのと同じく、教師の指導行為も語りかける言葉も、それが学習者によって「意味」と見なされなければ、教育としての有用なメッセージたりえない。
もちろん、対話がコミュニケーションとディスコミュニケーションから成り立っている以上、「意味」が達成されうるか否かは、対話(話す―聞く)一般に通じる問題でもあり、かならずしも「教える―学ぶ」関係に限定されることではない。だが、「教える―学ぶ」関係を考える際に前提としなければならないのは、教える側が学ぶ側よりも圧倒的に多くの量の知的情報を抱えている、という自明の事実である。つまり教師とは、学ぶ側を凌駕する知見と知性をつねに備えながら、むしろそのことによって、学習者の恣意に振り回される「弱い立場」にとどまらざるをえない逆説をかかえた存在というべきなのだ。そのことが、教師という主体に根源的な揺れをもたらす。教師が所有する知は、学校空間においてフーコー的な意味での権力を形づくるが、一方では、学習者の「理解」「習得」という不確実なリターンを手にするための賭け金の役割を負わざるをえない。
私は、教育という仕事が「純粋贈与」(矢野智司)であるべきだという認識をまったくもちあわせていないし、学校の場に「歓待」(ジャック・デリダ)の思想があるべきだとも考えない。学習者の学力を向上させたという個人的な達成感にせよ、自分がすぐれた教師であるという主観的な優越意識にせよ、教師は堂々と自分の仕事への報いを求めるべきだ。学校がエコノミーの空間であるほかないという前提に立つならば、教育という行為は、「贈与」ではなく「交換」の関係を望むべきなのである。
だがそれが「賭け」である以上、等価交換とはなりえないのも自明のことであり、教師の期待はしばしば裏切られる(学習者をかならず自分の期待通りに成長させられると確信する教師がもしいたとすれば、その者は教育者ではなくカルト宗教者であろう)。精細な教材研究や斬新な授業開発の試みのすべてが報われることはありえず、教師はたえず賭けに敗れつづける存在なのだともいえる。しかも、質量ともに充実した教材研究や学習者研究を行った(という実感を得ている)場合、つまり多額の賭け金をベットしたときほど、それが報われなかった際の悩みや徒労感は大きいだろう。その経験が積み重なると、やがて「この学級はこの程度のレベルの教材研究で十分」という妥協と怠惰が日常化する最悪の事態を招きかねない。その弊に陥らないために、我々はどのような認識に立つべきなのだろうか。
以下は、檜垣立哉『賭博/偶然の哲学』(注2)の一節である。タイトルからも判るとおり、「賭けること」についての哲学的考察を展開した著書であるが、ここでは本稿でいう「賭けとしての教育」にも通底する内容が語られている。
……進化的自然においてこの身体をもっているということは偶然的で、それにどう関わればいいのかということはまさに賭けであり、私の自由なるものは、そのかぎりでしか現れない。
社会や自然が問題になるときに、そうした文脈はさらに複雑化して際だっていく。リベラルな世界において、個人が自立し、個人の自由な判断がとりあえず尊重されているとする(それがどんなに夢想的であるとしても、そうおもえる側面は確かにある)。しかしそのときに、私が何かをなすことが、そもそも他人にどう受けとめられるのか、最終的にはよく分からない。他人がそれをどう判断をするかなど、原理的に私にはよく分からないからだ。近代以降の社会になって、まさにリスクが問題になる世の中(いわゆる自己準拠性が前面に出る再帰的な社会)というのは、それ自身、共同体的で超越論的な規範の崩れた世界である。だから自分の自発的な行為というものが、自分にとってもつ意味と、他人にとってもつ意味が同じである絶対的な根拠は何処にもない。それはある意味で、何処までいっても賭けである。
……賭けることには、一方では未来を予測する正確さの測定精度をあげることが含まれていると同時に、他方では未来を予測することの不可能性そのものが織り込まれている。つまり一方では、リスク計算をぎりぎりまで推し進めることが賭博者にとっての義務に近いが、他方では、実際には何が起こるか分からないことそのものが肯定されている。予想には限界が入り込んでいる。そうした肯定が、賭けることにも、あるいは賭けという事態において浮き上がってくる「現在という時間性」そのものにも含意されている。
ここで檜垣が語っていることは、いわゆる再帰的近代=リスク社会における「賭け」の問題であるので、本稿の文脈と厳密に一致するものではないが、たとえば、柄谷がマルクスの言葉をかりながら対話を「命がけの飛躍」と呼んだこと、あるいはニクラス・ルーマンが「二重の偶発性」の理念によってコミュニケーション行為を語ったこととの重なりを見いだすことができるはずだ。
いうまでもなく、たった45分間、50分間の授業でさえ、未来に何が起こるのか完全には予測できない。学習者から思いもよらない発言や質問が飛んできて慌てさせられたり、軌道修正が上手くいかず授業があらぬ方向に展開してゆく、といった経験は教師であれば誰でももちあわせているだろう。どれほど精密に指導案を作成しようとも、「何が起こるか分からないことそのもの」を教師は受け入れざるをえない。と同時に、予想できない事態の発生を生かして授業を再文脈化し、学習者の活発な思考を呼び起こすよう仕向けるのが授業者の能力であり(注3)、むしろそこに授業の積極性を見いだしている教師も多いだろう(そういう教師にとって、事前の構想通りに粛々と進行する、なんの偶然性も招かない授業はむしろ退屈なものだろう)。逆にいえば、たえず不確定な未来にむかって「賭け」ざるをえない役割を担っていることが、教師を価値ある主体たらしめているともいえる。
とはいえ、「教育とは賭けです。賭けですから負けることもあります」などと発言しようものなら、同僚や保護者から「なんと無責任な!」と嵐のごとくクレームが浴びせられてしまうかもしれない。冒頭のA氏のようにこの言葉を公の場で口にするのは、なかなか勇気の要ることだろう。
ふたたび檜垣の言説を引用するが、その「無責任」についてはこうのべられている。
……計算できないこととは、まさにリスクの議論で述べておいたように、われわれが身体をもっていること、われわれが自然の存在者であること、そのかぎりにおいて、われわれが現在を生きていることと深く関わっているのではないか。
賭博とは、今に身を投げだすことである。身を投げだすという行為の表現は象徴的でもある。身を投げることとは、身体がそれである自然性のなかで、自分の意志のかたちを測深することでもあるのである。身を投げだすことが何を意味するのか、そもそもわれわれには分からない。計算しえないことに依拠して、流れていく時間のなかで、現在という決断の一点を生きるわれわれは、基本的に身を投げだすという以上のことはできない。確かにそれ自身は無責任であるかもしれない。だが、これは現在を生きることそのものに関わる無責任性ではないか。統御しえない身体をもち、予測しえない未来を生きるということの本質に関わる無責任性ではないか。こうして、私たちの輪郭をつくるものである無責任性が、賭博において際だたせられているのではないか。
……私にとって、私の周りには、自分では何もできない領域、いいかえれば圧倒的に「無責任」な領域が広がっていることに気づかざるをえない。先に挙げた言語と身体というのはそのもっとも重大な要素である。自分の行ったことが何であるのか、行っていることがどういうことかは、われわれは言語の形式によってしか知ることはできない。しかし言葉も私が作るものでなければ、根本的に私がどうにかできるものでもない。言葉は明らかに共同的なものであり、身体的な自然を起源にしたものである、まずはそれに参入しなければ、言語行為そのものがなしえないのである。
我々にとっての未来が不確定である以上、すべての行為は「賭け」であるほかなく、ゆえに我々の周囲には「身を投げだす」ことしかできない「無責任」の領域がつねに広がっている。それが現在を生きるということなのであり、一見非日常的な娯楽に見える賭博行為こそがその事実を顕在化させる――檜垣が指摘しているのはそういうことだ。ここでいう「無責任」とは、いうまでもなく、授業準備に手を抜くといった「意図」の水準のことではない。人間が生きること=「賭け」において不可避な「無責任」の領域が、教育(具体的には授業)の場においても必然的に存在するということだ。
だから、教育は「賭け」でもありうる、という言い方は正しくない。冒頭でのべた通り、教育はかならず「賭け」なのだ。だが、「無責任」の三文字が学校においてもっとも忌避される言葉であることからもあきらかなように、さまざまな抑圧によってこのことはたえず隠蔽されている。一方で、教科教育学をふくむ教育研究の場では、可視的な「エビデンス」を生み出すことに汲々とする調査研究が跋扈しており、そこでは「賭け」の領域、「無責任」の領域などはじめから存在しないかのように黙殺されている。学習者がそれぞれ不可視のブラックボックスを抱えていることを認めざるをえない(あるいは、そのことに怖れを感じている)からこそ、未来の不確定性を縮減する「エビデンス」に固執したくなるのではないか? ――膨大な統計的資料にもとづいた調査研究が日々生産されているのを眺めていると、ついそのようなことを感じてしまう。
最後に、自明のことがらをまとめておこう。教師は質・量とも充実した教材研究、授業準備を行って――すなわち高い賭け金を投資して――学習者の学力向上の実感や国語教師としての矜恃の獲得という報酬を得ることをめざすべきである。我々の周りに「無責任」の領域がかならず存在している以上、教師は「賭け」にたえず敗れつづけるが、手抜きの教材研究――すなわち安い賭け金――しか張らないのであれば、それはもはや「賭け」ですらない。逆説的な言い方ではあるが、万全の準備をして臨んだ授業が結果として裏切られてしまう経験こそ、教師という仕事の価値の中心を形づくっているのだ。先行する哲学者たちは、そういう他者の他者性に出会う経験を「飛躍」「偶発性」「無責任性」の語で語った。国語科教育研究の立場から、その領域にどのような言葉や論理を付与するべきなのか。これについては今後の課題となるだろうが、すくなくとも、そういう領域が授業の場でつねに作動していることを隠蔽する必要はないのである。
*
国語科教育研究に足を踏み入れてから、この分野を支配している目的的なイデオロギーにいささか辟易することが多くなった。上で触れた「エビデンス」至上主義はその思考の最たるものだ。もちろん、目的的なイデオロギーが有効性をもつことなしに教科教育の研究は成立しないだろうから、たとえば統計的なデータを駆使する調査研究をいちいち否定したいわけではない(そんなことはそもそも不可能だ)。だが、国語科の授業に、必然性/偶然性、反復性/一回性、目的的な活動/非目的的な活動……といった二項対立的な価値をかりにもちこんでみるとすれば、私の関心は圧倒的に後者の方にある。前者ばかりが追い求められる実践と研究の現状にあって、後者の探究こそがむしろ強度をもった国語科教育研究の思想を創造しうるのではないか……と考えているのである。
(注1)柄谷行人『探究Ⅰ』(1986 講談社)。
なお、柄谷がいう「教える―学ぶ」関係とは、言語ゲームを共有しない非対称のそれを指しており、かならずしも学校空間がそこに想定されているわけではないが、本校では概念を拡張してこの用語を用いる。
(注2)檜垣立哉『賭博/偶然の哲学』(2008 河出書房新社)。
(注3)国語科授業における「予測不可能事象」の研究の代表的な成果として、学習者研究をも包含した藤森裕治『国語科授業研究の深層――予測不可能事象と授業システム――』(2009 東洋館出版社)がある。ただし、「賭け」という理念は偶然性の契機をかならず含むものなので、偶然の積極的意義を認めない藤森の主張と本稿の内容とは基本的に異なる。
※冒頭で紹介したエピソードの記憶の復元に関して、A氏より助力をいただきました。