高橋 利夫
(福岡県立修猷館高等学校教諭(理科))
1 教科「を」学ぶ/教科「で・から」学ぶ
中学校や高等学校の教員は、誰もが専門教科を持っており、それぞれに程度の差はあれ、当該分野のコミュニティの一員としての役割を意識しているはずである。まだ進む方向が定まっていない若い世代に対し、その分野の魅力を伝え、そこへ引き込み、次を担う若者を育成し、コミュニティの維持・発展に寄与する…といった役割である。教員がこれを強く意識するとき、生徒は、教科・科目「を」学ぶことになる。
しかし、高校を卒業した後、大学に進むにしても、社会に出るにしても、生徒の多くは、教科・科目の区分には収まりようのない様々な課題に取り組むようになる。このとき助けになるのは、より汎用的な(用途が特化されておらず、基本的であるが故に多様な場面で応用可能な)能力であろう。教科教育には、生徒がそれらを獲得するためのフィールドとしての役割もあるはず。この場合、生徒は、教科・科目「で」「から」学ぶことになる。
普通科高校の場合、生徒は10教科の授業のほか、総合的な探究の時間、学校行事、部活動、HR活動など、様々な活動に参加する。もし、これらの活動のそれぞれが「~を学ぶ」に終始すれば、「学校で学ぶことの多くは社会で役に立たない」といわれるような事態を招きかねない。多くの生徒は、教科・科目の枠組みから出て行くし、もちろん、社会に出れば部活動や学校行事はもうない…のである。
一方、学校での活動のそれぞれが「~で学ぶ」ためのフィールドとなり、「ここではないところでも機能する何か」を求めて互いに連携することも可能ではないだろうか。そして各教科は、この「何か」への寄与を可能とする知的・文化的な奥行きや題材の多様さ故に、学校教育に取り込まれていると考えることはできないだろうか。
2 「書くこと」の指導の意義は、書けるようになることだけではない
本書では、まず序章で、編者の「書くこと」の指導についての基本的な考えが、教科を越えて取り組むこととの関係で述べられ、続く第1部(1~5章)で国語科の先生方による、第2部(6~10章)でその他の教科の先生方による取り組みが紹介されたあと、第3部で、両編者らによって、教科を越えた指導の充実・深化に向けた「てがかり」が提示されている。
これらを通じて私が再認識したことのひとつは、「書くこと」が、先に述べた「ここではないところでも機能する何か」と、おそらく、かなり密接に繋がっているということである。編者は、序章で『多くの教師は「書くこと」の重要性を認識している』と述べており、続く1~10章でも、各執筆者が自らの実践の全体像を説明しつつ、「書くこと」の指導による「書けるようになった」にとどまらない生徒の変化に意義を見出だしているように感じられる。
「書くこと」は、そのものが多方面で役立つという意味でも大きな意義を持っている。しかし、「書くこと」を構成する、より汎用的・普遍的な「何か」、さらに、「書くこと」に堪能になることではじめて刺激される「何か」こそが、専門教科の枠を越えて、教育が取り組むべき共通の課題であるという捉え方もできそうである。ならば、数学の証明問題やプログラミング、そして持久走なども「書くこと」の指導と連携可能なのでは] …と、そのようなことを考えさせられた。数学の証明問題やプログラミングが、根拠(事実)から出発して論理のつながりを追うという意味で、「書くこと」と課題を共有しているのは明らかであろう。また、様々に「試行」を繰り返し、小さな更新を粘り強く求める過程の類似性に目を向ければ、持久走と「書くこと」の間でも教育的な連携は成立するように思われる。単なる比喩的な表現ではなく、そこで培われる注意力や創造性や思考・内省の在り方や…には、具体的な類似性が見出だされるのではないだろうか。
3 「教科を越える」を、「自身の教育活動の全体を通して」と捉えてみては
本書において、序章の「2. 教科を越えた指導を―国語だけにはしない」は「2.1 他教科の役割も大きい」から「2.2 他教科にこそ『書くこと』を」と続いており、これに呼応するように、実践報告も執筆者が国語科の場合と、他教科の場合とに分けられている。しかし、内容に注目すると、様々な取り組みをとりまとめる「核」として国語科の授業が機能している場合のほか、理科の場合、複数教科の連携の場合、担任クラスの場合、総合的な探究の時間の場合、管理職の場合などが混在している。どうも、「書くこと」の指導は、実践者が誰(どの教科)かできれいに分類・整理できるわけではなさそうである。
文章(書くこと)については、国語科の先生方による優れた実践例が多いことも、「国語科まかせ」の風潮が学校にありがちなことも事実であろう。しかし、本書のサブタイトルとなっている「事実を伝え、意見を述べる」が「書くこと」の本質であるという捉え方も、根拠となる事実を提示し、論理を追うことで結論に至るというプロセスの在り方も、根拠と主張を結びつける論拠の重要性も、国語科に特有のものではない。また、ほとんどの場合、各教員は、教科の授業だけでなく、総合的な探究の時間、HR、部活動、学校行事など複数の教育手段(「~で学ぶ」という観点から、敢えて「手段」とする)を併用しているはずである。
私たちが本書「で・から」学ぼうとするなら、「国語科での」と「その他の教科での」という区分から意識を積極的に遠ざけ、誰もがどこかしらで経験しているはずの「書くこと」を通した生徒との関わりを思い出しながら、各章に記された実践の具体的な場面を想像するのが良いのではないだろうか。「教育とは」、「自分がやりたかったことは」と、自身の教育活動を振り返り、その全体を通して「そもそも」を考え直す機会にもなりそうである。
4 自身の取り組みとの対比から課題を見出だす
そのような読み方をしていると、授業としての構成の緻密さ、注がれるエネルギーの膨大さ、組織的な取り組みとしての完成度など、本書で紹介された実践とは比較の対象になり得ない自分自身の教育活動にも、共通の願いや面白さや手応えや…が確かに存在することに気づく。またそれは一方で、優れた実践例と自身の取り組みとの差異を見出だすことでもあり、さらに考えることに繋がる。
例えば、私は、第5章の「HR日誌」の取り組みを、自身のそれと対照しながら読むことになった。私の場合は、A4版バインダーと自作の日誌フォーマット(裏面は文章を続けたり、絵を描いたり、何か貼り付けたりできるよう白紙)の組み合わせ。日直の生徒は、過去の日誌を綴じたバインダーと当日分の用紙を持ち帰り、一晩かけて皆の文章を読んでから、自分の分を書く。翌朝、私はこの1枚のみ受け取り、バインダーは次の日直へ。受け取った1枚は持ち帰り、赤ペンでびっしりコメントを書き込む。年度後半は、生徒が時間と労力を注ぎ込み、今の自分と向き合う「作品」となった文章に、部分的なコメントで応えるのが難しくなり、別紙に2000字程度の文章を書き、生徒の日誌と交互にバインダーに綴じ込むようになった。
この経験からは、高校生に「書くこと」を求めるとき、「良き読み手」を設定することの大切さを教えられた。担任しか読まないものと、クラスのほぼ全員がじっくり読むものとでは、テーマの選び方も、言葉の推敲の粘り強さも異なる。その意味で、学級日誌は、大きな可能性を感じられる題材であった。ところが、教科指導の中で課す物理の実験レポートや、教科「情報」の授業レポート等は、「評価」が絡む上に、通常、読み手は教員だけである。どうしたら生徒たちにとっての「良き読み手」となり得るのか…。
もちろん、全力で読む、丁寧にコメントする、課題提示の段階でテーマを絞り込んだり細分化したりを工夫する…などあるのだろうが、結局のところ、「あの人に読んでもらうのだから」が動機付けになるような「ひと」になることに勝るものはないようにも思える。そして、本書の実践事例に登場する先生方は、実は、その意味でもすごいのだろうなぁ…と想像することになる。
一方、事実と意見の区別、根拠と論拠と主張の関係、パラグラフ・ライティングやアウトライン・プロセッシング、正しい引用や要約などは、その意図するところを自身が常用している「教育手段」に結びつけることが十分に可能であるように思われる。
5 構えることなく、「ここ」から始める
各章の実践例からは、先生方の労力を厭わない姿勢と行動力、生徒への惜しみない愛情、垣根を越えて協働できる組織力などが想像される。同じように…などと思うと、その道のりの果てしなさに屈してしまいそうである。しかし、「これ」をやるのではなく、この背景にある教育的な願いに自分の方法・手段で近づくことを考えれば、やれることもありそうに思えてくる。
さらに、各章の最後に添えられた、両編者による解説や執筆者との対談、そして、第3部で両編者らが提示する「さらなる取り組みへのてがかり」が、優れた実践と、読者である私たちの足元とが地続きであることを示唆してくれているように感じられた。
そして、この感触は、「書くこと」を指導する側にいる教員だけのものではなく、「書くこと」や「考えること」に堪能でありたいと願い、小手先の技術(ハウツー)を求めず、「書くとは」「考えるとは」と、「そもそも」に立ち返って捉え直しを試みる多くの読者に共通するのではないだろうか。
物事の捉え方、考えの整理の仕方、いつもの授業で発する言葉…が変化しそうな気がする。そう、へんに構えることなく、「ここ」から始めていいのかもしれない。
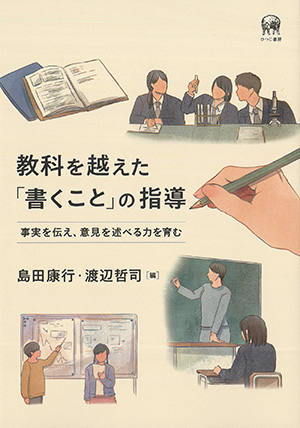
教科を越えた「書くこと」の指導
事実を伝え、意見を述べる力を育む
島田康行・渡辺哲司編
定価2400円+税
A5判 252頁
ISBN978-4-8234-1238-7
https://www.hituzi.co.jp/hituzibooks/ISBN978-4-8234-1238-7.htm











