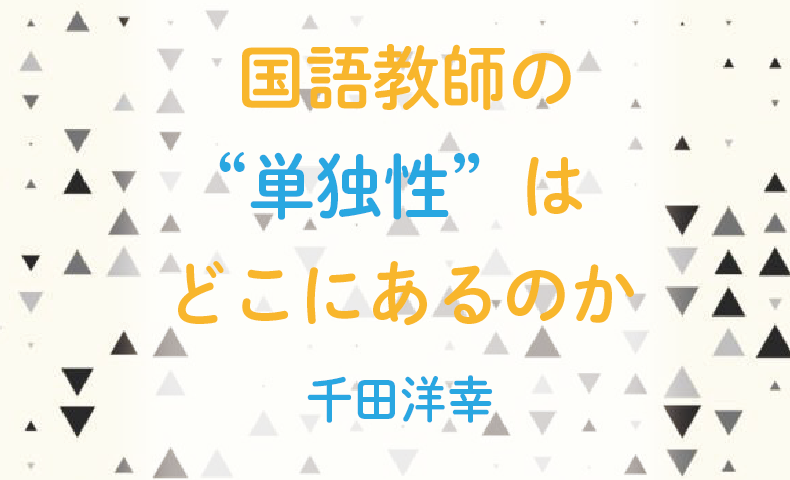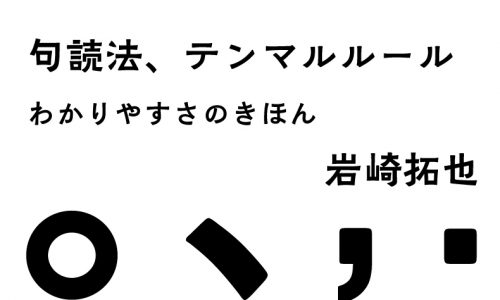先日、初年次教育の授業でリテラシーの問題を扱った際、試みにナイラ証言のエピソードを紹介した。ナイラ証言とは、イラクがクウェートに侵攻して約2か月後、「ナイラ」と名乗る少女がアメリカ合衆国議会人権委員会(1990年10月10日)で行った証言のことを指す。その内容は、イラク軍兵士がクウェートの病院で新生児を保育器からつぎつぎに取り出し、床に放り投げて殺害した、という衝撃的なものであった。「ナイラ」が涙ながらに訥々と語った言葉は多くのアメリカ国民の感情を揺さぶり、湾岸戦争への気運を高揚させる一因になったといわれている。
ところが後に、この「ナイラ」と名乗った少女はクウェート駐米大使の実の娘であり、クウェートに行った経験は一度もないこと、またイラク兵が新生児を殺害したという証言はまったくの虚偽であったことが判明した(背後で戦争を推進しようとする勢力と広告PR会社が暗躍していたとされる)。戦争プロパガンダの邪悪な成功例として、現在でも時おり触れられる著名な事件である。
受講生たちはさすがに唖然としながら聞いていたが、要するにここでいいたいことは、学習者たちが生きているいま・ここに驚きや衝撃をもたらす教材でなければ価値を持ち得ない、ということだ。国語科授業のなかで習得されたリテラシーやコミュニケーションが、教室の内部・教師の眼前でのみ通用する「お約束」の技術にとどまっていて、学校の外ではまるで能力として発揮されていない――こういう事態はしばしば起こりがちであるが、そこには教科書/教材の水準と構造をめぐる根深い問題があるように思う。
あまりナイラ証言の事例にこだわるべきではないだろうが、いまかりに、このエピソードを国語教材として扱う、という大胆な構想を立ててみるとしよう。「プロパガンダに欺されないようにしよう」などという安直な目標達成のレベルにとどまらないためには、大変な教材研究が要求される。アメリカと中東諸国とりわけイラクとの関係の歴史、中東におけるクウェートの位置、アメリカ国内における戦争推進勢力と反対勢力の力学、「ナイラ」を操った人間たちの意図とメディア戦略、広告会社の役割、証言を受けとめたオーディエンスの情動のあり方等々、「ナイラ」の証言がおかれた文脈をすべて踏まえた上で彼女の言葉の機能を読み解かなければならない。そういう作業を経ることによって、学習者は、「そもそもプロパガンダとは何か?」という根本的な問題と向きあうことになる。そこまで突き詰めることによって、ナイラ証言は、プロパガンダへのリテラシーを高める教材としてはじめて価値をもつ。逆にいえば、ナイラ証言の事例が、教師/学習者にきびしい歴史的・社会的認識をせまる強度をもつからこそ、そういう授業構想が成り立ちうる。
さて、小・中・高の国語教科書に、長年にわたり、戦争児童文学あるいは戦争文学のジャンルに属する教材が掲載されていることは周知の通りである。これらは通常、戦争文学教材あるいは平和教材と呼ばれる。もちろん教材として扱われる以上、ほぼすべての戦争文学教材は、反戦、非戦、平和を推進する社会的メッセージを内包しているのだが、ではそれらが真にアクチュアルな平和への意志を実現しえているのかというと、ことはそう簡単ではない。なぜなら、かりにも「平和」教材と称せられるためには、たんに第二次世界大戦等の歴史について文学的語りを展開するにとどまらず、戦争と平和の「現在」にふかくコミットするテクストの水準と強度が不可欠だからだ。
現状の小・中学校教科書における定番の戦争文学教材といえば、あまんきみこ「ちいちゃんのかげおくり」、今西祐行「一つの花」、米倉斉加年「大人になれなかった弟たちに……」などがあげられるが、果たしてこれらの物語がそういう強度をそなえているといえるかどうか。現在、テレビをつけてニュース番組を見れば、ガザでの虐殺の映像、ウクライナ戦争の映像が否応なしに眼に飛びこんでくる。それは大人も子どももおなじことだ。それら現実のニュース映像に比べれば、教科書掲載の戦争文学教材はじつに脆弱な戦争メロドラマにしか見えない――そういう感想をもつのがむしろ真っ当なリテラシーのあり方ではないだろうか。率直にいって、この三つの教材にかぎっていえば、「戦争とことば」という問題――すなわち歴史的・社会的文脈と一体化した言語の問題を考察するための国語教材として、無価値どころか、むしろ害悪ですらある。被害者としての立場への固執、抒情化された死の表象、戦争暴力のタブー化といった微温性に満たされたこれらの教材は、「戦争は感傷的な物語として描かれる」というメッセージと、「戦争とは感傷的な物語を生み出すための資源である」というメタメッセージを学習者に送り届けるにすぎない(注1)。当然、学習者の内面にはなんの驚きも衝撃ももたらされることはなく、また戦争についての認識の更新もなく、「戦争は悲惨だ」とか「くり返してはならない」といった教室内での「お約束」の発言が反復されるのみの授業に終始することになる。
国語教材における安易な戦争の物語化については、すでにさまざまな批判がなされている。永井聖剛は、「教室における予定調和の一つの典型例としては、いわゆる「平和教材」の読解が挙げられる」「答えは、学習する前に分かっている。教える側も、教わる側も、分かっている。ただそれを、事前に言わないだけだ。――これが、平和教材の読解の実態ではないかと思われる」(注2)と、戦争文学教材の授業がステレオタイプな道徳の反復に終わっている事態を正確に指摘している。永井はこうした立場から、米原万里「バグダッドの靴磨き」(注3)を、「既存の「平和教材」の読解にまつわる紋切型=予定調和を揺るがすだけの強度があり」、「戦争が決して過去の問題などではなく、現在進行形の問題であること、私たちの将来に関わることであること」を喚起する教材として評価し、授業実践の俎上にも乗せている(注4)。
私も永井とまったくおなじ理由で、戦争文学教材としての「バグダッドの靴磨き」を肯定的に評価している。この小説が12歳の少年の一人称語りによって構成されていることを考慮すれば、もしかすると中学生にも読解可能かもしれない。ならば、「大人になれなかった弟たちに……」など教科書から追放してこちらを掲載するべきではないか――とすら思う。すくなくとも、戦争文学教材を舐めてかかっている学習者、適当な平和主義を唱えておれば済むと考えている学習者に、安易な解答を許さない、きびしい問いを突きつける内容をそなえていることは確かだろう。
ただ、こうしたアクチュアルな教材は少数派であり、多くの教材はいまだに旧来の文学的戦争観の範疇にとどまっている。それらは、日々ガザの虐殺映像を見せつけられる学習者たちが抱いている戦争イメージとはかけ離れた代物にすぎず、「文学的な想像力を介して、過去の過ちとしての戦争の悲惨さをイメージすることと、現在も行われている戦争の悲惨さをイメージすること」(永井)の両者に届いているとはいえない。原爆や空襲や銃後の苦しみを語る物語の見せかけだけは具備しているものの、学習者の認識に強烈に働きかける、「平和」教材としてのパフォーマティブな意義はもちあわせていないのだ。
たとえば、烏賀陽弘道『世界標準の戦争と平和』(注5)という著書がある。地政学の知見を導入しつつ、国際安全保障の現状についてきわめてわかりやすくかつリアルに記述された、示唆に富む良書である。烏賀陽はここで、核兵器と軍事を話題にしながら、「カンボジアにせよ、旧ユーゴスラビアにせよ、ルワンダにせよ、戦後に発生した数十万・数百万という非戦闘員の大量虐殺は、どれも「核兵器なき国」で起きている」こと、逆に「核兵器を持つ国は、その破壊力の莫大さゆえに、直接の戦争を躊躇する、回避するようになった」と、いわゆる相互確証破壊にもとづく核抑止が機能している事態を指摘し、「核なき平和」などありえないのがグローバルな安全保障の現実なのだとのべる(注6)。さらに、「日本での安全保障をめぐる議論には「軍事は悪である」「核兵器は悪である」などという「善悪」「好悪」の判断が無原則に混入」し、「それが日本の安全保障をめぐる議論を現実から遊離させている」と批判する。
周知の通り、核抑止についてはさまざまな議論のあるところだが(注7)、烏賀陽の指摘はひとつの明晰な立場を示しているといえる(烏賀陽は1990年代前半にコロンビア大学大学院に留学した際、「国際政治の基盤にあるのは軍事と核兵器である」という認識が他国の常識であることに驚き、日本は取り残されたガラパゴスのような隔離空間であることを実感したという)。「軍事は悪」「核兵器は悪」と決めつける単純な道徳イデオロギーが、戦争文学教材における感傷的な平和主義の蔓延と不可分であることはいうまでもない。両者は、現実の戦争と、戦争を発生させる社会的状況に対してまったく思考停止している点で、同一の態度なのだ。
いまこの原稿を書きながら、今年の8月6日に開かれた広島市原爆死没者慰霊式・平和祈念式での、湯﨑英彦広島県知事のあいさつを想い起こす。ネット上などでたかく評価されたこのスピーチのなかで、知事は、「いわゆる現実主義者は、だからこそ、力には力を、と言う。核兵器には、核兵器を。しかし、そこでは、もう一つの現実は意図的に無視されています。人類が発明してかつて使われなかった兵器はない。禁止された化学兵器も引き続き使われている。核兵器も、それが存在する限り必ずいつか再び使われることになるでしょう」(注8)と語っていた。これに対して、核兵器が存在すればかならずいつか使用されるというのはいかにも情緒的な断定ではないか、核兵器と化学兵器を同列に並べることは誤りではないか、戦後の日本の平和に世界規模での核抑止力がすくなからず関与していることに目をつぶっていいのか、核兵器廃絶がなされたところで知事のいう「凄惨な歴史」は消滅しないのではないか――といった疑問を呈しておくことは無意味ではあるまい(もちろん湯﨑知事は、その程度の疑問は百も承知の上で戦略的に語っているのだろうが)。このスピーチも、聴衆を感情的に誘導するプロパガンダの一種であることはいうまでもないのである。
国語教科書には、松山善三「碑」、石垣りん「挨拶――原爆の写真によせて」、原民喜「夏の花」、林京子「空缶」など、原爆をテーマとしたさまざまな教材が収録されている。授業は当然、原爆の悲惨を強調し、核兵器廃絶の未来を希望する方向に収斂してゆくのだろうが、もし授業終了後に生徒から、「核兵器が存在しているお陰で世界平和が保たれているんじゃないですか?」「核兵器抜きの世界なんてもうありえないのに、こういう教材を学習することに何の意味があるんですか?」と端的に質問されたら、国語教師としてどのように答えるべきだろうか。この問いには、「夏の花」や「空缶」はもはや現代の戦争に届く射程をもちあわせていないのではないか、という疑義がふくまれているわけだが、これを受け入れるならば、原爆をテーマとする文学教材を扱う現在的な意義はいっさい消滅することになるだろう。いま我々が直面しているのは、学校あるいは教科書の外部に広がっている戦争の社会的・政治的現実に対して、そもそも戦争文学教材とその授業が拮抗しえているのか、という根本的な問題である。
現に遂行されている戦争と向きあえない教材、過去への回想のみに閉じてしまっている教材がもはや不要だとすれば、どのような教材であれば授業で扱う価値をもちうるのか。この問いに答えるのが難しいのは、時代の経過とともに戦争の姿が刻々と変容してゆくからである。だが、教師自身が現代の戦争・過去の戦争いずれについても可能なかぎり思考し、あらたな教材と授業方法を不断に開拓・更新しなければ、戦争文学の授業はいよいよ行き詰まりということになってしまう(注9)。そうならないためには、当たり前の教材研究を超えた努力――教師自身がみずからの戦争認識を鍛える努力――が、おそらく必要となる。
――と言うと、「戦争問題の追究は社会科の仕事であって国語科の範疇ではない」などという低水準の批判が聞こえてきそうだが、現実世界とあきらかな接点をもつ戦争文学教材を研究することは、教材の言葉が位置づいている社会・歴史・政治の文脈を研究することと同義なのだ。そもそも、社会科は言葉の教育と無縁などと考えること自体まったくの誤謬なのであり、国語科と社会科のあいだに明瞭な線引きができると思い込んでいる時点で、国語教師としての力量は疑わしいといわなければならないだろう。
本稿は残念ながら、戦争文学教材の未来について明瞭な結論を提示するには至らない。ただ、戦争の問題にかぎらず、国語教科書が広くこの社会・歴史・文化にかかわる情報に満たされている以上、国語科の枠にとどまらないさまざまな知見を吸収し、教材研究に導入することは、国語教師の当然の責務となる。「戦争文学教材を扱う主体」である前に、「戦争について知ろうとする主体」であることが要求されるのだ。このような責務は国語教師に多大な負担をもたらすことになるだろうが、同時に、膨大な知的情報に手を伸ばすことができるのはひとつの特権だともいえる。このことは、国語教師にとって、役に立たない知見や情報など何ひとつない、という事実をも意味するのである。
(注1)もちろん、小学校教科書に収録された戦争児童文学教材に学習可能性が皆無なわけではない。今西祐行「ヒロシマのうた」は原爆による大量死の表象によって、またいぬいとみこ「川とノリオ」は主人公ノリオの身体感覚の焦点化によって、かろうじて既成教材のセンチメンタリズムを乗り越えている。
(注2)永井聖剛「テクストとしての平和教材――「バグダッドの靴磨き」における言語活動――」(『早稲田大学国語教育研究』36号 2016.3)。既成の戦争文学教材・戦争児童文学教材の規範を問い直す試みは現在までも続けられており、最近の研究としては黒川麻実「国語科教育における「戦争」と「平和」――戦争児童文学教材史を踏まえて――」(『国語教育思想研究』32号 2023.12)、秋草俊一郎「戦争教材としてのティム・オブライエン「待ち伏せ」――あるいは翻訳小説の効用――」(『早稲田大学国際文学館ジャーナル』2号 2024.3)、構大樹「感傷から一歩はみ出る“平和教材”の読みをめぐって――田宮虎彦「沖縄の手記から」の拒絶と絡みつく視線――」『鳴門教育大学研究紀要』第39巻 2024.3)などが発表されている。
(注3)現在は『高等学校 文学国語』『高等学校 標準文学国語』(いずれも第一学習社、2023年)に掲載。
(注4)永井聖剛「実践報告 テクストとしての平和教材――「バグダッドの靴磨き」における課題解決型学習――」(『愛知淑徳大学論集』創造表現学部篇 8号 2018.3)。
(注5)烏賀陽弘道『世界標準の戦争と平和――初心者のための国際安全保障入門』(初版2019 扶桑社、増補新版2021 悠人書院)。本稿での引用は増補新版に拠る。
(注6)すこし長くなるが、注5前掲書より関連する部分をまとめて引用しておく。
朝日新聞はじめ日本のマスメディアが戦後長く喧伝してきたスローガンに「核廃絶」「核なき平和な世界を目指す」というのがあります。私もその朝日新聞の社員記者でしたから記憶に鮮烈なのですが、毎年8月6日、9日の原爆投下の日が近づくと、毎年新しい取材班が結成され、新たな「原爆ネタ」を探して取材します。平和記念式典は全国一面トップです。そのために支局や大阪本社はフル動員の態勢を取ります。そこでは毎年同じ「核廃絶」「核なき世界」というスローガンが繰り返されていました。
ところが、私がリアルタイムで経験した世界の現実はまったく逆でした。カンボジアにせよ、旧ユーゴスラビアにせよ、ルワンダにせよ、戦後に発生した数十万・数百万という非戦闘員の大量虐殺は、どれも「核兵器なき国」で起きているのです。日本のマスメディアが喧伝していたような「核なき世界」は平和でもなんでもなかったのです。むしろ、核兵器のない旧ユーゴスラビアやルワンダでは、自動小銃や拳銃、オノ・ナタといった通常兵器で、1人ひとり人間を殺し、核兵器に匹敵する人数が犠牲になったのです。
それとは逆に、アメリカ・フランス・イギリス・ソ連(ロシア)・中国といった核兵器保有国どうしは、第二次世界大戦後は全面戦争をしていません。それどころか、1945年8月9日を最後に、核兵器は使用されていない。つまり1人の人間も殺していないのです。(中略)
言うまでもなく、朝鮮戦争でもベトナム戦争でも核兵器は使用されていません。それどころか、朝鮮戦争で中国への原爆の使用を主張したマッカーサー国連軍司令官を、トルーマン大統領が解任したことは有名な史実です。
むしろ核兵器を持つ国は、その破壊力の莫大さゆえに、直接の戦争を躊躇する、回避するようになった。朝鮮戦争やキューバ危機をはじめとする歴史は、そうした核兵器保有国指導者の心理を伝えています。
私はこう考えています。「核兵器なき国には血なまぐさい虐殺がある。一方、核兵器のある国には平和と繁栄がある」。今、人類が手にしているのは、そんなアイロニーと矛盾に満ちた、ねじれた現実なのです。
ここで言う「核兵器保有国」には、その同盟国となることで庇護を受ける日本や韓国なども含めます。その核兵器保有国が享受しているのは「核兵器=大量破壊兵器に守られた平和」というグロテスクな平和なのです。いくら「核なき平和を」と声を嗄らして叫んでみても、人類はいまだかつて、そんなものを実現したことがない。「核ある平和」か「核なき虐殺」しか、人類は手にしたことがない。私たちはそろそろ、そうした国際社会の現実を否認し続けるのをやめねばなりません。
(注7)あえていえば、原爆文学教材を扱う教師は、核抑止論ぐらいは目を通しておいていいのではないだろうか。関連書は多数あるが、烏賀陽前掲書のほか、植木千可子『平和のための戦争論――集団的自衛権は何をもたらすのか?』(2015 ちくま新書)、秋山信将・高橋杉雄編『「核の忘却」の終わり――核兵器復権の時代』(2019 勁草書房)などは参考になると思う。
(注8)広島県公式ホームページ「広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式(令和6年)における知事あいさつについて」https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/52/06heiwakinensikitentijiaisatu.html より引用(2024年8月20日参照)。
(注9)だいぶ以前のことで恐縮だが、かつて学内研究プロジェクトの一環として、「新しい国語教材の提言と開発」というテーマのもと、戦争教材の開発と実験授業を行った(2004年)。勤務校の附属中学校2年生を対象とする3時間の授業で、教材として使用したのは朴宗根「日本の陸軍少年飛行兵を志願した朝鮮人少年」(古田足日・米田佐代子・西山利佳編『わたしたちのアジア・太平洋戦争2 いのちが紙切れになった』2004 童心社)である。その際に導入として資料を用いたが、あまり目に触れる機会もないので、この機会に公開しておく。教材開発のひとつのサンプルとしてとらえていただければ幸いである。(関心がある方は、以下のリンクからどうぞ。)
https://1drv.ms/b/s!AmrbCTY-QbPAhK4WyT34mDrV-xK2Fw?e=aPNUpc
資料として掲げたのは、(1)刺突の訓練(中国人を刺殺する初年兵の訓練)について回想されたエッセイ (2)北原白秋ほか歌人たちが戦争中に詠んだ戦意高揚の作品群 (3)日本語教育学研究者の小出詞子が回想した戦時下フィリピンでの日本語指導 (4)「大造じいさんとがん」を反抗と言いつのる椋鳩十の発言 (5)高村光太郎の戦争中/戦後の詩 (6)墨塗り教科書 の6種類である。ちなみにもっとも生徒たちの関心を引いたのは、(6)墨塗り教科書の復刻本であった。
なお、本教材である「日本の陸軍少年飛行兵を志願した朝鮮人少年」を扱った肝心の授業については、あきらかな失敗に終わった。この授業がはらんでいたと思われる問題について、拙論「学ぶことと読むことの間――「戦争を語ることば」の教材化から――」(千田『テクストと教育』2009 溪水社 に所収)のなかで検証を試みている。