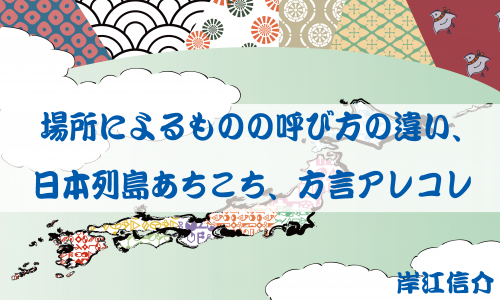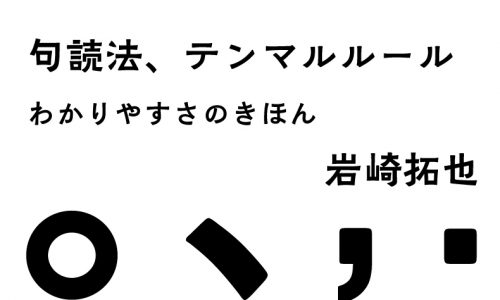田上孝一
(立正大学人文科学研究所研究員)
本書は言語学の専門研究論文集であるが、評者は言語学者ではない。そのため本書が言語学の研究書としてどのような学問的意義があるのか、本書に納められた諸論考のそれぞれについて、その研究内容の是非について学問的に論評することはできない。ではなぜ畑違いの評者に書評が依頼されたかだが、それは評者が『権利の哲学入門』(社会評論社、2017年)という論文集の編者であることと、動物倫理学の研究者として「動物の権利」についての論考を書いてきたからだと思われる。本書のテーマが「権利」であり、加えて本書に「ヒト以外の動物に「権利」はあるか」という章があることが、依頼理由ということだろう。
このような次第なので、ここでは門外漢の素人の読後感に、本書とはやや趣旨がずれるが、哲学的な概念としての権利と「動物の権利」について若干の解説をするという形の論評で許していただけると幸いである。
さて、本書の題名である「発話の権利」であるが、普通の日本語表現では余り聞いたことはなく、言語学の概念としても一般的ではないようである。普通の日本語で類似した表現としては「発言権」ということになるだろう。本書の提起する「発話の権利」と「発言権」は同じではないが、発話の権利というものを大まかに理解するための補助概念として発言権を例示するのは不当ではないだろうと思う。
発言権という場合、大抵は大仰であらたまった機会で使われるのが普通だろう。演説や質疑応答の際に十分な時間や回数がないと発話者が自らの発言権を侵害されたと主張するというようなのが、よくある場面だ。そのため、こうした発言権が日常会話で問題になることは少ない。それは普段の会話が対話者同士の権力関係を余り意識しないものだからだ。
ところが、よく考えれば我々は、日常的なごくありふれた場合でも、それとして意識することなしに、自らと対話者の位置関係、発話が行なわれる場での自らの社会的地位にふさわしい振る舞いをするように心掛けているのではないか。
こうした日常的な対人関係に潜む暗黙の権力関係というのは社会学ではおなじみのテーマで、本書の論考中でもゴッフマンの社会的相互作用論が参照されてたりもする。
本書の問題意識である「発話の権利」は、対人関係に暗黙裡に含まれる権力関係と、そうしたミクロ・ポリティクスの中でお互いに相互作用するという個々人のあり方の解明という、現代社会学では比較的一般になっている視座と共通するものがあるのではないかというのが、専門外の素人として抱いた印象である。編者によれば、伝統的な言語観は「発話の現場から独立したもの」と捉えられていたのだという。これに対して本書で対置されるのが、言語というのはむしろどこまでもコンテクスト依存的であるという見方だということらしい。だとすると、評者の素人的な見立ても、あながち的外れではないということになろう。
確かに、発話によるコミュニケーションは対人関係に潜むミクロな権力関係を前提し、その都度の発話者同士の適切な権利への配慮が重要な要素になるというのももっともである。本書の論考にはビジネスの場でのユーモア発言についての考察があるが、社長が冗談を言わない中で社員が冗談を言うのは憚られるし、その逆も然りであるというのは、日常的な感覚として理解できる。我々のコミュニケーションは確かに「発話の権利」を巡って展開しているというのは直観的に分かり易く、説得力もある。
それだからこそ、本書では権利概念それ自体の考察が欲しいところだったが、編者の方針なのか、本書には権利概念それ自体への考察はない。
ただ、仮に権利概念それ自体の意味を探求するとなると、本書にいう発話の「権利」が、言葉本来の意味での権利といえるのかどうか、俄かには判断がつかなくなる。
権利には法的な意味も哲学的な意味もあるが、権利それ自体の本質という哲学的な意味においては、権利というのは内在的価値のある存在に帰属する性質ということになる。
内在的価値というのはそれ自体の価値という意味で、内在的価値がある存在とは、その存在がその存在以外の何かに役に立つことがなくても、ただその存在であるだけで価値があるような存在である。その代表が人間で、人間は何かの役に立たなくとも、ただ存在しているだけで尊ばれるべきだと我々は常識的に考えている。これは人間には内在的価値があるからである。そしてこうした内在的価値のある存在に帰属するのが権利である。そのため、権利は「不可侵」だとされるのである。
こうなると、発話の権利というのはこういう根源的な意味の「権利」とは異なるということになる。発話の権利の場合は状況に応じて権利帰属主体が入れ替わることもあるが、本来の意味での権利は一度それが認められたら、状況に応じて有効化したり無効化されたりしないものである。
同じことは「動物の権利」についても言える。動物の権利というのは動物倫理学という学問分野で主張されていて、人間のみならずある種の動物にも内在的価値を認め、そうした動物の権利を擁護しようとする理論である。このため本書の「ヒト以外の動物に「権利」はあるか」章でもこうした意味における動物の権利とは「無関係」だとされる。
そのような非本来的な意味の「権利」ではあるが、発話ができない大型類人猿にも、人間を髣髴とさせる個体間の駆け引きがあり、個々の相互行為事例それぞれにおける権力関係への配慮が見られ、人間同士の発話の権利と類似した状況があるとされる。こうしてヒト以外の動物に言葉本来の意味での権利があるかどうかは元より問われないものの、厳密な意味ではない「権利」のようなものはありそうだという議論となっている。
本来の動物権利論を研究する立場からすると、大型類人猿が複雑な相互行為を行なっていること自体が、彼らが権利的存在である理由の一つということになるが、ここでは指摘するだけにとどめる。
また、発話の権利といっても文化的な違いが大きいのではないかという、これまた素人的な疑問もある。一般に欧米人は自己の発言権に対するこだわりが強い印象がある。だったら逆に日本人以上に自己の発言に執着せず、そもそも発話の権利自体を求めていないような文化があるのではないかという気もする。本書に収められた「バカ・ピグミー」の人々の会話分析は、素人的疑問が的外れではないことを示していて興味深い。こうした文化人類学的研究の章がもう一つ二つあるとなお良かったのではないかと思う。
ともあれ、本書は評者のような門外漢が読んでも興味をかき立てられる論点が多々あり、専門研究者ならばなおさら興味深く読めるだろうと思う。本書の「権利」概念は厳密に定義されることなく、本来の権利とは独立の意味で使われていて、それはそれで自由ではあるものの、言葉本来の意味での権利が本書で行なわれている議論とどういう関係にあるのかが知りたいという気持ちに、個人的にはなった。
最初に断ったように、門外漢の素人による雑駁な印象記に過ぎないが、何かの参考になれば幸いである。 なお、言葉本来の意味での「動物の権利」について詳しく知りたいという読者は、拙著『はじめての動物倫理学』(集英社新書、2021年)を参照して下さると幸いである。

発話の権利
定延利之編
定価2900円+税
A5判 244頁
ISBN978-4-89476-983-0
ひつじ書房
http://www.hituzi.co.jp/hituzibooks/ISBN978-4-89476-983-0.htm
田上孝一(たがみ こういち)
1967年、東京生まれ。法政大学文学部哲学科卒業。立正大学大学院文学研究科哲学専攻修士課程修了。博士(文学)(立正大学)。現在、立正大学非常勤講師・立正大学人文科学研究所研究員、社会主義理論学会事務局長を務める。著書に『初期マルクスの疎外論──疎外論超克説批判──』(時潮社、2000年)、『実践の環境倫理学──肉食・タバコ・クルマ社会へのオルタナティヴ──』(時潮社、2006年)、『フシギなくらい見えてくる!本当にわかる倫理学』(日本実業出版社、2010年)、『マルクス疎外論の諸相』(時潮社、2013年)、『マルクス疎外論の視座』(本の泉社、2015年)、『権利の哲学入門』(編著、2017、社会評論社)、『マルクス哲学入門』(社会評論社、2018年)『はじめての動物倫理学』(2021、集英社)など。