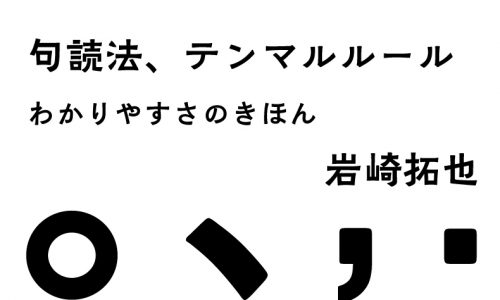評論家の類型的な物語
助川幸逸郎 今回は、遠藤周作の『白い人』にアプローチします。重里さんはつねづね、この作品を「通俗的」とおっしゃっています。
重里徹也 「通俗的」というのはきつい言葉ですね。そういってもいいのだけれど、観念的とか、類型的といってもいいでしょうか。
助川 重里さんの御持論として、根っこが評論家タイプの書き手は、純文学より通俗小説で成功しやすいというのがありますよね。
重里 評論家の能力のあるひとは、図式をつくるのが上手いのです。対比の構図をつくって、テーマの所在を明らかにしていく。それを深めていく形で小説を書くとなると、いい意味の知的なエンターテインメントに向いています。
助川 書いている当人にも何が問題なのか、明確には意識出来ていない。でも、どうしてもこのイメージが気になって仕方がない――そういう感じで書くほうが、純文学としては心に刺さるものができるのかもしれません。
重里 『白い人』はとにかく図式的で、ある種、問題の絵解きみたいになっている。信仰と悪徳とか、神と人間とか、ドイツとフランスとか。
助川 主人公はフランスに住んでいますが、父はドイツ人で母はフランス人です。厳しいカトリックの教育を受けたのに、ジャンセニズムの影響を受けて正統的なキリスト教信仰に疑いを持つ。それで、ナチスドイツがフランスに進行してくると、ゲシュタポの手先になって仲間を裏切るわけです。よくできた構図ではありますが、確かに図式的過ぎるともいえるでしょう。
遠藤周作と小川国夫
重里 それは文体の問題でもあるのです。遠藤の文章は高橋和巳などとも共通点があります。世俗的に使われている概念語によって、図式を組み立てて、問題を描こうとする。そして知的な物語に構成していく。彼らが大衆作家とか、直木賞的とか、通俗的とか、批判されるのは、この文体のせいです。
遠藤を同じカトリック作家の小川国夫と比べればよくわかります。小川の小説では、文体そのものが神を模索しているのです。言葉が「意味」をまさぐっているのです。これが本物の純文学(時代の無意識を顕在化する文学)といえるでしょう。文体が「意味」をまさぐっているのは古井由吉もそうでしょう。多和田葉子も、彼女の文体自体が「自由」を求めて揺れ動いている。開高健は文体が「物語」を拒絶して、のたうち回っている。
助川 小川の文章はダサイです。そのダサイところに、作者の身体レベルにまで通じる感覚が滲み出ています。遠藤周作や高橋和巳の小説は、そういう身体感覚と切れています。そこが小説としての物足りなさに通じているということでしょうか。
重里 身体感覚。なるほど。小川の文体はまさに身体感覚と心の動きが一体になっていますね。それは志賀直哉にも通じます。
助川 遠藤に話を戻すと、小説家になる前の段階では、遠藤は文学研究者だったのです。
重里 初期の文筆活動は、研究論文や文芸評論が中心でした。
助川 そういう「評論家としての頭の良さ」みたいなものが、『白い人』には、プラス・マイナス両方の面で現れている印象があります。
重里 ただ、研究者、評論家に徹しきれない、非常に小説家的なテーマを遠藤は抱えていたのでしょう。「キリスト教の神とは何か?」という問題を、自分の内面の問題として考えたい。そういう欲求が当初からあったと思うのです。だとすると、客観的に対象を分析しているだけでは答えは探せません。遠藤なりに、小説というジャンルで勝負する必然性はあったのだと思います。
ところが、キリスト教の神について小説で知的に問おうとするときに、日本を舞台にするとうまく状況が設定できません。逆にヨーロッパを舞台にすると、明確な図式が描ける。
助川 日本は八百万の神がいる国なので、一神教の信仰をめぐる問題が根づいていないということでしょうか。
重里 そうなのです。だから遠藤は、ヨーロッパを舞台に『白い人』を書かざるを得なかった。一方、小川国夫はオートバイに乗ってイタリアやギリシアを旅し続けた。二人の文体の違いは、二人のヨーロッパとの接し方の違いでもあるのでしょう。
高度成長期の日本人
重里 ところで、遠藤をめぐっては奇妙なことが起こります。戦後しばらくたつと、日本人の中には遠藤に近づいていった人が少なくなかったのです。状況が高度経済成長期を境に反転していった面があるのです。つまり、一神教の信仰をもとに築かれたヨーロッパ文明のほうが、八百万神を崇めたてまつる土着の伝統より、ある種の日本人にとっては思い入れがしやすくなった。この変化が、遠藤のその後の文筆家としての歩みや受容のされ方に、大きく影響している気がします。
助川 今のお話をうかがっていて頭に浮かんだのは、六〇年代のフランス思想がどのように輸入されたかという問題です。
五〇年代から六〇年代にかけて、サドやジュネなんかに触れながら、「悪」を論じる言説がフランスでは盛んでした。バタイユとかラカンとか。
重里 『白い人』からは、遠藤も身をもってその雰囲気を体験していた印象を受けます。
助川 ええ、私もそう思います。それで、こうした「悪」を論じる言説が何を問題にしていたかというと、功利主義的な「善」への批判です。あるいは、「生存」とか「快感」とかいった、形而下的なものを重んじる人々への異議申し立て。
重里 石原慎太郎の『太陽の季節』では、形而下的というか、即物的な快楽が礼賛されていました。石原の徳とするものに、バタイユとかラカンは疑いをさしむけていたわけですね?
助川 そういうことになります。では、どうしてこんな風に「悪」が語られたのか。一口にいえば、ブルジョワ的価値観を転倒させる根拠として、「悪」の意味や魅力が持ち出されていたとする見方が有力です。一九六八年を頂点とする反体制運動。「悪」にまつわる言説は、その理論的支柱になっていたのです。
一方、日本では、バタイユとかラカンによる「悪」の言説は、一九八〇年代に受容され始めました。好景気に沸き、「これからは思想とか道徳を棄てて、快楽だけを追求しよう」とみんなが考えていた時代です。
重里 そのころの日本人は、いわば「石原化」していた(笑)。
助川 そのせいで「悪」の思想が、「石原化」する根拠として広まってしまったわけです。「善」を顧みず、トコトン動物的快楽を欲する――そういう姿勢をラカンやバタイユは後押ししていると、多くの日本人は思ってしまったのですね。
重里 もともとは「石原的なもの」を批判する思想が、「石原的なもの」の守護神になった。
助川 私はそう見ています。
重里 ねじれがどこまであったかはともかく、少なくとも自分たちの頭の中では、西洋文明を消化できるような気がしてきたというのが、高度成長期以後の多数の日本人の実感なのでしょう。
助川 遠藤が留学したのは敗戦後まもない頃で、対外的な日本のイメージが良くない時期でした。捕虜の虐待問題とかが、戦後のヨーロッパでは問題にされていました。
当時の日本は経済的にも復興していなくて、アニメも漫画もまだ輸出されていません。日本に対するシンパシーを、周りにまったく持ってもらえない。そういう状態で、キリスト教の「神」というヨーロッパ文明の根幹をなす問題と遠藤は対峙した。このときどれほど孤独を感じたか、想像に難くありません。「自分の問題は、日本人にもフランス人にもわかってもらえない」という意識を抱えて、遠藤は帰国したことでしょう。
そこで、少しでもそれをわかってもらおうとして、一生懸命わかりやすい構図の小説を書いた。そうしたら、いつの間にか多くの日本の読者から迎えられるようになってしまった。
重里 ベストセラー作家・遠藤の背景ですね。
そこで思い浮かぶのが、遠藤の代表作ともいえる『沈黙』です。この作品の主人公は、日本人ではなく、ポルトガル人の宣教師です。極東の未知の国にキリスト教の布教にやってきた主人公が、いろいろな体験をする冒険譚というのが、全編の基本構造になっています。
面白いことに、私たちが『沈黙』を読むとき、みんな主人公である宣教師の視点に同化して読むのですね。江戸時代の日本人ではなく。
助川 その話、高度成長期以後に私たちの意識がどのように変わったのかを、象徴していますね。
そういえば、九〇年代の初めぐらいに、誰かがこんなことを書いていました。そのひとが、田園調布を歩いていたら、向こうからスケートボードに乗った日本人の若者がやってきて、ぶつかりそうになった。そのあとスケボーの青年は、「ジャップ!」と、そのひとを罵倒して去ったというのです。
日本人が日本人に向かって「ジャップ!」というのは、本当におかしな話です。でも、田園調布でスケボーに乗っている青年は、欧米人の仲間だとみずからを見なしていたのでしょう。そして、軽蔑すべきダサイおじさん・おばさんは、「日本の土民」であると。
そういう感覚は最近、ローカルアイドルとかご当地アニメとかが注目されるようになって、薄れてきたように思います。けれども、八〇年代から九〇年代にかけては、自分を「名誉白人」だと考える日本人が大勢いたことは確かです。
重里 今も「日本が嫌いで仕方のない人」は、たくさんいるでしょう。
助川 でも、それは一部の中高年インテリの話。若者は「ウチらには日本全体を動かす力はない。身近な人間関係の中でうまくやれていればいい」みたいな感じになっています。
この状況を私は、「江戸時代化」と呼んでいます。江戸時代の庶民って、天皇陛下や将軍様に支配されているという意識はないんです。天皇や将軍に直接会う機会って、ほとんどありませんから。庶民が実感できる「いちばんえらい人」は殿様。あるいは庄屋様。だから、「お前はどこに所属する人間だ?」といわれると、「日本人」ではなく、「どこそこ藩」か「何々村」になるわけです。現代の若者の感覚も、それに近いものがあるように思います。
新海誠監督の『天気の子』もそういう気分の中でつくられています。
自分の好きな女の子と、その弟と、自分を雇ってくれている編集プロダクションの社長と、その姪御さんと――『天気の子』の主人公は、基本的にその四人と幸せにやっていくことしか考えていないんです。仲間と幸福にやっていけるなら、東京が水没し、日本というシステムが異常を来しても関知しない。主人公のそういう「わがままな感覚」に、私は妙なリアリティーを感じました。だから、『天気の子』は個人的にも好きな作品です。
重里 乱暴に牽強付会をすると、一神教的な世界に行き詰まりを感じて、多神教的な世界を見直したいという一九九〇年代以降の日本人の心性の変化がそこにはあるように思いますね。
遠藤周作と「柄谷行人的なもの」
助川 しかし、八〇年代から九〇年代にかけては、欧米目線で日本を批判する言論が溢れていました。柄谷行人をはじめ、村上龍とか、椹木野衣とかが書いたその類いの文章を、私もけっこう真剣に読んでいました。
重里 昭和天皇が亡くなった時、皇居に向かって土下座をする人々が大勢いました。浅田彰がそれを評して、自分はこんな土人の国に住んでいるのか、といったようなことを言っていたのを記憶しています。
助川 その浅田が柄谷と組んで、九〇年代にやっていた『批評空間』という雑誌は、その種の言説のオンパレードでした。それが受け入れられたのは、「土着の部分」を切り捨てて「欧米」に同化したいという、当時の大衆の感情に合致していたからでしょう。
重里 大衆なのかな。知的エリート層といった印象を持ちますが。あるいは、「自称知的エリート」と呼べばいいか(笑)。一方で、「土着の部分」を切り捨てようとしても、べったりと結びついた要素が誰の中にもあるわけでしょう。そして、そのことをみんな薄々わかっている。
助川 それはそのとおりですね。
柄谷のお父さんは、工務店の経営者です。柄谷は甲陽学院から東大に行ったエリート中のエリート。けれども、そういう選ばれた道を歩む経済的基盤は、土着の構造と密接に結びついた事業によってつくられたわけです。
重里 柄谷の批評にそこの部分は反映されているのでしょうか。
助川 いいえ。それを書かないことが柄谷の弱さなのかもしれません。
ここで思い出したのですが、たしかある批評家が、柄谷行人の『探求』を評して「柄谷行人は遠藤周作と変わらないじゃないか」と言っていました。
重里 鋭いですね。今日の話がつながりました。
私は柄谷的なものに違和感がありました。そういう私にとって共感できる言論人といえば、吉本隆明でした。
助川 私も吉本隆明のことはずっと尊敬していました。「日本人にはみんな土着の部分があるのだから、そこから目を背けた思想は意味がない」という姿勢を、吉本は一貫して取っています。それはまさしくそのとおりだと思ったし、柄谷が吉本を激しく攻撃するのを、「前世代のエースを乗り越えるには、こうするしかないのだろう」と思って眺めていました。
重里 柄谷が二〇〇〇年代初めに社会運動をした時に、私は「こんなことをやっている連中より保守系の地方議員の方がマシだ」と思ったのを覚えています。
助川 柄谷は、先に申しあげたとおり、自分の土着の部分を直接は書いていません。ただ、同じ「工務店の息子」の中上健次とずっとつるんでいたのは、そういう形で彼なりに「土着」を引きうけていたようにも思えます。
重里 吉本が日本の近代で特別に重要視していた三人を知っていますか?
西郷隆盛、乃木希典、田中角栄です。いずれもアジア的な土壌に根づいていたということでしょう。
助川 先ほど、小川国夫と遠藤周作の文体の話が出ました。小川は、西郷隆盛なんかが根を下ろしていた「アジア的なもの」とつながったまま西洋の神と対峙した。対するに遠藤は、小川のような神との向きあいかたを、当事者の立場からは描かなかった。
遠藤がそのようにしか西洋とかかわれなかったのは、彼の留学体験がそれだけキツイものだったせいでしょう。しかし戦後の日本人は、遠藤のような屈曲もなしに、自分たちの「内なるアジア」から目を背けた。そうした構えにもっとも適合した思想家が、柄谷行人だったということになるでしょうか。
重里 遠藤は後年、アジアと正面から向き合おうとしていますね。
助川 バブル崩壊直後の最晩年に、インドを舞台にした『深い河』という長編を書いています。日本の伝統からも根こぎになり、西洋にも同化できず、いっぽうで経済的な発展にも限界が見えてきた――そういう隘路に陥った日本人が歩むべき新しい道を、懸命に模索している作品として私は読みました。
重里 それも含めて、遠藤の仕事は、戦後日本社会のありようや日本人の心の動きとつながっている。それがよくわかりました。