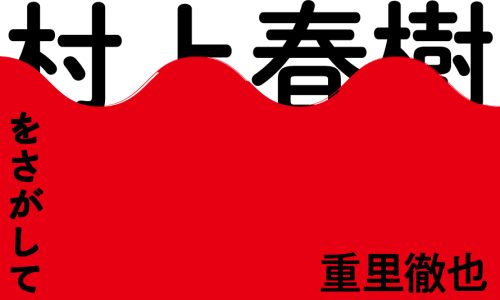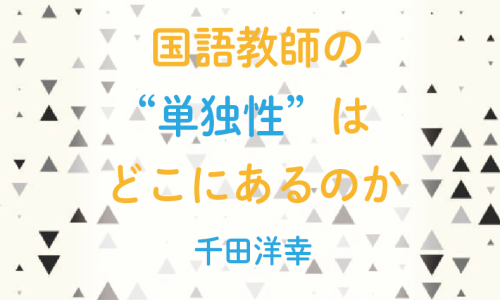前文
「芥川賞」という言葉は独特な響きを持った言葉です。日本で最も有名な文学賞で、あこがれや栄光を思い浮かべて口にする人もいれば、日本文学を取り巻く環境の負の側面として例に出す人がいるかもしれません。「画壇の芥川賞」などのように登竜門の代名詞として語られることも少なくありません。
芥川賞は1935年に創設されて以来、これまでに数々の文学シーンを演出してきました。新しい書き手を発掘するシステムとして文学史を形づくると同時に、その時代を映し出してきたともいえるでしょう。何よりも、人々の無意識の渇望や精神の揺らぎを代弁してきたのではないでしょうか。
これまでの受賞作からいくつかを選び、作品を詳しく論じることで、文学史と日本人の精神史を浮き彫りにしよう。そんなことを考えて、対談を続けることにしました。一体、何が見えてくるのか。ワクワクしながら、語り始めたいと思います。
重里 徹也
助川幸逸郎
移民する農民たちを描く
助川幸逸郎 第一回芥川賞受賞作です。
重里徹也 神戸港からブラジルへ旅立とうとする移民たちの姿を描いた作品です。「蒼氓」とは「無名の民衆」といった意味でしょうか。石川自身も移民の監督者としてブラジルに行った経験があります。
助川 私はこの小説には、今日性を感じました。
いまどきの若者は、伝統的なジェンダー観に縛られていないし、LGBTQなんかにも理解があります。つまり価値観は相当リベラル。なのに、自分と立場がちがったり、利害が対立したりする相手には、非常に不寛容です。
どうしてこうなるのか。格差が拡大したせいで、自分の力で「ここではないどこか」に行けるというイメージを、おそらく若い人たちは持てないんです。だから、「ここでがんばるしかない」と思う他なくなる。そうなると、違う立場の人間の心境を想像する余裕を持てないわけです。
重里 おそらく、「異文化理解」というスローガンはあちこちでいわれ続けているでしょう。ところが、ここでも、タテマエとホンネが分裂しているというか。自己愛の強い若者が多くて、それを刺激されると敵意がむき出しになる。
助川 ところが、この『蒼氓』に出てくる人びとは、日本ではいくら働いても食えないから、ブラジルに行こうと考える。この作品の舞台になった一九三〇年代には、そういう発想があったんですね。いまの若者は、日本にいても希望が持てないからといって、外国に行こうとはあんまり考えません。
貧困とか、格差の拡大とかは、たしかに無視できない問題です。けれどもそういう点だけから、現代日本の閉鎖的なムードを語ってしまうと、大事なポイントを見落としてしまう気がします。
重里 でも、もう少し経てば、日本人が中国に出稼ぎに行く時代が来るといわれますね。現在はアジア諸国からたくさん、日本に来ている人たちがいます。
助川 先日、岐阜駅前のコンビニに寄ったら、従業員の方が全員、外国人で驚きました。
重里 日本もそのうち、移民が来るだけじゃなく、移民を出す国に再び、なるのではないかと、ときどき考えます。
助川 それはありえますね。ただ、『蒼氓』の舞台になっている一九三〇年代は、日本の人口が増え続けている時代です。国内の生産力では、そんなにたくさんの人口を支えきれない。それで、日本にいては生活できない貧しい人びとが、食べることを目的として海外に出ました。
いまの日本は対照的に人口が減っている社会です。国内にとどまっていても、いちおう食べられるだけは食べられる。これから国の外に出ていくのは、もっとお金になる仕事、もっと刺激的な体験を求めるエリートです。
重里 その兆候はすでに見え始めているのではないでしょうか。外国企業に就職する人は少なくないですし、有名高校を卒業した後、日本の大学に行かないで、いきなりアメリカの大学に入るケースも増えていると聞きます。
助川 私のまわりでも、ちょっとおもしろいと感じさせるひとは、海外の大学を出ていたり、外国の企業で働いていたり……。そういう人は、物の見方もフェアで、柔軟性があります。
重里 発想の奥行きが違うということでしょうか。
助川 一方、日本でうまくやっていこうと決めて、この国にしがみついている人からは、考え方が固まってるな、という印象を受けることがときどきあります。
倫理も思想も問わない社会派
重里 さて、この『蒼氓』という小説は、しばしば「社会派」と評されます。これといった特定の主人公のいない群像小説で、移民を志す東北の貧しい農民たちを描いています。
助川 秋田の人間がいっぱい出てくるんですね。私の母が秋田生まれなので、親近感をもって読みました。
重里 ただ、『蒼氓』はたしかに社会を書いた小説なのですけれども、イデオロギーはほとんど前面に出ていません。この作品が発表されたのは一九三五年、社会主義者たちが大弾圧を受けて、プロレタリア文学が壊滅させられた後です。政治思想を掲げて社会状況を糾弾する小説は、危険すぎて公表できなかったのでしょう。しかしもともと、石川達三自身にイデオロギーがあったのかどうか。なかったのじゃないかという印象を持ちます。ある意味で素朴な正義感はあったでしょうが。
助川 石川は、戦間期から戦後にかけて思想的に変節したと批判されています。これは重里さんのおっしゃるとおり、石川にはそのときそのときの正義感はあったがイデオロギーはなかった、と考えるほうがすっきりする気がします。
重里 しっかりとマルクス主義を勉強したという印象は受けないですね。そして、この小説を読んでいて、非常に平板な印象を受けました。立体感に乏しいというか。
小説に立体感をもたらすものは、いろいろと考えられると思います。たとえば、五つ、挙げてみましょうか。これ以外にもあると思いますが。
まず倫理。善悪の区別ですね。平板な小説を書く作家の多くは倫理を内側から問おうとしない。二つ目が社会変革、革命といえばいいでしょうか。三つ目が信仰、宗教。絶対的な存在へのまなざしですね。四つ目が哲学、人間は何のために生きるのか、人生は何のためにあるのか、生きる意味とは何か。五つ目が美。美醜とは何かという問いかけ。
この五つが五つとも、『蒼氓』にはない気がするのです。
助川 重里さんがお挙げになった五つは、ようするに「価値観」ということですよね?
重里 そうですね。人間に価値をもたらしたり、価値について考えさせたりするものですね。もうひとつ、恋愛というのをどうしようか迷ったのですが。
助川 恋愛も「価値観」とかかわってきますよね。
重里 そういう「価値へのまなざし」がほとんど感じられない小説なのですね。社会にカメラを向けてはいるのですが、価値に対する思いを少なくても作家は自覚していない。小説空間から意識的にか、無意識にか、価値というものを排除している。そして、単に気の毒な東北の農民群像が描かれていく。そこに喜怒哀楽はあるけれど、それを串差しにするような垂直軸はない。
群像を見る視点はどこにあるか
助川 新聞の連載記事みたいな文章だなと思いました。
重里 ジャーナリズム的というか。これは言うかどうか迷いますが、敢えていえば、非常に文藝春秋的です。その意味では、芥川賞の第一回にふさわしい作品だといえるかもしれません。
助川 私はこの小説を読んで二つのことを考えました。一つは、この『蒼氓』に比べたら、プロレタリア小説のほうが通俗小説としてもおもしろいのではないか、ということ。プロレタリア小説は、しばしば極限状況を描くのでドラマチック。人物造形も、一面的なケースが多いとはいえキャラは立ってます。どちらも、『蒼氓』には欠けている魅力です。もう一つは、さっき新聞記事みたい、という言い方をしましたが、この文体はノンフィクションを書くほうがフィットする感じがするんです。ですからこの書き方で、石川自身のブラジル体験をありのまま書いて欲しかった。石川は、自分のブラジル体験を、『最近南米往来記』と銘うった実録として公表しています。どうしたわけか、この実録の方が『蒼氓』よりずっと文学的というか、美文的なスタイルで書かれているのです。『蒼氓』のニュートラルな文体で、実録を書いてくれたらよかったのに――そんな「ないものねだり」を、私はしてしまいます。
重里 この小説には、待機宿泊施設で移民に出発する日を待っている女性を、監督官の助手が犯す場面がありますよね。
助川 ええ。
重里 石川自身は、移民船の監督官の立場でブラジルに渡っています。ですから、『蒼氓』に出てくるキャラで石川にいちばん近いのは、あの男でしょう。東北の農民たちに距離を置く知識人っぽい人物。
助川 あの監督助手、名前は小水といったと思います。私もこの作品の中で石川にいちばん近いのは、小水だろうという印象を受けました。
重里 石川自身がああいうことをやらかしたかどうかは別として、あの監督助手の小水が石川の立ち位置です。そのせいか、移民を見下ろしている印象があります。群像を、やや上から眺めて書くという構造ですね。
助川 さっきも言いましたが、『蟹工船』のほうが起伏に富んでいる気がします。
重里 イデオロギーなしの『蟹工船』。革命や党が出てこない分、『蒼氓』のほうがフラットなのです。あの強姦など、倫理や哲学を問う契機になるはずなのですが。単に登場人物が性欲を処理しているだけですね。
太宰治と芥川賞
助川 でも、この作品、太宰に勝って受賞しているんですよね。重里さんなら、やっぱり太宰を落として、こっちに票を入れますか?
重里 うーん、それは難しいなあ。太宰はこのとき『逆光』で候補になっているのですね。『道化の華』なら『蒼氓』よりいいとはっきりいえます。でも、『逆光』は短いし、断片的な作品なので、太宰の魅力が全面的に出ているかというと、ちょっと疑問です。他の作品を良く知っていれば、この作品からも「太宰らしさ」を評価することはできると思いますが。
助川 芥川賞は新人賞なわけです。ではそこで選ぶべきは、「現段階の実力ナンバーワン」なのか、「将来的に安定して活躍してくれそうな書き手」なのか。言ってみれば、高校野球の優勝投手を探すのか、ドラフト会議をやるのか、という問題です。
実は、ちょっとした必要があってここ数日、高山羽根子の作品をまとめて読みました。非常に才能のある作家ということが、一文一文からつたわってくる感じでした。その高山の文章の残像がまだ消えない目で『逆光』を読んだら、時代やタイプの違いを越えて、ここにも一文一文に才能がにじみ出てる作家がいる! と思って感激してしまいました。
重里 石川にはそれはないと?
助川 ええ、そこまでの才気は感じません。そのかわり、太宰にも高山にも、もってる才能がでかいだけに、それを開花させるのは相当たいへんだぞ、と思わせる部分があります。甲子園では凄かったのに、そこで終わってしまう投手がけっこういますが、太宰の『逆光』からは、そういう危険の匂いもします。
その点石川には、安定して書いていくだろうという期待はできます。ドラフトで、確実に戦力になる選手をとりたいとなったら、私は太宰より石川を推します。
重里 ただ、石川達三の活躍する場所というのは、中間小説の世界だろうというのは、『蒼氓』の段階から予測はつきますね。
助川 文章の質が、純文学の文章ではないですね。
重里 そのわりに、『蒼氓』はこれ以降の芥川賞の性格を象徴している面もあるように感じます。芥川賞って、意外にチャレンジングな作品よりも、わかりやすいものが受賞しやすい。
助川 それから、芥川賞には、かなりジャーナリスティック性格があります。
『逆光』は、いま読んでもたしかに魅力的ですし、文章も普遍的な価値に届いています。しかし、一九三〇年代の文壇とか、この時代の日本社会を考えるには、圧倒的に『蒼氓』の方が参考になるんです。
文芸として、エヴァ―グリーンな価値のあるものより、そのときそのときの時流を映し出す作品が選ばれやすい傾向が、芥川賞にはたしかにある。そう考えると、『逆光』ではなく『蒼氓』という選択は、この賞らしい感じがしてきます。
重里 おそらく論文も、『逆光』より『蒼氓』の方が書きやすいでしょう。ただしその論文は、「一九三〇年代の日本社会」とか「ブラジル移民の歴史」とかいう視点を含むものになりがちでしょうね。真正面から、この作品の文体を論じる論文にはなりにくいように思います。また、この作品に示された思想性を論じるのも、あまり魅力的ではないように思います。
助川 純然たる文学論を書きにくい作品にも受賞させるのが、この賞のジャーナリズム性ですね。だからこそ芥川賞はいまでもこんなにメジャーなのかもしれません。
ただ、文藝春秋が選考委員にお願いして、時流に合致した作品を選んでもらっているわけではないんですよね?
重里 それは考えにくい。実作者が、無意識にか、こういう選択をする、というのはおもしろいですね。
助川 太宰は芥川賞をずいぶん取りたかったらしく、このあといろいろ運動もしています。去年、岐阜の歴史博物館で川端の展示があった折に、川端に「芥川賞をとらせてください」とお願いした太宰の手紙の実物を見ました。
『道化の華』なら受賞したか?
重里 でも、『逆光』で受賞するのは苦しいかなあ。
私は北杜夫を若いころから愛読しているのですが、北も何度も候補になりながら、なかなか芥川賞を受賞できなかった。『夜と霧の隅で』で受賞したのは候補四回目です。それで、アンケートに答えて「候補作はせめて自分で選ばせてほしい」といったようなことを書いていた記憶があります。
助川 どの作品で候補になるのかも、たしかに受賞に影響しますよね。
このときの芥川賞の候補作は、いまと同じように文春の社員が選んでいるんですか?
重里 このときは文藝春秋の社内で三十人ぐらい候補を選んで、それを中心にして永井龍男が五人の候補に絞ったようです。いまは、文春の編集者二十人前後がさまざまな形でディスカッションを重ねて候補作を決めます。
永井龍男のリアリズムからすると、『道化の華』より『逆光』だったのでしょう。永井がいうには川端康成も『道化の華』に消極的だったようですね。太宰の候補作が『逆光』でよかったのかどうか。選評でも触れられていますね。
助川 川端は、現実に女性と交渉するより、頭の中で女性に関する妄想を膨らますのが好きというタイプ。いま生きていたら、アニメの女性キャラのフィギュアーをずらりと部屋に並べてるかもしれません。そういう川端には、太宰の、生身の女性と心中をはかるような部分には、共感を持ちにくかったのでしょうか。それから佐藤春夫は、『道化の華』が候補作なら取れたかもしれない、って言っていますね。
重里 『逆光』には佐藤春夫の悪口が出てきますよね。選考委員の悪口を書いて、はたして受賞できるものなのでしょうか。
助川 そこが太宰らしい甘えというか、ツンデレというか……ほんとうに賞が欲しいのか、欲しい欲しいと騒いでかまってもらいたいだけなのか、たぶん本人にもわかっていなかったのではないでしょうか(笑)
重里 控えめにいっても、太宰は日本の近代文学で二十人を選べば、おそらく入ってくる作家でしょう。その太宰が芥川賞を取り損ねたというのが、太宰には気の毒だけれど、とても興味深いめぐり合わせだと思います。私たちが芥川賞について考えるときに、絶えず、芥川賞に距離を置いて相対化することを促す「重し」のようになっていると思えるのです。