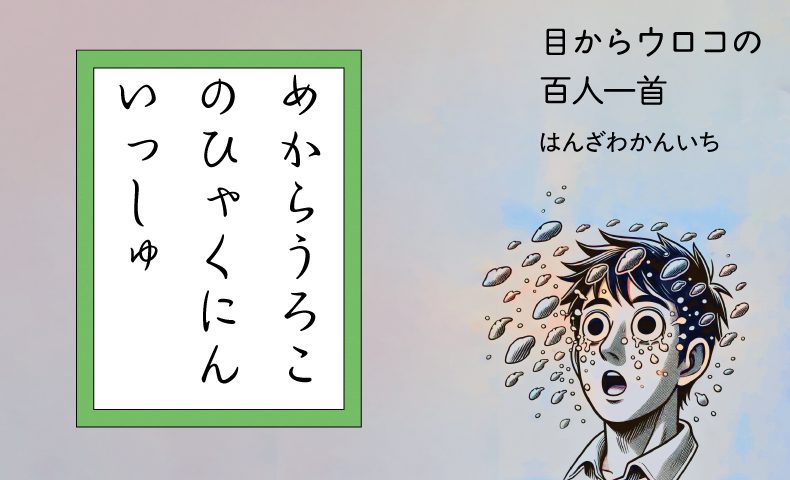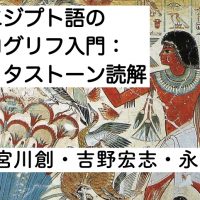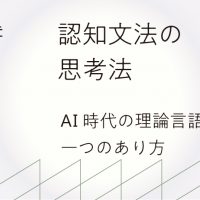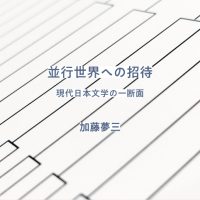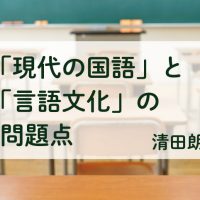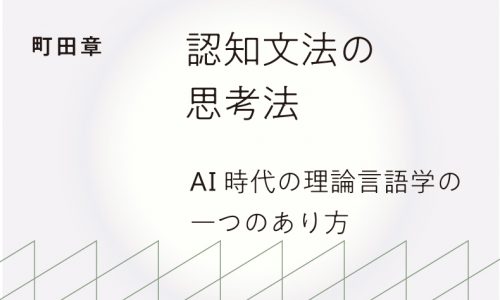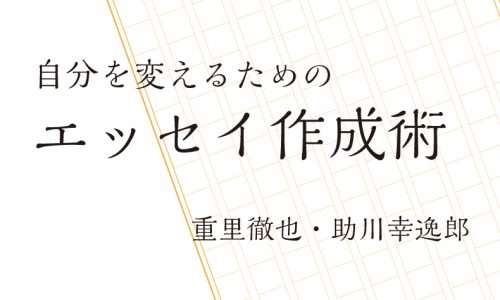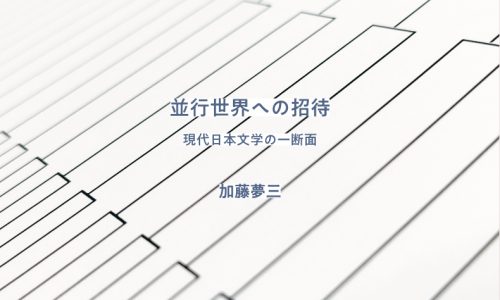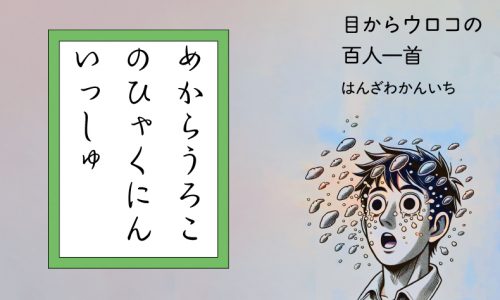秋の田のかりほの庵の苫をあらみわが衣手は露に濡れつつ
百人一首の冒頭に位置するこの歌は、「秋田刈る仮庵を作りわがをれば衣手寒く露ぞ置きにける」(万葉集、巻10・2174番)が本歌とされています。百人一首歌の本文は、後撰集(巻6・秋中・302番)から採られたものです。
本歌される歌とこの歌ではウロコ的な表現上の違いがあり、そういう関係があると言えるのか、疑問です。
〔ウロコ1〕「苫(とま)をあらみ」
元歌は「あれば」、この歌では「あらみ」のように、形式は異なりますが、どちらも第3句までの上句が下2句の内容に対する原因・理由を表わす表現になっているという点では共通しています。
しかし、元歌では「わがをれば」つまり私がそこにいるという、詠み手自身の状況を理由にしているのに対し、この歌は、家の屋根の苫(網目)が粗いという外的な状況を理由にしています。
そして、このような理由の違いが、結果を示す下句では逆転します。つまり、元歌では「露そ置きける」のように、外的な自然物(露)の現象に焦点が置かれるのに対して、この歌では「わが衣手は袖に濡れつつ」のように、詠み手自身の側に焦点が置かれているのです。
つまり、元歌では、詠み手から外的な対象に、この歌は外的な対象から詠み手に、表現対象が切り替わっているということです。これは、1首全体として見た場合、元歌は露、当歌は詠み手(の衣手)を中心に詠まれたということを意味します。
〔ウロコ2〕「衣手(ころもで)」
「衣手」とは衣の手のあたり、つまり袖のことです。この語が「露」とセットで詠まれる場合には、古典和歌での1つのお約束があります。それは、「露」が涙の比喩となり、それが落ちて、あるいはそれを拭って、袖が濡れるという関係です。
と、どうなるか。万葉集の元歌は、袖に露が置くという、文字通りの事態を描いているのみなのに、この歌は、そういう事態もふまえ、詠み手が泣くという事態を表わしていることになります。
〔ウロコ3〕「濡れつつ」
元歌は「露そ」との係り結びで、「けり」という詠嘆の助動詞で締めくくられています。これは、露が置いたという1回の出来事の気付きが1首の眼目であることを示します。それに対し、この歌は「つつ」という接続助詞を歌末に置くことによって、断言を避け、かつ袖が露(=涙)に濡れる状態が継続あるいは反復していることを示します。
以上のような、表現上の違いから見えてくるのは、何でしょうか。
万葉集の本歌とされる歌は、収穫を控えた秋の田の番人として泊るという、個人的な生活体験そのものを歌うのに対して、この歌は、そのような体験による独り寝の寂しさ・辛さという、心のほうを詠もうとしたということです。表現上は似ているところがあっても、言いたいことは、全然違っていませんか。換骨奪胎もいいところです。
定家はおそらく万葉集の歌ならば、選ばなかったでしょう。後撰集の歌のようになることによって、彼の目に適った和歌と認められたのです。
ちなみに、万葉集の元歌は、詠み手の記されていない、作者不明歌なのに、後撰集歌ではなぜか天智天皇!ということになっています。天皇が田んぼの番人をするなんて、ありえませんよね。
この歌が、まさに想像の歌として成り立っているということです。