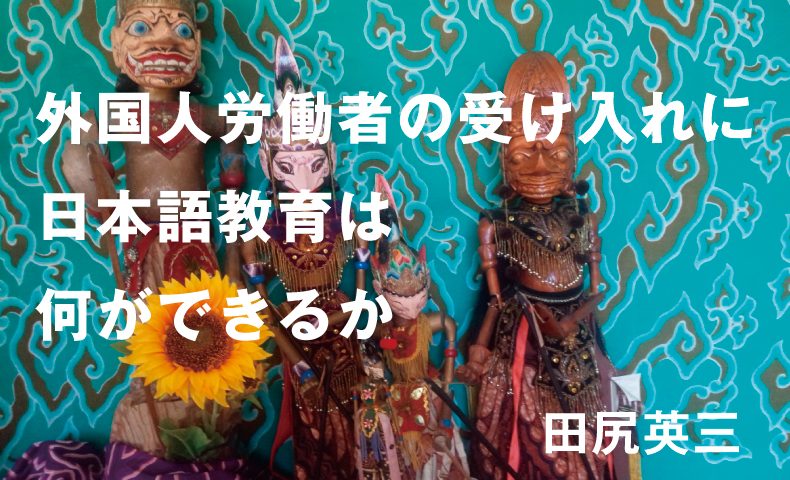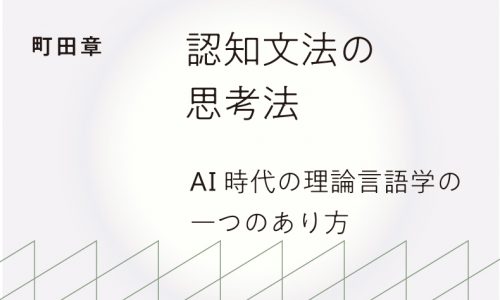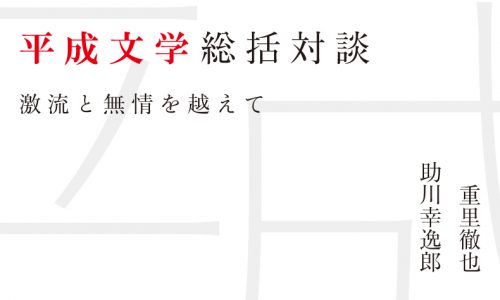★この記事は、2025年3月28日までの情報に基づいて書いています。
今回は、同じ「未草」の記事で千田洋幸さんの「国語教師の“単独性”はどこにあるのか」の第6回で、日本語教育を切り開いた一人である小出詞子さんを取り上げていますが、田尻には承服しがたい記述があるのでそれについて述べます。また、この時期には日本語教育の大事な会議がいくつか開かれているので、その会議の内容について説明します。
1. 千田さんの記事について
上述した千田さんの「未草」の記事第6回は、「『ひたすら実践に励むこと』の陥穽」という表題が付けられています。そこでは「教育実践を日々積み重ねることに充足し、児童・生徒から『良い先生』と慕われ、同僚や保護者からも認められ、教師としての自己肯定感を高めていく――一見、実践者としてのあるべき理想像のようではあるが、それだけにむしろ危ういのだ」と書かれた実例として、小出さん(田尻は1度だけお会いしていますが、直接教えていただいた訳ではないので、ここでは「さん」付けで呼ばせていただきます。ただ、田尻にとって、小出さんの存在感は、まさに「先生」でした)が取り上げられています。そこでの小出さんの人柄については、以下のように書かれています。
- (田尻注:長沼先生の思い出を書いた文章を引用して)まったく無邪気に回想されていること、さらに十八年後に編集・刊行された著作集にそのエッセイが堂々と収録されている事実に、ある種の実践者の典型を見いだす
- さしたる曲折や挫折もなく、日本語教育実践の開拓者のひとりとして順調にキャリアを積み重ねていった人物である
- かつて植民地で実践された日本語教育の「やり甲斐」を嬉々として語り(中略)内面的葛藤の欠如は、すくなくとも私にとってはおよそ理解しがたいことだ
- 宗主国の日本語教師として戦争責任と植民地責任を感じていたらしい小出は(中略)植民地時代の日本語教育の意義を自讃する認識に「転向」したのだろうか
- 戦時下の日本語教育の成果をも正当化しながらさらなる実践に励む。小出にしてみれば、日本語教育の実践者としてのアイデンティティと欲望にもとづき(中略)生涯においてなんら変節することなく、完全に一貫している
- 自分のせまい「現場」にひたすら閉じ籠って実践をつづけるかぎり、時流に流されながら、その時々の言語政策の代弁者をつとめて生涯を終えるほかないことは、小出の一事例を観察するまでもなく、日本の言語教育の歴史をふりかえってみればあきらかだ
小出さんが「内面的葛藤の欠如」であったとは、田尻は決して思いません。それは千田さんが引用している以下のような小出さんの発言でも明らかです。
- 私が日本語教育を行っていた頃は、日本の国家が強制的に、その国の人々に対して日本語教育を推進していました。[そこに住む人々の言語というアイデンティティを奪って]そして現在、あなたたちは日本語教師を目指しています。今は、あの時の日本語教育ではありません。全く違うのです。強制するのではなく、その国の人々から来てくださいと、請われて行くのです。求められれば、どこへでも行きますという姿勢が大切です。また、日本語教育の主体はあくまでも学習者にあるのです。この意味を噛みしめてほしい
ところが、千田さんによると、この文章は「戦争責任と植民地責任を感じていたらしい」としながらも、「戦後はそれなりの反省を表明して学生に『全く違う』(この言葉におおくの隠蔽や「跨ぎ」がひそんでいることはいうまでもない)日本語教育を講義し、日本の国力が増大して他国の日本語需要が高まれば戦時下の日本語教育の成果をも正当化しながらさらなる実践に励む」ということになっています。千田さんの記事の趣旨は、理論がなくて実践しか頭にない教師を批判することだと思います。しかし、現在の日本語教育の実践に理論的な裏付けがないと、どうして言えるのでしょうか。そのような実践例があればそれを示した上で、日本語教育を批判してください。このように一方的に小出さんを批判するのなら、もっと多くの日本語教育の文献を調べてください。日本語教育に限りませんが、安田敏朗さんの膨大な言語政策史の文献は必読ですが、千田さんの記事には、全く引用されていません。
この「未草」の読者は、千田さんが「注2」で示している小出さんに関わる論集を読んでください。小出さんへの関係者の気持ちが伝わると思います。
https://koidekinen.org/archives/research/2021-feature
千田さんにお願いがあります。千田さんの次の「未草」の記事で、田尻のコメントに対するご意見・ご感想を書いてください。千田さんの文章の読者が田尻の文章を読むとは限りませんので、このままでは日本語教育の側が一方的に批判されただけの結果となります。そして、千田さん自身が「注5」で言っている「国語教育者の戦争責任・植民地責任がなかば不問に付されたことは、現在も国語教育研究史の負の遺産としてかかえこまれている」の「負の遺産」を明らかにする研究をすることを期待します。そうしなければ、小出批判をした千田さんの姿勢とバランスが欠けると田尻は考えます。
2. 「就労」分野への日本語教育の関わり方
日本語教師や日本語教育学の研究者と言われる人たちは、「留学」分野には興味があります。しかし、「就労」分野では、高度人材と呼ばれる人たちへの日本語教育には研究グループが出来ていますが、非熟練労働者への日本語教育にはあまり関心を示していません。また「生活」分野の日本語教育はボランティア任せという実態は変わっていません。外国人の子どもたちへの日本語教育は、現場の教師と一部の研究者との研究会活動が続いています。難民の日本語教育については、一部の機関が公的には関わっています。外国での日本語教育は、国際交流基金が大きな役割を担っています。つまり、「留学」分野以外は、小規模の活動となっています。しかし、日本社会では、「就労」分野の日本語教育は大きな問題になっています。
現在の日本では、生産年齢人口の減少が喫緊の問題となっています。このような状況を前提として、以下に「就労」分野の日本語教育を考えます。
(1) 現代日本の外国人労働者問題と日本語教育
現在の日本社会の最も大きな問題は、人口減少です。その中でも、日本経済に最も大きな影響を与えるのは生産年齢の減少です。現在の日本では、高齢者や女性の就労率を上げるか、AIなどによる生産性の向上で切り抜けようとしていますが、それには限界があります。そこで、「移民」政策は取らないが、外国人労働者の受け入れ促進は進めたいというのが、日本政府の方針です。
日本に住む外国人労働者数については、総務省統計局の5年ごとに行われる「国勢調査」か、厚生労働省職業安定局が毎年行う「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」があり、出入国在留管理庁の「出入国在留管理統計」も参考になります。統計処理上、総務省と厚生労働省の資料には数字にズレがあります。ここでは、最新の資料である2025年3月14日公表の入管庁の「令和6年末現在における在留外国人数について」を使います。
2025年末の在留外国人数は,3,768,917人で、前年比10.5%増の過去最高です。増加数が最も多かったのは留学生402,134人で61,251人増、労働者としては技能実習456,595人で52,039人増、技術・人文知識・国際業務418,706人で56,360人増です。地域別の在留外国人数では、相変わらず東京都、大阪府、愛知県、神奈川県、埼玉県などの順ですが、ここで興味深い記事を見つけました。
人口戦略会議編著の『地方消滅2』(2024.12 中公新書)に増田寛也さんの発言に、「10年間で大きく変わったのは、外国人入国者の増加です。入国者数は各市町村ではなく、国全体の数字でしかないので確実なことは言えませんが、おそらく消滅可能性都市数の減少に寄与していると思われます」というものがありました。
また、3月24日の朝日新聞の記事では、3大都市圏(東京・大阪・名古屋)以外の地方都市の国際交流協定(MOU)2023年から極端に増えていることを扱っています。
増田さんの意見が的を得ているとすれば、在留外国人は地方に多く住み始めているということを意味します。地方には認定日本語教育機関や登録日本語教員は少ないので、その分、地方の日本語教室に負担がかかってきています。技能実習制度では、日本語習得の時間は実質的に現場任せとなっています。これでは、外国人労働者の雇用環境は守られません。地方自治体では、何らかの手を打たざるを得なくなっているのです。
地方における日本語教育の需要度は増しているのです。これは、日本語教育の世界に住む人にとっては日本語教育の需要度の高まりという「外圧」になっています。しかし、多くの日本語教師や日本語教育の研究者は、このことに目を向けようとしていません。これが、今の日本語教育の世界の状況です。
(2)「就労」分野における日本語教育の必要性
この数年間、外国人労働者の日本語教育については、この「未草」の記事でたびたび扱ってきました。田尻が「就労」分野の施策に日本語教育専門家の意見を聞いてほしいと言った公的な記録として残っているのは、第9回日本語教育推進関係者会議(2024年12月18日)の田尻の発言です。議事録が公開されていますので、確かめてください。
ここでは、田尻は次のように発言しています。
特定技能制度と育成就労制度の運用に関する有識者会議が来年の1月に始まるんですが(田尻注:実際には2月に始まった)、これに日本語教育の専門家がぜひ入ってほしいなと私は、ここで言ってもどうなるか分かりませんが、外務省なんかもこの会議に入っているので、この分(田尻注:「機会」と言ったつもり)にぜひその部分を入れていただきたいというのが希望です。
田尻は、以前から外国人受け入れに関わる会議に出席している国会議員にこの件を依頼してきましたし、この関係者会議での田尻の発言もあったことが関係しているのか、2025年2月27日の第3回「特定技能制度及び育成就労制度の円滑な施行及び運用に向けた有識者会議」で二人の日本語教育専門家が発表を行いました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53090.html
ただ、残念ながら、この会議で日本語教育の専門家が関われる範囲は、限られています。特定技能と育成就労については、技能実習制度の見直しを含めてすでに数年前から議論されてきて、大枠はこの段階ではすでに決まっているのです。今回の会議でも、育成就労の外国人の日本語能力についてのみ検討することになっているのです。第2回の会議資料1に明示されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001405013.pdf
そこでは、以下の2点が「主な論点」として掲げられています。
- 就労開始前までにA1相当の日本語能力の試験に合格していない外国人が受講しなければならないA1相当講習について、日本語教育の主体として認定日本語教育機関以外にどのようなものを認めるべきか、講習時間などをどのように設定するか。
- 育成就労の目標として定めるA2相当の日本語能力の試験の合格に向けて、育成就労期間中の日本語教育の主体、講習時間、方法等をどのように設定するか。
この会議では、この2点について日本語教育の専門家の意見を聞くことになっていたのです。この資料は、第3回の会議でも示されています。
2月27日に開かれた第3回の会議には、日本語教育の専門家として森下明子さんと島田徳子さんが意見を述べています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53090.html
森下さんの意見は、「講習を実施する主体について」で「認定日本語教育機関(就労)以外に認定日本語教育機関(留学)を含めた認定日本語教育機関も認めるべきである」というものでした。この意見は、今までの日本語教育施策の枠組みを逸脱したものです。認定日本語教育機関の扱う分野は、「留学」・「就労」・「生活」の3分野に決まっています。森下さんが日本語教育の専門家として、このような意見を政府の会議で発表することは、これまでの日本語教育施策の流れに反すると田尻は考えます。
島田さんの意見は、「要旨」での文章末は全て「~ではないか」となっており、そこでの日本語教育については、この会議の段階ではすでに検討してきたものがほとんどでした。この会議では、日本語教育の専門家としてできるだけ具体的な提案をしてほしかったというのがこの会議の意見聴取の趣旨でした。島田さんが示した「外国人材」の資料は、出入国在留管理庁の「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」でいう「専門的・技術的分野の外国人」であり、この会議で扱う外国人労働者は「上記以外の分野の外国人」(田尻注:非熟練労働者を指す)です。島田さんには、この会議の趣旨が十分に伝わっていなかったのではないかと考えます。
この会議の趣旨に最も合致した意見を述べたのは、国立社会保障・人口問題研究所の是川夕さんと移住者と連帯する全国ネットワークの鳥井一平さんです。
是川さんは、以下のような的確な意見を述べています。
- 育成就労制度における育成計画や特定技能2号への移行支援プランの作成において参考となる具体的な日本語教育カリキュラムを、制度施行までに制度所管官庁、及び業所管官庁が作成し、提示すること。
- (中略)施行から一定期間の間は登録日本語教員による代替を認めつつ、当該教員が認定日本語教育機関「就労」において一定の講習を受けること、及び国が示したカリキュラムに則って行う等、一定の要件を課すこと。
- 日本語教育(田尻注:日本語能力のこと)の測定方法については、単発の試験によらず、講習の修了(合格)を以て可とするなど、実態に即した想定方法を検討すること。
鳥井さんは、過去の外国人労働者受け入れの経緯と問題点を示した上で、「育成就労における日本語能力について」で以下のように述べています。
現在のところ「就労」課程を認可された認定日本語教育機関はなく、申請中も2つの機関にとどまっている。こうした状況では、2027年までに育成就労に向けた日本語教育の体制が整えられると思えず、日本語教育の状況をどこまで理解した上での提案なのか、疑問を持たざるを得ない。こうした背景には、(中略、ここでは会議名を列挙している)においても、日本語教育に関する専門性を持った有識者がひとりも参加していないことにあるのではないか。
これらの意見を受けて、会議では或る委員から森下さんに現在の登録日本語教員数(田尻注:11,051人)が聞かれましたが、森下さんは答えられませんでした。
大変違和感を持った意見を述べたのは、国際人材協力機構の杉浦信平さんです。「監理支援機関等の日本語教育担当職員の活用」では、以下のように述べています。
当分の間、相当講習では、登録日本語教員の助言と指導の下、国が示すモデルカリキュラムに基づく「相当講習実施計画」を策定し、100時間のうち、75時間を監理支援機関等の職員が対面で講習を実施し、25時間を登録日本語教員による対面またはオンラインで講習することを認める。
田尻は、この意見に強く反対します。これでは、誰でも日本語教育ができるということになり、現在進められている日本語教育施策に反します。
この3回の有識者会議を経て、「就労」分野の日本語教育が「特定技能の在留に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針について」が閣議決定されました。その基の資料が、3月11日に開かれた以下の会議の「資料1-2」のものです。
外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議(第21回)https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai21/gijisidai.html
この閣議決定した内容は重要なものなので、資料に基づいて詳しく述べます。
第三 特定産業分野及び育成就労産業分野において求められる人材に関する基本的な事項
- 1号特定技能外国人
(中略)
(3)1号特定技能外国人に対しては、日本語教育の参照枠A2相当以上を基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な水準を満たす日本語能力が求められる。当該日本語能力水準は、特定技能分野別運用方針において定める当該特定分野の業務区分に対応する日本語能力の試験等により確認する。
(田尻注:具体的にどの試験を使うかは示されていなくて、それぞれの分野で試験内容を決めてよいということになっている)
(4)特定技能評価試験及び日本語能力の試験は、特定技能制度により受け入れる外国人の利便性の確保の観点から(中略)原則として国外において実施する。
(田尻注:国内で行われた日本語基礎テストで替え玉受験が発覚して、一時海外での試験が中止になった)
(5)(中略)法務省は、特定技能評価試験及び日本語能力の試験の適正な実施を確保するため、必要に応じて、当該試験の内容について厚生労働省、文部科学省に対して助言を求めるなどした上、特定産業分野を所管する行政機関又は同機関が定める試験実施者及び日本語試験実施機関に対して指導等を行う。
(田尻注:日本語能力の試験については、法務省が扱うことになった。文部科学省は、「必要に応じて」「助言する」ことしかできないようになっている) - 2号特定技能外国人
(田尻注:2号特定技能外国人については、「日本語教育の参照枠B1相当以上」以外は、1号と同じ)
3. 育成就労外国人
(3)育成就労外国人に対しては、就労を開始する前までに、日本語教育の参照枠A1相当以上を基本としつつ、育成就労産業分野ごとに業務上必要な水準を満たす日本語能力が求められる。
当該日本語能力水準に関しては、育成就労分野別運用方針において定める当該育成就労産業分野の業務区分に対応する日本語能力の試験に合格すること又は相当する日本語講習を認定日本語教育機関(中略、法律名が入る)による就労のための課程の講習(中略、法律名が入る)等において受講することが求められる。就労開始前までに当該試験に合格していない育成就労外国人については、育成就労の開始から1年経過時までに当該試験に合格することが求められる。
また、育成就労外国人に対しては、育成就労を終了するまでに、(中略)日本語教育の参照枠A2以上の日本語の試験に合格することを目標として育成就労に従事し、当該日本語能力の修得に努めなければならない。
(田尻注:いずれも「求められる」や「努めなければならない」となっていて、どれだけ実効性があるかは今後注視しなければならない)
第四 特定技能所属機関に係る施策並びに育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るための施策に関する基本的な事項
(中略)
- 育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護のための施策に関する基本的事項
(1) 育成就労実施者の責務
イ 目標として定めた試験の適正な受験等
育成就労の開始後1年が経過する時まで及び育成就労を終了する時までに育成就労外国人に必要な技能及び日本語能力の試験を受けさせることは育成就労実施者の義務であり、これを通じ育成就労外国人が修得した技能及び日本語能力の評価を行うとともに、指導内容、方法、体制等に改善すべき点がないか点検すべきである。試験費用については育成就労実施者又は管理支援機関が負担する必要がある(以下略)
(田尻注:日本語能力の試験受験を育成就労実施者の義務として点は、注目すべきです)
5. 人手不足状況の変化等への対応
(田尻注:人手不足の状況に変化が生じた場合は必要な措置を講じるとあり、受け入れを縮小する可能性に触れています。ただ、その後に「再び必要とされる」場合には「再開の措置を講じる」ことを検討することも書かれており、状況に応じて受け入れの拡大・縮小が行われるとしています。また、「大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することを防止する」措置を講じることも書かれています)
なお、この資料で「望ましい」・「留意すべきである」・「求められる」などの表現が使われている事項については、施行にあたって実行が十分に担保されない可能性があると考えて取り上げないことにしました。
この会議の{資料3-1}の「特定技能制度・育成就労制度の基本方針に関する有識者会議での主な御意見等」では、是川さんや鳥井さんの意見は取り上げられませんでした。田尻は、今後もこの問題についての日本語教育の重要性を訴え続けていきます。
4. 日本語教師養成・研修推進拠点整備事業(近畿ブロック)第1回公開シンポジウムで感じた問題点
上記のシンポジウムが、2025年3月22日に大阪のヒルトンプラザウエストで開かれました。田尻はこのシンポジウムに参加して、この整備事業そのものに疑問を感じたので、以下に述べます。
なお、当日の資料は以下のURLで見ることができます。拠点校は神戸大学です。
https://language.sakura.ne.jp/kjlpt/event.html
田尻は、午後からのみ参加しました。
午後の神戸大学拠点責任者の石川慎一郎さんの活動報告を聞いて、石川さんはこの日本語教育施策がどのような流れの中で行われているかをご存じないように感じました。以下、資料に書かれていない当日の口頭での発言を扱います。
外部評価委員の広島大学の迫田久美子さんの当日の講評では、石川さんは英語教育が専門で日本語教育の仕事を引き受けて大丈夫かと思ったと言っています。迫田さんの講評そのものは、好意的なものでした。
石川さんが日本語教師養成を担う人たちを「高度人材」と名付けたことには驚きました。ここでは説明しませんが、これは明らかな間違いです。
石川さんのこの事業に至る時間的な流れの説明も、田尻には納得できないものでした。この点は、国際交流基金関西国際センター長の真嶋潤子さんの講演の中で修正されたと田尻は考えています。
日本語教育課の今村聡子さんと齊藤由人さんの資料は最新のデータが入っており有益です。
養成/実践研修機関で登録された機関の方が、どのように申請したかを話した中で、「気に入られるようにしていた」とか「必須の教育内容50項目を授業に当てはめたが、実際に運営するのはこれからで決まっていない点もある」とか発言しているのを聞いて、このような例を他の機関が真似をするようでは問題が起こると思いました。
田尻は直接審査に関わってはいませんが、この施策に関わっている会議の委員としては、このような考えで登録申請をすべきではないと強く思います。これではせっかく作った新しい取り組みが骨抜きになってしまいます。今後の審査は、本来の方針に沿ったものになることを期待します。
外部評価委員の中には、「私がどうしてここにいるか分からない」と発言する人もいました。冗談でも言うべきではありません。外部評価委員の選考は、どうなっているのでしょうか。
近畿ブロックは、大学は17機関ですが、日本語教育機関は5機関だけで、その他は国際交流関係の5機関が構成員です。
田尻には、近畿ブロックの主会では、この事業の本来の目的である、望ましい日本語教師養成の在り方を探るという方向性が見られませんでした。日本語教育関係のネットワーク作りにはなっていました。
近畿ブロックが他の地域よりも盛んであるというのが関係者内部の評価のようですが、田尻が見る限り、これでは他の地域には全く期待できないのではないかと心配になりました。がんばっているブロックもあると信じています。
なお、今回も外部評価委員は、「あと4年ある」と言っていましたが、これは前回の「未草」で触れたように間違いです。どうも外部評価委員は、全員間違った情報で評価をしているように見受けられます。
5. EPA看護師・介護福祉士国家試験の結果公表
2025年3月24日に、厚生労働省医政局からEPA看護師、社会・援護局福祉基盤課からEPA介護福祉士の国家試験の結果が公表されました。
インドネシアとフィリピンの看護師候補者はそれぞれ10人と11人受験して、合格者は、ゼロでした。ベトナムの候補者は13人受験して8人合格でした。
日本語教育関係者でEPA看護師に関わっている人たちは、この結果をどう受け取っているのでしょうか。
介護福祉士の試験結果については、初受験と再受験の合計数を示します。
インドネシアの介護福祉士候補者は649人受験して237人合格で、合格率は36.5%です。
フィリピンの介護福祉士候補者は487人受験して111人合格で、合格率は22.8%です。
ベトナムの介護福祉士候補者は178人受験して150人合格で、合格率は84.3%です。
相変わらず、ベトナム方式での養成システムが効果的です。
6. 技能実習法による処分の大幅な増加
2025年3月25日に法務省と厚生労働省から公表された技能実習法に基づき認定取り消しを受けた機関は、過去最高になりました。
特に大きいのは、業界首位の今治造船で2,134件です。因みに、2024年度の取消しは1,240件ですので、今治造船の事例がいかに大きいかが分かります。
技能実習法の規定では、今後5年間技能実習生の受け入れはできず、現在受け入れている全ての実習生は他社への転籍ということになります。
※今回は、当初予定していた最新の情報をかなり扱えなくなってしまいました。「未草」の読者は、自分で情報を集めてください。状況は、大きく変化しています。
現在、アメリカのトランプ政権では、DEI(DiversityとEquityとInclusionのことで、日本語では多様性、公平性、包摂性を示します)の見直しが行われています。外国人の受け入れにあたっては、このDEIが三つとも大事です。日本語教育関係者は、この動きにもっと敏感になってほしいと思っています。日本国内でも、アメリカと同じ動きが始まっています。近畿ブロックでの石川さんの説明では、多様性しか触れられていませんでしたので、田尻はもっと日本語教育の置かれている立場を理解してほしいと思いました。