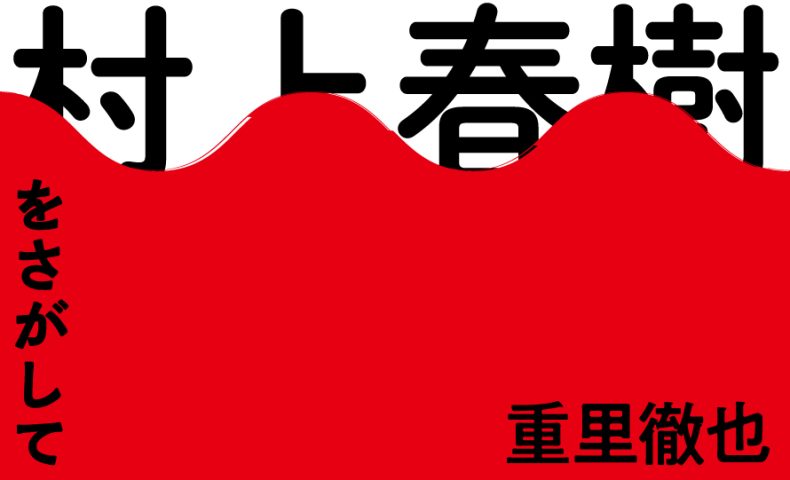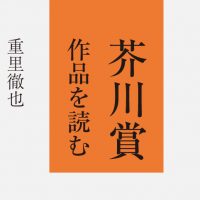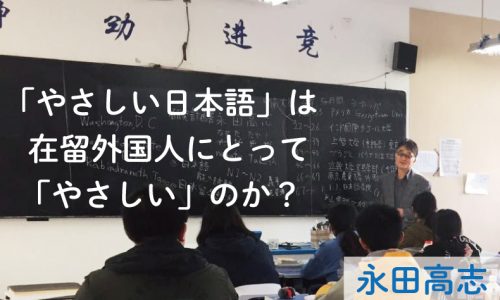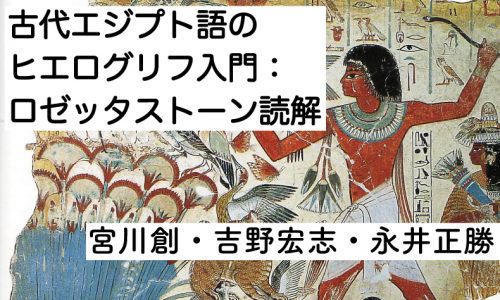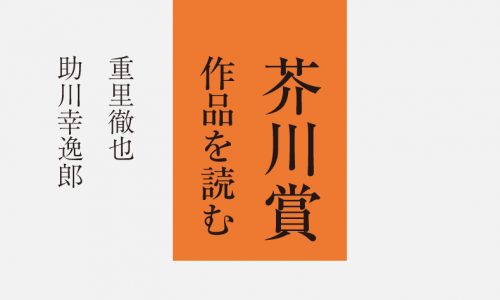村上春樹の小説を読み終わった後、何か解け切らない謎がこちらの心に残ることが多い。魅力的な物語で、とても楽しめて、満足な読書をした実感がある。なのに、振り返ってみると、あれは結局、どういうことだったのだろうと読み落としたものが残っているような感覚に襲われる。
長編にも短編にも、それはあるのだが、長編だと物語のドライブ感に身を任せた後なので、しばらくは謎がうまく整理できない。ところが短編だと、クリアに謎が浮かび上がってくる。それは長い間、心に残り、ふとした瞬間に思い出したり、解けたりすることもある。人の意見を聴いて、意外な答えがわかったような気になることもある。
河合俊雄の新刊『村上春樹で出会うこころ』(朝日選書)を読んで、そんな感覚を味わえた。短編集『一人称単数』(文春文庫)収録の作品を中心に、村上の短編小説を「人と人の出会い」という視点から読み解いた一冊だ。
河合は一九五七年生まれの臨床心理学者。京都大大学院教授などを経て、現在は京都こころ研究所代表理事。という紹介よりも、臨床心理学者で文化庁長官も務めた河合隼雄の長男といった方が、村上の読者にはわかりやすいだろう。
村上と河合隼雄が知り合ったのは一九九四年、アメリカでのこと。二人は志向が合ったようで交流は続き、『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』(新潮文庫)という魅力的な本もある。村上はどんな文芸評論家よりも河合を信頼していた。
私たちも、河合の言葉を読んで、改めて村上作品の深さに気づくことがあった。小説中の描写の表面だけを見て村上を批判する言辞も散見される中、村上の物語を心の深いところで、とらえている感触があるからだ。
河合俊雄も父親の姿勢を受け継いで、村上作品の建設的な読み解きをしている。神経は細かいところに届いていることが多く、村上の愛読者も安心して読めるのではないだろうか。
今回は『一人称単数』に収録されている短編『石のまくらに』を例に挙げて、河合俊雄の解釈に導かれてみよう。
『石のまくらに』は「文學界」の二〇一八年七月号に発表された。当時、村上作品に短歌がいくつも出てくるというので、話題になった覚えがある。こんな物語だ。
「ここで語ろうとしているのは、一人の女性のことだ」という意味深な一文で小説は始まる。村上作品によくあるパターンで、主人公の「僕」が年月を経てから、若き日の自分を回想している。「僕」は大学二年生の十九歳。問題の女性はたぶん二十代の半ばぐらいだったという。
二人とも東京・四ツ谷駅近くの大衆向けイタリア料理店でアルバイトをしていた。彼女が十二月半ばで店を辞めることになり、何人かで近所の居酒屋で軽い飲み会をした。阿佐ヶ谷に住んでいた「僕」と小金井で暮らしていた彼女は一緒に中央線で帰った。(村上の小説には中央線がよく出て来る)。「僕」が阿佐ヶ谷で降りようとすると、彼女が「今日きみのところに泊めてもらえないかな」と小さい声で言った。「小金井までは遠いから」という。(阿佐ヶ谷駅から武蔵小金井駅まで快速で二十分程度。かなり近い)。
それで一夜を共にすることになる。特徴的なことが二つある。一つは彼女が性的エクスタシーを感じた時に、他の男の名前を呼んでしまうかもしれないとことわることだ。彼女はその男がとても好きだ。でも、男は彼女をそれほど好きではなく、ただ、身体を気に入っているのだという。それでも、呼ばれたら、彼女は抱かれに行く。
むなしい一方通行の愛。「僕」は彼女がいきそうになったら、急いでタオルをかませる。彼女は「僕」が知らない、ありふれた男の名前を叫ぶ。タオルを強くかみしめながら。「僕」にも好きなのだけれど、関係を深められない女性がいるのだが、その女性の名前は口に出さず、彼女の身体の中に射精する。(重里注 その女性はあるいは「直子」という名前かもしれない。)
このアルバイト先の年上の女性がかなり、きつい恋愛を生きていることは確かだろう。身体がつながっても、心は出会わない。心の恋愛は不可能なのに、身体は全身で喜びを感じている。ただ、頑丈そうな歯で、「僕」が用意したタオルを思い切り、かみしめるだけだ。
この一夜で、もう一つ特徴的なのは、「僕」の部屋を訪れた女性が短歌を作っていたことだ。関係を持ってから一週間後、彼女が自分の歌集を郵送してきた。歌集といっても、活字印刷した紙を白い凧糸のようなものでとじた薄っぺらな簡易な私家版だった。
現実には二人はもう二度と会わないだろうと二人とも思っている。彼女から歌集を送ってきた封筒には差出人の住所も名前も書かれておらず、手紙もカードも同封されていなかった。歌集は「石のまくらに」というタイトルで、前書きも、後書きもなく、ただ四十二首の短歌が収められていた。ちょっと引用してみよう。
今のとき/ときが今なら/この今を
ぬきさしならぬ/今とするしか
やまかぜに/首刎(は)ねられて/ことばなく
あじさいの根もとに/六月の水
たち切るも/たち切られるも/石のまくら
うなじつければ/ほら、塵となる
短歌の解釈は難しい。小説中の「僕」は歌集中の八首が自分の心の奥に届く要素を持ち合わせていたという。その歌は死のイメージを追い求めていて、それも刃物で首を刎ねられる死だという。
短編『石のまくら』の紹介は終えて、ここからは河合俊雄に導かれよう。河合は村上作品を通時的にみると、出会いのあり方が変化し、深化していると評する。そして、短編集『一人称単数』は出会いについての根本的な要素を繰り返し示しながら、出会いについての様々な異なる局面を示しているという。
短編『石のまくら』について、河合が指摘していることを列挙しよう。まず、「僕」とバイト先の年上女性との出会いが偶然によるもので、なんらロマンティックな要素がないこと。合理的な理由もなく、共同体的な世界が包んでいるわけでもない。河合はこれを「ポストモダン的」と呼ぶ。河合がこの出会いと無差別殺傷(通り魔事件)との共通性に言及しているのが興味深い。「誰でもよかった」という、あれである。置き換え可能なのだ。
次に、彼女と彼女が好きだという男との関係もロマンティックなものではないことを指摘する。男は単に「身体がいい」から、彼女と付き合っている。美しさも、心のありようも関係がない。河合は村上作品では、身体の部分に焦点をあてたメトニミー(換喩)的なとらえ方が目立つという。そして、耳の魅力的なガールフレンドとか、髪の毛が薄くなっている男が好みの女性とか、いくつか登場人物の例を挙げる。人間を全体でとらえるのではなく、一部でつかまえること。なるほど、面白い指摘だ。この見方は日本の近代文学を見渡す射程を持っているように思った。
ポストモダン的な出会い。なんとも、乾燥した人と人の出会いだが、河合はそれにとどまらないのが、前期の村上作品と短編集『一人称単数』との違いだという。それは短歌という芸術作品が二人の関係に介在して、まがりなりにも共有されていることだ。河合はこの短歌のような役割を果たすものを「第三のもの」と呼ぶ。そして、この「第三のもの」は二人に共有されるだけでなく、「二人を包むもの」になるという。またそれは、「垂直的な世界を開き」「垂直的な深まりを通じて二人を結びつける」という。この場合、「垂直」という言葉は特殊な使われ方をしているが、私はその人間の実存に根ざしたもの、といった解釈をしておいた。その人間の生きる理由、生きていく時の根底的な存在の感触とでもいえばいいか。
河合俊雄はこの『村上春樹で出会うこころ』という本の中で、村上作品における「第三のもの」の存在を強調している。私には、それがこの本の最も面白い点だった。そして、この「第三のもの」があれもこれもと思い浮かんだ。『石のまくら』に即していえば、短歌である。二人の人間はポストモダン的に知り合い、肉体関係を持った後で、事後的に短歌を通して心が結ばれた。そうすると、短歌は二人の精神(魂といってもいい)の結晶のように浮かび上がって来る。そこに、人と人が出会う可能性も描かれていることに気づく。もう一度、短歌を読み直したくなってくる。
河合のこの本については、次回も引き続き、取り上げよう。