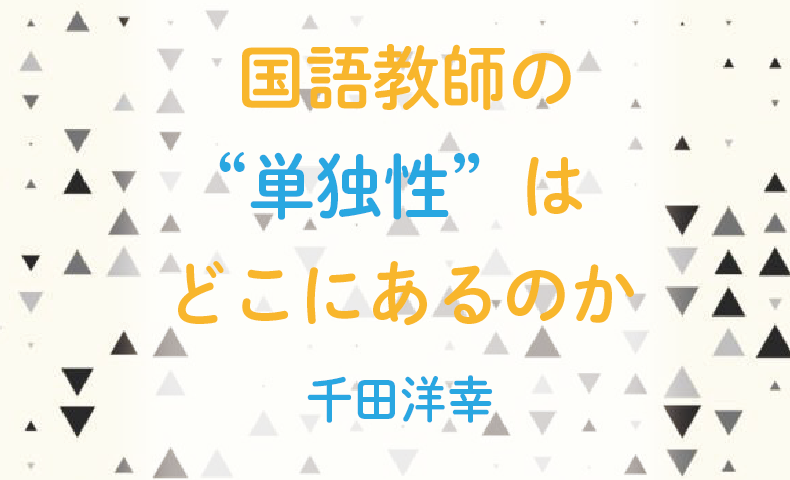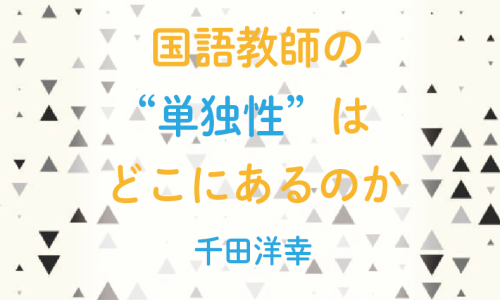いま、2024年のNHK大河ドラマ『光る君へ』最終回を見終わり、出来のひどさに辟易する感情を持てあましながらこの文章を書きはじめている。水準の低い脚本、幼稚な人物造型、存在感のまるでない俳優たちの演技、チープなメロドラマ的展開の醜悪さに憤懣やる方なくなりながら。
しかしふと、なぜ自分はこうも苛立っているのだろうかと思う。娯楽や趣味の一環であるべきドラマ視聴にそれほど感情を逆立てても仕方がないのではないか? だが、国語科教育、近現代文学、現代文化を研究領域とし、さまざまなジャンル/メディアの作品を読みかつ視聴してきた人間にとって、娯楽・趣味と研究の境界など存在しないも同然である。ドラマだろうがアニメだろうがマンガだろうが、純粋な楽しみとしてのみ触れることはもはやありえず、日常的な作品の受容にもつねに解釈と評価の行為がともなう。大げさに格好をつけていえば、それはほとんど「生きること」と同義なのだ。
このような文化経験のあり方は、娯楽は娯楽と割り切ってコンテンツを楽しんでいる人々からは異様に見えるかもしれない。だが、エンタメ系の作品であろうが、それを意識的に「読む」ことは、研究という仕事にたずさわる人間に特有の習性などであるべきではない。一定の知性をそなえた人間として在るからには、現代文化の受容/消費の場でも発揮される汎用的なリテラシーを獲得することをめざすべきだ。娯楽・趣味を堪能する瞬間においても、作品解釈のためのコードを発動させ、歴史、社会、文化の表象形態を読み込み、作品の価値/無価値をきびしく判断する主体であることを望むべきなのである。このとき、「娯楽や趣味の場に堅苦しい『学び』をもちこむのか」という批判は不毛だろう。あらゆるジャンル/メディアに対するリテラシーが要請されるこの時代にあって、快楽的没入と知性的解釈はつねに同時に遂行されるべきなのだ。たんなる好・悪の情動にのみとどまる作品鑑賞、貧しい物語をありがたがる退行した解釈コード、その昔東浩紀が「動物的な消費行動」といささかの揶揄をこめて概念化した「データベース消費」(注1)の亡霊などは、早々に死滅へと追いこむべきなのである。
話題はふたたび『光る君へ』に戻る。この物語の第1話(1月7日放映)で、主人公のまひろに落馬させられた藤原道兼(道長の兄)が怒ってまひろの母親を刺殺するという出来事が挿入された。紫式部の母親が藤原道兼に殺害されるというのはもちろんフィクションであり、いわば歴史の改竄・捏造であるが、そもそもNHK大河ドラマは史実を描くことをはじめから志向してはおらず、歴史をアダプト(翻案)してエンタメとして魅力的な物語を生み出すことに賭けているシリーズである。著名な歴史的人物が登場し、精密な時代考証によって時空間のリアルが保証されさえすれば、どのような世界を創造するかは制作する側の力量にかかっている。今回もそういう手法が踏襲されているわけなのだが、肉親の惨殺を目撃させて主人公に消えないトラウマを植えつける、という作劇法はいかにも旧弊で、初回から脚本の限界が露呈してしまっていた。
古くは斎藤環『心理学化する社会』(注2)で言及されているように、心にふかい傷を負わされた人物をストーリーの中心にすえるのは、1990年代以降の物語ジャンルでしばしば用いられた常套的手法である(典型として、旧版『新世紀エヴァンゲリオン』のキャラクターたちを思い浮かべてみればよい)。そこでは、消えない心の傷が作中人物をさまざまな行動や思考に駆り立てる動力となってゆくが、一方では、斎藤環が「いまや「トラウマ」とは、誰もが持つことができる極小の物語なのだ。政治にも思想にも、みずからの「実存」を仮託するようなリアリティが感じられないとき、ひとはより断片化、細分化された物語にしがみつくほかはないのではないだろうか」と語る通り、物語そのものが個の世界に内閉する結果ももたらす。そういうあり方が果たして『光る君へ』の主人公にふさわしいのか。私自身は、『光る君へ』のドラマ化が発表されたとき、権力と策謀がうずまく貴族社会のなか、ひとりの女性が物語作家としてしたたかに生き抜いてゆくプロセスが描かれるものと期待していたのだが、第1話での悪い予感は的中し、以後はまひろと道長の矮小かつ陳腐なメロドラマが延々と展開される愚作と化してしまった。
『光る君へ』の脚本は、『ふたりっ子』(1996年)『セカンドバージン』(2010年)などの話題作を手がけた大石静で、ドメスティックなストーリーを制作する際にはそこそこ優秀なシナリオを生み出していたが、平安朝の政治、社会、文化のダイナミズムとともに女性作家の自己形成の物語を描き出す力量はもちあわせていなかったようだ。あらゆるクリエーターが、震災やコロナ禍以後、あるいは現在も遂行されている二つの大きな戦争のさなか、虚構を創作する人間としてなにを語りうるのかを模索している現在、かつて大量生産されたトラウマ系主人公や、身分階層の異なる男女のメロドラマなどがアクチュアルでありうるはずもない。その一方で、『源氏物語』の内容を想像させる細部(小ネタ)を適度に作中に散りばめ、歴史学者と文学研究者に秋波を送りつつ、古典文学や平安朝史に該博な知識をもつ視聴者がSNS上で勝手に盛り上がってくれることを期待する。物語の水準を置き去りにしたまま、視聴者のSNS投稿の欲望を煽り立てる――それがドラマ創作の「現代的」手法でありテクニックなのだと思い込んでいるのであろうか?――ことが、この作品を愚作の域にまで転落させている致命的な錯誤なのである。
すぐれた作品をすぐれた作品として解釈し評価する文化リテラシーは、日々視野に飛びこんでくるコンテンツを漫然と受け入れるだけでは得られない。そこではやはり、国語科教育の場が相応の役割を果たす必要があると思う。もちろん、あらゆる学習者にいきなり批評家並みのリテラシーを獲得せよということは無理であるが、生涯にわたって現代文化の豊かさを享受する(あるいは、貧しさを批判的に享受する)主体であろうとするなら、文化的創造物を読み解くコードを一定の水準で所有していることは当然の作法だと考えるべきだ(注3)。小学校国語科で学習されている「伝統的な言語文化」の呼称をなぞっていえば、「現代的な表象文化」のリテラシーの必要性が国語科教育のなかで主張されてよいのである。もちろん、ポップカルチャーのジャンルが多岐にわたる以上、それは美術や音楽の領域でも可能であるが、多くのコンテンツが物語性を内包した上で成立している以上、やはり国語科が主要な立場をになうべきだろう。そのためには、さまざまなポップカルチャー作品を国語教材として扱うこと、すなわち積極的な教材開発への意志が教師の側に必要なのだ(注4)。
* * *
私は大学でアニメを中心としたポップカルチャーの授業を担当しているが、そこではTVアニメの第1話を題材としてしばしば扱う。制作側が時間と労力をかけて作るということもあり、第1話にはその作品の根本的な思想や手法がすでに表現されていることも多い。もちろん作品の選択は慎重に行われる必要があるが、アニメ第1話の考察は、中学校・高校もふくめ、十分に授業で展開可能だと思う。
ひとつの例として、周知の作品『鬼滅の刃』(原作2016年~2020年/アニメ版2019年~)のアニメ版第1話とそれ以降を取りあげてみよう。第1話「残酷」のあらすじは以下の通りである。
時代は大正時代。竈門炭治郎は、亡き父親に代わって炭焼きで生計を支えつつ、家族とともに山で平穏に暮らしていた。ところがある日、町に炭を売りに出かけた炭治郎が家に戻ると、家族はみな血まみれになって死んでいた。ただ一人、妹の禰豆子(注・「禰」は作中では「ネ+爾」)のみまだ息があり、炭治郎は彼女を背負って医者のもとに向かうべく、雪山を必死で駆け下りた。
その途中、禰豆子は突然鬼と化して暴れ出し、炭治郎に襲いかかった。実は炭治郎の家族を襲ったのは鬼であり、禰豆子は傷口に鬼の血を浴びて自分も鬼となってしまったのである。そこに鬼狩りの冨岡義勇が現れ、禰豆子を殺そうとする。しかし、自分の身を犠牲にして禰豆子を助けようとする炭治郎の戦いぶり、鬼と化しながらも倒れた炭治郎を守ろうとする禰豆子の姿を見て、冨岡は「こいつらは何か違うのかもしれない」と考え、禰豆子を殺すことを思いとどまる。冨岡は、目を覚ました炭治郎に「狭霧山のふもとに住んでいる鱗滝左近次という老人を訪ねろ」と告げて去る。炭治郎は亡くなった家族を葬り、禰豆子を連れて狭霧山に向け旅立つ。
物語の構造分析に一定の知識をもつ人であれば、このストーリーから、話型分析の古典であるウラジーミル・プロップ『昔話の形態学』(注5)をたやすく想起するだろう。
- 家族の成員のひとりが家を留守にする。
- 主人公に禁を課す。
- 禁が破られる。
- 敵対者が探り出そうとする。
- 犠牲者に関する情報が敵対者に伝わる。
- 敵対者は、犠牲となる者なりその持ち物なりを手に入れようとして、犠牲となる者をだまそうとする。
- 犠牲となる者は欺かれ、そのことによって心ならずも敵対者を助ける。
- 敵対者が、家族の成員のひとりに害を加えるなり損傷を与えるなりする。/家族の成員のひとりに、何かが欠けている。その者が何かを手に入れたいと思う。
- 被害なり欠如なりが〔主人公に〕知らされ、主人公に頼むなり命令するなりして主人公を派遣したり出立を許したりする。
- 探索者型の主人公が、対抗する行動に出ることに同意するか、対抗する行動に出ることを決意する。
- 主人公が家を後にする。
- 主人公が〔贈与者によって〕試され、訊ねられ、攻撃を受けたりする。そのことによって、主人公が呪具なり助手なりを手に入れる下準備がなされる。
- 主人公が、贈与者となるはずの者の働きかけに反応する。
- 呪具〔あるいは助手〕が主人公の手に入る。
- 主人公は、探し求める対象のある場所へ、連れて行かれる・送りとどけられる・案内される。
- 主人公と敵対者とが、直接に闘う。
- 主人公に、標(しるし)がつけられる。
- 敵対者が敗北する。
- 発端の不幸・災いか発端の欠如が解消される。
- 主人公が帰路につく。
- 主人公が追跡される。
- 主人公は追跡から救われる。
- 主人公がそれと気づかれずに、家郷か、他国かに、到着する。
- ニセ主人公が不当な要求をする。
- 主人公に難題が課される。
- 難題を解決する。
- 主人公が発見・認知される。
- ニセ主人公あるいは敵対者(加害者)の正体が露見する。
- 主人公に新たな姿形が与えられる。
- 敵対者が罰せられる。
- 主人公は結婚し、即位する。
「登場人物の機能」に関連する著名な31の分類である。プロップの同書はロシアの魔法昔話を題材とする分析だが、『鬼滅の刃』の物語全体と照合すると、「ニセ主人公」や「即位」などの一部を除き、驚くほど当てはまることがわかる。第1話のみに限っても、主人公(炭治郎)が家を留守にする、敵対者(鬼)が家族に危害を加える、主人公(炭治郎)が贈与者(冨岡義勇)に試され攻撃を受ける、主人公に禁を課す(「妹を太陽の下に連れ出すな」)、主人公(炭治郎、禰豆子)が家を後にする、などさまざまな符合を見いだしうる。
『鬼滅の刃』はそもそも古風な「鬼退治」物語の枠組みを保持しているが、たとえば石原千秋が整理している(注6)物語の四類型(主人公が内→外→内と移動する浦島太郎型、外→内→外と移動するかぐや姫型、主人公が大人になってゆく成長型、主人公が元の場所に戻る退行型)にもしっかり対応している。炭治郎たち鬼殺隊が鬼の世界(那田蜘蛛山、無限列車、遊郭、無限城など)に移動し鬼と戦う物語として読めば浦島太郎型、視点を転換して鬼舞辻無惨ほかの鬼たちが人間の世界に侵入する物語として読めばかぐや姫型、炭治郎が成長する物語ととらえれば成長型、炭治郎が故郷に帰還して元の生活を取り戻す物語ととらえれば退行型となる。要するに、『鬼滅の刃』は、これまで無数に反復されてきたグローバル/ローカルな物語類型をほぼ完璧に踏襲した形で成立しているのだ。
さらにこの作品には、過去にふかい心の傷を負った鬼殺隊隊士や鬼たちが登場し、『光る君へ』と同様、キャラクターのトラウマに依存する旧式の作劇法が駆使されている。同時に、人間と、人間が変身した怪物的存在とが対立するという構図は、すでに古典に属する萩尾望都『ポーの一族』(1972)や永井豪『デビルマン』(1972)等々から『魔法少女まどか☆マギカ』(2011)に至るまで数多く存在し、ある意味で定番の物語といってもいい。炭治郎は、「鬼であることに苦しみ 自らの行いを悔いている者を踏みつけにはしない」「鬼は人間だったんだから 俺と同じ人間だったんだから」「醜い化け物なんかじゃない 鬼は虚しい生き物だ 悲しい生き物だ」(アニメ版1期21話/原作43話)という認識をもち、彼の剣に倒された鬼は、人間だった時代に抱えこんだ怨念を昇華させながら死にいたる。いったん怪物に変身してしまった鬼を、もう一度人間世界に帰還させることが炭治郎の役割である。すなわち、この作品におけるトラウマ経験の表象は、鬼たちに個別のエピソードを刻み込むとともに、鬼を人間に復帰させ癒しをあたえる炭治郎のケアラー的役割を顕在化させ、正当化するための作劇術の一環なのだ(注7)。
こうして、『鬼滅の刃』は、多くの読者にとってすでに共通理解となっている要素を過去の作品から導入しつつ、通俗的人間中心主義のイデオロギーによって物語世界を塗りつぶし、「正義」の勝利やハッピーエンドの結末でなければ満足できない視聴者・読者を籠絡する。煉獄杏寿郎の「老いることも死ぬことも 人間という儚い生き物の美しさだ」「己れの弱さや不甲斐なさにどれだけ打ちのめされようと 心を燃やせ 歯を食いしばって前を向け」(アニメ劇場版「無限列車編」/原作63話)などといったセリフについ感動してしまう視聴者・読者が相手ならば、その程度のことはたやすいだろう。
そうすると、『鬼滅の刃』がメガヒットした要因のひとつが推測可能となるだろう。視聴者・読者が安心して受け入れられる類型的・典型的なストーリーに、味方と敵のキャラクターの豊富なヴァリエーションを用意し、要所には抜け目なく、感傷的な人間中心主義にもとづいた「泣ける」場面を配置する。わかりやすい物語、わかりやすい世界構造、わかりやすい感動を具備し、一方では聖地巡礼やコスプレといった身体を動員する快楽を提供し、またSNSにおいて愛読者が相互にかわす大量のコミュニケーションを誘発する。稲田豊史『映画を早送りで観る人たち』(注8)で使用されている言葉をかりれば、「幼稚な観客」「思考を止めている観客」の「バカでも言える感想」がSNS上で蔓延するわけだ。『鬼滅の刃』は、物語の話型を学ぶための好材料であるとともに、文化コンテンツに対する日本人のリテラシーの低下を露呈させているという意味で、文化受容の現状と、それを克服するための方向性を考えるための格好の教材となりうる――すこしばかり皮肉をこめた言い方をすれば、そういうことになる。
* * *
今回はいささかネガティブな事例にこだわってしまったのではないかと反省している。また連載中に教材について言及する機会があったら、もうすこし可能性のあるテクストについて考えたい。だが、かりにポップカルチャー作品を教室で扱いうるとして、そこで前提とすべき教材価値とはなにか――といえば、月並みではあるものの、やはり作品が生成する物語内容であり、思想であり、「テーマ」であると考える。もちろん、メディアリテラシー、マルチモーダルリテラシーの教材としてアニメやマンガを導入することは可能であるし、その実例も多いが、現状の社会におけるメディアリテラシーは、ネットあるいはSNS上でのヘイト、フェイク、ネットリンチ、プロパガンダなどを批判的に読み解く作業の方に傾注するべきだ。ポップカルチャーを教材化する試みは、過去の文学教育に匹敵する、あるいはそれを凌駕するストーリーと思想に出会うことをめざすべきだと思う。
こういう話題にふれるとき、日本映画の「主題」の欠落について、蓮實重彦をこき下ろしながら語った柄谷行人の発言(注9)を、いささかの苦笑とともに想い起こす。今回の話題のついでに引用しておこう。
僕は映画をよく見るけど何もいわない。しかし、日本の映画についてしゃべってくれと頼まれて、1回しゃべりに行ったことがあるんですよ。三年ぐらい前かな。そのときに、日本映画は主題が抜けているといいましたね。
例えば台湾の侯孝賢『悲情城市』を見たときに、このひとははっきり主題をもっていて、この映画で台湾の運命を描いている。天皇が敗戦の演説をしているときにオギャーと産まれる私生児が台湾です。監督自身は本土から来た外省人だけど、ネーションとしての台湾の形成を描こうとしたわけです。(中略)とにかく、彼の主題は明白です。僕がその映画を見に行ったときに、パンフレットみたいなのを見たら、蓮實重彦が、ここのアングルは小津の引用だとか、そういうことしか書いてないんですよ。
監督は明らかに、そのような主題なしにこの映画をつくらなかっただろう。技術的な問題は映画監督なら当たり前のことですよ。しかし、蓮實重彦は主題などを見るのは素人だ、俺はそんなバカではないという感じで書いていた。しかし、アングルがどうのこうのなんて、そんなもの映画をつくっている人間から見たらカスみたいな話ですよ。素人が映画を見まくって覚えた程度の技術論なんか関係ない。みんな苦労しているから、それぞれに技術をもっていますよ。批評家がそんなことを得意そうにいう筋合いはない。小説でも同じことですが。日本の映画がなぜだめかというと、主題がないからだ、あんなカスみたいな趣味的評論は全部否定しろ、主題をもつ以外に日本の映画は復活できない、と僕はいいました。小説も同じですよ。(中略)
根本的に主題がなかったら、ろくな映画はつくれない。主題を否定することで逆に何かをやっているかのように見えるとしても、多くの場合、そんなものはたんに、何もないだけ、です。
映画批評における蓮實の功績についてはいまさらいうまでもないが、ここでは柄谷の言い分を肯定しておくことにしよう。多くの国語教師が「活動中心でなければならない」という強迫観念に囚われている現在こそ、「主題」という旧来の概念を復活させるべきなのかもしれない。どんなにすぐれた文学、映画、あるいはアニメやマンガ……を教材化したとしても、そこに「主題」への視点がまったく欠落していたなら、「何もないだけ」の授業に終わらざるをえないからだ。
(注1)東浩紀『動物化するポストモダン――オタクから見た日本社会』(2001 講談社現代新書)
(注2)斎藤環『心理学化する社会――なぜ、トラウマと癒しが求められるのか』(2003 PHPエディターズ・グループ)。
(注3)だから、「つまらない授業」を「楽しい授業」にするためにポップカルチャー教材を導入するべき、という消極的な考え方には賛同できない。ポップカルチャーのリテラシーは現代社会で要求される重要な能力であり、だから学校での学習可能性を追究すべきである、というポジティブな立場を採るべきだ。
(注4)すでに知られているだろうが、この方面で奮闘している町田守弘の著作を紹介しておこう。『「サブカル×国語」で読解力を育む』(2015 岩波書店)、『学校教育におけるマンガの可能性を探る』(共著、2018 学文社)、『国語教育を楽しむ』(2020 学文社)、『サブカル国語教育学――「楽しく、力のつく」境界線上の教材と授業』(編著、2021 三省堂)。
(注5)ウラジーミル・プロップ『昔話の形態学』(原著初版1928、日本語訳1987。北岡誠司・福田美智代訳 水声社)。
(注6)石原千秋『読者はどこにいるのか――書物の中の私たち』(2009 河出書房新社)。
(注7)少々余談となるが、人間だった時代にまったくトラウマ経験をもたない童磨のような鬼も存在する。黒木朋興が「童磨のサイコパスの性格の核心とは、嬉しいとか楽しいとか苦しいとか辛いとかという感情を感じる回路がないこと」(「キリスト教の悪魔と『鬼滅の刃』の鬼」『頸城野郷土資料室学術研究部研究紀要』8-2 2023.4)と指摘するように、童磨は人間の感情を俯瞰しつつ徹底的に侮蔑の対象としており、それ故に作品を支配する凡庸な人間中心主義からまぬがれている。鬼舞辻無惨ですら消滅の間際、炭治郎に「私の意志を 思いを 継いでくれ お前が!!」などと口走ってしまうことからすると、童磨こそが「鬼の中の鬼」であるといえるだろう。
(注8)稲田豊史『映画を早送りで観る人たち ファスト映画・ネタバレ――コンテンツ消費の現在形』(2022 光文社新書)。『鬼滅の刃』について言及されている部分があるので引用しておこう。
ライトノベル原作ではないものの、序章でセリフが説明過多であると指摘したTVアニメ版『鬼滅の刃』については、小林氏(注・脚本家の小林雄次)も脚本家の卵たちも、「絵で見てわかることがそのままセリフになっている」点において違和感が強い、と口を揃える。
「僕がシリーズ構成をやっている作品でもしあの脚本があがってきたら、会議で必ず『ちょっと説明過多じゃない?』って言います。あそこまで説明しなくても原作の良さは十分出せると思うので」(小林氏)
具体的にはどうするのか。
「落下した炭治郎が雪のせいで助かったくだりをそのまま生かすにしても、せめて落ちた瞬間は周囲の状況を見せない。足を滑らせた炭治郎に『落ちた、僕はもうダメだ。死んでしまう!』みたいな表情をさせたあと、ドサッと落ちて『あれ? 助かってるぞ、なんでだ?』となってから初めて周囲の雪を見せる。そこで初めて『そうか、雪のせいで助かったんだ……』と気づかせる。そんな風に間や緩急をつけたいですね。『助かった、雪で』というセリフのみで済ませてしまうと説明でしかないのですが、説明をドラマにするのが脚本家の仕事です」
(注9)柄谷行人と村上龍の対談「時代閉塞の突破口」(柄谷行人・浅田彰他著『NAM生成』2001 太田出版)より。