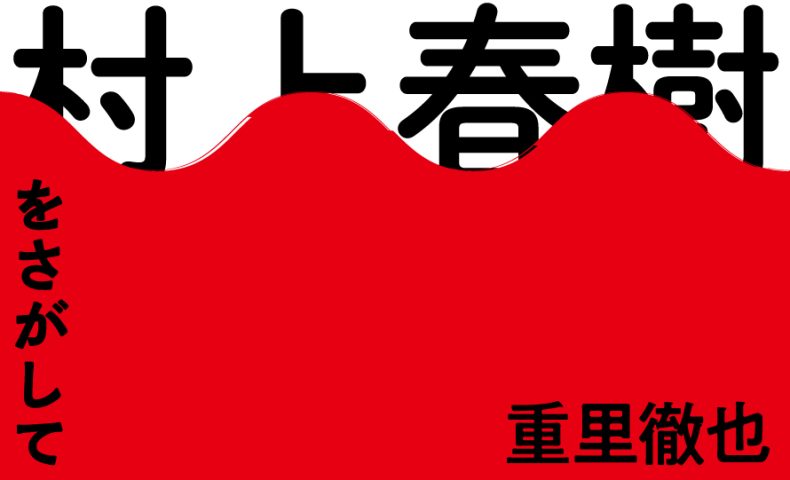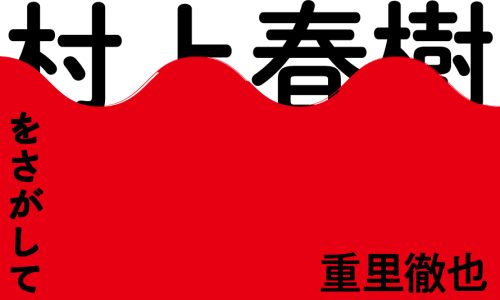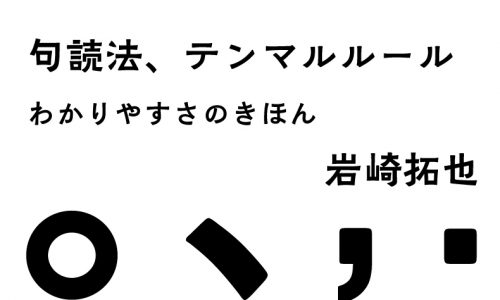司馬遼太郎がこんなことをいっていた。どんなに人工知能が発達しても、なかなか解けない人間の謎がある。それは恋愛と権力だ。この二つは最後まで小説のテーマとして残るだろう。
以前に読んだ文章を思い出しながら、私流に翻訳しているので、正確ではないかもしれない。ただ、恋愛(乱暴にいいかえれば、セックス)や権力(いいかえれば、政治)が人間という存在の闇で、なかなか論理的には解明できないというのは納得できそうな考えで、記憶に残っている。
司馬は後者の正体について、自分は日本史を主なフィールドにして生涯をかけて追求してきたといいたかったのかもしれない。私なら、これに犯罪や信仰も加えて、人間のブラックボックスと呼びたいところだ。
ある対象を殺すか(新しい一歩を踏み出すか)どうか迷うとき、あるいは、絶対的なるものの存在を信じるに至るとき、その決断には非合理的な部分も含まれているのではないだろうか? それも、闇と呼びたい気がする。
そんなことを思い出したのも、村上春樹の新しい訳でカーソン・マッカラーズの小説『哀しいカフェのバラード』(新潮社)を読んだからだ。読了後、すぐにもう一度、読み直したくなる本だった。小説の謎が、人間という存在の謎を貫いていた。
カーソン・マッカラーズ(一九一七~一九六七)はアメリカの女性作家。村上の「訳者あとがき」などによると南部ジョージア州コロンバスに生まれた。ピアノに才能を現し、ニューヨークのジュリアード音楽院に進むが、授業料を失くして入学を断念した。コロンビア大学の夜間部で小説創作を学んだ。
二十三歳で小説家デビュー。「天才少女」と絶賛され、ウィリアム・フォークナー、トルーマン・カポーティ、フラナリー・オコナーらとともに戦後の南部作家ブームの一翼を担った。しかし、いくつかの持病、アルコール依存症、同性愛に由来するトラブルなどで創作力が後退したという。
村上春樹はすでにマッカラーズの長編小説を『心は孤独な狩人』『結婚式のメンバー』の二作翻訳しており、いずれも新潮文庫で刊行されている。それに加えて、この『哀しいカフェのバラード』を翻訳して世に問いたいと希望していたという。何がそこまで村上の心を引きつけるのだろうか。
こんなストーリーだ。舞台はアメリカ南部のうらぶれた田舎町。長身で頑丈な身体を持つ独身のアミーリアは町で雑貨店を経営しながら、酒を製造したり販売したりし、医療行為でも評判を呼んでいる。万能感のある力のあふれる女性だ。
一人の背中の曲がった小柄な男が店を訪ねてくるところから、物語が動き出す。この男が意外にもアミーリアの心をとらえ、二人は一緒に暮らすことになる。雑貨店はカフェになり、町の人々の憩いの場所としてにぎわう。
実はアミーリアは以前に十日間だけ結婚していたことがあって、相手の男をひどい目に遭わせたことがある。この男は罪を犯して刑務所に入っていたが、出所してこの店を訪ねてくる。このハンサムな男は背中の曲がった男に異様なパワーを発揮して(同性愛がからんでいるのだろうか)、アミーリアとの仲を裂き、アミーリアにかかわるものをすべて破壊して町を立ち去っていく。この男とアミーリアとのすさまじい衝突は作品のクライマックスだ。
このように紹介しただけでも、救いのない物語だとわかるだろう。なぜ、この小説がそれほどに心に重いものを残すのだろうか。それは人間という存在を恋愛(セックス)と暴力という二つの側面からむき出しにしているからだろう。この物語が哀しいのは、人間がとことん哀しい動物だからだろう。
村上は「この三人はそれぞれに深い欠落を抱え、業を背負い、矛盾に苦しみながらも、暗闇の中で必死にそれぞれの愛を求めていたのだ」「その求め方の真摯さこそが、たとえそれが間違った悲劇的な方向に進むことになったとしても、この小説の確かな核心であった」と記している。
私は、村上が自作のいくつかについて語っている言葉のようにも感じた。救いはないが、愛を真摯に求める心のあり様。愛の檻に自ら進んで入っていく人間という存在。そこが読んでいるこちらの心に響くのだろう。
本には山本容子の銅版画が多く掲載されている。村上自身が装画を依頼したという。山本の絵はシンプルな線が魅力で、この救いのない、かたくなな閉じた小説を少し開くことに貢献している。それは小説世界を私たちに身近なものにしている。そう、つい自分の周囲でも、これほど極端な形では表れないものの、こういうことはしょっちゅう起こっているのだ。