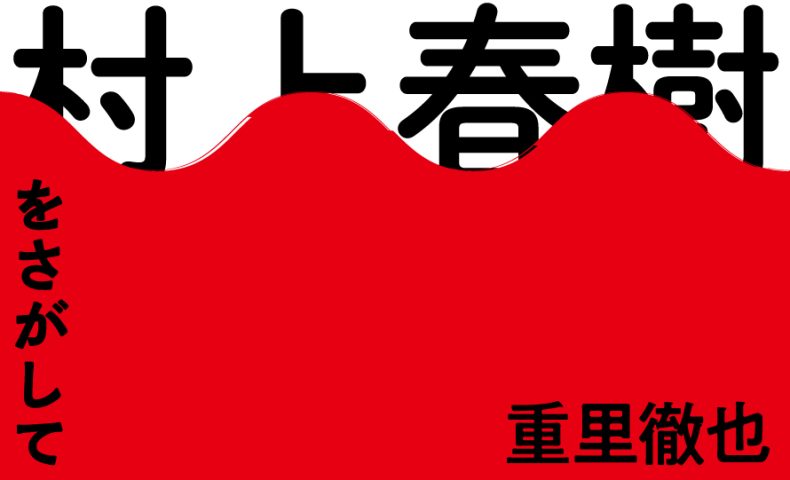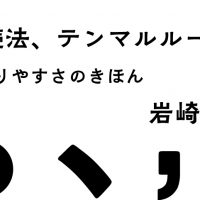三島由紀夫に『夏子の冒険』という長編小説がある。この作品と村上春樹『羊をめぐる冒険』とを比較する議論がある。村上作品が三島作品の影響を受けたかどうか、断じるのは難しい。しかし、両作品を比べることは、三島と村上という二人の作家の相違を考えるうえで、とても興味深い。
『夏子の冒険』(以下、『夏子』)は「週刊朝日」の一九五一年(昭和二十六年)八月五日号から十一月二十五日号に連載され、朝日新聞社から刊行された。私は角川文庫で読んだ。とても読みやすい小説で、それだけに三島の特徴がよくうかがえるようにも思う。こんな物語だ。
主人公の夏子は二十歳の女子大生。裕福な家に育ち、美人で大勢の多様な男たちが彼女の周囲に群がる。しかし、彼らに自分に見合う情熱を見いだすことができず、突然に北海道函館の修道院に入ると言い出す。
函館へ向かう旅の途中で、輝く目を持つ、猟銃を背負った青年に出会う。実は彼は熊に襲われて死んでしまった恋人のかたきを討つために、その熊を狩りに北海道へ行くのだという。青年の話に感動した夏子は、無理やりに彼に同行する。青年は熊を仕留めることに成功する。ところが東京への帰路、通俗的な日常の夢を語り始める青年に幻滅して、夏子は「やっぱり修道院へ入る」と言う。
ポイントを二つ挙げよう。
一つは、「熊」という目標がある青年が輝く目をしていることだ。育ちのいい美人の夏子に惹かれる男たちには、青年の熊に対するような情熱を傾ける対象がない。せいぜい、カネを稼ぎ、マイホームを建て、ゆとりのある満ち足りた生活をしたいだけだ。その彩りとして夏子のことを考えている。
しかし、青年も熊を仕留めた瞬間に、目の輝きを失ってしまう。そして、凡百の男たちと同様に、どこかの商品カタログに載っているような、退屈で世俗的な夢を語り始める。そんな青年に夏子は全く魅力を感じない。
もう一つのポイントは「修道院」だ。世俗と切り離された聖なる異界として、修道院はこの小説で描かれている。ある絶対的な存在(神)に仕えることで、日常を脱して、永遠なるものとともに暮らすということだろう。
夏子の心の片隅には絶えず、修道院が存在している。そして、修道院は日々の生活の中で異物として静かに自己を主張している。修道院での具体的な生活が描かれるわけではない。しかし、神という絶対者に仕える生活が、戦後日本の日常とは全く違う別物として、この小説の最初から最後まで、読者の視野に入るように仕掛けられている。
一方、村上春樹の『羊をめぐる冒険』(以下、『羊』)について考えてみよう。この小説は村上にとって三作目の長編小説になる。「群像」一九八二年(昭和五十七年)八月号に一挙掲載され、講談社から刊行された。現在は講談社文庫で読める。
このようなストーリーだ。主人公の「僕」は二十九歳。友人と広告代理店を経営している。ある日、右翼の大物の秘書から呼び出され、星印のついた特殊な羊を探すように脅される。その羊は右翼の大物の超人的な能力の源だという。「僕」は耳のモデルをしている女性と北海道へ行き、問題の羊を探す。やがて、十二滝町にある富豪の別荘へたどり着く。
そこで「羊男」と出会い、親友の「鼠」と対話する。実は「鼠」は羊に憑かれたまま、自殺していた。「僕」が別荘から出ると、右翼の大物の秘書が待っていた。秘書は「僕」に多額の小切手を与え、別荘に向かう。「僕」は鼠に依頼された通り、別荘を爆破する。「僕」は故郷のバーを訪れて、小切手をバーの主人に渡し、無残に埋められてしまった海辺にかろうじて残る砂浜で二時間泣いた後、立ち上がる。日常に戻るのだろうか。
三島の『夏子』と村上の『羊』がよく比較されるのは、ストーリーを振り返っただけでも理解されるだろう。両方とも若い主人公が、動物を追って東京から北海道へ行く。それは日常から離れた非日常への冒険だ。両作品とも、獲物はみつかり、仕留められる。そして、主人公たちは世俗の地上的な日々に帰ってくる。
相違も明らかだ。『夏子』の主人公はいつも聖なる異界にあこがれ、なんとか、この日常を超えた世界へ行けないか、志向している。ある絶対的なもの、永遠なるもの、それは多分に神秘的なものを求め続けている。それと一体化したいと考えている。そして、そこにはたどり着けない。
『羊』の主人公たちは真逆だ。星印のついた羊に象徴される絶対的な権力、圧倒的なパワーを忌避し、目の前の一杯のビールを大切にする。日常をいとおしみ、日々を大切にする姿勢がここにはある。羊を屠るために、親友の鼠は自らの命を犠牲にする。
こんなふうに並べてみると、随分と図式的だが、三島と村上の違いがよくわかるだろう。非日常的な神秘を追い求める三島と、そんなものの誘惑を拒否して、日々の生活をいとおしむ村上。
『羊』の冒頭近くで三島由紀夫自身が登場する。「一九七〇年十一月二十五日のあの奇妙な午後」と書き出される章があり、「僕」は女の子とICU(国際基督教大学)のラウンジにいる。そのテレビで、自衛隊市ヶ谷駐屯地で割腹自殺した三島のニュースが流れている。
音声はほとんど聞き取れなかった。しかし、「僕」は「我々にとってはどうでもいいことだった」と思う。三島に対する拒絶感を主人公があらわにしたシーンで、「群像」で初読して以来、記憶に残っている。
来年は生誕百年ということで、三島由紀夫がさまざまに論じられることだろう。村上という場所から三島という作家を眺めるのは、私にはかなりしっくりとくる方法だ。