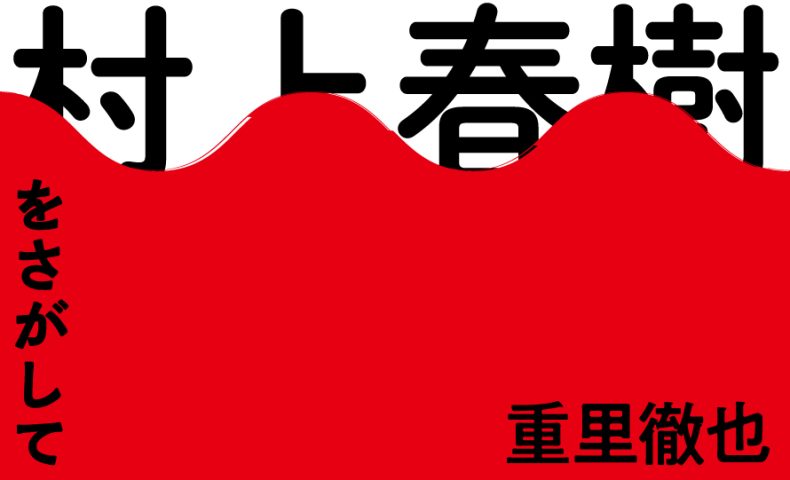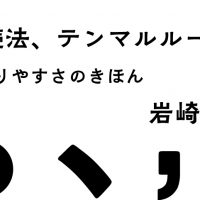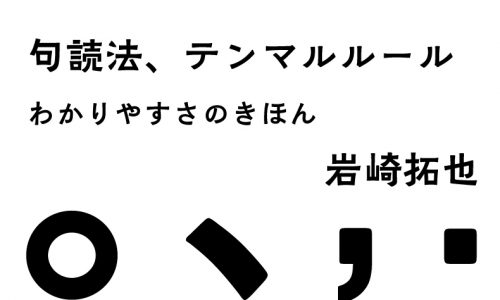二十歳の誕生日に、私は何をしていただろう。一九七七年秋。一浪して、やぶれかぶれで入った大学で、あまり熱の入らない日々を送っていた。ロシア語の授業が週に六コマあったが、難しさを痛感するばかり。がむしゃらに勉強することもなく、かろうじてついていく感じだった。
誕生日に何をしていたのかも覚えていない。織田作のまねをして、革ジャンパーを着て大阪・ミナミをほっつき歩いていたか。家庭教師をしていた中学生に英語を教えていたか。自分がどう生きていくのか、まったく展望がなく、水が流れるのを川岸から見るように、日々が過ぎていくのを眺めていたのではなかったか。
柄にもなく、そんなことを考えたのは、村上春樹の短編小説『バースデイ・ガール』を再読したからだ。村上の六つの短編を原作にしたアニメ映画「めくらやなぎと眠る女」(ピエール・フォルデス監督)が公開されるのをきっかけに、原作の一つである『バースデイ・ガール』を読み直したのだ。
この小説は書き下ろしで短編集『バースデイ・ストーリーズ』(二〇〇二年、中央公論新社)に収められた。この本は今では「村上春樹 翻訳ライブラリー」の一冊として、同じ版元から刊行されている。
誕生日をめぐる、さまざまな短編から成る一冊だ。収められている小説は、『バースデイ・ガール』以外、すべて海外の作家によるもので、村上が選んで翻訳している。本人によれば、「最後のおまけというべきか、蛇足というべきか」、自ら一編を書き下ろして収録したという。
そうはいうけれど、抜群に面白い。村上作品らしく、謎に満ちていて、その謎を解こうとすると、深く読み込んでしまうという仕掛けがされている。
こんな物語だ。
小説の全体は、三十歳を過ぎた女性が自身の二十歳の誕生日に起きた出来事について、「僕」に語っているという設定になっている。中年の入り口から、青春の決定的な出来事を振り返る。村上の作品によくあるやつだ。たとえば、『ノルウェイの森』もそうだった。
「僕」が誰なのかはわからない。作家自身と思わせるようにも書かれているが、小説の読み方としては早計だろう。まあ、確かに男性のようなのだけれど。
女性は二十歳の誕生日に、普段と同様に東京・六本木のイタリア料理店でウェイトレスのアルバイトをしていた。高校時代からずっと交際していたボーイフレンドと数日前に深刻な喧嘩をしたばかりだった。同僚のアルバイトの女の子は風邪をこじらせていて、自分が仕事に出るしかなかった。
その日、店のフロア・マネージャーが急な腹痛で倒れてしまい、彼以外に誰も姿を見たことがないオーナーに、彼女が夕食を運ぶことになった。彼女はオーナーから年齢を尋ねられて、その日が誕生日であることを打ち明ける。オーナーは誕生日のプレゼントに一つだけ願いをかなえてあげよう、と言う。彼女はためらいながら、一つの願い事をオーナーに話す。
小説の中で、彼女の願い事は明かされない。オーナーは「君のような年頃の女の子にしては、一風変わった願いのように思える」と返す。彼女の願い事は、もっと美人になりたいとか、賢くなりたいとか、お金持ちになりたいといったことではなかったからだ。
思い出話を聴いていた「僕」は彼女に二つの質問をする。「その願い事はかなったのか」「願い事としてそれを選んだことを、あとになって後悔しなかったか」
彼女はこの二つの問いにはっきりとは答えない。そして、謎めいた、しかし、村上の思想の核心のようなことを話す。
「人間というのは、何を望んだところで、どこまでいったところで、自分以外にはなれないものなのね」
そんな物語だ。
彼女の言葉に、その通り、と同意するか、やれやれ、とため息をつくか、そんなことないだろう、と反論するか。人はいろいろだろう。ただ、これが村上作品にひかれるかどうかを分ける岐路のような気もするが、どんなものだろう。
私の考えはこうだ。彼女の願いは「充実した人生が送れますように」とか、「意味のある人生が送れますように」とか、「後悔しない人生が送れますように」とか、「生き生きとした人生が送れますように」といったことではなかったか。
そして、そのためには、自分自身の人生を精一杯生きるしかないのだ、ということなのではないか。自分を百パーセントに生きるしかないのではないか。今はそう考えているのだろう。
あなたは二十歳の誕生日に何を願うか。あるいは、何を願ったか。作品は穏やかにそれを問いかける。そんなふうに私は読んだ。私は二十歳の誕生日に何も願わなかったし、今さら、そんなことをきかれても、戸惑うばかりなのだけれど。