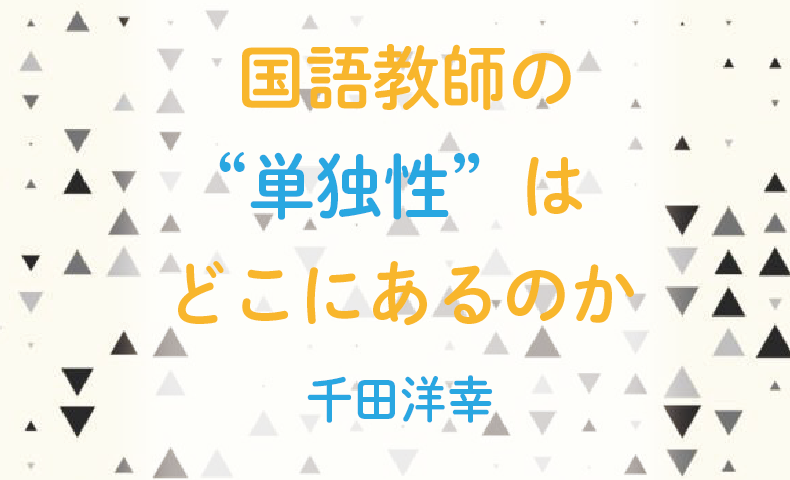前回は、学校教育・教科教育の場に蔓延する子ども中心主義こそ、棄却されるべきイデオロギーであることについて語った。このことは、「子ども好き」であることが、教師の職務の必要条件ではないということをも意味する(もっとも、子ども嫌いの人はそもそも積極的に教職を志望しないのだろうが……)。世のなかにはもしかすると、「自分は子どもに愛情をもっていないのかもしれない」などと真面目に悩んでいる教師がいるのかもしれないが、そのような不安をかかえる必要はまったくないということだ。教師に必須の資質とは、すぐれた教科の研究者―実践者であることであって、それは子どもへの愛情の多寡とはかならずしも一致しない。むしろ子どもへの過剰な意識に支配されることは労働の不健全さに直結する、ということは前回も強調した通りである。
それでは、教科の専門性を形づくるべき基盤とはなにか、という話題にもうすこしとどまり、とくに私個人の研究的関心の中心でもある教材の問題に触れながら、今回の考察を進めていきたいと思う(注1)。
とはいえ、コンピテンシー・ベース優勢の、あるいはコンテンツ・ベース批判の風潮のなかにあって、教材の問題をいまさら取りあげることはいささか古風な姿勢に見えることだろう。だが、国語科教育研究の理論の多様化が推し進められている(ように見える)状況にあって、国語教師の能力の源泉であるべき教材解釈の力は衰弱の方向へむかっているのではないか、と私は考えている。
たとえば、国語科教育研究の理論的な「確立」をめざす文脈のなかで語られた、つぎのような言説がある。
……コンテンツ・ベース批判においては、コンテンツを提供する「親学問」が問題視されることになる。国語科教育における「親学問」は、教育職員免許法的に言えば、国語学・国文学・漢文学・書道である。これらの学問と国語教育学は混同(同一視)される傾向にあり、単元学習などに代表される国語教育学の学習者中心主義は拾われることなく、内容主義だと批判される場面も少なくない。まず、国語教育学はこれらの学問とは別のものであることを強く広く発信していく必要がある。
また国語教育学では、上記以外にも、言語学、心理学、社会学、哲学など、諸学問を背景に、「言葉」を探究する。国語教育学を蛸壺型の保守的な領域と見做すことは誤解であるということができよう。
むしろ、諸学問が諸学問のまま、教育実践の場に持ち込まれることに、内容伝達主義や教条主義の根源があることを認識する必要がある。目の前に子どもを置かない諸学問が教育に持ち込まれることが、学習者不在で内容重視の教育を助長していることに、諸学問はもっと自覚的になるべきである。
そして、こうした状況を食い止める役目を果たしているのが国語教育学(教科教育学)である。国語教育学は単なる内容知・方法知ではない。諸学問を教育実践へと翻案するための、臍帯となる理論を構築していく領域が国語教育学なのである。そして、そのためには、ディシプリンが必要である。(注2)
周知の通り、教育職員免許法では、中学・高校国語免許の取得条件として教科に関する科目の履修が定められており、国語学、国文学、漢文学、書道の所定科目が必修となっている。一方で、森が批判するように、そういう「親学問」をベースとした国語科教育の編制はもはや現代の教育にふさわしくないのではないか、という疑義もしばしば提出されている。それはたとえば、教員養成大学のカリキュラムの動揺のような形で具体的に現れ出てもいる。
だが、このような批判は、すくなくとも国語科教育においては的を射ているとはいえない。なぜなら、「諸学問が諸学問のまま、教育実践の場に持ち込まれる」という事態など、ほんの一部の自覚的な実践を除いて、ほとんど存在しないにひとしいからである。現実の国語科の授業は、文学研究や言語学、コミュケーション理論、メディア理論など、隣接する人文科学の尖端とはおよそかけ離れた水準で行われているのが実状であり、前者に後者の研究成果が実現しているなどとは到底いえない。学習者中心主義の名のもとで、学問などとは無縁な、水で薄められた「擬似学問」が授業のベースとなっているのが現実である(その程度の知見でなされた授業準備を、教材「研究」と称することの欺瞞はいうまでもない)。ことは国語教育「学」においても同様であり、たとえば、「読むこと」教育の研究におけるテクスト分析の水準が文学研究のそれを凌駕したことなど一度もない。森は、「国語教育学はこれらの学問(注・国文学など)とは別のものであることを強く広く発信していく必要がある」というが、そもそも両者が「同じもの」であった事実など存在しないのだ。この意味で、国語科教育研究は、「諸学問を教育実践へと翻案するための、臍帯となる理論を構築」するどころか、逆に両者を分断する役割を果たしてしまっている。
国語科教育(研究)がかかえるこうした問題は、歴史的・社会的動態であるはずのテクスト=教材が、授業の場でいっこうに更新されていかないという悪弊ももたらす。定番教材の「山月記」の授業などはそのわかりやすい例だ。この教材の実践史においてよく知られている増淵恒吉「文學作品における形象の問題」(注3)を開いてみると、李徴が虎に変身してしまった理由の解釈、李徴の独白中に出現する「臆病な自尊心」「尊大な羞恥心」への注意喚起、文体の格調の高さの強調、さらには「僕は自分の中に、自己を主張する念が、いかなる場合にも働いているのを意識するにつけ、自己を捨て去ることができずに虎となった李徴に、何か、自分の分身のような感じを受ける」という生徒の感想の誘導に至るまで、古典的な「山月記」実践の読解プロセスがほぼ網羅されていることを確認することができる。そして情けないことに、現在の「山月記」の授業の多くは、約七十年前のこの実践論文とほとんど大差ない内容で行われているのである。
「山月記」の研究史上で重要な蓼沼正美「『山月記」論――自己劇化としての語り」(注4)により、李徴が独白する「臆病な自尊心」「尊大な羞恥心」などの自己語りの言葉を、「彼自身が自分の語る言葉によって捕われていることには気づかず、しかし自己の(悲)劇性だけは限りなく増幅させてしまうという、言わば自己劇化」としてとらえる解釈が示され、李徴が彼自身の過去を正確に語り、誠実に意味を付与しているという素朴な読みはほぼ完全に転倒された。そもそも1980年代以降の語り論の成果を踏まえるなら、物語に登場する語り手が事実のみを透明に語っているなどという認識は成立しえない(その意味で蓼沼による李徴の語りの分析は、1980年代以降の語り論を領導した亀井秀雄、小森陽一、石原千秋などの系譜に位置づく正統のテクスト分析である)。蓼沼論を前提とするなら、「臆病な自尊心」などの言葉を生真面目に考察してきたこれまでの授業はほとんどひっくり返ってしまうはずなのだが、この論を踏まえた実践はほとんど見当たらないし、逆に批判的に取りあげた実践も視野に入らない。もちろん蓼沼論のみをことさら特権的に扱う必要はないが、すくなくともこの七十年間の研究の推移がほとんど実際の授業に反映されないのは異常なことのはずなのに、それを何とも思わない怠惰が常態化しているのだ(注5)。同様に、たとえば「こころ」がたんなる三角関係の恋愛の物語として読まれたり、「舞姫」の一人称・回想・記述という語り形式がまったく無視されてしまったりする授業が、いまだに行われている始末なのである。
教材のリテラシーの欠如という点では、かつて小学校国語科の定番教材だったアルフォンス=ドーデ「最後の授業」が教科書から一斉に消滅した出来事も思い浮かぶ。当時の小学校教師は、蓮實重彦によって提示された「最後の授業」批判(注6)を実践史上の重要な出来事ととらえる視野をもたず、また、「フランス語は、世界でいちばん美しい、いちばんはっきりした、いちばん力強い言葉である」というアメル先生の認識に言語帝国主義の片鱗を見いだす解釈力ももちあわせず、「最後の授業」を国語愛にみちた感動的な教材として遇しつづけるという言語社会学的無知を曝しつづけた。この件に関しては研究者や教科書編集者も同断であり、田中克彦による「言語的支配の独善」「植民者の政治的煽情の一篇」(注7)という明晰きわまりない批判と出会って、あわててこの教材を教科書から引っ込めるという体たらくだった(注8)。教科書教材をめぐるこうした恥ずかしい事例は、他にいくつもあげることができる(注9)。
こうしてみると、過去から現在にわたって国語教材の研究と実践に不足しているのが、国語科教育の外部からもたらされる周辺諸科学の知であることはあきらかだ。たとえば文学教材の授業であれば、その教材の研究史・実践史はむろんのこと、数ある文学理論書の大体の内容ぐらいは踏まえておくのが当然であるのに、多くの教師はそういう基礎作業を行っていない。さまざまな理論的情報をインプットしてみずからの教材解釈のコードを解体・更新し、授業の構想や展開のヴァリエーションを豊かにする努力を怠ると、手垢にまみれた旧式の授業に安住したり、イデオロギーの不公正を逆に価値と判断してしまったりする誤謬におちいる破目となる。
教員養成大学に勤務していて否応なしに見せつけられるのは、この20年ほどのカリキュラム変遷のなかで、授業技法の向上をめざす科目が増加しつづける一方、テクストを徹底的に読解し議論の対象とする科目と時間が大幅に削減されていること、そして知識と教養の蓄積という教師にとって当たり前の努力が軽視されつつある傾向だ。このことは、国語教師の能力の不可欠な基盤となる読解力の衰弱を招き、長期的には教科書教材(特に「読むこと」教材)の水準の低下を引き起こす。コンピテンシー重視の風潮や、いまだに強固な子ども中心主義のイデオロギーがそういう傾向に拍車をかけている。
国語科の授業あるいは論文等における過剰な(?)研究的志向への批判として、「学習者を文学研究者にするわけではない」とか、「学習者を言語学者にするわけではない」といった言葉が時おり聞こえることがあるが、これなども浅薄な教材研究が跋扈する現状を示す一例だろう。もちろん、国語の学習者たちのすべてが言語学者や文学研究者をめざす必要はない。だが、かりにも国語教師を名乗るのなら、文学や評論文の授業では学習者を文学研究者や批評家に、文法の時間は学習者を文法研究者に、漢文の時間は学習者を中国古典研究者に育てるつもりで、教えるのが当然ではないのか。「国語の良き担い手を育てればいいのであって、研究者を作りたいわけではない」などという手ぬるい意志しかもたず、手ぬるい教材研究にもとづいた手ぬるい授業に甘んじることは、教師としての知性の欠如に直結すると私は考えている。
国語教師としての人生を知的主体として生きぬくためには、言葉のただしい意味での教材「研究」を取り戻す、というしごく基本的な手続きがまず必要だ。「教師は支援者であるべき」とか、「教師はファシリテーターであるべき」といった脅迫がはびこり、教師の主体性の簒奪と知力の劣化が堂々と肯定される状況にあって、教材を「研究」する意義をどう再構築すべきなのか。これは、コンピテンシー・ベース/コンテンツ・ベースをめぐる議論が置き去りにしている「国語教師の実存」にコミットするための、重要な問いだと考えている。
*
国語科教育の研究者と実践者は、国語科教育研究がなぜ人文諸科学からまともに相手にされず、いつまでたっても「第二学問」(もちろん桑原武夫「第二芸術」のパロディである)扱いなのか、その理由をよく考えてみるべきだと思う。
私が考えるかぎり、大きな理由は二つある。 第一の理由は、教育行政側が提供する理念・概念の無批判な受容と使用、すなわち御用学問丸出しの姿勢である。私はもともと近代文学研究が自分のフィールドであり、1990年代に国語科教育研究に越境してきたいわばよそ者(?)であるが、まず驚いたのは、学習指導要領が改訂されるたびに「ゆとり教育」「生きる力」「伝え合う力」「主体的・対話的で深い学び」「資質・能力」等々のワードがトレンドのように扱われ、研究と実践における必須かつ必然の概念として流通してゆくことであった。以来、「行政側が勝手に押しつけてきた用語を無自覚に濫用して恥ずかしくないのか?」「この人たちの頭の中は学習指導要領に占領されているのか?」「国語科教育についての自分自身の思想はまったくもちあわせていないのか?」という疑念をずっと抱きつづけ、それは現在にまで至っている。いうまでもなく、折々の施策に便乗してみずからの研究を推進したり正当化したりする態度は、人文諸科学から徹底的な軽蔑を浴びせられる。当然、学問などと名乗るのはおこがましいということになる。
第二の理由は、端的にいって、研究の理論的水準の低さである。私はかつてつぎのようなことを書いた(注10)。
私は授業中などに、「国語科教育学は「学問」ではない」と公言し、学生たちをしばしば困惑させている。大方の国語科教育研究者は、「何を言う!」と鼻白むことだろう。だが、ある研究分野が「学問」と呼ばれるためには、他分野、他領域の“知”との相互交渉が存在しなければならないはずである。要するに、他分野の研究に何らかの影響を与えることができなければ、「学問」を名乗るに値しないということだ。いうまでもなく、哲学、社会学、歴史学、心理学といった人文諸科学の分野においては、それぞれの思考体系のあいだでたえず“知”の交換が行われている。文学研究の領域には、まがりなりにも「文学理論」と呼ばれる多様なセオリーが存在し、それは文学解釈の場のみならず、さまざまな分野での使用に耐えうる。ひるがえって国語科教育学はどうかといえば、他分野の理論を一方的に「押し戴く」ばかりで、国語科教育(学)の圏域の外部、ひいては“知”の世界全体にインパクトを与える研究など、ほとんど生産されていないのが実状ではないか。
これは、国語科教育学の身内でしか通用しない「理論」や「学術用語」ばかりをせっせと磨いてきたことの、当然の帰結といえよう。もちろん、国語科教育学は、教科教育の現場で有効性をもつ“実学”をめざすべきなのだから、他の研究分野との関係など意に介する必要はない、という考え方はあり得る。だがそれなら、国語科教育学は「学問」を僭称する資格はないのだから、「学」などと名乗らず、もっぱら「職能訓練」を自称するべきだろう。
現在でもこの考えはまったく変わっていない。などと言うと、『国語科教育学研究の成果と展望』Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(注11)に網羅された研究の歴史的蓄積を無視するのか、と怒りをむけられるのかもしれないが、国語科教育研究が、隣接する諸科学――文学理論、言語理論、コミュニケーション理論、メディア理論、認知心理学、発達心理学、教育社会学、教育哲学等々――と真に拮抗する水準を獲得しえているのかどうか、冷静に観察してみればよい。つけ加えていえば、国語科教育研究がかかえる理論的水準の問題は、さきに触れた教材リテラシーの脆弱さという現実とも、決して無関係ではないのだ。
全国大学国語教育学会は、「国語科教育研究はなぜ人文諸科学から蔑視されているのか」というテーマのシンポジウムを一度企画するべきだと、私は本気で思っている。国語科教育の関係者たちがみな黙殺・逃避を決め込んでいるこの問いを正面突破しないかぎり、国語科教育研究の学問としての自律などありえないのだ。
(注1)本稿では「学問」の語が頻出する。この語がすくなからずまとっている権威性を私は好まないが、今回は文脈上必要なためあえて使用する。
(注2)森美智代「ディシプリン重視の立場から「教科の本質」を再考する」(『国語科教育』83集 2018.3)。
(注3)増淵恒吉「文學作品における形象の問題――「山月記」の取扱い方について――」(『日本文学』1956.11)。
(注4)蓼沼正美「『山月記』論――自己劇化としての語り」(『国語国文研究』87号 1990.12)。
(注5)このあたりの問題については、「自己物語の戦略――中島敦「山月記」を読み直す――」(千田洋幸『読むという抗い――小説論の射程』2020 溪水社)で触れた。
(注6)蓮實重彦『反=日本語論』(1977 筑摩書房)。
(注7)田中克彦『ことばと国家』(1981 岩波新書)。
(注8)「最後の授業」消滅をめぐる経緯については、府川源一郎『消えた「最後の授業」――言葉・国家・教育』(1992 大修館書店)がくわしい。
(注9)私は国語科教育法の授業の際、教科書疑獄事件、墨塗り教科書、そしてこの「最後の授業」のエピソードを、国語教科書・教材をめぐる恥辱の歴史(俗にいう黒歴史)としてかならず紹介することにしている。教科書や教材が特定の歴史・社会におけるイデオロギーの産物にすぎないこと、そして国語科教育に付託された「正しさ」がいかに当てにならないものであるかを学生にしっかり認識してもらうためである。
(注10)千田洋幸「巻頭言」(『学芸国語教育研究』29号 2011.12)。
(注11)国語科教育学の各領域における研究史と文献がまとめられており、国語科教育研究者・実践者必携の書とされる。Ⅰは2002年(明治図書)、Ⅱは2013年(学芸図書)、Ⅲは2022年(溪水社)に刊行。