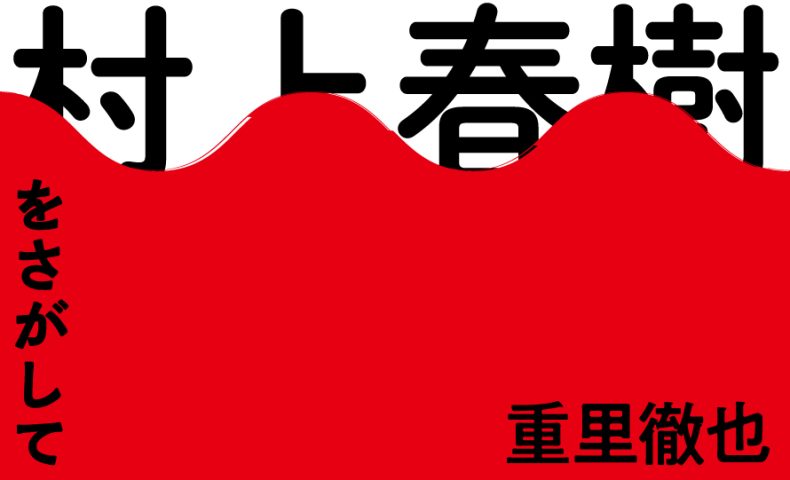村上春樹の短編小説『夏帆』が「新潮」六月号に掲載されている。今年三月一日に早稲田大学の大隈記念講堂で開かれた「春のみみずく朗読会」で披露されたものだ。会場で村上の声で聴くのも貴重な経験だったが、やはり活字で何度も読み返せるのも楽しい。
『夏帆』はこんな物語だ。主人公の夏帆は二十六歳。都内の美術大学を卒業後、絵本作家として暮らしている。彼女は二年余り交際していた恋人と別れたばかりだ。
担当編集者のはからいでブラインド・デート(紹介してもらって知らない相手と過ごすデート)することになる。一緒にコース・ディナーをとり、デザートを終えて、コーヒーを待つ間に相手が言った言葉から、小説は始まる。
「これまでいろんな女性とデートのようなことをしたが」「正直いって、君みたいな醜い相手は初めてだ」
この気分の悪いデートの後、夏帆は容貌の美醜をめぐっていろいろと考えることになる。自分のこれまでの人生を振り返る一方、年上で裕福らしい相手の男について、編集者に尋ねたりもする。
夏帆は同じ男からもう一度、デートに誘われる。夏帆は好奇心からか、昼間で食事をしないという条件で再び、会うことにする。男はこれまでに何人かの女性に対して、同じことを言って侮辱してきたらしい。「あなたは病んでいる」と指摘した夏帆に対して、男はルッキズム(人間の価値を外見だけで決める考え方)と、美を求め続ける人々が多いこと自体がダブル・スタンダード(二重基準)で、世界が病んでいるのだと反論する。
男の指摘はなかなか深いところを鋭くついている。タテマエとホンネの矛盾といってもいい。口では「美醜なんて人の価値に関係ない」と言いながら、実は美しいルックスを他人にも自分にも求める志向。現代において、多くの人々がこの矛盾を生きているのではないだろうか。世界は病んでいるし、人間は価値の分裂を生きている。
小説は夏帆がこの問題をどうやって乗り越えていくかを描いている。彼女は絵本作家にふさわしく、無意識の力で物語を創出し、このテーマに答えを見つけていくのだ。
ルッキズムにとらわれないで、生き方の軸をつかむにはどうすればいいか。今の時代に切実な展開を読んでいて、思い出した村上の小説は、『品川猿』だった。短編集『東京奇譚集』(新潮文庫)に収録されている。こちらも女性が、自身の無意識に深く沈み、自分のアイデンティティー(自分らしさ)を獲得するストーリーだった。
こちらの主人公も二十六歳の女性だ。村上の視点では女性の二十六歳というのは、自らの生き方やあり方について、考える年頃なのだろうか。
自動車の販売店で働く彼女を突然のトラブルが襲う。ときどき自分の名前が思い出せなくなってしまうのだ。何か病気ではないかと疑った彼女は総合病院で診てもらうが、精神科の領域ではないかと言われる。
彼女は区役所の「心の悩み相談室」へ行く。そこで女性カウンセラーのカウンセリングを受ける。自身の心の底にあるものが徐々に明らかにされていく。十代のころの不可解な経験が思い出され、名前を奪った不思議な存在がつかまえられる。そして、自分の心に巣食う闇も暴かれる。
ヒロインは自分の名前を取り戻し、生き直そうと思うことになる。今まで気づいていながら、見ないようにしてきた自身の心の闇をしっかりと意識して。『夏帆』と同じく、不愉快なトラブルから、自分の人生を見つめ直し、新しい人生を生きる物語だった。
村上春樹は人々のちょっとした異変や、日常ではなかなかはっきりと自覚できないでいる心の奥にあるものを見逃さない。そして、トラブルはいつも、無意識の力で克服されることになる。
これが村上の思想だともいえるだろう。人が心のトラブルを解決するためには、自分自身の無意識をまさぐるしかない。無意識の底へ深く潜っていけば、自ずと自分がどのように生きるべきか、わかってくるという考えだ。村上の二つの作品はそれをわかりやすく表現している。