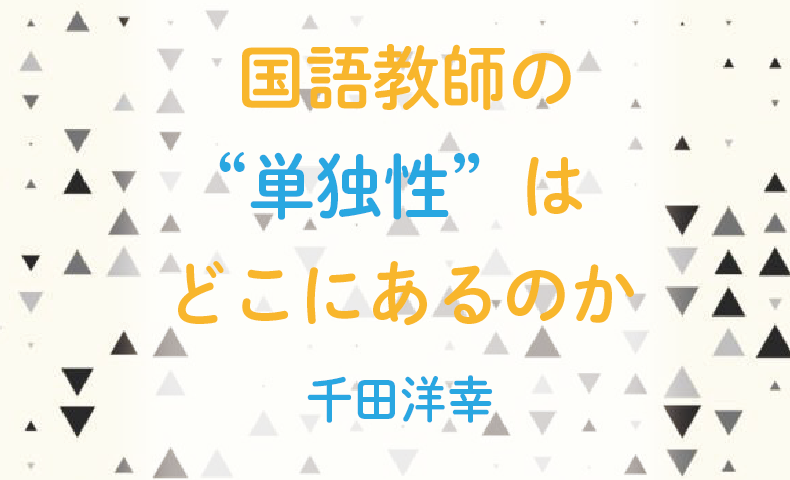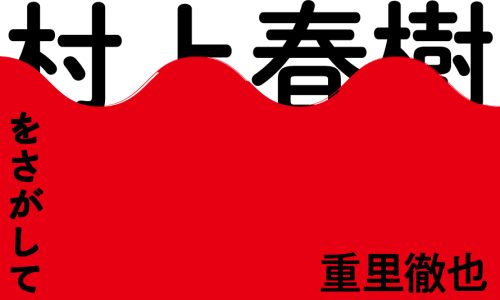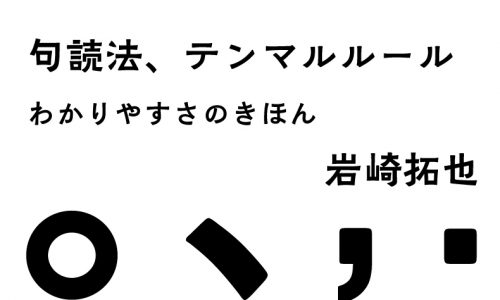私が国語教育の研究に足を踏み入れた1990年代、子ども中心主義の理念はすでに自明の前提とされていた。ほぼ1980年代以降、教師が権力をもって学習者に知識を注入する授業、一方向的な講義調に終始する一斉授業の形態はきびしく批判され、あらかじめ価値を内包していると見なされていた教科書教材――とくに定番教材――の権威も解体されていった。子どもが教室で「生き生きと」学習活動に取り組む姿が礼讃され、読む、書く、話す聞くいずれの領域の授業であれ、学習者相互の「交流」の場を設定することが必須となっていった。教師がみずからの役割をミニマムにし、学習者の「主体的」な学びを呼び起こすことがすぐれた授業の条件とされる。こうしたイデオロギーが変わらずに現在まで生きつづけていることは、現行の学習指導要領が「主体的・対話的で深い学び」の理念のもとに成り立っていることからもあきらかだろう。
本稿の目的のひとつは、このように常識化されている子ども中心主義を転倒させ、国語教育の主体を教師の手に取り戻すことにある。などというと、とんでもない反動的・復古的な認識を表明するのかと思われるかもしれないが、べつにかつての家父長制的な秩序をふたたび教室に復権させようと画策するわけではない(そんなことはもはや不可能だ)。「子どもの主体的な学び」(注1)の名のもとになにが失われたのかを検証すること、その検証にもとづいて、国語教師が“言葉”あるいは“文化”そのものを行為するパフォーマティブな主体としてよみがえる契機を見いだすこと。これがここでの考察の目的であり、出発点でもある。そして最後に、国語教師として生きるとはどういうことか――という解答のない問いに、ほんの少しでも接近することができればと思う。
戦後の学校教育を俯瞰すると、子どもという実体/概念の特権化があらわになるのは、前述の通り1980年代以降だと考えられる(注2)。周知の通り、この方向性は受験競争や詰め込み教育に対する批判と反省にもとづいており、教育という制度に備わった権力を否定し、子どもの学びの自由と主体性を保証することが意図されていた。私が専門とする文学教育の領域に限っていうなら、この時期は読者論の方法が導入され、周知されていった時期にあたる。W.イーザー『行為としての読書』(1976)の日本語訳が刊行されたのが1982年であり、その後、関口安義『国語教育と読者論』(1986、明治図書)、田近洵一編『「読者論」に立つ読みの指導』小学校編・中学校編(1995、東洋館出版社)をはじめとする、読者論の方法にもとづいた国語教育研究・実践の著書、論文がつぎつぎに公にされた。国語教育における読者論の盛行が、学校教育そのものが掲げる子ども中心主義と密接に関連していたことはいうまでもない。テリー・イーグルトンから「リベラル・ヒューマニストのイデオロギー」(注3)といささかの皮肉をこめて言及されていたイーザーの読者論は、読むことの教育における「読書の民主主義」を保証する理論的モデルとして研究者・実践者から重宝され、現在にいたるまで文学教育論のひとつの潮流を形づくっている。
読者論の導入以後に顕著となったのは、読みの「多様性」とか、「個性」的な読みとかいった、学習者の個別の読解を尊重しながら授業の文脈に組み込んでいこうとする用語の氾濫である。これらの言葉は、一種のマジックワードとして警戒されることも多いものの、読むことや書くことの実践研究の場で、あるいは学習者研究の場で、いまでもしばしば使用される用語だろう。
学校における「多様性」「個性」の要請について論理化しようとするとき、いまだに有効でありつづけているのが、ミシェル・フーコー『監獄の誕生』(注4)における規律・訓練権力の概念である。この理論を熟知している人にとっては今さらというところだろうが、今回の考察にとっては必要なことなので、あらためてフーコーの「お浚い」をしておこう。
その権力(注・規律・訓練権力)は〔人々の〕もろもろの力を減少するためにそれらを束縛するのではない。それらを多様化すると同時に活用するように、それらを結びつけようと努める。その権力は、自分に服従するものを何でも一様に全体として順応させるかわりに、切離し分析し区分し、その分解方式を必要かつ充分なさまざまの単独性へ及ぼす。流動的で雑然として無駄な多量の身体ならびに力を、多様性のある個別的な諸要素――切離された小さい独房、有機的な自立性、段階的形成を中心にした同一性と持続性、線分状の組合せ――として《訓育を課す》のである。規律・訓練こそが個々人を《造り出す》のであり、それは個々人を権力行使の客体ならびに道具として手に入れる、そうした権力の特定の技術である。それは自らの極端さをもとにして自らの超権力を当てにできる勝ち誇った権力ではない。計画的な、だが限りない経済策をもとに機能する、つつましやかで疑い深い権力である。
フーコーの規定は明快である。規律・訓練権力とは、この社会を持続させるために多様な個性を「造り出」し、能力や性格を選別し、適所に配置するための権力であり、それが機能する典型的な場のひとつが学校である。したがって、学校とは子どもがもつ個別の性向を抑圧し平準化する罪深い場所だ、という俗見はまったくの誤謬にすぎない。あからさまな例えでいうなら、この社会は成績上位層のみでも成績下位層のみでも成り立たないし、真面目な人間のみでも不真面目な人間のみでも成り立たない。それぞれの人間が多様な能力と多様な性格をたずさえて適当な領域・階層に散りばめられていることが社会を円滑に回すために必須なのであり、だから学校は不断に個性と多様性を産出することを要請される。そして、この著書に収録されている試験についての著名な分析が語る通り、試験こそは個々人を可視化し、記述・分析可能な対象とし、しかもその結果=能力の判定を自己責任として受け入れさせるための周到な規律・訓練権力の形式なのである。
このように述べると、いや自分が教えている子どもたちは日々「自発的に」「生き生きと」学習に取り組んでいる、「権力」などそこには介入していない、という素朴な疑問をあらわす教師がかならずいるものだが、そもそも規律・訓練権力とは、子どもに対し「自発的にその強制を自分自身へ働かせる」(フーコー)べく内面からうながす力のことをいうのだから、「生き生きと」学校共同体に参加している子ども並びに教師こそ、規律・訓練権力の構造の真ん中に位置しているにすぎないのだ。
こうして学校は、社会の維持のために有用なエネルギーをいずれ回収するべく、子どもたちの個性と多様性を効率的に磨きあげるための場所となる(この意味で、「資質・能力」の育成と「主体的・対話的な深い学び」の実践を要諦とする現行の学習指導要領は、じつに忠実にフーコーの主張をなぞっているといえるだろう)。ここで鍵となる概念が、「権力の行使をできるだけ経費のかからぬように」しながら、「権力体系のすべての構成要素の従順さ、ならびに効用を増加させること」――フーコーがいうところの「経済策」(エコノミー)である。これを押しすすめてゆけば、教師の労働力を安く買いたたくいわゆる「学校のブラック労働」の問題に行き着くことはあきらかだろう。教育のエコノミーとは、子どもの個性化・多様化の要請と、教師の労働力の合理的搾取という学校の二つの機能によって達成される。フーコーの理論は、新自由主義下でまさに問題となっている教師の労働環境の問題、子どもの経済的・文化的階層と格差の再生産の問題、さらにそれらを自己責任として受け入れさせるマインドの問題にまで射程が届いている点で――すなわち、それらの問題が近代教育の歴史的必然として出現していることを明示してくれる点で――すぐれた現在性を保持しているのである。
規律・訓練は公教育を公教育たらしめるシステムそのものであり、学校のなかで学び、働くことを選ぶかぎり、この力学の磁場から逃れることはできない。規律・訓練権力の外部は存在しない。学校の外への通路はつねに社会に通じ、優等生であろうがアウトローを演じようがいずれは社会のどこかに位置づけられる未来が待ち受け、多くの人間はそれをみずから受け入れる。学校は「社会人」になることを猶予された場所などではなく、むしろもっとも洗練された社会的空間なのであり、同時に、そのことをたくみに隠蔽する機能をもあわせもつ。このことはいまさら確認するまでもない、自明の事実だ。
こうした論理は、ある種の教師にとってはあまり認めたくない「不都合な真実」なのかもしれない。実際、私の経験では、フーコー理論に対してあからさまな不快感を示す教員はしばしば存在した。大事なのは「目の前の子ども」を育てることだ、学校を構成する権力などいちいち意識してもしかたがない――という教師が、現実の学校ではマジョリティなのだろうし、そういう教師はおそらく、「目の前の子ども」と関わることを教師としてのアイデンティティを保証する第一の要件と考えているのだろう。
たしかに、子どもから一定の承認を得ることなしに、教師としての仕事を持続していくことは不可能だ。多くの教師は、「目の前の子ども」から肯定されることによってかろうじて己れの存在を支えているのだろう。だが、そういうあり方が招き寄せるのは、結局、子どもへの依存がもたらす教師としての主体の空洞化にすぎないのではないか。
教師として生きてゆくからには、代替不可能な「この私」(注5)――すなわち教師としての単独性の意識がどうしても必要である。だがその単独性が子どもへの依存によってしか成り立たないならば、「子どものため」の懸命の労働を都合よく吸い上げられ――それで満足だという教師は好きにすればいいわけだが――、仕事を終えるまでの数十年をかけてみずからをすり減らし、目の前から子どもたちが去った後には抜け殻となった自己のみが残される、という惨めな事態に陥りかねない。
当たり前のことを確認することになるが、教師―子どもの関係は、学校という社会的要請にもとづく空間の内部でのみ発生する関係、すなわち社会的に構築された繋がりであり、だから教師にとって子どもは代替可能であり、子どもにとっても教師は代替可能な存在である。ところがこの事実を露骨にさらけ出してしまうと学校のシステムに支障をきたしかねないので、あたかも両者のあいだに「愛情」や「信頼」にもとづく関係があるかのように、あるいは学校にはそれがたえず必要とされなければならないかのように、演じること、振る舞うことが成員に要請されているにすぎない(もちろん、学校の共同性をそういう黙契のもとに成り立たせるのも規律・訓練権力の機能である)。子どもにそれぞれ個性を授け、社会に送り出す役割を教師が否応なしに担わなければならないとすれば、子どもは、柄谷がいうところの「この他者」であることはあり得ず、「社会的な他者」であるほかはない。「目の前の子ども」の存在によって教師がみずからの単独性を保証しようとすること自体がそもそも不可能なのであり、それが可能であるかのような幻想にとらわれてしまったときには、深刻な歴史的・社会的不公正が呼び寄せられることすらありうるのだ。(注6)
よって、教師の単独性は「教科の専門性」によって保証されるしかない、というしごく当然の結論に至りつくことになる。みずからが担当する教科に関して高度な水準の理論、知識、技能を具備していることだけが教師のアイデンティティ形成に奉仕する。「目の前の子ども」に自分がどう受け入れられるかを考えるよりも、教科専門の知を徹底的に鍛えることの方が絶対に先であり、ゆえに座学は実践よりもかならず優先されなければならない。子どもが習得すべき「資質・能力」は何かだの、「主体的・対話的で深い学び」はどう実践すべきかだのを考えている暇があったら、教材研究や教材開発の能力を向上させることに時間と労力を費やすべきだ。教科教育の研究者・実践者としてすぐれた知性を獲得しようとする意志こそが「この私」性を作り出し、同時に教師の労働を健全化するのであって、結局はそういう教師しか子どもの知性の発達に貢献することはない。すなわち、「目の前の子ども」のことばかり考えている教師ほど、結局は子どもに害悪しかもたらさない、という逆説が生じうるのである。
さて、このように述べると、「子ども中心の思考と高度な教科の専門性は一体であるべきもので、二者択一ではない」とか、「昔ながらの内容主義を復活させるのか」といった批判がおそらくやって来るのであろう。そういう発想がそもそも国語教育の研究と実践の水準を低下させているのだが、それについてはこれから徐々に言及してゆくこととし、今回は国語教師の主体のあり方について考えるためのごく基本的な前提を確認するにとどめたい。今後は、「偶然性」あるいは「賭け」といった概念を導入しながら、国語教師/国語学習者の非対称性に価値を付与するためになにをすべきか、について考察を進めてゆきたいと思う。
(注1)「子ども」という概念はきわめて領域があいまいだが、ここでは、「教師=大人と非対称化された存在」という広い意味で使うことにする。
(注2)元森絵里子「〈子ども支援=教育保障〉の歴史的位相――子ども期の/を通した統治の変遷」(『現代思想』2024.4)その他を参照。近年の子ども観を問い直す試みとして、元森絵里子・南出和余・高橋靖幸編『子どもへの視角――新しい子ども社会研究』(2020、新曜社)もあげておく。
(注3)テリー・イーグルトン『文学とは何か――現代批評理論への招待』(大橋洋一訳 1985、岩波書店)。
(注4)ミシェル・フーコー『監獄の誕生――監視と処罰』(田村俶訳 1977、新潮社)。
(注5)柄谷行人『探究Ⅱ』(1989、講談社)。
(注6)「目の前の子ども」に情熱を注ぐあまり思考停止に陥り、大きな歴史や社会をとらえる視線を失うという事態は、戦中―戦後のような激動期にしばしば起こりうる。少々唐突かもしれないが、子どもに擬似的な理想像を見いだそうとする願望が戦争協力に直結してしまった事例として、著名な綴方教育実践者である東井義雄の回想を以下に掲げておこう。
私は、戦時中、弁解の余地もない戦争協力者であった。当時の私の気持に偽りはなかったつもりだが、それだけに、私は本気で戦争に協力した。その協力の記録が「学童の臣民感覚」なのだ。/努力しても努力しても戦いになじめず、戦勝祈願の神社参拝に参らせられても、どうしてもかしわ手がうてなかった私が、遂にかしわ手をうつようになったのは、子どものいのちの中に、本然に民族のいのちの流れを感じるようになったからだ。おとなたちの戦争協力理論には嘘も感じたが、理くつや思想以前の日常感覚の中に「臣民感覚」とでもいうべきものを感じては、どうしようもなくなってしまった、というのが私であった。こしらえものの思想は信じられなくても、いのちの直接表現である「感覚」の中に「臣民感覚」を見ては、信じないわけにはいかなくなってしまった。そして、そこから私の「本気」の戦争協力がはじまった。(中略)
(東井義雄「私の「いのち」の思想について――飯田・汲田・坂元、三氏の書評に導かれて考える――」『教育』99号 1959.4)
私は、にわかに「しあわせ」になった。おこりっぽい私、遊んでいても、子らとたわむれていても、ほかの若い教師たちのように、子どもと一体になれない私が、にわかに、素直に遊べるようになった。
本稿は国語教育者の戦争責任を考える場ではないので、これ以上の追求はしない。ただし東井はこの文章を自省と自罰の文脈のなかで書いており、その姿勢に特筆すべきものがあることは東井の名誉のためにつけ加えておこう。一方、戦中―戦後のこうした教育者の例は多く、戦時下での翼賛的言動に頬被りして戦後も活動しつづけた西尾実、石森延男、国分一太郎、教師として戦争協力に加担したことに触れながらもそれを論理化することをまったくしなかった大村はまなど、枚挙にいとまがない。