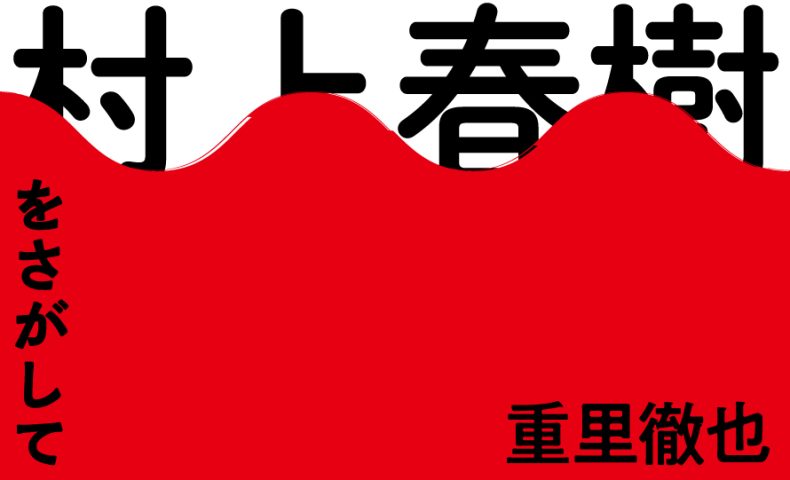昨年発表された村上春樹の長編小説『街とその不確かな壁』(新潮社)で忘れられない女性の登場人物がいる。主人公の「私」は福島県の会津若松からローカル線で約一時間の町の図書館長として働くことになる。鮮やかな印象を残すのは、この町の駅近くのコーヒーショップを一人で経営している三十代半ばの女性だ。
彼女は札幌の出身。二十四歳で結婚したが、二年前に離婚した。女子大を出た後、銀行に勤めていて、その退職金と貯金で、この店の権利を買った。自分を知っている人が一人もいない場所で暮らしたかったのだという。
主人公はこのコーヒーショップで温かいコーヒーを飲み、ブルーベリーのマフィンを食べる。店では小さな音で古いジャズがかかっている(実は有線放送)。
彼女を考えるうえで最も特徴的なのは、性交ができないことだ。彼女は主人公と親しくなるのだが、性行為ができないことを打ち明ける。普通の人生を歩んできたのに、セックスできないことだけが普通じゃないのだという。離婚もそれが原因のようだ。
これは、直子ではないか。確かに直子だ。自殺しなかった直子だ。
読んでから十カ月後に、私にそう気づかせてくれたのは、台湾の淡江大学教授で村上春樹研究センター所長の曾秋桂だった。指摘されてみれば、なぜ、気づかなかったのかと思うほど、自明なことのように思えた。
曾の講演は今年三月十五日に早稲田大学の国際文学館(村上春樹ライブラリー)で開かれた。講演の内容は、村上の新作長編と、川端康成の掌編小説『不死』を比較する試みだった。両者とも登場人物たちが生の世界と死の世界を往来することに共通点があることを指摘した。生と死が地続きだというのだ。
小川洋子が昨年の「新潮」六月号に発表した文章「垂直移動に耐える」においても、全く同じ作品で村上と川端の共通点を探っていた。小川の文章は、村上作品の主人公も、川端作品の主人公も、過去に決定的な欠落(恋人の死や、結婚を約束した女性との別離など)を経験していて、その過去に縛られ、身動きできなくなった人間を描いているというものだった。小川と曾は同じ作品で、村上と川端の間に違った共通点を見いだしたことになる。興味深いことだ。
それはそれとして、曾の講演のうちで、私にとって最も衝撃的だったのは、コーヒーショップの女性と直子を重ねたことだった。曾は講演の中で、これについてはほんの一言しか触れなかった。講演後に個人的に質問にいくと、両者は性愛が不可能だという類似点を教えてくれた。それで私は身体が震えるほどに、思い当たったのだ。これは間違いないと直感した。コーヒーショップの女性は、直子の転生した姿なのだ。
直子。村上作品の読者なら、おなじみの名前だろう。村上の前期作品では、何度も、おそらく同じ女性が姿や名前を変えて登場する。主人公が失ったこの女性について、村上はその死を鎮魂するかのように繰り返し、小説に描いている。
デビュー作『風の歌を聴け』(一九七九年)から、六作目の長編『ダンス・ダンス・ダンス』(一九八八年)に至る作品をめぐって、一人の女性が反復されて描かれていることを指摘した小島基洋『村上春樹と《鎮魂》の詩学』(二〇一七年、青土社)は優れた村上春樹論だ。「直子の鎮魂」を軸に精緻に作品群が分析されていて、村上を考えるうえで避けて通れない一冊だろう。
小島が何度か引用する文章がある。『風の歌を聴け』の一節だ。主人公の語り手は付き合った女性たちを振り返る。
「三人目の相手は大学の図書館で知り合った仏文科の女子大生だったが、彼女は翌年の春休みにテニス・コートの脇にあるみすぼらしい雑木林の中で首を吊って死んだ。彼女の死体は新学期が始まるまで誰にも気づかれず、まるまる二週間風に吹かれてぶら下がっていた。今では日が暮れると誰もその林には近づかない」
この三人目の女子大生。小島の文章に導かれると、彼女が命を絶ったのは、一九七〇年三月らしいとわかる。第二作の『1973年のピンボール』(一九八〇年)では彼女に「直子」という名前が与えられる。小島はここで、直子の故郷の街の構造がピンボールに似ているという驚くべき指摘をしている。それで、死んだ直子がピンボールに姿を変えて現前しているというのだ。このことから、主人公がピンボールをしている時に、このゲーム機械と会話をするのも納得できる。
ピンボールは主人公に語りかける。「あなたのせいじゃない」「あなたは悪くなんかないのよ」。あるいは、小説の後半ではこんな具合だ。「ずいぶん長く会わなかったような気がするわ」。これに対して主人公は「考えるふりをして」指を折る。「三年ってとこだな」。一九七三年は七〇年から三年後だ。
『ノルウェイの森』(一九八七年)は、作品全体が直子という女性の鎮魂になっているとも読める。主人公の幼なじみの友人(すでに自殺している)の恋人で、主人公が大学進学のために上京した後、東京で偶然に出会った直子。主人公は彼女と付き合うが、彼女は心の不調から性交することができず、やがて京都の山間部にある療養施設に入り、自殺する。
『ノルウェイの森』は恋愛の不可能性を前にして、いかに恋愛が可能かを探った小説とも読める。この作品について小島は、直子がフランス語を学んでいるのに対して、主人公の「僕」はドイツ語を学んでいることに注目する。フランス語やフランス文化が直子に関連づけられているのに対して、主人公はドイツ語やドイツ文化の側にいるという構図だ。そして、〈フランス〉が死、〈ドイツ〉が生のイメージを帯びていることを論じている。
これも私が気づかなかった論点だった。小島の筆致は精密で、何度か読んだ『ノルウェイの森』をフランスとドイツの対比という視点から思い出させてくれた。小島は、主人公をめぐるもう一人の女性である緑が女子高校で習ったフランス語を捨てて、大学ではドイツ語を学習していることにも触れている。
そして、『ダンス・ダンス・ダンス』(一九八八年)では主人公をめぐるユミヨシやユキなどの女性たちが、《進化》して再帰しているのがたどられる。この時に札幌にある「ドルフィン・ホテル」が重要な場所になっている。小島の本に教えられて、村上の初期作品で、女性たちが何度も転生し、姿を変えてよみがえっているのを実感した。
さて、最初の話題に戻ろう。『街とその不確かな壁』に登場するコーヒーショップの女性が直子の転生した姿なのであれば、この小説には二人の直子が出て来ることになる。
もともと、この作品は主人公である十七歳の「ぼく」が十六歳の「きみ」と出会い、恋愛に陥ることから始まる物語だ。ところが、突然に「きみ」と連絡が取れなくなる。後に中年になった「私」は、高い壁に囲まれた街(異界のような場所)を訪れ、図書館で働く「きみ」と再会する。この街はかつて、「きみ」が「本当の私はそこにいる」と語っていた場所で、「きみ」と「ぼく」が共同作業のようにして作り上げた空想の街だ。
壁に囲まれた街(異界)で働く少女「きみ」は、明らかに直子だろう。コーヒーショップの女性が転生した直子だとすれば、この小説には「直子」といわば「シン直子」の二人が登場していることになる。そこがとても興味深い。
なぜ、直子はシン直子になって〈再帰〉したのだろう。それも、主人公を取り巻く女性たちに縁のある札幌から。
私は生命の循環とか、魂のリレーとかの言葉を思い浮かべるのだが、どうだろうか。この小説では別に二つの仕事の継承(福島の町の図書館長、異界の街の夢読み)も描かれており、それと重なるものとして論じたくなる。あるいはそこに七十代も半ばを迎えた村上春樹の心境があるのではないだろうか。
◇ ◇
村上春樹の仕事にさまざまな角度からアプローチします。基本的には月一回の掲載です。