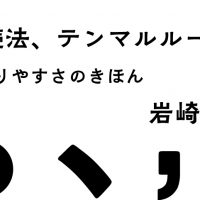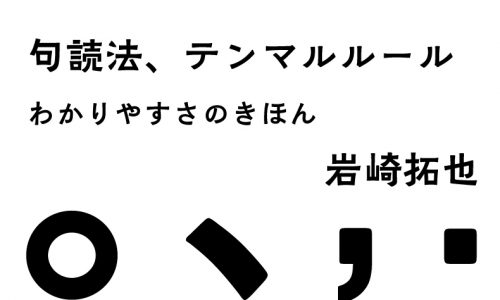文部科学省 教科書調査官(体育) 渡辺哲司
1. 国語教師たちの“狭く深い”一冊
これは国語教師たちの、国語教師たちによる、国語教師のための一冊だな――と私(評者)は感じた。書いた人も、読むべき人も国語教師である。ふつう市販書は、読者を少しでも増やそうと間口を広げるものだが、そういう意図が本書には感じられない。内容も、国語教師どうしのやりとりに閉じている。閉じていて狭いが、そのぶん深い。
そうした本書の特徴(国語教師どうしのやりとりに閉じた狭さと、深さ)のおおもとになっているのが、全23章のうち22章の冒頭に置かれた質問状である。それらは、もともと現場の国語教師たちから編著者(こちらも元国語教師。今は大学で未来の国語教師たちを教えている)に宛てられた書簡だという。そして、それらの質問状に編著者が答えていく――というのが本書の基本的なつくりである。よって、内容は自然と、国語の授業を掘り下げるようなものとなる。それを読者は“傍から見る”ように読むわけだが、疎外感はなく、ちょうど舞台上の演劇を見るような感じだと言えば当たりであろう。
2. 問い中心、問いベース
そうして質問状(問い)から始まる各章の中身――編著者の答え――が、また問いのオンパレードである。その数、実に200(各章に10前後)。いずれも、もと(質問状)の質問を細分したり拡張したりするように立てられたものであり、そうした問いに一つ一つ答えるような形式(問答形式)で各章は展開する。
私にとって印象的なのは、編著者によって立てられた200の問いの一つ一つが、とても“細かい”ことだ。例えば、次のような問いは、国語教師ではない人にとっては細かすぎて、それだけでは何を言っているのかわからないだろう。
・学習課題と作品との出会いを往還的に行うことのよさはどんなことですか(問い27:第3章 「単元びらき」を調える)
・領域単元ではその領域学習と語彙学習とどちらを優先すればいいですか(問い128:第12章 「語彙学習」を日常化する)
・物語文の発問に対する答えが広がりすぎるのはなぜですか(問い170:第16章 「発問」を見直す)
ただ、考えてみれば、いわゆる現場の問いは、常に細かいものである。国語の教室に限らず、スポーツや料理など“芸事”の現場でも、科学研究の場でも、それは同じだ。現場で突き詰めている人の内に湧き出ずる問いは、当人以外には「何を言っているのかわからない」ほど繊細・微妙なことが多い。ところが当人は、そうした問いを絶対に見過ごすことができず、自分なりに解決しないかぎり一歩も前に進めない。専門家の仕事とは、すべからくそういうものであろう。
なお、本書のそうした問い中心、問いベースの構えは、児童生徒たちの学習活動にも及んでいる。本書では、第9章(「問い」を立てる)が一応その核になっているが、他の章にも《私の問いを立てる》というフレーズが頻繁に登場する。ここでは「私の」が重大な意味を持つ。それは、教師が与えた問い、学級のみんなで決めた問いではなく、一人の子どもの内に湧き上がる問いこそが大事だということを意味する。そうした問いを自らの言葉で定立し、自ら解決していく力こそが、これからの世界を生きる人たちには必要だ――という編著者の考えは、本書の基調であり、他方で現在世界の教育界の潮流に掉さすものでもある。
3. “前線”と“後方”の架け橋に
本書を読んで私が感心したのは、教育の前線たる教室から見れば後方にあたる、学習指導要領や検定教科書への言及(取り上げ方、説明の仕方)が巧み、かつ適切であることだ。とりわけ学習指導要領などは、往々にして現場の教師たちから「実践を“がんじがらめ”に縛るもの」「上からの押し付け」と忌み嫌われ、見向きもされない。しかし、それらは本当のところ、いくつかの重要な役割をもって“あるべくしてある”のであり、現場の支えとなっている(注1)。そうしたことを、編著者は第1・2章ほかの随所でうまく説明している。さすがは、学習指導要領と“にらめっこ”でつくられる検定教科書の編集委員を務め、大学の教員養成課程で教えている御仁だな――とそのわけを私なりに納得した。
そして、そのような「後方」のことがらが、本書では、前線たる現場で生まれる問いと巧みに結びつけて論じられる。その様子を「国語教育の前線と後方との間に橋を架ける」と言い表すこともできるだろう。そんなふうに感心するのは、私が完全に後方側の人間だからかもしれないが。
4. 授業研究は健在
他方、本書を読んで私が“安心”したのは、最終の第23章(「校内研究」で成長する)を読んで、いわゆる授業研究が今でもしっかり機能しているのを感じ取ったときだ。授業研究とは、基本的には、授業をめぐる教師どうしの自発的な学び合いのことである。なお、この章だけは、書き手が教室からやや距離を置いた人たち(学校長と教育委員会指導主事)なのだが、その人たちも元は国語教師のようであるから、ここでも「教師(国語教師)どうし」の基本は崩れていない。
ところで、そうした授業研究こそ、日本の学校教育の卓越性の源――という見方が世界にあることを、読者はご存知だろうか。日本発の授業研究は、lesson studyという英語になって、今日では国際的に通用するらしい(注2)。一方の日本では、このところ、教師の多忙化などによって授業研究が廃れつつあるのではないかと懸念される。しかし、本書を読んだ私は、授業研究はいまだ健在で、何時でも何処でも「やればできる」し、実際にやられているのだな――と心強く思った。
教育一般に目を転ずれば、授業研究の他にも、日本の公教育には世界に誇るべき美点がいくつかあるようだ。私の専門領域(体育)でも、例えば、ほぼ全ての子どもたちが学校へ歩いて通う習慣や、その結果であろう高水準の体力などが、世界的に高く評価されている(注3)。それらの事象は、日本の人々にとって“あたりまえ”であるがゆえに、あるいは人々の視線が内向きである(国内にしか向けられない)ために、価値ありとは気付かれていない。しかし同時に、世界の体育関係者たちからは驚きと羨望の目で見られている――というわけだ。
本書の最終章では、授業研究にスポットライトが当てられる。そこを読んだ人は、日本の公教育が持つ美点の一つを知り、せっかくのそれをむざむざ廃れさせてはならず、大事に守り育てていかねばならないと思うだろう。それを編著者がねらっていたかどうか、私にはわからないけれども。
注
注1 この点にピンと来ない人は、例えば、次のような問いへの答えを考えてみてほしい。
・本当にゼロから自力で各回の、1学期間の、あるいは1年間の授業(学習指導内容)をつくれと言われて、できるか。
・いわゆる転勤族の子が転校先でも大きな支障なく学習を続けられるのは、なぜか。
注2 詳しくは、Peter Dudley編 (2015) Lesson Study: Professional Learning for Our Time (Routledge) ;小柳和喜雄・柴田好章編著 (2017)『Lesson Study(レッスンスタディ)』(ミネルヴァ書房)等を参照。
注3 子どもの身体活動を国際的に調べる取り組みが進んでいる。そのうち日本の状況については、アクティブヘルシーキッズジャパン「日本の子供・青少年の身体活動に関する報告2022」(https://activekids.jp/reportcard/)を参照。