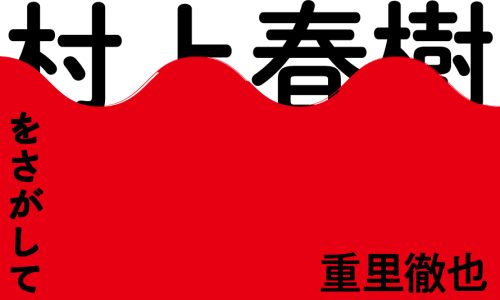文部科学省 教科書調査官(体育) 渡辺哲司
1. “役に立つ”研究書
とある大学のキャンパスで──日本人学生がアメリカ人教授の講義を聴きながら思う。「わかりやすいんだけど、いつもそう最初から結論っぽいことをズバズバ言われると、引いちゃうんだよなぁ」と。一方、その学生が書いたエッセイを読んだ教授は「うーん、それで結局、何を言いたいのかしら?」。次のフランス人学生のエッセイには「私の問いを勝手に作り替えて、まともに答える気がないのね!」と立腹。教授を立腹させたフランス人学生のほうは日頃「日本人は他人の意見を気にしてばかりでヘンだけど、アメリカ人みたいに自分の主張ばかりを、他の考えは存在しないかのようにするのもヘンだ」と思っている。そんな教室の片隅ではイラン人学生が「あの人たち、浅知恵しかない人間どうしで何を議論しているのかしら」と訝しむ。
以上は、本書の第7章2節「論理/非論理、納得/不服を分けるもの」を基に私(評者)が創作した架空の一場面である。大して面白くもないのは私の腕が悪いせいであって、本書の著者のせいではない。もしもこれが本当の腕利きの手にかかれば、面白い寸劇の1つも出来るのではないだろうか(ただし、元の書籍はほんの少しもふざけたりせず、たいそう真面目な筆致で書かれている)。
それはともかく、本書は、日本と世界の人々の相互理解とよりよい言語コミュニケーションの実現に寄与するであろう“役に立つ”研究書である。その恩恵を直接的に受けるのは、何かしらの意味で日本(あるいは他の各国)を代表して他国の人々と交渉なり協働なりをする立場の人たちだろう。その例として、国際的な政治やビジネスの世界で働く人たちはわかりやすいが、他にも、異国にルーツを持つ子どもたちの教育に携わる人などが挙げられよう。それらの人々が、本書で学んだことを生かして各々の現場でよりよいコミュニケーションを実現し、成果を挙げれば、その背後にいる大勢の人たちにも間接的な恩恵は及ぶことになる。
2. 至適のタイトル
『「論理的思考」の文化的基盤』というタイトル(書名)は、本書にとって至適である。これを見た人は、きっと「世界で自明のもの、万国共通のものと思われている論理的思考にも、実は文化の違いによる差異や多様性があるって話じゃないかな」と予想するだろう。ご明察、実際の内容もその通りである。何らかの事実を伝え、意見を述べるために書かれた文章のタイトルは、その内容の最も簡潔な要約であるべし――という一般教則に照らして、これほど的確なタイトルも他にあるまい。
なお、ここでいう「論理」は、論理学の教科書が説くような定式化された形式論理(三段論法など)のことではなく、いわゆる日常の論理を指す。つまり、人々が日々の暮らしの中で考え、会話や文章を通じて伝え合い、納得し合うことの中には、どんな情報(要素)が、どんな順番で並べられているのか――ということだ。それを著者は「思考表現スタイル」と呼び、そうした思考表現スタイルの多様性と、それを生み出す文化・社会的基盤とを解明し記述することに、次節でふれるとおり、ずっと力を尽くしてきた。
3. 過去二作とのつながり、相違点
私の知る限り、著者には、本書に直接つながる主要な書籍が過去に2点ある。刊行順に、2004年の『納得の構造―日米初等教育に見る思考表現のスタイル』(東洋館出版社)と、2021年の『「論理的思考」の社会的構築―フランスの思考表現スタイルと言葉の教育』(岩波書店)の2点である。うち1点/一作目では、思考表現スタイルの日・米の違いが詳述された。続く2点/二作目では、さらにフランスを加えた3か国の間で思考表現スタイルの違いが詳述されるとともに、特にフランスの思考表現/論理的思考のスタイルがフランス社会によって意図的に構築されたものであると論証された。いずれも、専門書にしては広く多数の人に読まれ、インパクトを与えたようだ。
そして本書では、比較される国および思考表現スタイルの数が、イランを加えて4つに増えた。ここまでは、ひと続きの流れとして記述できる。
ところが本書には、対象の国/思考表現スタイルの数などとは次元の異なる、過去二作との間に一線を画すような特徴がある。それは、各々の国の思考表現スタイルが単に“その国のもの”として示されているのではない 点だ。
本書では、アメリカ、フランス、イラン、日本という4つの国の思考表現スタイルが、世界における(おそらくは典型的な)4つの教育原理をそれぞれ代表するものとして提示されている。つまり、それらの4か国は“たまたま”調査された国ではなく、過去の社会学的知見(第1章で解説)に基づいて理論的に想定される4つの異なる教育原理――著者の命名によれば、経済原理、政治原理、法技術原理、および社会原理の4つ――に拠って立つ国の代表として、意図的かつ計画的に選ばれた国であるというわけだ。その点は、過去二作ではほとんど表現されていなかった。
では、4つの教育原理とは何か。詳しくは本書に譲るとして、それを4つに分かつものは、一般に教育を成り立たせている2つの指標――1つは目的(技術か、価値か)、もう1つは手段(経験的知識か、体系的知識か)――の組み合わせだという(第1-2章で詳述)。ちなみに、上記4つの教育原理のうち経済原理はアメリカ、政治原理はフランス、法技術原理はイラン、そして社会原理は日本が、それぞれの代表とされている(第3-6章で詳述)。
以上の内容は複雑で、なかなか容易に読み解けるものではないが、幸い、形式(文章の“見た目”)を手掛かりにして内容の理解が進むようにと配慮されている。すなわち、約280頁の全体は、3つの部、9つの章、47の節に区分され、その各々に的確な(最も簡潔な要約であるような)見出しが付けられている。しかも、字下げで始まる各段落の第1文には、大抵その段落の要点が記されている。そのため、読者は、見出しと各段落第1文を拾い読みするだけで要点と話の流れをつかむことができる。
――ということから、本書は明らかに、効率を重視し、それを高める技術と経験的知識を重視する「経済原理」に則ったアメリカ流のスタイルで書かれているとわかる(著者はそのように述べてはいないけれども)。
4. 成果の応用:思考表現スタイルの切り替え
以上のような内容(研究成果)の応用として著者がポイントに挙げるのは、思考表現スタイルの切り替えである。そのポイント自体は、2004年の一作目から変わらず一貫している。しかし、そうした切り替えの行為を言い表す語は、一作目の「スイッチ」から今回の「ザッピング」へと変わった(終章:p. 272)。切り替え可能なスタイルの数が、日・米の2つから、フランスとイランを加えた4つへと増えたため、操作する道具のイメージも[モードA/B]のような二値スイッチから、多チャンネルのTVリモコンへと変わったらしい。そうした比喩表現の適否はともかく、思考表現スタイルの切り替えが、本書による学びを実地に生かす(研究成果を応用する)ためのポイントであることに変わりはない。
ちなみに、この点(思考表現スタイルの切り替え)について、私はかつて、2021年の二作目を読んだ際、著者の説を公然と批判(疑問を公言)したことがある。そのときの言い分を、少し長いが引用しよう(参考文献1)。
(前略:著者の説は)つまり、異国の人に相対してはその国の思考表現スタイルに合わせよ――と読める。そのような振る舞いは、たしかに仏・米両国の人を相手に仕事をする人や両国で学ぶ人にとって、エンパワーメントになるだろう。
しかし、もし他の多くの国にもそれぞれの流儀があって、それらの国の人々と自分が交流するとなったら、どうだろう。各国の流儀に合わせる労もさりながら、そもそも各国の流儀をもれなく学ぶ環境は整うのか、教える人はいるのか。“お国柄”への個別的対応とは別に 、あるいはそれよりも前に、われわれが試みるべきこともあると思うのだが――。
当時の私は、「あの国も、この国も」となったら大変すぎるから、いっそのこと“人間ならば”の視点に立って、生物としてのヒトの認知・知覚の働きに即した統一的なコミュニケーション・スタイルを追求し、世界中に広めたほうがいいんじゃないか──との考えを腹蔵していた。
しかし、最新の三作目(本書)を読んで、我々が理解・習得すべきスタイルはとりあえず4つでよさそうだと知り、それならば出来ぬこともない、と思い直した。そして、批判の矛を収めることにした。
さて、そうなると、我々の次なる関心は、4つある思考表現スタイルの切り替えを、コミュニケーション技術としていかに習得するかであろう。その点、著者が本書の中で提案しているのは、中等教育でスタイルの違いを意識させ、高等教育で文理共通の基礎教養として教えることだ(終章:p. 275)。その提案には、私も反対しない。かつて大学で入試や初年次教育に深く関わった経験に基づき、今では初等中等教育行政の一端を担う立場から、ただ「なるほど」と思う。
5. 残った疑問
他方、私が「なるほど」と思えず、解けずに残った疑問を1つ提示しておきたい。その疑問の種は、あとがきの中の次の記述(p. 281)にある。
このモデルを使えば、中国をはじめとした他の国の教育の説明も可能になるが、その場合は、異なる原理の「複合型」になるはずである。
「このモデル」とは、先に節3で紹介した4つの教育原理を規定する、考え方の枠組みのことである。それを著者は「教育文化の四元モデル」と呼んでいる。
私が納得できないのは、上掲の記述の末尾にある「異なる原理の『複合型』になる」というくだりだ。そのくだりは、同書内のそれ以前の記述と、どうにも“つじつまが合わない”ようだ。なぜなら、先行するいくつかの章では、4つの教育原理の独立性や相互の排他性などが、次のとおり再三にわたって強調されているからだ。
- 教育文化の四つの原理は、固有の指標から成り立ち、それぞれが独立したシステムとして完結している(序章:p. 11)
- 次章で示す四つの教育原理もそれぞれ独立した思考とその表現法、時間意識、因果の考え方、推論の型、論理と合理性をもち、交わることはない。(第1章:p. 39)
- 各原理の思考表現スタイルを成り立たせる部分をシャッフルしたり、折衷したり混ぜたりして使うのは不可能だ(第7章:p.260)
- 教育文化の四元モデルは、二つの指標をかけ合わせることで四つの相互に排他的な原理を提示する「非統合のモデル」となっている(終章:p. 265)
- 各原理で重視される能力は相互に排他的(終章p. 269)
これらの記述群を素直に読めば、異なるスタイルの複合は無理だろうと思えるし、「複合型」のイメージも湧いてこない。
これは私の邪推かもしれないが――著者も心の内では4つの原理で十分(どの国も、教育の「目的」「手段」という2軸を交差させて出来る4つの象限のうちいずれか1つに収まるはず)だと思ってはいるものの、まだ実際にこのモデルを適用・検討してみた国が少なく自信も持てないため、つい“筆が滑って”そんなユルい表現をしてしまったのではないだろうか。
そうした邪推?の当否はともかく、くだんの「残った疑問」を解くためには、著者もあとがきの中で期待を述べているように、さまざまな国に「四元モデル」を適用・検討する作業を積み重ねていくことが必要だ。その作業には、まず彼女自身が取り組むだろうが、世界にある国の数や文化のバリエーションを考えると、一人ではなかなか…。そこで私としては、日常の論理とその“お国柄”に関心を寄せる人たちが一人でも多く参画してくれたら――と思う。そのような思いを持って、「残った疑問」を本稿の締めくくりに提示してみたのである。
参考文献
1:渡辺哲司(2022)「連載 教育の窓 第52回:渡邉雅子『「論理的思考」の社会的構築―フランスの思考表現スタイルと言葉の教育』岩波書店、2021年」日本教育評価研究会『指導と評価』5月号: pp. 50–51.