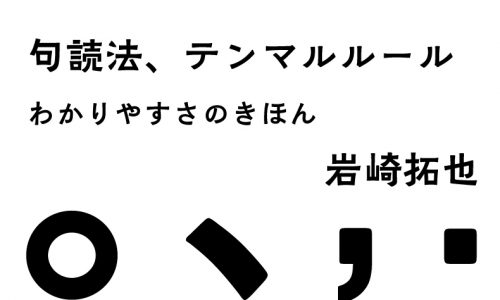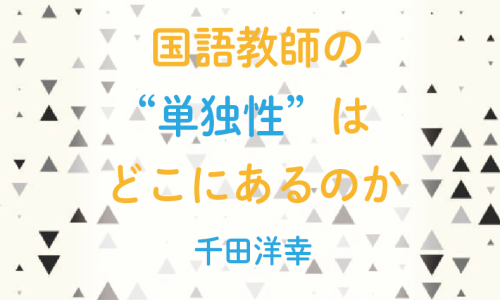あすこま
島田先生、渡辺先生
お手紙ありがとうございました。『あらためて、ライティングの高大接続』の編著者お二人が、僕のブログでの感想を読んでくださり、それに対する反応を公開書簡の形でくださったこと、とてもありがたく思いました。
さて、そのお手紙の中で、島田先生と渡辺先生は、大きく次の2点に言及されていました。
①著者の皆さんの関心は日本のライティング教育全体にあること。その上で、高大接続をメインテーマとしたのは、小学校から続く日本のライティング教育の不備が表面化する地点であることや、世間の関心などの戦略的理由からであること。
②「アカデミック・ライティング」の意味を、狭義の「アカデミック・ライティング」(学術論文やそれに準じたレポート)ではなく、「学校で書かれた、事実や意見を伝える文章」に拡張することで、私たちは校種の違いを超えて協働できること。
この2点を受けて、僕もお二人への返信を書きます。少し迂遠な身の上話から始まりますが、おつきあいください。
僕個人のライティング教育(僕は主に「作文教育」や「書くことの教育」と呼んできましたが、ここではお二人の用語に合わせます)へ関わりは、20年以上前、学生時代のアルバイトで小論文の模試の採点をしたことに始まります。その後、最初の赴任校で大学入試に向けた小論文の講座を担当しました。そういう意味で、僕自身もちょうど高大接続の場面に立ち会うところから、ライティング教育への関心を深めたことになります。
当時の僕が多くの小論文の採点や指導を通じて抱えていたのは、「これは本当に書くことを教えているのだろうか」「ライティング教育とは何をすることか」という問いでした。当時の小論文指導で一般的だったのは、「医療」「科学」「環境」などのテーマごとの知識を仕入れ、それを何々式の文章展開の「型」に落とし込んで書く、というもの。僕も当初は「型がないよりはある方が書きやすい」くらいに考えていましたが、いざ採点や添削で読む側に回ると、笑ってしまうくらいに紋切り型の文章に出会うことに、愕然としました。合格する(不合格を避ける)ためにはリスクを取れない、この程度ができれば実際に合格できている。それもわかりますが、指導が行き届けば行き届くほど、ますます書き手が声を失って、同じことしか話さなくなる。自分は一体何をしているのだろう、これで子供達は「書く力がついている」、いや、それ以前に「考えている」と言えるのだろうか。そういう疑問が、自分のライティング教育の出発点でした。書くことは考えること。その直感が、当時の自分の中にすでにあったのでしょうか。
その後ライティング教育に関心を持つ中で出会った言葉に、Writing is thinking and rethinking on paper. という言葉があります。アメリカのライティング教育指導者ナンシー・アトウェルの言葉です。書くことは、考えること、そして考え直すこと。ライティング教育に関心を持つようになった僕は、このアトウェルの言葉に強く惹かれました。書くことは、僕たちにゆっくりした思考の時間をもたらします。日常のにぎやかすぎるおしゃべりや、流し読みするためのメディアに囲まれている僕たちが、いったんドアを閉じて一人で考える。何気なく過ごしていた世界の中で立ち止まり、世界を見つめ、新たな発見とともに捉え返す。書くとはそういう時間を持つことであり、書くことを通じて、僕たちは自分の考えを深めることができる。次第に、書くプロセスを通じて、書く前には持ち得なかった「発見」を持つこと。そういう体験を書き手にもたらす文章が「良い文章」の第一の条件だ、という考えが、僕の中に醸成されていきました。
そして、素晴らしい「発見」をしたら、人はそれを伝えたくなるもの。その時に、「どう伝えようか」という表現への欲求が生まれます。よりよく伝えるために、どう書くか。全体の構成は、一文の長さは、文と文を繋げるための接続表現は、効果的なレトリックは…。いわゆるライティング教育は、こちらに焦点を当てたものが多い。もちろんそれは必要な技術で、学校の国語教師が教えるべきものでありますが、発見の喜びや表現の欲求のないところにいくら技術を教えたところで、どうにもなりません。
こういう僕の見方について、お二人には(少なくとも渡辺先生には)ある程度は同意してもらえるのではないかと思っています。というのも、『あらためて、ライティングの高大接続』の序章で、渡辺先生は、ライティングについて「考えることを抜きにしては遂行不可能といってよいほどに、あるいは、考えることを自然に誘発・促進するという点で、思考とはほとんど一体不可分である」と述べて、特に「発見的な思考が促される」点にその価値を認めていらっしゃったからです。そこは、僕たちが話をする出発点になりそうだ、と思っていますが、いかがでしょうか。
そして、ここからは、「ライティングの価値は発見的思考をもたらすことにある」を共通の出発点として仮に受け入れてもらえるとして、お二人のお手紙の①②の点について、反応してみます。
①に書かれた日本のライティング教育の不備について、ご著書の序章では、小中高と大学の間で構造的に切断が起きている点を指摘されていました。小中高では曲がりなりにも教員養成と学習指導要領で一貫性が保たれており、そこから大学へのギャップがある。その通りだと思います。
ただし、僕の経験談に過ぎませんが、個人的には「小中」と「高校」の断絶も大きいように感じています。概して、義務教育である「小中」の教員は教育学部出身者が多く、学習指導要領を読んで守ろうとする意識も、良くも悪くも強い。一方で、高校の教員は各専門学部・学科の出身者が多く、学習指導要領への関心も比較的薄く、授業は個々の教員の学問観で作られている。そんな傾向を、肌で感じています。高校ではライティング教育を受ける状況が二極化すると渡辺先生も指摘されていましたが、その背景にあるのは、「高大接続」問題の陰に隠れたライティングの「中高接続」問題なのではないでしょうか。
ですが、その可能性も念頭に置きつつ、ここではやはり議論の枠組みを共有するために、「小中高」をひとまとまりのものとして捉えましょう。だとしたら、小中高で、ライティングについて何が一貫して教えられているのか、を考える必要があります。その「一貫性」の中で、書くことを通じて自分の考えが深まり、書く前とは異なる地点に自分自身を連れていく体験、発見的思考をもたらすライティング体験を、子供たちは十分に積めているのか。それを積むためにはどうしたらよいのか。それが、この返信を書くことで僕がたどり着いた問いです。
②「アカデミック・ライティング」の意味を、「学校で書かれた、事実や意見を他者に伝える文章」に拡張すること——。大賛成です。以降、そのように定義を共有して話をしましょう。その上で、発見的思考をもたらすライティング体験を積む上で、アカデミック・ライティングの、つまり「他者に事実や意見を伝える文章」の役割を考えていけたらと思います。
もちろん、発見的思考をもたらすのは、「他者に事実や意見を伝える文章」だけではありません。物語を書くことは、それまで細かく考えもしなかった、自分とは異なる立場や年齢の人の感情を追体験することに繋がるし、詩歌を書くことも、言葉と言葉の結びつきが自律的に世界を構築していくことへの驚きを伴います。それを前提としつつ、このやりとりでは、お二人の関心であるアカデミック・ライティングに絞ってみましょう。
「事実や意見を伝える」ライティングは、それに先立つ「伝えたくなる事実や意見」の存在を必要とします。その事実や意見が本人にとって発見的思考をもたらすものである時にこそ、事実や意見を伝える文章を書くことは、最も効果的なライティング教育として機能する。僕は、そう考えます。そもそも、アカデミック・ライティングは、書き手の知的な発見を助けるための形式なのです。狭義のアカデミック・ライティングである論文が、個々の研究者の発見を助け、それを共有するための便利な形式であることと同じように。
ここで僕は、具体的な伝え方の形式(手紙の書き方、メールの書き方、レポートの作法…)を教えることを無視するのではありません。「伝える」という行為の先に他者がいる以上、他者に伝わるように書くこと、書き手と読み手の共同体の中で時間をかけて作られてきた約束事=形式を守って書くのは必要な技術です。ですが、それらを身につけさせるだけでは、決まった「型」に仕入れた知識を流し込んだだけの、あの20年前の小論文と変わりがない。それに、今後も様々な文章形式が現れては消える中で(中学校の教科書では、すでにメールの書き方が出ており、SNSの「打ち言葉」に言及する教科書もあります)、生徒たちが出会いそうな形式を全て教えるなんて無理なこと。その意味でも、特定の形式を教えることにこだわりすぎるのは、よくありません。彼らに必要なのは、これからの人生でどんな形式の文章に出会っても(例えば、大学で論文という形式に出会っても)、その形式の特徴を掴み、それを真似ながら書くことに一歩踏み出せる自信を持つことです。
そのためには、小・中・高校にいる若い書き手たちは、何度も書く行為の中に自分を投入し、そこから書く営みについて、あるいは書き手としての好みや強み・弱みについて考える必要があります。そうやって得た書くプロセスへの理解と、書き手としての自分自身に関する理解が、新しい文章形式に出会った時にうまく対処する自信の源となるでしょう。そういう自信を作ることが、中等教育までのライティング教育の役割ではないか、と僕は考えます。
でも、ライティングのプロセスや書き手としての自分を理解するには、長い時間がかかります。その時間を支えるのは、ここでもやはり書く行為に伴う発見の喜びに他なりません。思いもよらぬ事実を発見して、世界の見え方が変わる喜び。自分の内奥から、これまで思ってもみなかった考えが生み出された喜び。その発見の喜びこそが、それを他者と分かち合いたい欲求につながり、また、実際に分かち合えた喜びにつながっていく。では、どうしたら「発見」をともなうライティング教育ができるのだろうか。ここでも僕は、先ほどと同じ問いにたどり着いたようです。
お二人の手紙のおかげで、ここまで書き進めることができました。ここでいったんこの問いを手放して、旅に出させてみたいと思います。旅の行く先の一つは、もし許していただけるのでしたら、お二人のところでしょうか。旅から帰ってきた時、この問いがどんな風に姿を変えているか、楽しみにしながら日々の仕事に戻ることにします。
それでは、また。