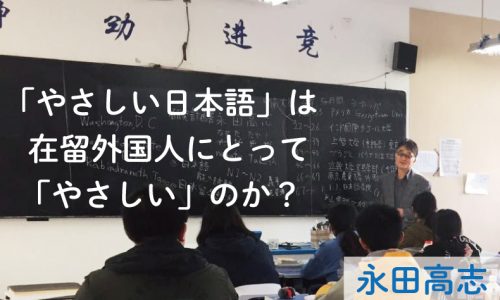島田康行・渡辺哲司
1.批評に応える
2021年1月に刊行した本書『あらためて、ライティングの高大接続』に対し、方々からおおむね好意的な感想がeメール等で寄せられてくるなか、丁寧な批評を個人のブログで呈示してくれた人がいる。自らを作文教育に興味のある国語科教員と称する「あすこま」氏だ。
https://askoma.info/2021/02/14/8264
そのコメントは、われわれ著者にとっては少々痛いが、思考を刺激される建設的なものでもあった。そこで、本書の著者8人のなかでも重い責任を負う2人がきちんと応答しようという話になり、このように版元のwebマガジンの誌面をお借りする次第である。あすこま氏の他にも、興味のある方は遠慮なく参入していただきたい。
2.「あすこま」氏による注意喚起
あすこま氏がわれわれに注意を呼びかけるのは、要するに、ライティング教育をもっぱら大学におけるアカデミック・ライティングの視点から見たのでは取りこぼしがある――という点だ。その理由・根拠として、氏は次のような事項を挙げる。
①そもそも高校までの「書くこと」の指導は大学の下請けではない。
②大学進学率が半分強であること(われわれが高大接続を“皆”の課題というときの、理由の一つ)は、裏返せば、半分弱は大学生にならないということだ。
③大学生には、レポートや論文を書く以外にも、言語生活者としてさまざまな「書くこと」があるはずだ。
そのうち①は、初等中等教育の人なら抱くのも当然の思い(違和感)である。また②③は、常識に基づく真っ当な指摘である。
そうしたあすこま氏の注意喚起を、われわれはひとまずそのまま受容しようと思う。そのうえで、われわれの立場や考え方を(本書では述べなかったことを含めて)説明したい。さらに、あすこま氏の視点を改めてわれわれのなかに取り込むようなつもりで、より高い次元で、高大接続という“窓”から日本のライティング教育の問題を覗き見て、考えてみたい。
3.われわれの立場・考え方
まず、あすこま氏とはいくぶん異なるであろう、われわれの立場や考え方を説明する。
現代日本において、小学校から中学校・高校を経て大学へと連なるライティング教育の不連続性やその不足点、不備なところが最も鮮烈に表面化するのは、高校と大学とのつなぎ目だ――とわれわれは見る(詳しくは本書の序章で述べた)。そこにこそ、日本のライティング教育に内在する問題を覗き込んで見るのに打ってつけの窓が開いているのだと。
それと同時に、そこ(高・大のつなぎ目)は、教育上の問題に世間の耳目を集めるのにも好適なポイントだと見る。先述のように、大学進学率が半分強(50%超)であることは、問題がそれなりに“皆”のものであると主張する際の根拠になる。そのうえ何より、世間が高い関心を寄せる大学入試とも絡んでいる。よって、そこを足場とすれば、日本のライティング教育について人々がもっとよく考えてくれるのではないか、議論も起きるのではないか――と考えるわけだ。
つまり、われわれがライティングの高大接続を、具体的な現象としては大学新入生がレポートを満足に書けないことを一書のメインテーマとするのは、そこ(高・大のつなぎ目)にしか関心が無いためでは決してなく、上記のようないくぶん戦略的な意図を腹中に蔵してのことだ。説明が足りなかったところは、素直に反省したい。
4.協働のための提案:「アカデミック・ライティング」再考
あすこま氏の注意喚起に応じ、氏の視点をも取り込んで、できるならば氏とともに問題の解決に取り組むべく、ここで一つの提案をしたい。それは、氏のコメント内にもしばしば登場する「アカデミック・ライティング」の語の意味を再考(再定義)することだ。
通常、英語のacademicは「学術的な」と和訳され、そうした(学術的な)文章の典型例として、論文(学術論文)やそれに準じた形のレポートが挙げられる。あすこま氏も、そうした意味でアカデミック・ライティングの語を用いているし、そのような用い方は、国際的に見てもべつだん問題を起こすようなものではない。
しかし、実のところ英語のacademicには、日本語の「学術的な」と比べていくぶんか広い意味があることを、われわれは経験から感知している。例えばacademic performanceは、小・中学生の学力テストの得点などを含む学業成績一般を指す。また、現在日本の教育界でも注目されるacademic language(学習言語)は、平易に言えば、学校で教師が「この子はできる」と思うときに「この子」が使っている言葉の総体であり、日常会話なら流暢にこなせる外国籍の子(非母語話者)の学業成績が振るわない場合のカギと見られるものだ。そうした用例から推察できるacademicの意味は、学術的などというものではなく「学校の」あるいは「学校的な状況における」というほどのものであって、大学やプロ研究者のサロンに限られるものではない。
そうして「アカデミック」の意味を「学校の」などと捉え直すと、小・中・高・大といった学校の区切りの意味は小さくなる――とは言えないだろうか。学校とは、本質的に、子どもが社会の構成員として育つための仕掛けあるいは場所として、意図的につくられたものである。言葉について言えば、状況・感情・背景知識などを共有する人たちに囲まれて「あれ」や「これ」で用が済んでいた小さな世界から、多様な人々に対して自分が見聞きしたこと(事実)や考えたこと(意見)を言葉で伝えなければやっていけない大きな世界へと出ていくための、訓練を積む場所である。そこには小・中・高はもちろん、幼稚園や大学までが等しく含まれるだろう。
また、そのように「アカデミック」の意味を捉え直すと、あすこま氏が言及する「ジャンル」すなわち文章の種別も、あまり気にしなくて済むようになるだろう。物語や詩歌は別としても、「一般的な論理的な文章」「生活に関わる実用文」などは、本質的にレポート・論文とは区別しがたいものだし、区別する必要もたぶんない。同じくあすこま氏が挙げる「引用の仕方」も、レポート・論文のために取り立てて学ぶというよりは、他者の意見を事実(fact)として表現・伝達するための技術として、もっと汎用的なものとして学ぶことができるだろう。
以上のことから、「アカデミック・ライティング」という語の意味の再考を通じて、われわれはよりよく協働できる――と思うがどうだろう。日本のライティング教育が抱える問題は大きく、根深く、その歴史も長い。それを解決するための取り組みは、過去の経緯から、とても息の長い(世代を超えるほどの時間を費やす)ものになると予想できるし、とにかく多くの人の手(皆でよってたかってやること)を必要とするだろう。そこで最も大事なのは「小異を捨てて大同につく」精神と、小異(小さな対立や矛盾)をより高い次元で統合し、発展的に解消しようとする――いわば弁証法的な止揚をはかる――態度であろう。われわれは、あすこま氏のような優れた実践家と、ともにやっていきたいのである。