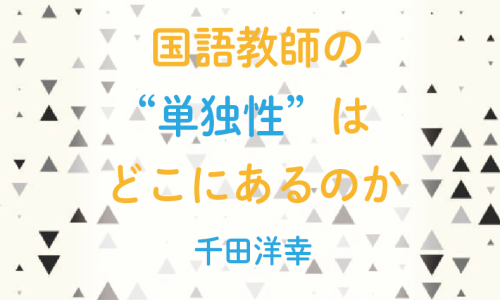『1Q84』の物語構成
村上春樹に関しては、さすがにここで詳細な紹介の必要もないかと思いますが、言うまでもなく世界的な名声を得た現代日本を代表する小説家のひとりだと言ってよいでしょう。本連載において何よりも重要なのは、村上が作家活動の初期から一貫して、いま・ここの時空間を揺さぶっていくような幻想的作風を得意としていたことです。今日ではもはや珍しいものではなくなりましたが、どちらかと言えばいわゆる身辺雑記的なリアリズム小説が支配的だった日本の文壇において、村上はやや特殊なタイプの書き手であったとも言えます。
『1Q84』は、2009年にBOOK1とBOOK2が刊行され、発売から半月後には瞬く間にミリオンセラーを獲得しました。翌年、事実上の続編となるBOOK3が刊行され、現時点で3部構成となっています。その筋立ては、予備校の数学教師をしている天吾という男性と、表向きはスポーツインストラクターをしているものの、実際には極秘で暗殺業を営む青豆という女性の視点が、交互に入れ替わるかたちで展開していきます。天吾と青豆は、10歳の頃に出会い、互いに強く惹かれ合っていたのですが、その後は長いあいだ離れ離れになっていました。
天吾は小説家を目指しており、その縁でふかえりという少女の書いた『空気さなぎ』という魅力的な小説作品と出会い、ふかえりと共同で『空気さなぎ』を完成させようとします。出来上がった『空気さなぎ』は新人賞を受賞し、好調な売れ行きを見せるのですが、天吾はあるとき夜空に月がふたつ浮かんでいるのに気づき、自分自身が『空気さなぎ』の物語世界に入り込んでしまったのではないかと考えるようになります。
一方の青豆は、ふとしたことで首都高速道路の非常階段を降りてから、何か違和感のある世界に迷い込んでしまったような感覚を抱き、その世界を「1Q84年」と名づけます。青豆は、「さきがけ」という宗教組織のリーダーを務めている男性を暗殺する依頼を受け、その任務を遂行するために奔走していくのですが、いざ始末のためにリーダーと対面した際、自分は「リトル・ピープル」という「1Q84年」の世界を支配する存在の声を聴くものであると知らされ、さらに現在の天吾の身に危険が迫っていることを告げられるのです。
その後、BOOK2の結末で、高速道路の非常階段が塞がれ、もはや「1984年」に戻れないことを自覚した青豆は、手にした拳銃で自殺を図ろうとするのですが、寸前のところで思いとどまり、さまざまな試行錯誤を重ねた結果、BOOK3の末尾でついに青豆と天吾は再会を果たします。ふたりはもとの世界(「1984年」)に帰還しようと試みますが、最終的に戻ってきた世界がもとの「1984年」なのかという確証のないまま、ともあれ新しい世界をふたりで生き抜いていくことを誓い合い、物語は終幕します。
ざっと上記のようにまとめましたが、『1Q84』にはほかにも「マザとドウタ」や「パシヴァとレシヴァ」など、謎の残る設定が多く導入されており、ここでそのすべてを仔細に検討することはできません。以下では、なかでも「1984年」と「1Q84年」という並行世界を往還することの意味に焦点を絞り、そこから村上作品にとっての並行世界の記述作法を考えてみたいと思います。
ひとつきりの現実世界
まずは、青豆が「1Q84年」に入り込んでしまったことをはっきりと自覚する場面を引用しておきましょう。
どこかの時点で私の知っている世界は消滅し、あるいは退場し、別の世界がそれにとって代わったのだ。レールのポイントが切り替わるみたいに。つまり、今ここにある私の意識はもとあった世界に属しているが、世界そのものはすでに別のものにかわってしまっている。
注目すべきなのは、「1984年」と「1Q84年」の世界が明確に異なった姿かたちをしているわけではなく、青豆も気づかないまま、いつの間にか別の世界に迷い込んでしまっていたということです。ふたつの世界は明確に異なる時間・場所に現れていたわけではなく、高速道路の非常階段を通じて、まさに地続きに繋がっていました。後述するように、こうした重なりのうちに描かれた物語世界の造形は、『1Q84』の作劇構造を考えるうえでも非常に重要なところです。(✳)
もっとも、自分の意識ではなく「世界そのもの」が「すでに別のものにかわってしまっている」という感覚は、村上作品のモチーフとして頻繁に導入されているものでした。そもそも、村上作品に並行世界が登場するのは『1Q84』が初めてではありません。すぐに思い出されるのは、本連載でも前に少し言及した『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』でしょう。この小説作品もまた、「世界の終り」と「ハードボイルド・ワンダーランド」という章が交互に展開し、ふたつの世界が並列しながら語られていく構成となっています。作中の後半で、「世界の終り」とは「ハードボイルド・ワンダーランド」の「私」の脳内に広がる心象風景であったことが明かされ、「世界の終り」の「僕」はそこからの脱出を試みるのですが、最終的に「僕」は「本当の現実」に戻ることを拒否し、壁に囲まれた街に戻ることを決断します。
このような『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』と『1Q84』の結末を比べたとき、どのようなことが見えてくるでしょうか。大澤真幸は、双方の小説作品がどちらも最終的には「虚構の世界」に滞留・逢着するという点で共鳴した主題系をなしていることを指摘しつつ、その前提のもとで、なお『1Q84』に固有の特質を見いだそうとします。大澤によれば「『1Q84』において、1984→1Q84→1984という移行の結果として、つまり現実世界の否定の否定を介して、到着点である現実世界(1984)は、それ自体、もう一つの並行世界として現象している」のであり、それを「起点となる現実世界から見たとき、現実世界は自分自身の否定(可能世界)の否定となっている」と言うのです。起点としての現実世界の〝現実らしさ〟をア・プリオリなものとして据えるのではなく、むしろ可能世界(並行世界)のあり方こそが時として〝現実らしい〟のであり、ゆえにもともとの現実世界を並行世界の断片とみなしていくような逆転した世界認識が、『1Q84』には描かれているのだと大澤は主張します。
ここで提示された大澤の読解に一定の説得力があることは間違いありませんが、しかし現実世界であろうと並行世界であろうと、ある特定の時空間のまとまりを唯一の特権的な〝現実らしさ〟の基盤として考えようとする趣向は、ともに暗黙の前提となっていたように思います。もっとも、それは並行世界を取り扱った物語文化の宿命のようなものかもしれません。たとえば、前田塁は『1Q84』を含めたゼロ年代の〝並行世界もの〟の物語様式について、「一方で私の今いるこの現実を設定し、他方で完全に架空の現実を設定して、主人公は両方を往復する」ものとまとめつつ、「それって結局は、一方の世界では現実世界が担保されていて、他方では架空性が担保されていて、そのどちらが居心地いいですか、みたいな話になる」と述べています(前田塁ほか「村上春樹とミニマリズムの時代」『思想地図』vol.4、東浩紀ほか編、日本放送出版協会、2009.11)。
先述したように『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の結末もまた、「ハードボイルド・ワンダーランド」ではなく「世界の終り」を自身が居るべき世界として承認していこうとするものでした。東浩紀の言葉を借りれば、それは確かに「現実よりも虚構を、自然主義のリアリズムよりも記号のリアリズムを選ぶことを明確に打ち出している」わけですが(「メタリアル・フィクションの誕生」『文学環境論集──東浩紀コレクションL』講談社、2007.4)、それでもなお「記号のリアリズム」こそが 特権的な〝現実らしさ〟を獲得しているという点で、それは(『1Q84』と同じく)どちらかひとつの世界を本位とする考え方の裏面に過ぎないとも言えるのです。
『1Q84』では、「見かけにだまされないように。現実というのは常にひとつきりです」という冒頭に登場するタクシードライバーの言葉が、物語全体を統制するかのように幾度も記述されます。そういう意味で『1Q84』は、少なくともある一面において、やはり自分(たち)が居るいま・ここを、「ひとつきり」の現実世界として受け止めていくような筋立てとなっていたと言えるでしょう。事実、BOOK3の結末は次のようなものでした。
ここがどんな世界か、まだ判明してはいない。しかしそれがどのような成り立ちを持った世界であれ、私はここに留まるだろう。青豆はそう思う。私たちはここに留まるだろう。この世界にはおそらくこの世界なりの脅威があり、危険が潜んでいるのだろう。そしてこの世界なりの多くの謎と矛盾に満ちているのだろう。行く先のわからない多くの暗い道を、私たちはこの先いくつも辿らなくてはならないかもしれない。しかしそれでもいい。かまわない。進んでそれを受け入れよう。私はここからもうどこにも行かない。どんなことがあろうと私たちは、このひとつきりの月を持った世界に踏み留まるのだ。天吾と私とこの小さなものの三人で。
(傍点原文、引用部は以下同様)
「ひょっとしてここはもうひとつの違う場所ではあるまいか」と疑いながらも、天吾と青豆は「進んでそれを受け入れよう」とします。もともと、青豆は「さきがけ」のリーダーから「1984年はもうどこにも存在」せず、「ドアは一方にしか開かない」と宣告されていました。その言葉を信じるか否かはともかく、「1Q84年」という別世界への予期せぬ渡航と、「1984年」と思しき世界への帰還という一連のプロセスが、自分自身が居るべき時空間はどちらの側にあるのかという問いを青豆たちに突きつけたことは確かでしょう。その意味で『1Q84』の長大なストーリーは、強い愛の力によって新しい世界を、自分たちが生きるべき本当の居場所として肯定するものであり、前述したように『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』ときわめて類似した物語構造を有しています。こうした〝ひとはどちらかの世界を選ばなければならない〟というテーゼは、かたちを変えつつも他の村上作品にも頻出するものでした。それを、たとえば高度情報社会に生きる人間の主体性を再考する契機として評価することもできるでしょう。しかし、同時に村上作品に対する批判を招くことにもなりました。その点を次節で見ておきましょう。
(✳)川村湊は、この点について「今までの『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』は完全に二つの世界が別個に、もちろん関わり合いはあるんだけど別個に存在していて、最終的に別個に存在しながらどこかで繋がってしまっていた」ものの、『1Q84』は「必ずしも別個の世界がパラレルに進んでいくのではなくて、実は繋がっている」という点に特有のリアリティを読み取っており、多くの示唆を得ました(「なぜこういう物語が展開されなければならなかったのか」『村上春樹『1Q84』をどう読むか』河出書房新社編集部編、河出書房新社、2009.7)。
拡張現実の拡張
『1Q84』に対する批判としてよく知られているもののひとつは、宇野常寛『リトル・ピープルの時代』(幻冬舎、2011.7)でしょう。宇野は、『1Q84』において強大な分かりやすい敵としての「ビッグ・ブラザー」ではなく、いま・ここの内側で散発的に現れ出る「新しい悪」としての「リトル・ピープル」を描いたことを評価しつつも、村上は「完全にビッグ・ブラザーが死に絶え、リトル・ピープルだけが存在する新しい世界を、新しい時代の私たちと世界との関係を、「巨大なもの」のイメージを、彼は多くの手がかりを提示しながらもまだ捉え切れていない」と喝破します。「内外で圧倒的な存在感をもつあの村上春樹の想像力ですら、加速度的に進行するこのリトル・ピープルの時代に追いつくだけで精一杯なのが現状」であり、「これはある種の──かつて「文学」と呼ばれた想像力の敗北でもある」と言うのです。
そして、宇野は「新しい悪」を描くための分析装置として、いま・ここのあり方を多様な仕方で読み換えていくような〈拡張現実〉(Augment Reality)の概念を導入することを提案します。その主張が端的にまとまった部分を引用しておきましょう。
ビッグ・ブラザー亡きあとのリトル・ピープルの時代──それは、世界が非人格的なネットワークによってひとつにつながれた時代、世界に〈外部〉が存在しなくなった時代だ。このとき、〈現実〉に対置し得るものはかつての意味での〈虚構〉ではあり得ない。かつてのように、失われた大きな物語を埋め合わせるために〈ここではない、どこか〉=〈外部〉に消費者たちを誘う「仮想現実」ではもはやあり得ないのだ。既に世界に〈外部〉が存在しないことが明白になった今、「仮想現実」的な〈反現実〉はもはや機能しない。世界には終りもなければ外部もない──そんなときに〈反現実〉として作用するもの、それが私たちの想像力によって彩られ、多重化した〈いま・ここ〉の現実、すなわち〈拡張現実〉なのだ。
宇野は、こうした〈拡張現実〉的な感性がむしろポップカルチャーの分野に散見されるものだと述べ、そこに「現代文学」の全般に関わるある種の臨界点を剔抉しようとします。あらゆる「現代文学」の作品群が宇野の言う〈拡張現実〉に応じきれていないのかどうかはともかく、ゼロ年代においては従来の「仮想現実」的なイマジネーションが成り立たず、ゆえにいま・ここの外側ではなく内側に沈潜し、その積極的な読み換えを試みなければならないという宇野の主張は、なおも啓発的な論点を提起していると言ってよいでしょう。こうした発想の淵源には、以下のような浅田彰の見解が関わっているものと思われます。これもしばしば今日の文化現象を語る際に援用されるものですが、重要なところなので長く引用しておきましょう。
ジル・ドゥルーズのわかりやすい言葉でいえば、この現実の他にいろんなポッシビリティ(可能性)があるということではなく、ほかならぬこの現実がヴァーチュアリティ(潜在性)においていかに多層的で豊かであるかを発見することが重要なんだ、と。そこのところを、その後に出てきたSFやアニメやコンピュータ・ゲームは全部間違えている。(…)今ここにある世界を一元的に固定した上で、それとは別の神秘的な可能世界をいろんな形で勝手に想定してしまうわけです。そして、その点からすれば、今ここでどんな無茶苦茶をしても別の世界で救われるんだ、ということになる。それはたんにくだらない妄想です。本当はこの現実しかない、言い換えればメタロジックなんてものはないんだから。
(浅田彰+中沢新一「オウムとは何だったのか」『諸君!』1995.8)
浅田いわく、ひとは「別の神秘的な可能世界をいろんな形で勝手に想定してしまう」ものだけれども、それでも最終的には「本当はこの現実しかない」ことを受け止め、現実世界の「潜在性」を発見していくべきなのです。それは、唯一の特権的な現実世界としてのいま・ここのあり方を掘り下げ、そこに「多層的」な豊かさを認めようという点で、間違いなく宇野の言う〈拡張現実〉の議論の下敷きとなるものでもありました。
こうした論の構えは、本連載の冒頭で示した柄谷の「単独性」をめぐる議論と同じように、ある種きわめて〝健全な〟〝正しい〟ものであったと言えます。しかし、僕はどうしても気になってしまうのですが、現実世界はただひとつであるという信念は、それほど普遍の前提として人びとに納得してもらえるのでしょうか。必ずしも、現実世界を唯一の特権的ないま・ここであると認めなくてもよく、しかし安易に「別の神秘的な可能世界」へと現実逃避することもないような仕方で、絶えず矛盾や錯誤のなかに揺曳する複数的な世界のありさまを受け止めることが、文学という営みには可能なのではないでしょうか。どちらが〝現実らしい〟のかという選択自体を宙吊りにし、いま・ここといつか・どこかを並存させながら語る ような表現戦略──そこに、宇野とは異なる意味での〈拡張現実〉的な感性の発現を認めてもよいように思えるのです。
村上作品のなかで、そのような趣向は『1Q84』よりも以前の長編小説『ねじまき鳥クロニクル』において徴候的に示されていました。
僕の意識の一部はまだ一軒の空き家としてそこにある。それと同時に僕は、僕としてこのソファーにいる。そしてこれからどうすればいいのだろうと考えている。どちらが現実なのか、僕にはまだうまく決められない。「ここ」という言葉が僕の中で少しずつ分裂していくような気がする。僕はここにいる。でも僕はここにもいる。僕にとってそれらは同じくらい真実であるように思える。僕はソファーに座ったままその奇妙な乖離の中に身を浸している。
(『ねじまき鳥クロニクル〈第3部〉鳥刺し男編』新潮社、1995.8)
上の場面に描かれているのは、「一軒の空き家」と「このソファー」のどちらにも跨った「僕の意識」の多元的なありさまです。芳川泰久は、この場面について「多世界のそれぞれを〈いま・ここ〉として「僕」が生きるということにほかならない」と述べつつ、「〈切断〉によって〈いま・ここ〉には「もう無い」世界を、つまり〈ここ〉からは決定的に失われ、もはやぎりぎり〈そこ〉としか指呼しえないほど不可能になった世界を、もう一つの〈ここ〉として召喚可能にしているのである」と述べています(『村上春樹とハルキムラカミ──精神分析する作家』ミネルヴァ書房、2010.4)。まさに、みずからの帰属する世界の造形が分裂し、どちらが本当の意味での「ここ」なのかという問い自体を成り立たなくさせる意識のあり方が、『ねじまき鳥クロニクル』には書き込まれていたのだと言えるでしょう。
ならば『1Q84』のなかで、こうした「ここ」の認識論的な多層性は、どのような仕方で描かれていたでしょうか。
私はたまたまここに運び込まれたのではない。
それがそのイメージの訴えかけることだ。
私はいるべくしてここにいるのだ。
私は誰かの意思に巻き込まれ、心ならずもここに運び込まれたただの受動的な存在ではない。たしかにそういう部分もあるだろう。でも同時に、私はここにいることを自ら選び取ってもいる。
ここにいることは私自身の主体的な意思でもあるのだ。
もともとの世界(「1984年」)に自分の拠りどころを求めつつも、青豆は新しい世界(「1Q84年」)に生きることを「主体的な意思」によって「選び取っても」いました。前節で見たように、「1Q84年」の世界が「1984年」の世界に重なり合うような存立構造をしていたことを想起してみれば、こうした青豆の決断に、ふたつの世界に跨って「主体的な意思」を発露していくような、宇野とは異なる意味での〈拡張現実〉的な表現の発露を読み取ることができるでしょう。つまり、ひとはどちらかの世界を選ばなければならないという〝健全な〟テーゼを回避し、複数的で多元的な世界に対する矛盾や錯誤を肯定するような信念のあり方が、この場面には断片的ながら見いだされるのです。
別の箇所でも、青豆は自分のいる「1Q84年」が、天吾の書いた小説作品の一部なのではないかと考えたうえで、「それは天吾の物語であると同時に、私の物語でもあるのだ」と述べていました。そして、天吾と再会を果たした際、青豆が「1Q84年」と呼んでいた時空が、天吾にとっては「猫の町」と名づけられたものであったことが明かされ、双方にとって異なっていた世界の造形は、結末において同じ「ひとつきり」のものとして再定位されるのです。
言わば、青豆にとっての並行世界と天吾にとっての並行世界は、各々に異なる相貌をしていながらも 同じいま・ここだったのであり、その意味で『1Q84』は、それぞれの生きる世界の多様な現れ方を、まさに並行世界として描き出そうとするものでした。村上作品の文学的想像力は、こうした「ひとつきり」の世界の認識論的な重層性を、時空間そのものの存在論的な分裂として記述することに、その表現戦略の意義を認めることができるのではないでしょうか。
その後の村上春樹は、幾つかの短編とまとまった長編を交互に発表するという、『1Q84』以前から続いていた執筆のリズムを崩すことなく、2017年には『騎士団長殺し』(新潮社、2017.2)という長編小説を刊行しています。『騎士団長殺し』は、直截的に並行世界が描かれているわけではありませんが、現実世界とは異なる秩序法則で動く地下世界の探究など、いま・ここに沈潜するイメージの豊かさを描くという試みは共有されています。こうした物語様式が、ともあれ「純文学」の書き手としては異例なほど多くのファンを獲得してきたことの背景には、やはり今回見てきたような並行世界の記述作法が、時代状況と分かち難く結びつくかたちで関係づけられるように思うのです。
次回は、新海誠監督の映画『君の名は。』(コミックス・ウェーブ・フィルム、2016)を扱ってみたいと思います。