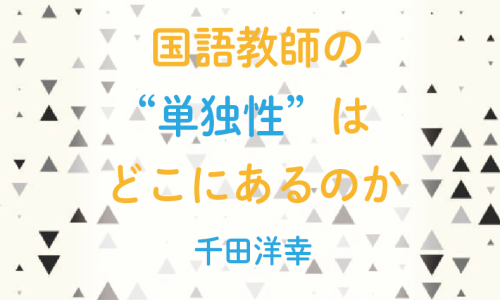ヒシヒシと感じる鮮やかな才能
重里徹也 思い出深い作品です。一九七六年の初出時に「群像」で読みました。芥川賞を受賞することを予言して、友人たちに面目をほどこしました。
助川幸逸郎 どんなふうに感じられましたか。同時代に読まれて、衝撃的でしたか?
重里 力があるな、イメージが鮮烈だな、全体がよくつかめないなりに、これは何ものかだな、という感じですね。否定的なことをいう人もいましたが、小説が読めない人だなとブラックリストにメモしました(笑)。実は当時、私は大学受験のために浪人していたのです。予備校に通いながら、あまり熱のこもらない、といっても、サボってしまうわけでもない受験勉強をしていました。それで、今、整理すると二つのことを思ったのですね。
一つは自分とは全く違う、こんな青春があるのだなあということです(笑)。それはそれで衝撃的でした。薬物と乱交パーティーとロックの青春。自分との距離の大きさを感じました。ところが、もう一つ、思ったことがあったのです。それは矛盾するようだけれど、これは明らかに自分の内面も代弁してくれている小説だということでした。たとえば、こんな箇所ですね。主人公とリリーが雷雨の中、自動車を走らせて、学校の校舎にたどり着いた場面。
<規則正しく並んでいる机と椅子は、無名戦士の共同墓地を思わせる>
しっかりと私の思いを代弁してくれているじゃないかと思ったのです(笑)。
助川 私は今回三十年ぶりくらいに読み返しました。書き出しの一ページを読んでまず思ったのは、これを書いたひとは、本当に特別な才能だなということですね。描写のつなぎ方とか、文章の呼吸みたいなものから、天才といってもいい筆力をヒシヒシと感じました。
重里 私も今回、何回目かに読み返して、とても優れた作品だなと改めて思いました。非常に優れた小説ですね。こういう形で、敗戦後三十年経った日本人の内面を描いたんだなっていうのを改めて感じました。
敗戦後三十年の日本の貧しさ
助川 そうです。たいへんシャープな作品なんですけれども、ただ中に書かれている出来事は、本当に単調でつまらないんです。だけどそれは、村上龍の発想の乏しさとかではなくて、戦後三十年目の日本の貧しさですよ。最後に鳥がいて、自分は鳥を映すんだって言っていますけど、本当に鳥を映している膜みたいになっているんですよね、この作品自体が。
重里 鳥って何なんですか。
助川 アメリカを中心とした外部だと思いますね。
重里 私もそう思います。主人公のリュウは自分自身を人形だと思いますね。モノだと思う。その次には空っぽだと思う。何回か、空っぽという言葉が出てきますね。最後に出てくるのが、タイトルになっている限りなく透明に近いブルーですね。ガラスの破片ですけれども。自分自身をそんな風にたとえていることに、非常に切実なリアリティーを感じました。
助川 そうですね。
重里 ただ、この作品が世評とは違うのは、アクティブな小説ではないんですよね。
助川 そうです。
重里 観察している小説ですね。見る小説です。主人公のリュウはずっと自分の外を見ているのですね。
助川 三島由紀夫は志賀直哉のことを、「すぐれた文章家だが、文体がない」と評しています。三島に言わせると三島に言わせると、文体というのは世界解釈をするためのツールなんです。志賀直哉は、一個の私心なき純粋な感受性である、ただ世界を感じるだけで解釈はしない。それで、素晴らしい文章家ではあるけれど、志賀は文体を持たないんだと三島は言っています。三島の見解では川端康成も、志賀と同じ意味において文体のない作家です。
この『ブルー』の文章も、解釈をしないで世界に対するセンサーとして生きている人間の言葉です。三島が生きていたら、「村上龍は天才的な名文家だが文体を持たない」と評したかもしれません。
重里 それは、わざと、意識的にやっていますね。フラットに凸凹つけないで世界を映し出している。そういう描写の力をまざまざと感じました。
助川 本当にセンサーに徹した視点から書かれているいうことですね。それが結局最後のガラスの破片のイメージに、世界を映し出すブルーのガラスのイメージに結晶していく。
重里 確か大岡信が指摘していたけれど、これは自我論にもなっていますね。自我というものをそういう風にしたいんだ、ということですね。透明なガラスの破片のようなものにしたい。
助川 出てくる音楽も映画も全部アメリカのものです。戦後の日本は、もちろん軍事的・政治的にはアメリカの支配下にあります。加えて、文化的にもアメリカの作品がいっぱい入り込んできて、こちらの方でもアメリカの属国みたいになっている。でも、多くの日本人が、そのことを直視していない。そうした「戦後日本人の鈍さ」に苛立ち、「アメリカに圧倒されている自分」を描くことによって、戦後日本の隷属状況を白日の下にさらそうとした。それが、この『ブルー』なんだと思います。
重里 そういうことですね。そして、そこにとても生々しくて、切実なものを感じますね。
助川 村上龍はその後ずっと書いていくわけですけれども、佐世保に生まれて、アメリカに晒されて育った。そういう人間が上京後、福生に行ったというのは、わかるような気がします。あたかもアメリカの影がないが如く生きている東京の人々を見て、耐えられなくなったのではないでしょうか。それで、深海魚が水圧を求めるように、アメリカの支配が可視化されている環境を求めた。そうやって見つけた場所が米軍基地のある福生だった、というのがすごく伝わってきますよね。
対照的な静と動
重里 主人公をめぐる人間関係が二つのグループに分かれているのですね。つまり、一つはリュウとリリーの生活。もう一つはそれ以外の若者たちの集団。リュウだけがその両方に属していて、意識的に分けていますね。
助川 そうなんです。それで、リリーといるときはものすごく描写が静かなんですよね。
重里 静と動が対照的ですね。
助川 本当にそうですね。結局、リリー以外の連中といるときは、薬物でラリったり、黒人を交えて乱交したりして、ゴタゴタやっているんです。静と動の対比がものすごく効いていて、リュウが純粋なセンサーなんだ、というのはリリーのシーンがあることによって、よけい際立っていますよね。
重里 際立っています。
助川 リュウという主人公は、乱交パーティーみたいなものの手配師をしているわけですよね。それで自分の手配したパーティーに参加して、麻薬をやったりセックスしたりしている。パーティーの渦中にいるプレーヤー的なところと、そういう状況を手配師として演出しているメタな部分と、リュウには両方の性格がある。その演出家、メタレベルに立っているリュウという目線が、リリーのいるところで、たぶん現れているんだろうなって思って読んでいました。
重里 なるほど、よくわかります。
助川 それによって、ダイナミックに見える乱交シーンでも、リュウが実は完全に受け身であるということがしっかり見えてくる構造になっているんだと思うんですよね。
重里 そして、メタレベルの観察者、リュウというものが、実は村上龍の真骨頂のように思います。これは世評と違うかもしれませんが。
助川 今回ちょっと面白いなって思ったのが、村上龍が結局ずっとアメリカにやられっぱなしの日本という状況を作品にしていたのに、バブルのあたりで変化するということです。『テニスボーイの憂鬱』(一九八五年)の前半と後半が全然違うんだ、という論文を昔、書いたことがあります。アメリカに隷属している日本から、ある種一等国になって堂々としている日本という自国に対する認識の移り変わりが、村上龍にあったと思うんです。そしてこの村上龍の「転向」は、日本人全体の自己意識が変わったことを反映しています、バブル前夜の一九八四年ぐらいに、「もはや目標とするべき外国のない一等国」だと日本人は自国を考えるようになった。『テニスボーイ~』は、この変化を鋭敏にとらえた作品です。
それで、そこから例えば『五分後の世界』(一九九四年)みたいな方向に行くんだと思うんです。『限りなく透明に近いブルー』を書いている段階の村上龍なら、『五分後の世界』みたいな状況は仮想としてもありえない、日本人はあんな根性のある民族ではない、といったと思うんです。ところが『テニスボーイ~』の第一部と第二部の境目の段階で、日本は実はもう少しきちんとやれる国なんだ、という風に村上龍は考えるようになった。
この村上龍の変貌は、例えば古井由吉の軌跡とある意味でパラレルなように見えます。『槿(あさがお)』ような「小説らしい小説」を書く方向性を断念して、「古典の世界と対話する自分自身」を書くようになっていった古井由吉の転換と、村上龍の転換は時代的に重なっています。
バブル前夜に、日本は大きく変化したのだけれど、今でも日本人は、あの時、何が起こったのかということを整理しきれていないと思うのです。バブル後の失われた二十五年、とか言われていますけれども、バブルの前後に起こった変化をきちんと理解しないと、日本は停滞からは抜け出せないのではないか。そういう感じを、今回『ブルー』を読みかえしながら改めて思いました。
「行動」ではなく「観察」の作家
重里 私はずっと村上龍の小説をリアルタイムで読んできました。それで彼の資質ということをよく考えます。それは、このデビュー作に現れているように、「アクション」の作家ではなくて「見る」作家なのだ、「観察」の作家なのだ、ということですね。行動する作家ではなくて、自分自身の内面や自分の周囲や社会の情況を観察する作家だということです。彼の印象に残る作品というのは、長編だと『テニスボーイの憂鬱』であり、『心はあなたのもとに』(二〇一一年)であり、最近作の『MISSING 失われているもの』(二〇二〇年)なのですね。あるいは評価する人が多い『料理小説集』(一九八八年)や『映画小説集』(一九九五年)といった短編集になるわけです。村上龍は、ちょっと世間の評判とは違うところに真価があるんじゃないか、というのがずっと読んできた私の考えなんですけれども。
助川 それは本当にそうだと思いますね。梶井基次郎の『ある心の風景』に、「視ること、それはもうなにかなのだ」という一節があります。それで『ブルー』の中でも、見ることは楽しいよ、とリュウは言うわけです。こんなことは誰も言っていませんが、村上龍はある意味梶井基次郎に似ています。村上龍は、視点人物が何かを起こすときより、何かが起こるのを見ている場面で筆が冴える作家です。
重里 非日常の作家みたいな感じがありますけれども、そうではなくて、実は「その状況下における日常」を観察する作家なんじゃないか、という風に思いますね。
助川 それは本当にその通りですね。
重里 日常のちょっとした裂け目に非常に敏感で、それを深く描く作家ですね。基本的には、日常を描く作家なんだと思います。
助川 「日常のちょっとした裂け目」というと、『コインロッカー・ベイビーズ』(一九八〇年)に印象的な場面があります。ハシが養父母と一緒に上京してきて、高級レストランに行くんです。そこのレストランではピアノの生演奏をやっていて、ハシの養母が「何かリクエストはないか」って訊かれて、「牧場の朝」って言うんです、恥ずかしそうな小声で。「牧場の朝」は小学校の音楽でやる歌ですよね。都会の高級レストランで「牧場の朝」をリクエストしてしまう場違いさ。そこに、ハシの養父母の貧しさ、もっといえば戦後日本の庶民の貧しさが端的に表されています。こういうところに、村上龍の才能の本領があると思うんです。たしかこの場面の「場違いさ」の意味については、三浦雅士がどこかに書いていたように記憶するのですが。
重里 そこはね、村上龍自身はあまり意識しないで、無意識でやっているんじゃないか、という気がします。無意識でどんどん書けてしまうのじゃないかな。アクションの部分は意識的にやっているわけです。頑張っているわけです。迫力のある描写が楽しめます。けれども、そのアクションを見ている人物、あるいは、ふと我にかえる人物、さめて状況を感じている人物は、無意識にどんどん書けるのではないかという印象を持ちます。そして、そこに村上龍の本当の魅力、奥深い魅力があるのではないか、という気がします。
それは『半島を出よ』(二〇〇五年)でもそうですね。北朝鮮のコマンドが福岡に上陸する。激しいアクションは魅力的なのですよ。でも、それを東京から映像で見ている人物がいるわけです。その描写は天才としか評することができない奥深さがあります。それが村上龍でしか描けないシーンなのだと思います。日常を描きながら、登場人物が裂け目や違和感、不協和音を感じ取って、それを面白がったり、それに引き込まれたりするわけです。そこが村上龍の真骨頂ではないかと思います。このことは、あるいは本人は意識していないかもしれない。この作家は、実はまだまだ論じられるべきものがあるような気がするのですけれど。どうですか。
助川 ある程度は言及はされているけれども、それが村上龍の本質にかかわるということは言われていない気がします。
『昭和歌謡大全集』(一九九四年)にテロリストになっていく女子学生が出てきます。彼女が通っている学校が「花びら女子短大」っていうんですね。九〇年代当時、都心の低レベル短大に通っていた学生の「緩さ」というか「能天気さ」っていうのが、「花びら女子短大」という名前によってすごくコミカルに表現されているわけです。このネーミング、スゲーなあって思って、読みながら大爆笑しちゃいました。
重里 文学的にはかなり大きい存在で、これからさらに論じられていく作家なんだろうと思いますが。
文学界の清原和博
助川 ただやっぱり私は、ある種、清原和博だなと思うところがありますね、村上龍は。もちろん清原も通算五百本以上のホームランを打って、実績は一流なんですけれど、彼の才能から考えたら、ホームラン王を五回くらい獲っていてもいいですよね。
重里 そうなんです。
助川 あの才能で、シーズンに四十本以上打ったことが一度もないというのは、残念なことですね。シーズン五十本、通算六百五十本、打ってもいい。
重里 最近、元・プロ野球選手が盛んにユーチューブに出るようになりましたね。ときどき面白い番組があります。それで、ある番組で清原が藤川球児と対談していたのですね。藤川球児が質問するわけです。「今もし逆指名できたら、高校三年生で、どこの球団に行きたいですか」。そうしたら、清原は何て言ったと思いますか?
助川 阪神ですか?
重里 はい、そうなのです。阪神って言ったわけですよ。今ごろ分かったんか、ということですよね。もっと早く気づいてくれよ、ということです。今の話を聞いていて、それを思い出しました。村上龍にもそういうところがあるのではないですか。
助川 清原は巨人に入りたがって、道を誤ったのかもしれません。
重里 そう思います。現役時代は勘違いがあったような気がします。ドラフトだからどうしようもないけれど、もし、PLから阪神に入っていたら、永久欠番になるような選手になったかもしれません。時代を体現する存在になったでしょう。そんなことを考えていました。
助川 そういえば、ひところ山田詠美が、中沢新一との対談集(『ファンダメンタルなふたり』一九九一)なんかで、「村上龍はバブルで浮かれてトチ狂った」みたいな批判をしていました。山田は、『テニスボーイ~』後半以降の村上龍の展開に、いろいろ感じるものがあったのではないかと思います。巨人に行きたがる村上龍に対し、「お前は阪神とか西鉄向きのキャラで、巨人はガラじゃない」と言いたかったのかもしれません。
重里 星野仙一にしても、田淵幸一にしても、山本浩二にしても、巨人に行かないことで大成したのだと思います。
助川 そんなところですかね、結論としては。
重里 一つだけ、残しておきたいことがあるのです。井上靖が芥川賞の選評でこの作品を支持しています。それもあって、僅差で受賞したわけです。この作品に反発した選考委員もいたわけですね。ギリギリでの受賞です。ウィキペディアによると、井上靖は当初、反対票を入れようとしていたが、息子に提案されて支持することになったと記述されています。
私は「ウィキペディアを引用する時は必ず、典拠にさかのぼって裏を取れ」と常日頃、学生に教えています。それで、私も、ことの経緯を井上の長男の井上修一・筑波大学名誉教授(ドイツ文学)に直接に尋ねました。井上靖研究会で、年に二回ぐらいお会いするのです。確かに、その通りだということでした。これはいい作品だ、ということを父親に言ったというのですね。ギリギリの受賞だったことを考えると、修一先生の言葉が村上龍に芥川賞を受賞させた、という面があるかもしれません。感慨がありました。
助川 それである意味、歴史が変わったわけですね。
重里 日本の文学史が変わったかもしれませんね。現実というのは、面白いものですね。