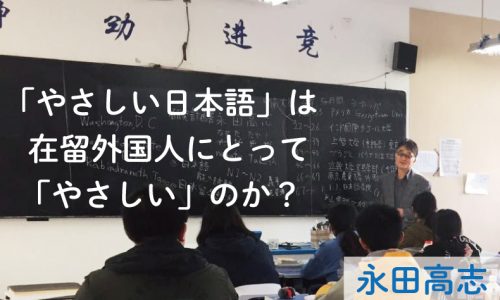在日コリアンと日本語
重里徹也 初めて外国籍の書き手が芥川賞を受賞した作品ということになります。在日コリアン作家にとって、日本語とは何なのか。そんなことも考えさせられる作品です。小説としても、とても印象的なものです。
助川幸逸郎 作品を読んでいると、いくつか日本語が不自然なところがあります。言い回し的に言って。李恢成は日本で生まれているんですけれども、完全なる日本語ネイティブという感じではないんでしょうかね。
重里 デリケートなところですね。同時にこの作品の魅力ともかかわることだと思います。李の両親は朝鮮半島の出身ですね。李は在日二世になるわけです。だから、ハングルと日本語と二つの言語の間で生きてきたのだろうと思います。ただ、北田幸恵による「作家案内」(『またふたたびの道・砧をうつ女』講談社文芸文庫に所収)によると、李は一九三五年に樺太の真岡町(現・ホルムスク市)で生まれ、一九四七年に札幌に引き揚げています。札幌西高校から、早稲田大学の露文科卒業ですね。日本語を日常語として身に着ける一方、ハングルでは小説を書けないことに直面したと記されています。
助川 立原正秋は、朝鮮半島に生まれています。立原の第一言語はだから、日本語ではなく、ハングルなのですね。物心ついてから習得した日本語で書いているから、立原の文章はとても明晰で、英語に訳しやすいといわれているようです。立原自身は、自分では韓国の血を引いて日本に生まれたと称していましたが、実は生まれたのも韓国だったと、高井有一が立原の評伝の中で明らかにしています。立原は韓国に生まれたから、彼の日本語は、子どもの時はたどたどしかったらしいです。そういう人物だから立原は、日本語となれあわなかった。それが「英語に訳しやすい明晰さ」とつながったのでしょう。
この李恢成の文章も、日本語ネイティブではない人の日本語という感じがします。母語というものの意味を、改めて考えさせる日本語だなと思いましたね。
一つ一つ確かめながら書かれた言葉
重里 私がまず感じたのは、センテンス(一文)が短いことですね。短いセンテンスが連なっていく文章で、何か言葉の一つ一つの意味、文の一つ一つのつながりを確かめながら書いているような、そういう文章ですね。一つ一つの言葉をとても大切にしていて、これでいいのかどうかということを確認しながら書き連ねている小説といえばいいでしょうか。そんな感じがしました。言葉がとても確かなのですね。何度もたたきながら、石橋を渡っているのです。
それがすごくいいな、と思ったわけです。何か、そこからにじみ出てくるようなものがある。それが、先ほど言った最初は「母国語」であるハングルで小説を書こうとしたけれども、書けなかったという体験とつながっているように思います。父母の地である朝鮮半島は植民地になっている。その朝鮮半島の言葉で創作を試みたけれども、自分にとっては不自由な言葉でなかなか書けない。小説は結局、植民地の宗主国の言葉である日本語でないと書けないことがわかった。この非常に切ない矛盾を引き受けている日本語なのじゃないのかなと思うわけです。そこが独特の切実なリアリティーを生んでいる。緊張感と確かさを生んでいる。
助川 はい。けれども、これ、母親を書いていて、非常に母性への憧れを書いているわけです。そのことと、母語ではない、体と密着しているわけではない言語で書いているということ、この矛盾がとても効いている作品だと私も思います。男性作家が母親像を描くと、母なるものに対して抱いている理想像みたいなものと、その男性の実際の母親に対する感情みたいなものがドベーッと混ぜこぜになってしまっている場合が多いと思います。そうなると単なるマザコン小説になってしまって、女性から見るとちょっとついていけないみたいなところが出てくると思うんです。
これは母語にもたれかかってナチュラルなものとして母性を描いていないだけに、逆にすごく抽象的な、イデアルな母性みたいなものの表現に成功していると思うのですね。男性が「母性なるもの」に対して感じる飢えみたいなものを、非常に抽象化というか、普遍化して書いているところがある。そこがこの作品の成功の一つの原因かもしれない、という感じが私はしました。
重里 つまり、女性に対して抑圧的であることを感じさせない母性ですね。母性を男がマザコンのままにベタッと書くと、女性が読むと非常に抑圧的な感じがするのだと思います。それはステレオタイプな母親という立場を無理やりに押し付けられているような感じがするからですね。この小説はそれを免れている。つまりそこのところが相対化されているのです。なぜ、そういうことができたかというと、宗主国の言葉で小説を書いているという意識が、いい意味での距離感をもたらしているからだと思うのです。それで、危うい薄氷を歩くような感じで日本語が連ねられている。その結果、そういうイデアルな母性みたいなものを表現することができたのじゃないかと考えます。母親像というものが純粋化され、洗練されているのだと思います。
母親を描く意味
助川 やっぱりあのおばあちゃん(主人公である「僕」の母親の母)が出てきて、孫である語り手を抱きしめる。それで、おばあちゃんくさくて嫌だ、みたいな場面が出てくる。ああいうのも、とても効いていますね。それで、「僕」の祖母が娘(「僕」の母親)を語るわけです。
そういう形で、単に母親が母親として語られているだけではなくて、娘としても語られている。子どもから母親を語る立場と、母親から娘を語る視線とが交錯しているわけです。ここのところも、この作品が非常に成功している要因ではないかと思います。要するにこの母親像がとても立体的に描かれているわけですね。これも成功の理由なのかな、という気がしましたね。
重里 語り手の「僕」の祖母も、語り手の「僕」自身も、母親のことを「張術伊(チャン・スリ)」とか、「術伊」と、名前で呼びますね。それも、この女性を客観的に浮かび上がらせる要因になっていると思います。また、その祖母が「僕」の母親に寄せる感情も、「僕」の母親に対する思いも、うまく相対化されて描かれている。これがこの小説の魅力ですね。
助川 あの語り手になっている主人公のおばあちゃんは、主人公の母親と実の親子ではありません。語り手のおばあちゃんは、「母」として「娘」を哀惜している。けれどもおばあちゃんは、血のつながりによってあらかじめ担保された「母性本能」に促されてそうしているわけではないのです。そういう形で、「母性」とは「本能」ではなく「関係性」なんだ、ということが明確に示されている。このあたりにも、この小説が「母性」を描きながら「マザコン文学」になっていない秘密があるように思います。
重里 文章も、人物の描き方も、とても清々しいのですね。ベタベタしない。樺太の風土もあるのかなあ。
助川 私はこういう「男性が自分の母親について語る小説」って、基本的にあまり好きではないんですけれど、この作品は好感を持って読むことが出来ました。
重里 私は少年とか、子どもとかを主人公にした小説って、あまり好きではないのですよ。つまり作家自身を思わせる少年が出てきて、彼を主人公にして幼少時の象徴的な出来事を描くというタイプの小説ですね。そういうのは、あまり好みません。そういう小説は、作品としての完成度が高くなりがちです。子どもの視点で描くので、いろいろなことを書かないで済ませられるからです。たとえば、世の中の複雑な事情とか、男と女のこととか、広い意味での政治的な駆け引きとか。そういうものは子どもの視野に明瞭には入ってきにくい。そういうことをはっきりと描かないで済むので、小説世界をまとめられやすい。それで完成度が高くなる。
芥川賞や三島由紀夫賞の受賞作には、あるいは、その他の新人が対象の文学賞受賞作には、そういうものがけっこうあるように思います。完成度を高くしやすいから、目立った欠点が少なくなる。複数の選考委員が、欠点を指摘しながら選考を進めていくと、残りやすいのです。だから、私はこの作品を読む時にも、やっぱりかなり警戒して読んだのです。でも、読み進むうちにそういう警戒が必要ではない作品だなと感じました。
人間を描くということ
助川 選評を読むと、李恢成はこのようなエモーショナルな作品ではなくて、もっと問題意識を尖らせたような作品で受賞してほしかった、というものもあるのですけれども、その点に関してはどうお考えですか。
重里 これはね、芥川賞というものの性格を感じますね。
助川 はい。
重里 この作品が小説として優れていると評価することに、芥川賞の立場というものが現れているのではないでしょうか。
助川 具体的にいうとどういうことですか。
重里 しっかり人間を描け、ということですよね。
助川 うーん。
重里 井上靖や瀧井孝作が高く評価していますね。なるほど、と思いました。
助川 在日コリアンの人ならではの問題をストレートに打ち出した作品っていうのにも意味があると思うんです。しかしこの小説の場合、在日コリアンの人物を描きつつ、もっと抽象度の高い普遍的な問題に届いているように思います。政治的な背景だとか、時代的な状況だとかを知らなくても深く味わえるところがあって、こういう作品もありではないか、という気がします。
母を描く意味
重里 ところで、二つの民族で揺れ動くような場合に、父親ではなく、母親を描くと優れた作品が生まれやすいような感じがするのですけれど、その辺はいかがですか。
助川 そうなんですね。これは内田樹が言っているんですけど、国家というものが父性なんですね。だから、父性の問題というものは、やはり、それなりに民族を区切っていったり、家を区切っていったりするわけです。
それに対して母というのはもっと普遍的、一般的なものです。多分これを父の問題で書いてしまうともっと民族対立が前面に出てきてしまうように思います。
重里 複雑で難しい問題になってしまいがちですね。
助川 母の方から、妻の方から、女性の側に焦点をあてて描くと、たぶん、民族対立みたいなものを超えた普遍的なベースが出てくるのでしょう。だからこそ、逆に二つの民族が対立しているという問題が、どちらの側にとっても共感できるような形で描けるんじゃないかな、と思うのです。
重里 これはね、文学というものの面白いところだと思うのですよ。真正面から描こうとすると上手くいかないのだけれど、ちょっと迂回したり、斜めや横から見たり、視点を低くしたり、裏側から見たりすると、とても鮮やかに対象が浮き彫りになるというところがあるのですね。
ただ、母親という存在は生活レベルのつながりを直接に感じさせるものですね。そういうものの強さから、国家とか、民族とか、そういったものが相対化されるということもあるのでしょうね。
助川 はい。本当に。文学でしか描けない問題というものについて、この頃つくづく考えるんです。昨日も授業で話していたんですけどもね。
重里 その文学でしか描けない問題というものに対して、芥川賞はとても敏感なところがありますね。それは、実際に小説を書いてきた実作者が選ぶ文学賞だからだと思います。評論家が選ぶのとは違うのだということを私は強調したいです。そして、このことは、芥川賞がメジャーな賞であり続けていることの理由の一つでもあると思うのです。
助川 評論家はやっぱり論じやすい作品が好きですから。
重里 あまり良質ではない評論家は、図式的な小説が好きですね。文学研究者も、そういうところがありますね。
小説は腹で読め
助川 論じやすい作品というのは、問題がはっきりと提出されている作品です。だけど、実作者はその問題がはっきり出ているかどうかということよりは、その問題が抽象的ではなくて、実感として腹に、頭じゃなくて、腹に響くかどうかっていうことで判断しますね。明確じゃなくてもいいから、しっかりとお腹に届くかどうかっていう観点から実作者は選びます。どうしても評論家は頭で明確にわかるように問題が書かれた作品を評価しがちですね。
重里 二流の評論家には、頭のいい人が多いからでしょうね(笑)。彼らは明快に図式が描けるもの、わざとらしいぐらいに「問題」が提示されている小説を評価しますね。それは能力の低い評論家ほど、そうですね。それで、わかりやすい作品を称賛してしまう。その怖さはありますね。ときには何かのイデオロギーを使って評価し、ときには状況論にからめて批評する。新聞記事みたいな図式を好むのですね。
小説は頭でもなく、胸でもなく、やっぱり腹で判断すべきですね。小説は腹で読み、評する時は手で書くべきです。これは鉄則ですね。頭で書いたり、頭で評したりしていたら、ろくなことはない。腹に響く小説を選ぶということで、芥川賞はメジャーな賞であり続けているのだと思います。そのために、頭では整理しにくいものも、評価できるという面があります。これが、実作者が選ぶ芥川賞の歴史として考えられるのではないかと思います。
「人間を描けているか」というのは、よく問題になる言葉ですね。直木賞でもよく議論されます。人間を描けているか。他のいい方もあります。その人物の体臭が伝わってくるか、その人間の顔が見えるか、その人物が向こうから歩いて来たら、わかるか。人物が立体的に描けているか。書き割り(舞台の背景などを平面的に描いた大道具)のように平板ではないか。その人物と握手をしたいか。一方で、作家は自分の腸(はらわた)を見せているか、という評し方もあります。「人間を描く方法にもいろいろあるだろう」という反論もあるだろうし、「現代人は体臭などしない」とか、「平板な人物像にリアリティーがある」とか、そんなことを言いたい人もいるでしょう。けれども、そういう言辞は小説というものを根底で捉え損ねているように思いますね。やはり、人間を描いてこその小説だと思うわけです。
助川 確かに人間をしっかり描いた小説は魅力的です。ただ、「世界が滅びる」みたいな感覚をキラキラしたことばで語る三島由紀夫の小説なんかも心にしみるわけです。古山高麗雄や李恢成の作品もいいけど、三島由紀夫も魅力的です。「人間」という言葉は広くとらえたいですね。
重里 もちろんそうですね。その通りだと思います。大江健三郎や古井由吉の受賞作も、見事に「人間」を描いています。ただ、候補になった新人の小説から一作か二作を選ぶ時に、芥川賞はわりとうまくやっている。それは実作者が図式や論理で選んでいるのではないからだ、ということを思います。このことは、芥川賞というシステムが長い年月にわたって機能している理由の一つだと考えます。
ところで、李恢成という作家については、この講談社文芸文庫も絶版になっていますけれども、今また読まれるといいな、という作家ですね。この作品を評価する力を日本の社会も少しずつ養うことができていたらいいのですが。
助川 もう一回、評価したい作家ですね。要するに最初の外国籍の作家であるとか、在日韓国人作家の作品であるとか、この作品にはいろいろと背負っているものがありました。それを取っ払って、どれだけ腹に響く問題を描いた作家として読めるかという観点から、もう一回検証し直す価値のある作家ではないかという気はしました。今回読んでみて。
重里 そんな風に思いますね。学生にも読ませたい小説の一つですね、これは。