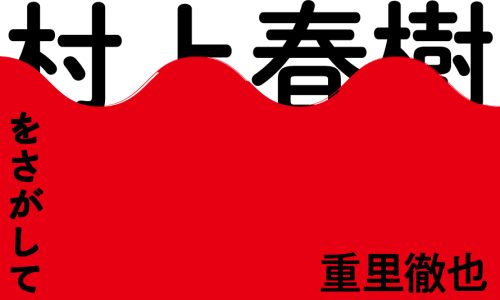無能な中央政治と優秀な現場
重里徹也 コロナ禍で閉塞感を感じる日々です。ただ、振り返ってみると、日本列島で生きる人々はこのところずっと災害に振り回されてきました。一九九五年に阪神・淡路大震災があって以降、地震や異常気象など災害続きです。そのころから、コロナに至るまで、ずっと共通しているのが、中央の政治があまりうまく機能していないのではないかということですね。能力の低さをさらけ出しています。
助川幸逸郎 阪神大震災そのものは天災なんですが、話題になったのは政府の救援物資よりも、民間の救援物資、たとえば、ダイエーの中内が自分でヘリコプター飛ばして救援物資を早く運んだという話がありましたね。
重里 そうなのです。人々の共助はかなりうまく機能しているし、民間には優秀な人が多い。それはボランティアの人々から、暴力団組員まで、いえることでした。また、暴動のようなものも起こらない。人々はおおむね秩序だって災害に対処しました。ところが、政府の動きが鈍いのですね。
助川 そうですね。今回のコロナにしても、二〇一一年の東日本大震災にしても、同様の図式が見られました。個人では非常に知的な人もいれば、勇気ある行動をとった人もいる。ところが、東京の政治システムが毎回毎回、対処に失敗しているように思います。
重里 東日本大震災の時、地元の市長や町長には優秀な人が多い印象を受けました。市役所や町役場の職員、スーパーやコンビニで働く人たち。自衛隊や消防団の人々。まじめで機転が利き、しっかりと対応した人が多くいたように思います。ところが、中央の政治家は手も足も出ないような感じがしました。事態に対応できない。機敏な判断ができない。東京電力の東京本社の幹部にもそういう印象を受けました。絵に描いたように無能なのですね。それが無残なほどにあらわになった。
助川 旧日本軍と同じですよ。大本営とか関東軍とかはバカなことやっている。現場の指揮官や兵隊さんには優秀な人がいるのだけれどという。
繰り返されるインパール作戦
重里 それで、この新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)の下においても、日本政府の無策を批判するのに、よく戦争中の日本軍のデタラメぶりが例えに出されます。ガダルカナルがどうだったとか。
助川 インパール作戦に似ているとか。
重里 インパール作戦のことを少し調べると、なぜ、こんな無謀な作戦を実行したのか、信じられない思いですね。本当に、バカじゃないの、という感じです。ところが、それと共通したようなことが、二〇二一年のコロナ禍においても行われているという印象があります。日本の政治システムというものが、大きな問題を前にして、その無能ぶりをさらけ出している。弱さ、もろさを露呈しています。
助川 敗戦後、上が吹き飛んでシステムが一回壊れた。それで現場の健全な人だけが残った。ところが、システムが復活して、完成してしまった途端に、また元の戦前のバカなシステムに戻ってしまったみたいなところがあります。一人一人の人間は決してダメではないと思うのですが。
現場で頑張っている人、優秀な人はいるのだけれど、何かが起こった時にシステムとして判断ができない、対処ができないというのは日本の病理ですね。
重里 今回のコロナ禍でも、現場にはたくさん優秀な人がいると思います。医者、看護師、保健所の人など、能力が高く、まじめで、心情のきれいな人は多くいるように思います。テレビに登場する大学の先生や病院の医師にも、とても知的で優れた判断力を持っている人がいるように思います。ところが、それが日本政治というシステムの中では埋もれてしまう。なかなか生かされない。そんな感じで、日本全体が鈍くなっているような気がしますね。足がすくんでしまっているのですね。
なぜ、こんな話をしたのかと言いますと、『プレオー8の夜明け』の話に入りたいのです。私はとても優れた小説だと思います。芥川賞史上、屈指の名作といってもいいでしょうね。高校時代に読んで以来、ずっと惹かれ続けている作品なのですが、この小説の思想とは、システムにはもう期待しないというものなのですね。けれども、この地獄のような現場をどうすれば、少しでも楽しく生きられるかを模索する主人公の姿を描いている。非常に芯の強さを持って書かれている小説だと思います。それが、こちらの心に響いてくるのですね。芥川賞作品を読み続ける中で、戦争を扱った作品を入れたいと思った時に、『プレオー8』が思い浮かんだのです。
システムが壊れた後で
助川 私はこの小説で最も共感したというか、かわいそうだなと思ったのは、金井中尉ですね。ある種エリート軍人でこれまでやってきた人なのでしょう。日本のシステムの中ではエリートとして振る舞ってきたのが、捕虜になってシステムが壊れてしまって、裸で投げ出されてしまっている。それでシステムは守ってくれないから、個人として愛されなきゃいけない。それで、もうオカマになって、愛されようとするわけじゃないですか。
自分がそれまでのアイデンティティーみたいなものを完全にかなぐり捨てている。逆に言うと、それを全部捨ててしまえるところが金井中尉の優秀さというか、鋭敏さともいえるのではないかと思います。この人はただエリートコースに乗っていただけではなくて、システムが壊れたときに本当に裸になった自分には何の価値もないんだって思った時に、必死になって愛される道を探しにいった。その時に自分の男としてのアイデンティティーすら捨てなければ自分は生きていけないのだというところに直面してしまったのだと思います。金井中尉とはそういうキャラかなと思った時に、この人は現実と向き合っているんだろうなって思いましたね。端から見て。
重里 軍人としてのアイデンティティーがもう全て失われてしまった世界ですよね、これはね。戦犯容疑でベトナムの刑務所に抑留された兵士たちの日々が描かれているわけですが、軍隊の階級社会は壊れてしまっている。その中で無防備な個人として生きていくのに、それではどうやって生きていきますか、ということが書かれているのだろうと思います。この主人公のしたたかさとしなやかさが、とても印象的だったですね。
助川 主人公は自分に見栄を張らないですね。大人ですよね。
重里 大人ですね。徹底した自己相対化がなされています。いつも、自分を他人の眼で見ている。
助川 そうですね。水浴の時に動作が遅いとフランス兵に細竹でビシビシと尻を叩かれます。でも、あまり痛くない。それで、平気で叩かれてやる。ところが乱暴なフランス兵がいて、そいつに蹴っとばされるととても痛いから、それは一生懸命に逃げ回る。ところが、仲間は、私がわざと細竹でぶたれて、みんなをかばっていると誤解して、ほめてくれる。そんなことを主人公が考える場面もありますね。
重里 東南アジアの湿気と高温がひどい刑務所で過ごすというのは、耐えがたいことですよね。しかも、いつ死刑になるかわからない。ところが、そこで何とか精一杯、日々を楽しく過ごそうとする。芝居をやったりして。そういうのも、涙ぐましいようなユーモアがあります。
助川 そうなんですよね。そのくせ、ちょっとかわいくて。みんなの為にやっているんだぞって誤解されるのだけれど、それを言っちゃあ、おしまいよって、ちょっと思っている。言ってくれるなよ、照れるじゃないか、みたいな感じじゃないですか。
重里 そうなのです。都会人の繊細な感覚ですね。
徹底した自己相対化
助川 そうです。都会人の感覚だし、やっぱりすごい知性を感じますよね。これがホントの知性だと思います。徹底した自己相対化も知性がもたらすものですね。子供っぽくひねくれて、自分の卑小さをシニカルに言い立てるのではなくて。そういうのは過大な自己愛の裏返しの表れですからね。そうじゃなくて、本当に自分の等身大の存在価値みたいなものがわかっている。自分の良心と同時に自分のセコサもわかっている。
重里 表立ってはあまり書かれてはいないですが、主人公たちは生と死のギリギリのところで生活しているのだと思います。いつ死刑になるか、誰もわからない。いつ自分の人生が閉じてしまうかわからないせっぱ詰まった極限状況で日々を送っている。自分の運命を自分で決められない。死ねと言われれば、死ぬしかない。そういうヒリヒリとした状況に置かれているのだけれど、それははっきりとは書かない。隠し味にしている。つまり、感傷的なことは直接には書かないのですね。
助川 この刑務所に至る過程でも、ちょっとしたタイミングで自分は殺されていたかもしれない。逆に言うと、殺されたやつもちょっとタイミングが違えば、全然無事だったかもしれない。正しい心で、正しい状況判断をすれば助かるというものではないのですね。主人公たちが置かれているのは、そういう状況です。
重里 徹底した極限状況といえるでしょうね。そういう中で、狂気に陥らないで、平常心みたいなものをどのように保つのか、ということが描かれているのだろうと思います。これは、とても射程の長い小説ではないでしょうか。
助川 本当に、等身大のしなやかな小説ですね。逆に言うと人間ってそういう状況でも例えば、娯楽を求めたりする存在だということですね。
重里 女性にラブレターを書いたり。
助川 ちょっとかわいい男の子(日本兵)を女性アイドルみたいにしてみんなで取り合ってみたり、とか。なんかそういうつまらないことに意義を見いだしている。結局どんな非日常も日常にして生きてしまうある種人間のしたたかさと悲しさがすごく出ていますよね。こんな非日常でも日常にして、日々のちょっとしたつまんないことでいらついて喧嘩したり楽しんだりしちゃうっていう人間の悲しさみたいなものがすごく出ていますよね。
声高に「正しさ」を主張しない
重里 それで主人公は決して、声高にはしゃべらないですね。大きな声で主張しない。目の前のことしか言わない。観念的なことをいったり、正義という言葉を使ったり、そういうことは一切、口にしない。いつも、つぶやくようにしか話さない。
助川 これは裏返して、人生訓にしてもいいと思います。簡単に声高なことを言ったり、かっこいいことを平時に言ったりする人間というのは、信用できない。あてにならない。
重里 特に「正しいこと」を大きい声で言う者は絶対にあてにならない。おそらく、そいつはうそをついている。本当にそんな感じがします。
講談社文庫の解説を開高健が書いています。「孤徳の文学」というタイトルが付けられていますが、記憶に残る文章です。開高健は全身を戦争という狂気につかまれて、生涯を過ごした作家だと思います。ベトナムの風土も熟知している。その開高がこの小説を激賞しています。
たとえば、文体ですね。「したたかな苦渋を濾過した“かるみ”と、ほのぼのとした微光のようなユーモアがいきわたっていて」、戦争や戦場を描いた数々の文学作品でまったくユニークだと評しています。流木のような文章だというのが言い得て妙ですね。人物や風景の描写に形容詞を使っていないというのですね。日本語の文章というのは形容詞から腐っていく。流木のような文体とは、形容詞や修飾語をそぎ落として、岸辺に流れ着いたようなものという意味でしょうね。
助川 私は逆に、これは何かを足していこうと思えば、いくらでも足せる文体だと思うんでね。例えば、わかりやすくするために主語をもう一回足したり、目的語をもう一つ足したりすると、ちょっと波長が乱れてしまうというような、そういうスタイリッシュな文章ではないのですよ。わかりやすくするためだったら、何度でも同じ主語が出てきてもいいし、何度同じ言い回しが出てきてもいい。これが本物の散文というものではないかと思います。
重里 漢字の熟語はカタカナで表現してもいいし、どこで改行したって大丈夫だし、というような感じでしょうか。スタイリッシュな文章というのは、例えばどういう作家のものが思い浮かびますか。
助川 例えば三島由紀夫もある意味そうですし、堀辰雄もそうだし。
重里 そういうものと対極にある文章ということなのでしょう。
助川 だからカッコいい文章ではないけれども、なんでもかける文章ですね。ある種小説家の一つの理想の文章じゃないですかね、これは。
しなやかで温かい文体
重里 とてもしなやかで、自由な文章ですね。けれども、装飾ははぎ取っている。着飾らない。それに人懐っこいですよね、なんか。温かみがある。体温を感じる。
助川 そうなんです。愛嬌があるんですよ。要するに。チャーミングなんだと思うんですよね。可愛げがある、凄く主人公が。
重里 このチャームの正体は何なのですか。
助川 自己愛みたいなものがないことでしょうか。愛されようとか、受けようとかしていない人間ってチャーミングなんですよ。
重里 年齢もあるのでしょうね。芥川賞受賞作というと比較的、若い人の作品が多いですが。
助川 五十歳ちょっと前ぐらいですね、これは。この力の抜け方は五十じゃないと出ないですよね。
重里 それと戦争体験、この刑務所体験から、数十年経っている、ということもあるのでしょうね。
助川 そうですね。私にはとても尊敬していて、すごいなと思う作品がいくつかあります。芥川賞作品でいうと、大江健三郎の『飼育』もそうですね。中上健次の『岬』もそうです。だけど五十歳超えて、今から自分がどういう文章を書きたいかという時に、こういうのをやりたいなあって、重里さんとずっと芥川賞作品を読んできて、一番思ったのが、今回のこれですね。
本当に共感しました。私は短歌結社に入っていて、毎月、結社の雑誌に短歌を十首ぐらいずつ投稿します。その時に何を目指しているのかっていうと、なかなかできないんだけれど、こういう世界を詠みたいんです。気取らないで自分に見栄を張らないで、そして自分のセコサを自嘲とかにならないですっきり見据えて。そういうものを歌えるような歌を作りたいなと思って、毎月やっているわけです。もちろん、私はこんな風にはできないんですけれども、でも目指しているのはこういう方向ですね。
重里 私は俵万智の短歌に惹かれるのですが、彼女の歌にもそういうところがあるのではないでしょうか。
助川 俵万智は上手いんですよ。「寄せ返す波のしぐさの優しさにいつ言われてもいいさようなら」という歌がありますよね。これ何気ないようでいて「寄せ返す波のしぐさの優しさに」というところで、すごくほんわかした歌を予期させるわけです。なのに次に、「いつ言われてもいいさようなら」っていわれると、ドキッとするじゃないですか。だから、平常心をさらりと詠んだようでいて、一首の中にドキッとするようなスリルとサスペンスを仕込んでいる。これは平凡な私を上手に表現しているというよりも、上手いということを素人に気づかせないぐらいものすごく上手い歌なのです。
古山はそういうんじゃないんです。そういう技巧なんかは一切構わないところがあります。俵万智は俵万智で、並の歌人じゃないのはまちがいありませんが。俵万智は、とにかく技巧が水際立っている。千年以上のこの国の歌の歴史の中においても、トップクラスといっていいうまい歌人だと思います、技巧という点で言えば、俵万智は、和泉式部とかとの比較に耐えるレベルではないでしょうか。