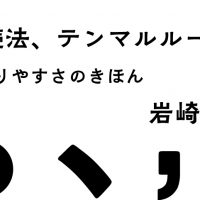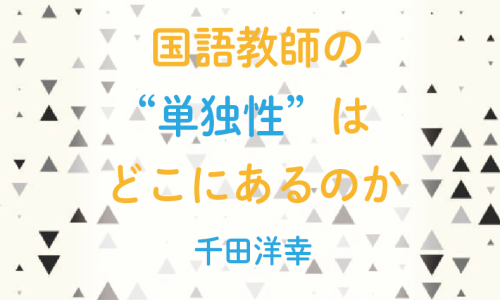「私とは何か」という問いの不可能性
1990年代の日本が「SF冬の時代」と呼ばれていたのが嘘のように、ゼロ年代の日本では数多くのSF小説が発表され、ひとつのブームと言ってよいほどの文化現象を巻き起こしました(✳)。その旗手としての役割を担った重要な書き手のひとりとして、円城塔の名を挙げることに異論の余地はないでしょう。これもまたゼロ年代の(夭折した)SF作家として著名である伊藤計劃とともに、2006年の第7回小松左京賞の最終選考に残るかたちで注目された円城は、実験的な小説作品を次々と発表し、狭義のSFの領域だけでなく純文学の分野でも話題を集め、2011年には芥川賞を受賞しました。今回の連載で取り上げたい『Self-Reference ENGINE』という小説作品は、もともと前述の小松左京賞に応募され、その後ハヤカワ書房から刊行された円城の実質的なデビュー作であり、2013年にはアメリカの大きなSF賞として名高いフィリップ・K・ディック賞を受けるなど、世界的にもきわめて評価の高いものです。
『Self-Reference ENGINE』は、いくつかの短編が連なって構成されており、そのあらすじを説明すること自体がとても難しいのですが、全体をゆるやかに統御する設定として、作中の時間や空間、さらにはそこに住まう人びとの記憶までもが自在に改変されていくという特徴があります。この物語世界は、無数に関係づけられた宇宙(と、さしあたり呼ばれるもの)の連鎖によって作り上げられており、それらは相互に循環・生成を繰り返す運動体として見立てられています。そのような物語世界においては、かけがえのない「私」という自己像もまた、後述するような仕方で、分裂と統合を繰り返しながら存在論的な揺らぎを含んでいかざるをえません。すなわち、本作においては、近代小説の扱うべき思想的課題のひとつとしてあったはずの「私とは何か」という問いは、もとより正しく実を結ぶことがありえないのです。
しかし、一方で『Self-Reference ENGINE』には、みずからのアイデンティティのかけがえのなさを希求しようとする登場人物たちの意思が、やや率直なほどシンプルに表明されてもいました。ひとつの例を引用しておきましょう。
その奔流の中にあって、それでも首尾一貫性の回復を試みる巨大知性体との行動は、多分こうまとめるしかない。
(10:Daemon)
ジェイムスはジェイムスでいたい。
このジェイムスがジェイムスではないならば、ジェイムスにそう思わせているものを見つけ出したい。それは白紙への抗弁なのかもわからない。かつて動物に仮託して想像され、子供の中に夢見られていた、白紙への抵抗だ。白紙と呼ぶことすら適当とは言いがたい、ただの透明、あるいは真空への申し立てだ。真空ですらない、ただそのままの宇宙への、最早宇宙とすら呼びがたい素体への、無すら存在しない無への憤りだ。
外的世界としての時間・空間のあり方が、人間の理解を超えた上位の知性体によって無限に改変されていくような状況下で、なおも「私」の唯一性・特権性を担保するものはありえるのか。あるとすれば、それはどのようなものなのか。仮に『Self-Reference ENGINE』がこういった主題系を扱っているとすれば、それはある意味で、決して果たされることがないのにもかかわらず、何とか「この私」のあり方に近接しようと格闘してきた文学的想像力の変奏だとも言えるのかもしれません。では、その違いはどのようなところにあったのでしょうか。
この点について、かつて僕は、自己言及を回避するような「私」語りの方法論的転回という視座から、ひとつの読解を示したことがありました(✳✳)。以下では、もう少しそれを展開させるかたちで、『Self-Reference ENGINE』において多元宇宙(=並行世界)が扱われていることの思想的な意義について迫ってみたいと思います。
(✳)その具体的な流れについては、たとえば限界研編『ポストヒューマニティーズ――伊藤計劃以後のSF』(南雲堂、2013.7)所収の諸論などが参考になります。
(✳✳)今回の論旨は、拙著『合理的なものの詩学――近現代日本文学と理論物理学の邂逅』(ひつじ書房、2019.11)の「補論ⅱ」で述べたことと重なる面を多く含んでいます。よろしければ、併せてご参照ください。
並行世界の「私」
先述したような作中の「私」の造型について、もう少し具体的に見ておきましょう。『Self-Reference ENGINE』では、人間を超越した巨大知性体や超越知性体による終わりのない抗争の結果、線条的な方向性をはらんだ時間や空間の秩序が機能不全を起こすという設定が盛り込まれています。何しろ、そのような時空改変によって既存の物理法則を破壊する方法が人びとの理解を超えているので、各々の世界の住人たちにはそもそも何が行われているのかも分からないわけですが、さしあたり直截的な日常生活の弊害としては、「私」の心理的記憶そのものが、別世界の「私」と不可避的に混淆してしまうような状況が生じていきます。
たとえば、登場人物のひとりであるジェイムスは、彼が聞いた台詞がいつ話されたのかについて決して思い出すことができないものの、それは確かに別の宇宙で敷島という人物が聞いた台詞と正確に対応していました。
「正直な見解を聞きたい。サンタフェ研のアンクル・サム、その進める時空再統合計画の勝算は」
(05:Event)
「零です」
「それは確率的にか、組み合わせ的にか」
「有限個の解は存在するでしょう。時空が砕ける以前の時空に我々が帰還できるような解は。しかし他の有限個の解の可能性がそれを選択することをわたしたちに許しません。有限を無限で割ってみて、確率的に零です。彼は暴走するでしょう。北米西部中域を道連れに」
「この現象に対する理解度は、私たちもあなたがたもあまり変わりがないのです。無限で割られた有限の数、すなわち零という意味において」
10:Daemon
それはさっきも聞いた台詞だと抗弁しかけるが、さっきがいつのさっきなのかが思い出せない。
このようなかたちで、相互に孤立した宇宙に暮らす人びとの意識がつながってしまった物語世界においては、ふとした瞬間に、異なる宇宙に生きる誰かの記憶がランダムに嵌入されてしまうことになります。また、作中では空間を跨いだ記憶の混淆が描かれていましたが、時間もまた「イベント」によって機能不全を起こしているのだとしたら、たとえば〝かつてこうであった〟自分や〝これからこうなるであろう〟自分とのあいだに、記憶の混淆が起こるということもありえるのかもしれません。何しろ『Self-Reference ENGINE』の物語構造そのものが、そうした可逆的な時空の流れを取り扱っているわけであり(✳✳✳)、そこから「私」が「私」であるための心理的な連続性の亀裂がモチーフとなることは、言わば当然の成り行きであるとも言えます。
もちろん、記憶の混濁という問題を厳密に考えてみるならば、こうした設定にはやや微妙なところがあり、ロジカルな整合性がつけられるものであるのかは議論の余地があるでしょう(そもそも記憶というのは、ある一部分だけを取り出して、自在に他人と混成させたりすることが可能なものでしょうか?)。ただ、こうした趣向の凝らし方は、「私」が「私」であるという確信の仕方を揺さぶるために、きわめて有効な意義を持っていることは確かだと思われます。
「私」が他の誰とも異なっているという端的な事実は、別世界に生きる(であろう)「私」ならざる誰かにもまったく同じように成り立つはずであり、それは「私」の唯一性・特権性を説明するものではありえないのではないか。そのような疑念が頭を掠めたとき、おのずと「私」と「私」ではないものの区別はつくのかという問いが誘発されることになります。
「この平面宇宙に、お前と限りなく似た女の子が存在するかどうか」
(15:Infinity)
それが三日前に祖父がリタに出した問題だ。祖父の問いの常として、題意すらよくわからない。
問いが無限について何かを訊いていることは明白だ。この宇宙は、平面をなしていると信じられている。無限に広がる平面。その地表には、無限の数の人間が暮らしている。それがイベント後のこの宇宙の姿だとされている。(…)
どの程度の自分が自分なのだろうとリタは考える。
DNAが同じ配列を持っている人間。それはかなりリタに近い。しかし双子同士が当人同士ではないように、それはリタとは少し違う。
ニューロンの配線が結構かなり似た人間。それは近いかもわからない。もしかしてリタと同じように考え、今もリタと同じように考えているかも知れない誰か。家族もリタだと思うかも知れない。顔が違っていたりしたらすぐにばれるだろうけど。
でも考え方としてはどうもしっくりこない。こんな条件で絞っていっても、それはリタにとてもよく似た人がいるとしたらどういう人かということにすぎない。何かが逆だ。祖父が聞きたい答えはきっとこういうものではないだろう。
ここでは登場人物の言葉を借りて、並行世界の「私」たちと、ほかならぬ「この私」の差異についての思索が展開されています。かつて、昭和初期に独創的な文業を成し遂げた作家として知られる稲垣足穂は、「一たい、こゝに僕と君といふ二人が、このかぎられた時間と空間のなかにゐるのがほんとうであつたら、同じやうに、同じ僕と君とが、又別の時間と空間とのなかに存在することも可能でないか」と述べましたが(「「タルホと虚空」──理屈つぽく夢想的な人々のための小品」『ゲエ・ギムギガム・プルルル・ギムゲム』1925.7)、言わばそのような当て所ない夢想の発現が、ここでは約80年の時を経てSF的にップデートされていると言えるでしょうか。
もちろん、並行世界のなかで無限に近しい「私」が無数に存在するとすれば、それら「私」同士の社会的な属性(柄谷行人が言うところの「特殊性」)は区別がつきえず、必然的にその差異は「単独性」の在り処に求められることになります。(というより、無限の「私」がいたとしても、実際に感じたり考えたりする個体がこの個体でしかありえない以上、つねに「単独性」は「特殊性」に先立っているわけで、その差異のあり方を事後的に考察すること自体が本来はナンセンスなのですが。)しかし、どのような仕方にせよ、それをこの現実世界に固有の問題として説明しようとしてしまった瞬間、「単独性」は「特殊性」と混同されてしまい、その核心は手のひらから滑り落ちてしまうことになるのです。
では、そのような隘路に対峙した際に『Self-Reference ENGINE』が示した回答は、どのようなものだったのでしょうか。
(✳✳✳)波戸岡景太は、それを「予告篇的物語学」という卓抜な比喩で形容しています(『コンテンツ批評に未来はあるか』水声社、2011.11)。
多宇宙という戦略
注意しておきたいのは、『Self-Reference ENGINE』の登場人物たちが、各々の「私」なるものの中身を、きわめて柔軟で可変的なものとして捉えていたことです。たとえば、作中のある宇宙空間における「僕」は、意識のなかに混入する別世界の「僕」との交わりのなかで、「自分は誰であるべきなのか」(06:Tome、傍点引用者)を考えつづける存在として描かれています。ここにおいて、「私」という存在のあり方自体が、弾力的に生成変化するものとして捉えられていることが了解できるでしょう。
そして、こうした思考の道筋を支えるための重要な役割を果たしているのが、並行世界という設定なのです。「この私」が回帰すべきただひとつの現実世界が、多元的に拡散してしまうとき、現実世界そのものの「この」性もまた疑えてしまうのではないか。もちろん、それは実際のところどうであるのかという論理的なレベルとはまったく別の次元で受け止めるべき事柄でしょう。しかし、昨今の宇宙物理学の領域では、まさにこの問題がアクチュアルな議論を巻き起こしているようなのです。
この点については、いくつもの判りやすい参考書・解説書が刊行されており、専門外の僕がいい加減にまとめるよりは、そちらをご覧いただいたほうが良いのですが、要するに掻い摘んで言うならば、この宇宙空間は、あまりにも人間が住みよいように絶妙な物理定数のもとで成り立っており(これをファイン・チューニングと言います)、確率の概念を適用するならば、同じような宇宙空間が無数に存在し、そのなかのひとつの宇宙空間がたまたまこのような形態を取っていると考えるほうが自然ではないかというものです。こうした素朴な疑念を導きの糸として、著名な宇宙物理学者であるロバート・ディッケやブランドン・カーター、日本では佐藤勝彦などが旗振り役を担い、20世紀の後半には多種多様な新しい宇宙モデルが考案されていきました。ここでは、青木薫『宇宙はなぜこのような宇宙なのか──人間原理と宇宙論』(講談社現代新書、2013.7)から「インフレーション・モデル」の説明を引用しておきたいと思います。
インフレーション・モデルの多宇宙ヴィジョンによれば、われわれの宇宙は、無数にある泡宇宙のひとつにすぎない。(…)この壮大でダイナミックな多宇宙ヴィジョンを、どう受け止めたらよいだろうか? こんな途方もないものを、信用してもよいものだろうか?
はっきりしているのは、この新しい多宇宙ヴィジョンは単なる思いつきや空想の産物ではないということだ。「宇宙論の標準モデル」は、「エキゾチックな」理論ではない。それは「コンベンショナルな」理論にもとづき、観測と実験によって支持されているモデルなのである。むしろ、よほどエキゾチックで恣意的な過程でも設けないかぎり、この多宇宙ヴィジョンを追い払うのは難しそうだ。
この説明にもあるように、今日の宇宙物理学において、いくつもの並行世界の実在は「エキゾチックな」ものではなく、むしろきわめて理に適ったものとしてみなされつつあるようです。『Self-Reference ENGINE』が、こうした宇宙モデルを直截に受け継いだ物語世界を構築しているとまでは言いませんが、少なくとも作中を彩るSF的な装いの大きな要素として、そのような科学的イマジネーションを借用していることは確かでしょう。そして、それは単なる細かな意匠の次元ではなく、作中における登場人物たちの思弁自体をも枠づけています。「巨大知性体ペンテコステⅡ」の崩壊に伴い、第16章の「私」が思い描いた思考実験を参照してみましょう。
クローンをめぐる自己同一性に関する議論は繰り返すにも物憂い。しかも記憶までを含めて自在に加工が可能となると、問題は拡散しきってしまって、いちいち取り上げようにも無力感の方が先にたつ。ある朝目覚めてみると甲虫であり、甲虫自身が発生以来のただの甲虫として自己を認めている場合に、何の問題が起こるというのか。巨大知性体の操作能力は、既にそうした領域にまで達していた。
(16:Sacra)
ある「甲虫」が自身を「甲虫」であるとみなすとき、その判断がもともとの「甲虫」自身によってもたらされたものなのか、あるいは何らかの外的環境の変化によって生じたものなのかを問うことに区別をつけることはできません。それは、「甲虫」が「私」の問題にすり替わってもまた同じことです。宇宙が無限に反復を繰り返し、その都度過去が分岐しつづける作中の世界観においては、「私」が「私」であるという揺るぎない確信の明証性そのものが失効してしまわざるをえません。ここにおいて、先述したようなかけがえのない「私」という造形は、「私」が「私」であるという確信の定立が、「この宇宙」の「この私」だけに生じた唯一のものであるという前提によって、初めて意味を持つものであったことが明かされているのです。
しつこいようですが、上で示したような思考の筋道は、なお「この私」をめぐる一連の議論とは無関係であり、「私」が「私」であることの確信がどれほど揺らぎえたとしても、依然として「この私」の唯一性・特権性は端的に保証されているでしょう。しかし、宇宙物理学などの領域において並行世界の実在が本格的に議論され、その存在感がありありと感得されつつある時代状況において、このようなSF小説が書かれたのはきわめて示唆的なことです(✳✳✳✳)。そこには、生涯付き合いつづけねばならなかったはずの現実世界の〝こうでしかなさ〟を認めなくてもよいのだという、ある種の爽やかな解放感が刻まれているように思えます。
その後の円城は、先述したように『道化師の蝶』(講談社、2012.1)で芥川賞を受賞し、狭義のSFの分野を超えて本格的に純文学の世界へと参入していくことになります。(なお、この時の芥川賞選評は、選考委員のひとりであった石原慎太郎が「こんな一人よがりの作品がどれほどの読者に小説なる読みものとしてまかり通るかははなはだ疑わしい」と酷評したことでも話題となりました。)冒頭にも名を挙げた伊藤計劃の創作メモを引き継いで書かれた小説作品『屍者の帝国』(河出書房新社、2012.8)が人気を博し、SFの領域でも堂々たる評価を確立させた円城は、近年では『プロローグ』(文藝春秋、2015.5)や『文字渦』(新潮社、2018.7)などで、言語システムそのものの自律性/他律性を主題とした実験的小説を多く発表しています。同時に上田秋成『雨月物語』の現代語訳などにも果敢に挑戦し(『日本文学全集』第11巻、河出書房新社、2015.11)、多方面にわたってマルチな才覚を見せているところですが、少なくとも『Self-Reference ENGINE』に端を発する円城の作風の重要なポイントとして、今回見てきたような問題意識があったことは間違いないように思います。そして、それは現実世界の揺らぎをめぐるゼロ年代の文化状況と、確かな共鳴を果たしていたのです。
次回は、舞城王太郎『ディスコ探偵水曜日』(新潮社、2008.7)を扱います。
(✳✳✳✳)仮に宇宙物理学の研究成果など考慮に入れなかったとしても、1990年代以降の時代状況において、現実世界はこうでなくてもよかったのではないかという想念が、それまで以上に人びとの感性を覆いはじめたことを、複数の社会学者や心理学者が指摘しています。ゼロ年代の物語文化が、こうした社会思潮の騒めきと密接に結びついていることは確かであり、いわゆる〝並行世界もの〟という作品様式の台頭も、こうした文脈から理解される必要があるでしょう。この点については、千田洋幸『ポップカルチャーの思想圏──文学との接続可能性あるいは不可能性』(おうふう、2013.4)が参考になります。