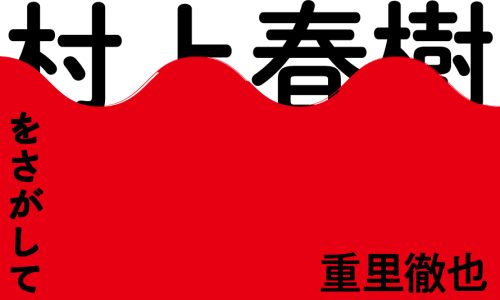「ポスト・セカイ系」の想像力
青土社から刊行されている文化系の批評誌『ユリイカ』2007年4月号は、1冊まるごと米澤穂信の特集号でしたが、その煽り文句は「ポスト・セカイ系のささやかな冒険」というものでした。「セカイ系」というのは、大まかに言えば「きみ」と「ぼく」のごく私的な人間関係が、この世界全体の出来事に重大な影響を及ぼすような物語文化の総称のことを指しています。その荒唐無稽とも言えるちぐはぐな壮大さが、主に(僕自身を含めて)ゼロ年代に入ってから思春期を迎えた中高生たちの大きな共感を呼んだ一方で、眼の前にある社会問題に対する批判精神が根本的に欠如しているとして、一部の知識人たちから批判の的となっていました。
そのような物語の潮流と比べて、日常生活のふとした謎や些細な違和感に焦点を当てようとする米澤の作風は、確かに「セカイ系」的なスケールとはおよそ無縁であり、ある意味でそれは新しい感性の賜物だとも言えるでしょう。ただ、今回取り扱いたい『ボトルネック』(新潮社、2006.8)という長編小説は、主人公が並行世界に迷い込むことから始まる変則的な青春ミステリーであり、米澤作品のなかでは珍しく大掛かりなSFギミックが登場するものとなっています。この小説作品の検討を通じて、今回は「セカイ系」的な想像力と「この」性をめぐる議論の関連──というよりは、関連の無さ(?)──について考えてみることにしましょう。
『ボトルネック』のあらすじは次の通りです。2年前に恋人を亡くした嵯峨野リョウという高校生は、その弔いの地で謎めいた声に招き寄せられ、突如として並行世界に迷い込むことになります。その世界は、もともとの現実世界に限りなく類似しつつも、いくつかの出来事や事実が決定的に異なっており、そこでリョウは、もとの世界では生まれないことになっていた姉サキと出会います。新しい並行世界ともとの世界の違いを検討していくなかで、リョウはもとの世界ではもう会うことのできない恋人ノゾミと再会を果たし、図らずもそこからノゾミの死の謎をめぐる手がかりを掴んでいくことになります。最終的に、ノゾミの死にはフミカという従妹の邪悪な好奇心が関わっていたことが明らかとなるのですが、同時にリョウは自分さえ居なければ、もとの世界でもノゾミは死ななかったであろうことを理解し、自分が存在したことによる実害の大きさに絶望することになります。物語の結末で、リョウはもとの世界へと半ば強制的に帰還するのですが、自分の確かな存在理由は見つけられないまま、どちらかと言えば後味の悪いエンディングを迎えることになります。
この小説作品が提示する主題のひとつは、やはり自分という存在が世界にとって根本的に不要なのではないかという、ある種の屈託を抱える人びとに特有の疎外感・閉塞感にこそあるでしょう。実際、作者自身も『ボトルネック』の読みどころについて、次のように語っています。
青春小説とは本来、主人公がいかにして自らを正当化していくかを描くものですが、彼はまだ自己を認識しているつもりになっているだけで、自分と向き合えてもいない。『自分探し』の旅の準備さえ整っていないんです。言わば青春以前小説ですよ。
(「著者に聞く!」『小説すばる』第20巻11号、2006.11)
数多ある「青春小説」のように「自らを正当化していく」のではなく、むしろその手前で逡巡し、「自分探し」のできなさを描こうとする米澤の創作姿勢は、同時代において過度に肥大化した「セカイ系」的な自意識のあり方に対して、ひとつのアンチ・テーゼとなりえていたのかもしれません。しかし後述するように、多少とも冷静に考えてみれば、自分が現実世界に対してどのような存在感を有しているのかということと、自分という存在のただ端的な唯一性・特権性は、まったく異なるレベルの問題でしょう。むしろ、この両者が互いに混同されてしまうような独特の価値観の形成こそが、ゼロ年代における時代精神の大きな特質であったと言えるのではないでしょうか。その意味で、『ボトルネック』における自意識のあり方は、実のところ「セカイ系」的な感性と意外なほど近しかったとも考えられるのです。
「個性」は存在理由になるか
この小説作品のクライマックスとなるリョウの独白の場面を抜粋しておきます。
「(…)俺も最初から気づいてた。二日前からわかってた。もし、『間違い』があるとしたら、それは」
息を呑む。見え透いた結論なのに、それを言うとき、くちびるが痺れた。
「俺だって」
瓶の首は細くなっていて、水の流れを妨げる。
間違っていたのは、サキが生まれなかったこと。嵯峨野家に生まれた二人目が、サキでなくリョウだった、そのこと自体。
並行世界における旅路の果てにリョウが理解したのは、自分の代わりにサキという人間が生まれてきたことで、世の中のあらゆる事態が好転しているという実に残酷な真実でした。激しい無力感に苛まれるリョウは、みずからを「ボトルネック」に見立て、その懊悩は次のような思索へと展開していきます。
兄は言った。他の誰にもない個性が、誰にだってある。お前はお前しかいない。
なるほど、そうだろう。否定しようもない、当たり前のお題目。
しかしそれは何も意味しない。違っていることはそれだけでは価値を生まない。
嵯峨野サキの生きた世界の方が、嵯峨野リョウが生きた世界よりもいい場所だという事実を前にしてなお、ぼくにはぼくのいいところがあるさなどと思い続けていたとしたら、それは、想像力がないとかいうレベルの話ではない。ただの馬鹿だ。
注目すべきなのは、リョウが自分自身に「他の誰にもない個性」を認めながらも、同時に「違っていることはそれだけでは価値を生まない」と考えていることです。つまり、本連載の初回に示した柄谷行人の言葉を用いてまとめるならば、リョウにとっては、端的にいま・ここに現れている「この私」(=「単独性」)という存在のあり方よりも、ある社会的属性のなかに示される個性(=「特殊性」)の〝善さ〟こそが、みずからの存在理由として何よりも重視されているのです。
しかし、先にも示したように、率直に言って僕にはこの感覚がどうしてもよく分かりません。事実として「単独性」と「特殊性」はほとんど無関係の事柄であり、単なる確定記述の多寡に過ぎない「特殊性」の度合いをなぜそこまで強調するのかが、いまひとつピンとこないのです。なので、リョウの考えていることに対して、正直なところ共感はほとんどできないのですが、しかし同時に、リョウのような考え方が、ゼロ年代の読み手に対してある種の説得性を喚起しえたという事実については強く興味を惹かれるので、そのポイントとなる論理をもう少し精査するためにも、ここで作者自身の言葉を補助線として参照しておくことにしましょう。
デビュー作の『氷菓』からずっと自分が書きたかったことは、思春期の全能感についてなんです。全能感が試練にあって崩れ去るなり正しい自負に変わるなりする過程を描いてきたのですが、全能感の裏返しとして、完全な無力感というのがあるのではないかと思ったのですね。ここまで七作ほど書いてきまして、そろそろこの全能感と無力感というテーマについて総括したいという考えがありました。そこで全能感の化け物を書くか無力感の化け物を書くかと考えて、無力感の化け物のほうが小説になるだろうと判断して書いたんです。
(笠井潔+米澤穂信「ミステリという方舟の向かう先」『ユリイカ』第39巻4号、2007.4)
引用部分では、作者によって「思春期の全能感」と「無力感」が対比されており、『ボトルネック』は後者の可能性を追究した小説作品であると位置づけられています。しかし、リョウはそれほど世界に対して「無力」な存在なのでしょうか。実際、リョウが存在したことにより、もとの世界で起こった諸々の出来事はかなり激しい影響を受けていたわけであり、見方によっては、リョウはかなり強い「個性」を持っているとも言えます。それが世界に対して〝善い〟ものであったかどうかというのは、しつこいようですが、単なる社会規範のなかの決まりごとに過ぎず、本来あるべき「個性」の強さに対しては本質的に無関係なものでしかありません。そういう意味で、リョウは「全能」とは言わないまでも、みずからの存在感をもっと他者に対して誇ってもよかったはずなのです。(✳)
しかし、実際に『ボトルネック』が示したのは、そのような善悪の判断基準とは無関係にあるべき「個性」のあり方を、特定の倫理体系に依拠した交換可能な社会的属性にすり替えてしまう認識論的な誤謬が、少なくともある一定数の読者から大きな支持を集めているという興味深い事実でした。では、そのような解読格子の成立には、どのような文化的地盤が関わっていたのでしょうか。
(✳)新しい並行世界では、結局のところリョウはひとりではほぼ何も行動できず、サキがリョウを主導し、物語内の謎を解明する役割を果たしていました。リョウの無力感は、こうした作中における主体的判断のできなさと密接に結びついているものと思われますが、まさにそういった己の立ち位置をめぐる悩みと、「この私」が端的に特異な存在であることの疑念が混同されてしまうような思考回路こそ、今回の章で僕が問題にしたいことの核心となります。
〝自分らしさ〟至上主義のイデオロギー
精神科医の斎藤環は、ある統計調査をもとに、今日(ゼロ年代以降)において若者たちの承認欲求が高まりつつあることを確認したうえで、「かつての執着気質の背景にあったものが「生き延びること」への執着と不安であったのに対し、現在の若い世代にとっては、それがさして重要ではなくなりつつあるのではないか」と問うています(『承認をめぐる病』日本評論社、2013.12)。斎藤によれば、「生」への執着に「かわって前面に出てきたものが「実存の不安」、すなわち「自分は何ものか」「自分の人生に意味はあるのか」といった不安」であり、統計調査が示す承認欲求の異常な高さは、その具体的な表れだと言うのです。今日において、他者からの承認こそが人生の意味を決定づけ、またみずからの存在理由と直結するかのような事態が訪れつつあることは、しばしば他の論者からも指摘されていたところですが、斎藤はそこに各々の生存欲求にすら優先しうるような、若者たちを取り巻く対人状況のドラスティックな転回の痕跡を読み取ろうとします。長くなりますが、再び斎藤の指摘を引用しておきましょう。
二〇〇〇年代に入って心理学ブームが退潮すると同時に前景化してきたのが、「コミュニケーション偏重主義」である。これは単純に言えば、対人評価の基準がほぼ「コミュニケーション・スキル」に一元化されてしまうような事態を指している。いまやそれは、単なる「若者の気分」を超えて、一種の職業倫理のようなものにすらなりつつある。その結果として、コミュニカティブであることは無条件に善とみなされ、コミュニケーション・スキルの有無は、就活などをはじめとして、しばしば死活問題に直結する。
このような社会にあっては、「発達障害」などの正当な理由なしに、コミュニカティブならざることは承認されにくい。こうしたコミュニケーション偏重主義は子ども社会にも浸透しており、例えば中学高校における「スクールカースト(教室内身分制)」の序列においてもコミュニケーション・スキルが最も重視されるという。それゆえ学校時代にコミュニケーション弱者であること、あるいはそのようにみなされることは、その後の人生においても過重なハンデとなりうるのである。(傍点原文)
斎藤が指摘するように、今日において最も要請される人びとの資質が「コミュニケーション能力」に偏重しているのだとすれば(僕も実際そうなのだろうと思いますが)、その資質に長けている人びとにとって、それは各々の対他関係においてスムーズに生存していくために、いかに〝自分らしさ〟を仮構し、どのような「私」を「私」であるということにするのかという、自己演出としての「私」づくりの技法と直結するでしょう。コミュニカティブであるということは、ひとえに自分の社会的属性を「キャラ」として、他者よりも抜きん出るかたちで押し出すことができるという意味にほかならず、特に教室空間においては、複数の「キャラ」による協同的な演技こそが奨励されていることは、多くの教育学者たちによって指摘されているとおりです(✳✳)。もちろん、ここで言う「キャラ」とは、ほかならぬ「この私」にあらかじめ備わった所与のものではなく、こういうひとだと思われたい/思われたほうがよいという打算に依拠した生存戦略の産物でしかありません。ただ、たとえ無自覚であったにせよ、こうした〝自分らしさ〟至上主義に枠づけられた時勢のあり方と、リョウの葛藤が共振していたのだとすれば、そこにゼロ年代の文学が背負わされた課題の一端を読み取ることもまたできるはずです。
『ボトルネック』のなかで、そのことを象徴的に示している箇所が、前節の引用部でも言及されていた兄ハジメの発言と、それに対するリョウの反感でした。引用しておくことにしましょう。
「いいか、何があったか知らんがな、思い違いをしちゃいけない。ひとにはそれぞれ、違った長所があるもんだ。
まあ、オレの妹は確かに賢い。使えるやつだ。頭のよさとか、ひとあたりのよさとかでは、敵わないかもしれない。だけどな。だからって、お前が卑屈になることはないんだぞ。お前にだって、きっとオレの妹よりもいいところがあるんだから。それどころじゃない、他の誰にもない個性が、誰にだってあるんだ。
お前はお前しかいないんだ。お前にしかできないやり方で、その何とかって子と付き合ってやればいいじゃないか」
……そうだな。兄が言えるのは、このぐらいの台詞が精一杯だろう。
やっと、はっきり言える。ぼくはこちらの嵯峨野ハジメも受け入れられない、と。生き様も経験も、抱く感想さえ薄っぺらな男。頭一つ抜きん出てることなど一生できないだろうこいつのどこに、生きる甲斐があるのか。ひとの受け売りをもっともらしい顔で並べ立てるのが馬鹿らしい。自分が何も考えてないことに気づきもせず説教しているつもりになっているのが滑稽だ。ぼくは言葉にせず、思うさま兄を蔑んだ。
ハジメの述べていることは、とりわけ引用の前半部は明確な根拠を欠いた説教に過ぎず、確かに「薄っぺら」なものであったのかもしれません。しかし、後半部にある「お前はお前しかいないんだ」云々という部分は、さほど面白い事実を言い当てているとは思いませんが、それでも端的に正しい命題であり、リョウはみずからの「個性」に思い悩むのであれば、まずその自明な「私」の唯一性・特権性を「滑稽」だと思わずに受け止めることから始めなければならなかったはずなのです。
しかし、こうした自身の端的なかけがえのなさを、リョウやリョウに共感する読者たちが素直に肯定できないのだとすれば、それは何より「単独性」を「特殊性」に還元させようとする時代の趨勢に拠るものでしょう。みずからの存在のあり方を、ある社会規範に対する有用性というモラルの水準で考えてしまうことが、ゼロ年代において生じた特有の文化的条件であったのだとすれば、『ボトルネック』はその模範的な好例たりえていたのかもしれません。少なくとも「セカイ系」にせよ「ポスト・セカイ系」にせよ、ゼロ年代における文学的想像力の発現は、この困難を含み込んだかたちでしか展開しえなかったと言えるでしょう。(✳✳✳)
米澤穂信の小説作品は、いわゆる「古典部」シリーズ(『氷菓』〔角川文庫、2001.11〕など)をはじめとして、その多くがアニメ化などのメディアミックス展開がなされており、思春期に特有の切なさを掬い取るきわめて繊細な表現描写に、僕も強く惹きつけられています。そういった作風のなかで、これまで『ボトルネック』は、米澤の〝毒〟の部分があらわれた小説作品だと評されていましたが、僕にはむしろ『ボトルネック』こそが、最も真っ当なかたちで時代の感性を反映させていたように思えてなりません。それは、誰かに承認されることがみずからの生き方に直結するような社会状況において、いま・ここに固有の居場所を持てない人びとによる行き場のない閉塞感が託されていたように思えるのです。
しかし、だとすればそのような閉塞感を突き破るための糸口はどこにあるのでしょうか。僕としては、こうした点にこそ、並行世界と「この」性をめぐる一連の問題系を扱った小説作品のポテンシャルが試されているのだと考えています。『ボトルネック』において、ついにリョウは、もうひとつの新しい世界に対していかなる親近感を抱くこともできませんでしたが、そこに自分の居場所があろうがなかろうが、当人の意思や感情とはまったく無関係な仕方で、ある並行世界そのものに特別な情念を感じてしまう(=もともとあった現実世界の「この」性が疑いうる)ということがありえるわけで、そこに〝「私」とは何か〟という伝統的な文学の課題とは趣向の異なる思考や感性の発現を読み取ることができるはずなのです。そのことを考えるために、次回は円城塔のSF小説『Self-Reference ENGINE』を扱ってみたいと思います。
(✳✳)たとえば、土井隆義『友だち地獄──「空気を読む」世代のサバイバル』(ちくま新書、2008.3)などが参考になります。
(✳✳✳)ただ一方で、そのような〝自分らしさ〟など無かろうと、もとより全ての人間は、最初から交換不可能なかけがえのなさを手にしているのだという、あたかも道徳の教科書のような主張もまた、リョウや『ボトルネック』の読み手にとっては空虚に響くのはないでしょうか。それが間違っているというわけではなく、ここで言うところのかけがえのなさというのは、現実世界のなかである固有の位置(=それによって自分が自分として生きるに値するような何か)が全ての人間たちに与えられているといった、単なるつまらないお題目でしかありえず、そのような主張もまた〝自分らしさ〟至上主義のイデオロギーを裏側から支えているように思われるからです。各々の人間たちにとって生きるに値する〝自分らしさ〟など、有っても無くてもどちらでも構わないのですが、そのような事柄とはまったく無関係に、「私」という存在のあり方には、取りもなおさず「この」性が備わらざるをえないという点が、ここで何よりも忘却されてはならないことであると思われます。(しかし、それが真の意味で忘却されることなど本来的にありえるのでしょうか?)