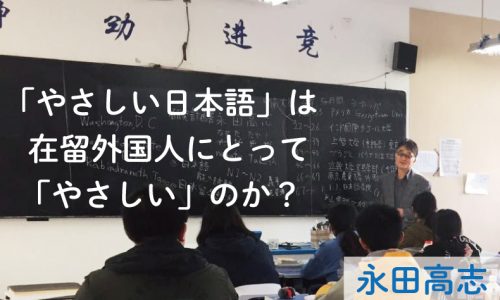ある種のメルヘン
助川幸逸郎 私は読んでいて二つのことを思いました。選評などで、これはまさしく小説だと評されていますが、小説というよりもこれはある種のメルヘンですよね、男の側からすると。
なぜ、志乃が「私」のことを好きになるのかをもう少しリアリティーをもって伝えるべきではないのか。おそらく、「私」には自覚がなくても、この女が「私」を好きになる理由がもっと生々しくあるはずですね。それが伝わってこないと、リアリティーがないなと思ったんです。
重里徹也 そうなのです。いかに「私」がもてたかという話なのだけれど、魔法を使ったみたいになっている。魔法を使ったのなら、どのような魔法だったのか、説明してほしいですね。
助川 美しい女が自分のことを好きになってくれた、それですごく幸せを感じてくれている。これは、ある種のメルヘンですね。美しい夢としては共感して読みました。一方で、この作品は文章がすごくいいんですよ。
重里 鍛えられた文章ですね。
助川 比喩が巧みですね。ただし三島由紀夫の比喩みたいに言葉だけが華麗で、書かれた内容より言葉そのものに目が行くようなものにはなっていない。「冬のなごりのつめたい風が底まですきとおった水面にたえず皴をたたんでいるというのに」とか。鮮やかに情景が浮かびます。春先の冷たい風が吹いて水面に皴のような細かい波が立っていて、はよくあることだけれども、情景が鮮やかに浮かぶ比喩ですね。「街は陽になえて、病む人のように色をうしなっていた」とか。「陽になえて」というのは、まだ寒い時期の午後の日差しの感じをありありと脳裏に甦らせます。細かい文章が一つ一つリアルで、でも全体としておとぎ話みたいに美しい夢の話になっている。それで、相手の女性がなぜ主人公の「私」のことを好きになるか伝わってこない。部分部分の表現は生々しいのに、全体としてはメルヘンになっている。まるで生々しい夢を見たときのような感覚の小説でした。
重里 その二つのことは私も考えていました。「夢」「メルヘン」と指摘されましたが、確かにとても軽やかな感じがするわけです。軽快で洗練された感じといえばいいか。それはどうしてかと考えると、この人は場面を作るのがすごく上手いのです。少ない言葉で場所を的確に描く。それがダイレクトに伝わってくる。この上手さが際立っているのではないでしょうか。それで、けっこう重いことを描いても、重力が軽減されている。それは読みやすさの理由にもなっている。土地、建物、風物を少ない文字数で描き出すのがとても上手い。ベタベタとは描かない。スパッ、スパッ、スパッと端的な言葉でつないで、場面を切り替えていく。それが一つ。
それから文章のことです。この人が使わないエレメントが二つあります。一つはオノマトペ。もう一つは形容詞。オノマトペと形容詞を使わない文章なのです。そして、比喩は指摘されたように装飾的な比喩ではなくて、文章の中に埋もれているような自然な比喩を使う。そんな風に感じましたね。
助川 自然主義系作家の文章ですよね。物語の乗り物になる文章ではなくて、文章そのものに意味を持たせていくような文章ですね。
重里 モダニズム系の作家ではなく、私小説や自然主義小説の文章です。
助川 これ、スカスカの文章で書いたら、俗っぽくって堪えられない話になったと思うんです。
重里 中身だけだと、ライトノベルになるかもしれないような内容ですね。
助川 そうそう。だから本当にそういう内容なのにとりあえず最後まで読ませちゃうのは、目の詰まったきっちりした文章の成果ですね。日本文学の一つの王道をいく、純文学の文章ってこういう文章だよねっていうお手本みたいな文章ですね。この文章できっちり丁寧に書いてあるからバカバカしいって感じにならないで、きちんと最後まで読めるのでしょう。
重里 日本語の力というものを存分に発揮している文章ですね。
助川 才気あふれる文章だとか、物語の乗り物として優れている文章というのはいろいろとありますけれど、日本の純文学の王道を行く文章という点では、これですね。純文学の文体と感じましたね、これは。
志乃はなぜ、「私」を好きになったのか
助川 ところで、普通は私小説系の物語って自分がもてなかった、自分の恋愛がうまくいかなくって破滅していく話を書くわけですよね。ところがこれは自分がもてて家庭を作る話を書いてくわけですよ。三浦哲郎というと井伏鱒二の弟子ということをよく言われます。井伏にはもう一人、やはり青森出身の太宰治という弟子がいます。自分がもてた話で何とか持たせちゃうのは太宰ですよね。そういう点では、三浦も太宰も、伝統的な私小説というより、少し異質だなと感じるんです。
ただ、太宰の小説だとこいつ絶対もてるなってわかるわけです。自分が自慢げに書いてなくても。なぜもてるのかは何となく、言わなくても伝わってくる。ところが、この『忍ぶ川』は主人公がなぜ、志乃にもてたのか、きちんと描いていないのです。人気のある志乃が、他でもない「私」とどうして将来を誓うようになったのか。いまいち伝わってこない。
重里 そうですね。結局、「私」はこんなにモテたんですよっていう話になってしまっている。読者がそこに乗っかれるかどうかというのはあると思いますね。こんなに上手くいくかよっていう人もいるでしょうしね。
助川 吉行淳之介の小説だったら、主人公がたまたまハンサムだったというだけじゃなくて、ちょっとニヒルなところとかがセクシーに見えるんだろうな、というのが、きちんと伝わってくるじゃないですか。こういう男を好きになる女っているよなっていうのが何となく理解できる。ところが、この『忍ぶ川』だと普通のあんまり金のない学生ですよね。他の振られてしまった先輩とこの人とどこが違うのかが、いまいち伝わってこない。
重里 一人、自動車会社に勤めている志乃の婚約者みたいな男がいたでしょう。そいつに比べたら、主人公の方が賢くて、真面目なのでしょうね。頭のよさそうな学生で、一途なところがあって、深読みしたら、それで好きになったのかなっていう感じですか?
助川 私が思ったのは、志乃の父親のことでした。この父親は結構、学がある人だったんですよ、きっと。それで、父親はある程度いい家庭で、教育も受けていたのに、自分は今、飲み屋のお姉さんになっている。子どもの時には色街の射的屋で育った。そういう教育レベルの高いところから没落した父親の娘というのは、アカデミックなものとか、学歴とかに対するあこがれがものすごくあって、この主人公も多分他の大学生と比べても旧家で昔からのおぼっちゃまくんの家柄だから、代々、家で受け継がれた教養の雰囲気みたいなものが何となくあって、それに対するあこがれでくっついたんじゃないかなって私は思ったんですね。
志乃が持っている知的な世界とか、教養とかに対する、今は遠ざかっているけども、接したかった憧れみたいなせいで、この主人公が自覚しないで持っている教養ありげな感じに惹かれたんだと思うんです。自動車会社のセールスマンは仕事ができるけれど、全然そういう文化だとか教養だとかに対する理解がない。だから全然好きじゃない、みたいなことだったのでしょう。ところが、この小説にはそれを書いていないです。
重里 父親への志乃の思いは想像できますよね。それはしっかりと書かれています。遊女が死んだ時に、父親がその遺体を世話したというエピソードとかは書かれていて、おっしゃるように父親をどこかで誇りに思っているようなところがある。確かにこの父親というのは知的なところがある。けれども、親から勘当されて。
助川 上手く生きられなかった人ですね。
重里 器用さがなかったのでしょうね。それで、崩れていった人なのでしょう。ということは見えてきます。その父親への思いが、この主人公の「都の西北にある大学」の学生に重なっているのだろうというのは想像できますよね。
助川 早稲田の学生の中でも、なぜ、この主人公だったんだろうっていったときに、多分父親への思いを重ねられるようなところが、この主人公にあったはずなんだけど、そこがきっちり書かれていないかなと思います。
重里 あるいは、文学志望と関係のあることかもしれませんね。それを書くべきですね。そこは。父親は文学崩れ(文学を志望してかなわなかった人)なのかなと思いました。
助川 主人公は自覚していないけれども、そういうところがあって、それが書かれていれば、これはファンタジーではなくて、二人の出会いがすごく運命的なものになったのだと思います。二人の組み合わせは必然だったんだというのが伝わってきて、もっとこの小説は説得力があったし、最後の二人がくっついていく場面にしても本当にこうなるしかなかったんだな、というのが強く出たはずだと思いますよね。
なぜ、志乃の思いを描けなかったのか
重里 恋愛小説には鉄則があります。出会いは偶然だけれど、恋愛は必然だったというものです。その必然をしっかりと書かないと、恋愛小説として説得力を持ちにくいですね。必然に触れないと。
助川 もうちょっと頑張れば書けたのに。現実ではたぶん、三浦哲郎の奥さんは三浦のそういうところが好きになったのに、三浦はそれを書けていないんです。
重里 どうして書けなかったのでしょう。
助川 太宰治だと兄のことや、自分を温かく支援してくれている周囲の人たちのことを書いて、頼りになる大人に甘えている子供みたいな立場に自分のポジションを取ります。すると、子どもがこんなにみんなに優しくしてもらえてうれしい、みたいな調子でもて話も書くから、嫌味にならないわけです。けれども、三浦哲郎は、要するに自分の魅力みたいなものとか自分のどこが他人に好かれたのかみたいなことを書けない文体と視点でこの題材に挑んでしまったのじゃないでしょうか。それで、方法的に書けなかったのだと思います。才能の不足というよりは。この文体だと何だか知らないけど、もてているよっていう書き方になってしまうんですよね。
重里 単純にいうと、自慢話をするのが嫌だったということじゃないのでしょうか。
助川 簡単にいうとそうですね。自慢話を上手に書くには、違う文体を獲得する必要があったのでしょう。
自慢話を自慢話でなく書けるような方法を太宰は持っていた。ところが、この伝統的な自然主義の文体だと、要するに「私」というものを読者よりも上に設定できないわけです、簡単に言うと。かなり低いところに自分を設定しないと書けない文体なので、これだとなぜ、自分がもてたのかって理由がきっちり書けないんですね。
重里 けれども、その分、読者が感情移入しやすくなったということはありますね。なぜ、もてたのかを書くと、感情移入しにくくなるかもしれません。いい気なもんだなってなってしまうかもしれません。それが嫌だったのではないですか。それを避けたかったのでしょう。
背景にある階級の問題
助川 いい気なもんだなっていうか。教育レベルという話をしましたけども、それをいってしまうと階級的な問題が出てきてしまいますよね。それは伝統的な私小説というものが抱えている矛盾ともいえるでしょう。私小説作家の多くはもともとそんなに階級が低くありません。貧農の家に生まれたり、工場労働者の息子だったりしたら、高等教育は受けられませんから、なかなか小説家なんかなれないわけですよ。ある程度の家に生まれて学問もさせてもらって、それで私小説作家になっているわけですよね。そうすると、自分がこういう風なところに今のような境遇にあるということを深掘りしていくと、結局、自分の特権性みたいな問題に行きあたってしまうわけです。
自分はこんなにみじめな暮らしをしているんですと書いているけれども、それを書いてる自分が今日ここにいたって、ただ悲惨な暮らしをしているのではなくて、悲惨な暮らしをしているということを小説に書いて原稿料がもらえてしまう構造がそこにはあるわけです。これは、ある種階級的な問題と関わらざるを得なくなる。たぶん、三浦哲郎は、日本の小説が抱えているすごく大きな問題とぶつかっているのだと思います。三浦個人の問題ではないと思います。
重里 この問題を深掘りしていくと、なぜ、太宰治が特権的な作家になれたのかということにも触れられそうですね。おそらく、そこには非合法の左翼運動の経験がかかわっているのでしょう。三浦はそういう問題で悩まなかったのかもしれません。自分が社会的にどういう位置にあるのか、その社会はどんな矛盾を抱えているのかを深掘りしなかったのではないでしょうか。あるいは左翼運動の正体を切実に体験することがなかったのではないでしょうか。三浦がなぜ、志乃さんに「私」がもてたのかを書けなかったかという問題は、非常に深い理由があるということですね。日本近代文学史を一望するような問題ですね。
助川 三浦一人の腕が悪いとか才能が足りないとかっていう問題ではないですね。
重里 三浦はだけど、それは本能的に書かなかったのでしょうか。俺の方法じゃ書けねえよな、これは書かない方がいいのだ、書かない方が結構のいい小説になるのだということですか。
助川 この文章とこの視点を選んだ段階で、自動的にそこは排除されたのじゃないですかね。文体と視点が物語内容を制約しているのだと思います。
井伏鱒二に惹かれた作家たち
重里 それを書こうとすると、新しい文体と視点が必要だったということですね。ところで、井伏鱒二の弟子だというのはどう思われますか。私が少し思ったのは、手紙が割と大きなウェイトを占めていることですね。これは井伏的だな、と思いました。
助川 なるほど。太宰も書簡体が好きですよね。
重里 好きですね。そんなこともちょっと思いましたね。それにしても、井伏鱒二とは何なのですかね。日本近代文学における井伏鱒二というのは。
助川 あまり目立たないけれど、こうやってお話ししていくと、重要なポジションにいる作家ですよね。井伏については、私は文体と物語の問題を考えます。物語を運ぶのに適した文章というものがあって、たとえば宮本輝や井上靖の文体がそうです。この二人の文体は、俗っぽいといわれることもありますけれど、文章という「仲介役」をあまり意識させず、物語世界に読者を引き込む力はピカイチです。井伏とか三浦哲郎とかの文章は、そういうものとは全く違って、文章そのものに意味があるというタイプの小説ですね。
重里 お話を聴きながら、しきりに開高健のことを思い出していました。開高も井伏を高く評価し、慕った作家ですね。開高の文章にもそういうところがあるのではないでしょうか。文章そのものが目的の小説というか。
助川 井伏、三浦、開高と並べると、それぞれ文章のタイプが違うのですが、いずれも、ものすごく緻密ですね。アバウトじゃないですよね。いい加減じゃない文章です。
重里 密度が濃いですよね。文章が自立しているといえばいいか。
助川 そういう文章を設定してしまうと、逆に物語を動かしにくくなるのではないでしょうか。
重里 あるいは言葉自体が物語性を持ってしまうのでしょうね。物語があって文章があるのではなくて、文章自体が意味を作っていく。
助川 そういうことです。あまりにも文章が、書いている側の感受性や思考をリアルに反映するから、嘘をつけない文章になってしまうのですね。結局、ちょっとアバウトに書いていると、近似値で書けるから、嘘が仕組めるのだけれども、井伏も三浦も開高も、そういう近似値の文章ではないのです。
厳密に自分が感じたことを書いていく文章だから、そうすると本当はこうやって体験したのだけれど、実際は小説の都合としてはこういう話にした方がいいんだよねっていう、そういうことがしにくいのですね。対象と叙述主体の関係が少しでも変わると、そのズレが如実に出てしまう文章だから、「ほんとうはこういう体験をしたけれど、作品にはこう書いておく」ということがやりにくい。敢えてやってしまうと、そこに不具合が生じる。こういう文体を駆使して、物語を展開するということはやりにくい気がしますね。
重里 その嘘をついたところで、文章が浮き上がってしまうのでしょう。それは井伏も開高も三浦も、共通しているんじゃないかという気がしますね。
助川 文章を精密にしすぎると、虚構を描きにくくなるという傾向はある気がします。
重里 ただ、逆に言うと開高も井伏も三浦も、フィクションよりも言葉の方が信じられるということなのでしょうね。あるいはフィクションを信じられないというか。物語よりも言葉の方が信用できるということなのじゃないかな。
助川 そういうことかもしれません。
重里 そういう精神に基づいて、そういう姿勢で、三浦も小説を書いたのだろうなということを思いました。それは『黒い雨』も『輝ける闇』も、そうなのでしょう。