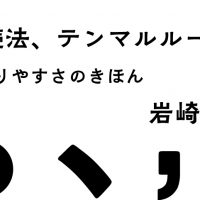ヴァーチャル・リアリティの射程
もう一度、しつこいようですがこの連載で考えようとしていることを確認しておきたいと思います。それは、たとえ世界の複数性を認めても揺らぎえない「私」の「この」性は、果たして世界そのものの側にも適用可能なものであるのか、また適用可能であるとして、それは論理的に理解することができても、易々と感覚的に納得することができるものなのかという問いに集約されます。そのような思考実験は、主としてSF的な意匠を借りて行なわれることが多いため、おのずと本連載でもSF作品を取り上げることが多くなると思いますが、もちろんSFであることがこの問題を扱うための必要条件というわけではありません。むしろこういった問題が、SFという形式を借りて表現されるべきものであるという暗黙の前提(?)があることもまた、僕にはとても不思議なことのように思えます。
さて、今回はヴァーチャル・リアリティ(以下「VR」と略記)の登場がもたらした問題系を考えてみたいと思います。とはいえ、ある仮想世界を想定し、そこに相応の〝現実感〟を与えようとする試み自体は、いくらでもその起源を遡ることができるでしょう。ただ、すでに多くの指摘があるように、VRの概念は1990年代以降、家庭用コンピュータの本格的な普及によって、それまでとは比べ物にならないほど人びとのものの見方を抜本的に変えていくことになりました。事実、1990年代日本の言論空間では、コンピュータ・ネットワーク上に拡がるVR──それは当時「サイバースペース」と呼ばれていました──への言及が活発になされています。雑誌の特集などもあげればきりがないのですが、ここではたまたま手元にあった同時代の書物の抜粋を引用しておくことにしましょう。
ところで、サイバースペースの中での「主体」のあり方について少し考えてみよう。主体はそこでは無数の断片に分断され、複数の現在の中に切り裂かれてしまう。簡単に言えば、そこでは「主体」のリニアな連続性と一貫性は、ちょうど空港のトランジット・ルームにいる得体の知れない外国人のように、サイバースペースにおける無数の「現在」の断片の中で解体されてしまう危機にいつもさらされていることになるわけだ。彼のアイデンティティを保証するものは内ポケットに入っているパスポートだけである。だが、パスポートが保証するアイデンティティとはそもそも単なる記号にすぎないのではないだろうか。それは誰が持っていてもいいような抽象的な表徴にすぎない。
(室井尚『情報宇宙論』岩波書店、1991.7)
もちろん、サイバースペース(VR)のなかで「私」のアイデンティティが無限に拡散したからといって、実際に考えたり感じたりしている「この私」という存在が複製されるということは絶対にありえません(そもそも、実際に考えたり感じたりする存在が複数〝いる〟とはどういうことなのか、僕たちには原理的に想像すらできないでしょう)。その意味で、それは広義のドッペルゲンガーのような現象と本質的には何ら変わらず、「私」の社会的な属性には重大な影響を与えうるにせよ、なお単独的な「私」のあり方とは根本的に無関係であるとみなすべきだと思われます。
しかし、現実世界の「この」性についてはどうでしょうか。こちらも論理的に考えるなら、実際に存在する現実世界(この宇宙空間)の姿かたちは複製可能であるにせよ、端的な事実として〝ある〟いま・ここのあり方自体を模造できるということはありえません。したがって、「私」の場合と同じように、現実世界の「この」性は本来的に揺らぎえないのですが、僕たちは時として、あたかも現実世界の「この」性が瓦解し、VRの向こう側へと越境するかのような錯覚に襲われるのではないでしょうか。少なくとも、広義のVRを扱った物語作品は、それがどこまで意図された結果であるのかはさておき、こうした多重化されたリアリティの記述に大きな情熱を注いでいるように見えます。ここでは、その象徴的な事例として岡嶋二人『クラインの壺』(新潮社1989.10)を検討してみましょう。
「本物」らしさをめぐる問い
『クラインの壺』は、あるゲームシナリオの原作を担当した大学生の上杉彰彦が、そのシナリオをもとにした最新鋭のVRゲーム「クライン2」(K2)のテストプレイヤーに任命され、高石梨紗というもうひとりのテストプレイヤーとともに、現実世界とVRを相互に行き来するという筋立ての小説作品です。物語が進むにつれ、ある日いきなり梨紗が失踪したことを契機に、上杉は梨紗の友人である真壁七美とともに、VRの提供企業であるイプシロン・プロジェクトが、アメリカで人体実験のようなかたちでVRのテストを強行した結果、多数の死者を出していたことを突き止めていきます。そして七美と上杉は証拠を押さえるために研究所に乗り込んでいくのですが、イプシロン・プロジェクトのスタッフに見つかってしまい、脱出を試みるもエレベーターのなかでついに捕らえられてしまう……かのように思われたのですが、実は上記の設定こそが「クライン2」の本当のシナリオであり、上杉は知らないうちに自身の原作とは異なる物語展開に参加させられていたというのです。こうしたドッキリ(?)計画の成功を喜ぶイプシロン・プロジェクトのスタッフを尻目に、もはやどちらが真実(本当の現実世界)なのか区別がつかなくなった上杉は、研究所から逃走し、最後の手段として自殺を試みる──というところで、物語は幕を閉じます。
作中では、まずVRゲーム「クライン2」が、現実世界と寸分の区別がつかない「本物」らしさを提供するものであることが繰り返し強調されています。たとえば、上杉が初めてゲームのなかに足を踏み入れた時の感想は、以下のようなものでした。
これがK2のシミュレーションなのか──?
信じられなかった。僕の周りにあるものは、すべてが本物だ。この上着も、靴も、ベッドも壁も天井も、前にある小さなドアも──なにもかもが本物だった。本物としか思えない。
また、物語が進み、実は現実世界だと思われていたものの一部も、VRによって捏造されたものだと確信した上杉は、七美に以下のように語り聞かせます。
「あの中では、すべてが現実になる。そこにあるものは、木も、家も、道路も、人も、なにもかもが現実なんだ。実際に入った人じゃなきゃ、口で説明しても理解はできないかもしれない。K2の中では、そこに作り出されたものはすべてが本物として知覚できる。触ることができるし、その暖かさや冷たさや、固さや柔らかさも、匂いも音も、完全に現実なんだよ。でも、すべてがニセモノだ。なにもかも、データを組み合わせたニセモノなんだ。自分の身体さえね」
いまでこそ、VRの「本物」らしさは広く人びとに共有されたものとなっていますが、未だインターネットの接続すらままならない時代であった1980年代において、現実世界と見紛うほどの「本物」らしさの演出は、登場人物たちに大きな衝撃を与えるものだったでしょう。そして、一連の話に驚く七美に対し、上杉は「『クラインの壺』を使えば、そこに入った人間の、頭の中を組み替えることができる」し、もはや「そいつの記憶を作ってしまうことができる」のだと説明します。ここで、外部世界の「本物」らしさが、みずからの「記憶」をも信頼できないものにしてしまうことが主張されているのです。
少し話はずれてしまいますが、僕はあと数十年以内にタイムマシンが発明されるのではないかと推測しています。それは、実際に過去に渡航できるということを意味するのではなく、人びとのあいだで過去として共有されているイメージを最新鋭のVRで再現することならば、ある程度近い将来にできるのではないかと思っているからです。それは「本物」の過去ではないではないかという反論を抱く方は、そもそも何をもって「本物」とみなされるのかを考えてみてください。現在の時点でまったく記録が残っておらず、また誰の記憶にも想起されることのない過去というのを、僕たちは果たして把捉することができるでしょうか。哲学者の大森荘蔵が主張するように、過去というものが現在から遡行的に捉えられたイメージの再構成であるとすれば(『時間と自我』青土社、1992.3)、それを現在の地点に創造(捏造)することで、過去世界への渡航は容易に実現できるように思うのです。
では、こうしたイメージの創造(捏造)による世界認識の変化は、いま・ここに〝いる〟という「私」のアクチュアルな感覚とどのように関わるでしょうか。もちろん、前回に扱った夢世界の航行を想起していただければ分かるように、現実世界であろうがVRであろうが、とにかく「私」が〝いる〟いま・ここの時空間こそが、あるべき真なる世界の姿であると認めてしまえば、もとより「本物」らしさをめぐる認識の亀裂は生じえないわけですが、しかしVRを扱った物語作品は、往々にしてそうした確信を揺らがせてしまうようにも思えます。『クラインの壷』から引用しておきましょう。
この手は、誰の手なのだろうか?
梨紗に手を預けながら、僕は思った。
あるいは、これはコンピュータによって、僕の網膜に映し出されたシミュレーションなのだろうか?
梨紗の手を握りしめた。
しっとりとした柔らかい手だった。
どうやって見分ければいいのだろう? 今、僕の見ているものが、現実にそこにあるかどうかを、僕はどうやって知ればいいのだ? この手は、壺の内側にあるのか、それとも外側なのか?
現実世界とVRの差異が、ここで「壺の内側」と「外側」という比喩で語られているわけですが、もちろんこれは、位相幾何学における「クラインの壺」の概念を援用しているものと思われます。正確な定義はともかく、「内側」と「外側」がいつの間にか縫合されてしまう「クラインの壺」の描像は、現代思想を語るための哲学的モデルとして多く借用されてきました(その最も有名なものは、おそらく浅田彰『構造と力──記号論を超えて』〔勁草書房、1983.9〕でしょう)。つまり、ここで現実世界とVRに区別をつける視点自体がそもそも無意味であることが示唆されているわけですが、ではそのような着想は、容易く人びとを納得させるものであったのでしょうか。
世界はただ「この」ひとつである
1995年、着実に社会的存在感を発揮しつつあったVRの思想的意義について、社会学者の大澤真幸は次のように述べています。
仮想現実は、メディアを使った現実の再現、現実の類比に他ならない。やがてメディアが電子的なものになり、その技術的な性能が向上すると、仮想現実も「真」に迫ったものになる。つまり、仮想現実と現実との外観上の相違が縮小してくるのだ。そうなると、類比の関係が逆流し、現実の方こそが仮想現実ではないか、現実も仮想現実と同じような仕方で構築されているのではないか、との発想が現れるようになる。これが、逆方向の再類比である。ポスト・モダン的な思潮も、基本的に、これと同じ形式の類比の反転に依存している。「前衛的」な思想も、「大衆的」に進捗するメディア的な現象と無縁ではなかったのだ。
(『電子メディア論──身体のメディア的変容』新曜社、1995.6)
VRという科学技術は、極論すれば現実世界と仮想世界の区別などなく、拡散するアイデンティティとただ無為に戯れていればよいという「ポストモダン」の思想と非常に親和性の高いものです。実際、両者の共振関係を主張するような言説も、1990年代には数多く現れました。それは、VRを扱った物語作品もまた例外ではありません。
先にも述べたように、『クラインの壺』の結末は、自分が〝いる〟いま・ここが、現実世界とVRのどちらなのかを知るために、上杉が自殺を仄めかす場面で終わっています。その記述は、次のようなものでした。
僕の意識は、とうとう逃げ遅れてしまった。考えれば考えるほど、コントロールが効かなくなる。幾度も、山の向こうに向かって叫び声を上げた。自分の感情が、次第に鈍くなってくるのを感じる。
ここは、どちら側なんだ?
また、鏡を見た。
「どっちにしても、たいした違いなんかない」
声に出して言ってみた。
それを確かめる手段がない以上、考え続けること自体が無駄なのだ。答えは、二つに一つしかない。
壺の、内か、外か。
自分が〝いる〟場所が分からなくなってしまう身体感覚は、前回の『夢の木坂分岐点』と同じように、それ自体として今日の情報消費社会における自己認識の戯画ともなりえているでしょう。しかし、仮に本当の意味で世界の「内側」と「外側」が「クラインの壷」のようにくるりと反転するものなのだとすれば、上杉自身が述べるように「どっちにしても、たいした違いなんかない」のだから、いま・ここがどちらの世界なのかを見きわめようとする試み自体が、そもそも無意味な行動であるとも言えます。それは、ある種きわめて「ポストモダン」的な感性であり、現代的な対処の仕方だと評価できるのかもしれません。
ただ、同時に注意しておきたいのは、上杉自身がそのことに気づいているにもかかわらず、なお「どちら側」なのかを気にせずにはいられないということです。壺の「内側」か「外側」かを知るためならば、みずからの生命を投げ打っても構わないという上杉の姿勢は、先ほどの「ポストモダン」的な(=現実世界と仮想世界の存在価値がもとより同等であるとみなす)考え方からすれば、決してスマートなものであるとは言えません。しかし、そのような上杉の決断が、作中でひとつのカタルシスを生み出し、読み手の共感を誘うものであったということ自体が、良くも悪くもVRというものに対する人びとの変わらぬ見方を象徴的に示していたとも考えられるのです。
実際のところ、僕たちは〝自分探し〟(=本当の「私」探し)を易々とやめられないように、世界がただ「この」ひとつであるという素朴な経験を信じていたいのではないでしょうか。言い換えれば、ごく平凡なことですが、僕たちは自分が〝いる〟現実世界の「この」性を、(いま・ここでありありと把握されているというアクチュアルな感覚ではなくて、)それまで過ごしてきた経験や歴史の厚みを備えた時空間のあり方に求めずにはいられないのではないでしょうか。そうであるとすれば、VRという科学技術は、どれだけ精巧に現実世界を模造しようとも、もとよりこの現実世界(=「本物」であること)の唯一性・特権性を再確認するための迂回装置としての機能を持つに過ぎないでしょう。もちろん、それでも別に構わないわけですが、以上のような見立てが正しいならば、VRを扱ったSF作品の主題系は、その見た目(?)に反して、ゼロ年代における〝並行世界もの〟の物語文化における問題意識と、むしろ背馳するものであったと言えるのかもしれません。その意味で『クラインの壺』の結末は、まさに上杉が現実世界の唯一性・特権性を信じられるどこまでも健全な人間であったことを、図らずも逆説的に証し立てていたのです。
その後、岡嶋二人はもともとコンビで活動していたのですが、『クラインの壷』の発表を最後に解散し、うちひとりは井上夢人という名前で現在も作家活動を続けています。特にSFの領域では、黎明期のコンピュータ・ウィルスの暴走を描いた『パワー・オフ』(集英社、1996.7)や、自覚なき多重人格者の犯罪行為を扱った『プラスティック』(講談社、2004.9、これは本当にミステリーとしても異色の出来だと思うので、ぜひ読んでいただきたいと思います)など、非常に洗練された小説作品を数多く発表しています。一方で、VRの台頭から20年以上が経過し、仮想現実(Virtual Reality)ならぬ拡張現実(Augment Reality)の隆盛が叫ばれるようにもなってきた今日、私たちの感性は、1990年代からさらに変貌しつつあるのかもしれません(✳)。そのような状況下において、『クラインの壺』の結末における上杉の決断は、現実世界の唯一性・特権性とは何なのかという古くて新しい問題をめぐって、いま一度足を止めて考えるに値するような論点を提示しているようにも思えるのです。
ちょっと無用に込み入った話になってしまったかもしれません……。次回は、VRの文化的意義をまた別の角度から考えるため、小説作品ではなく押井守監督のSF映画『アヴァロン』(日本ヘラルド、2001)を検討していくことにしましょう。
(✳)拡張現実の社会的意味については多くの研究があるものの、手に取りやすいところでは鈴木謙介『ウェブ社会のゆくえ──〈多孔化〉した現実のなかで』(NHK出版、2013.8)が平易な解説を施しています。