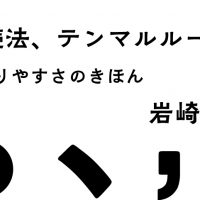小松原哲太
神戸大学大学院 国際文化学研究科言語コミュニケーションコース講師
キーワード: 定型表現、認知言語学、コーパス言語学、構文、談話機能
1. 定型表現と創造性
本書は、認知言語学を背景とした、定型表現とその拡張用法の研究書である。「定型表現」には、イディオム、慣用句、ことわざ、連語、格言、決まり文句、故事成語、などがある。例えば「鬼に金棒」である。「鬼に金棒」は比喩的なフレーズとしては確かに定着している。(文字通りの意味の理解は、桃太郎のデフォルメされたイメージくらいでしかないが…)こういったフレーズを研究することが、言語の理論研究にかかわるのか?それが、案外かかわるのである。
定型表現は、個人の言語知識として記憶され、言語コミュニティのなかで慣習化された表現である。定型表現は、そのまま使える便利な固定表現でもあるが、創造的な拡張表現の鋳型でもある。例えば「鬼に金棒」は、以下の例では、広告効果の下支えになっている。
「鬼に金棒 弁慶に長刀 ローソンにATM」(2010年7月21日東京中央線車内広告)
ここでは、前置きの2つの定型表現が呼び水となって、「AにB」が相乗的効果の意味を表す構文としてはたらく。3番目の拡張的用法では、「ATM」の道具としての強力さ、「ローソン」の擬人化された屈強なイメージが喚起される。
2. 本書の目的
本書はこのような、定型を踏まえて「定型を破る」現象の考察を通して、人間の創造的な言語使用の基盤となっている知識について、社会・認知的な観点から考察を行っている。
定型表現は、いわゆる「意味の合成性」の原理(全体の意味は構成要素の意味の総和であるとする原理)の反例として、認知言語学で重視されてきた。(認知文法の提唱者 Ronald W. Langackerの公式ウェブサイトのURLはhttp://“idiom”.ucsd.edu/~rwl/ である。)本書は、認知意味論、認知文法を背景とした従来の理論的研究に加えて、コーパスから収集した事例の実証的研究も行っている点に特徴がある。具体的な文脈を重視し、定型表現の談話機能の考察にまで踏み込んでおり、定型表現研究の新しい視点を提示している。
本書が取り組む研究課題は、以下の3点である。
- 定型表現の非字義的特徴および拡張用法の基盤となるような認知的動機づけと知識はどのような特徴をもつのか(第3章)。
- 定型表現の拡張用法の基盤となる慣習的知識とその成立の過程とはどのようなものであるのか(第4章)。
- 拡張用法のパターンとその談話的機能とはどのようなものか(第5章)。
3. 定型表現と文脈
第3章「慣用句の意味的なゆらぎ―修飾関係と文脈の観点から」では、定型表現の固定されているように見える意味が、文脈によってはゆらぐことが示されている。語の意味が文脈に複数の意味を示すことは、これまでの意味論でよく知られている。例えば「手」の意味は、「手を握る」「手を出す」「手を切る」のように、文脈によって異なる。これに対して、慣用句も多義的になり得ることは、広くは認識されていない。例えば「手を回す」には、少なくとも以下の3つの用法がある。
文字通りの手を動かす動作 (例)「向こう岸に向かって手を回して合図する」
慣用的な身体動作 (例)「さりげなく肩に手を回す」
抽象的な行為 (例)「事件が明るみにでないように手を回した」
定型表現は、その名の通り、形式と意味の結合が定まっている表現であるように思われる。しかし、定型表現は、あらゆる発話で同じ意味を示すわけでなく、特定の文脈においては、活性化される意味領域が変化するのである。
4. 定型表現の構文
第4章「慣用句とことわざの形態的・意味的傾向」は、1つ1つ独立しているように見える定型表現のなかに、構文的な表現パターンが存在することを論じている。定型表現に使われている文法構造には、例えば以下のような形式的パターンが存在する。
「AにB」 (例)「なめくじに塩」「猫にかつおぶし」
「AてもBても」 (例)「明けても暮れても」「泣いても笑っても」
「AよりB」 (例)「花より団子」「論より証拠」
形式だけではない。意味にもパターンが存在する。例えば、「AにB」という形式には、以下のような意味が結びついたパターンがある。
<非効果> (例)「かえるの面に水」「しゃかに説法」
<相乗的効果> (例)「泣きっ面に蜂」「鬼に金棒」
<アンバランス> (例)「ちょうちんに釣り鐘」「掃き溜めに鶴」
<心神衰弱> (例)「青菜に塩」「なめくじに塩」
定型表現の意味には、構成要素となる語の比喩的な意味だけでは十分に説明できない含意が存在する。この含意が、特定の構文形式と結びついている可能性を、本章の考察は示唆している。
5. 定型表現の拡張用法
第5章「定型表現の拡張用法―『決まった言い回し』は決まったままか?―」は、定型表現が拡張され、修辞性を発揮する事例に注目し、定型表現の拡張用法の機能と制約について論じている。本章の研究成果の1つは「AにBなし」「AでBをV」という形式の日本語ウェブコーパスにもとづく分析結果である。以下の3点が、特に注目される。第1に、この調査では拡張の元となる定型表現よりも、拡張用法の方が、生起頻度が高い場合があることが分かった。例えば、「学問に王道なし」は、元表現の頻度は10例であったのに対して、拡張用法(例えば「ダイエットに王道なし」)は34例であった。第2に、拡張用法のバリエーションとしては、以下の7つのパターンが観察された。
- (1) 内容語の拡張 (例)「学問に王道なし」→「子育てに王道なし」
- (2) 句の省略 (例)「陰で糸を引く」→「糸を引く」
- (3) 態の変化 (例)「真綿で首を絞める」→「真綿で首を絞められる」
- (4) 助詞の拡張・省略 (例)「看板に偽りなし」→「看板に偽りはない」
- (5) 自他交替 (例)「真綿で首を絞める」→「真綿で首が絞まる」
- (6) 音韻的拡張 (例)「死人に口なし」→「死人にグッチなし」
- (7) スクランブリング (例)「肩で息をする」→「息を肩でする」
第3に、定型表現には、拡張に使われやすい部分構造と、使われにくい部分構造があることが確認された。例えば「学問に王道なし」のはじめと終わりを拡張した「_に王道_」の事例は74例であったのに対して、中間部を拡張した「学問_ _なし」の事例は2例であった。
定型表現は無制限に拡張できるわけではない。拡張用法では、発話文脈の意味に適応しつつも飛躍しすぎず、元表現が喚起できなければならない。文脈への適応と元表現の維持は、トレードオフの関係にあり、両者の均衡状態を保つことで拡張用法が適切に使用されるのである。
6. 本書の意義
定型表現という言語現象は、認知言語学と関わりの深い3つの研究領域である、コーパス言語学、構文文法、レトリックの交差地点にあり、本書はこの3方向に興味深い示唆を与えるように思われた。
コーパス言語学では、大量の用例にもとづく統計的分析が行われることが多い。例えば「AにB」という形式の高頻度パターンを抽出するだけであれば、現在の技術では容易に実行できる。しかし、このなかには、定型表現とその拡張用法が含まれている。そして、後者は、前者がなければ存在し得ない表現である。この事実は、コーパスにどのような表現が存在するかを調べる、という基礎的な作業において、定型表現と拡張用法の関係を加味する必要があることを示している。
定型表現にもとづく拡張用法が生産的に使用されているということからは、定型表現の部分構造が、構文として機能しており、部分の総和としては得られない意味を伝達する役割を担っていることが示唆される。特に第5章で示された、生産的な定型表現の部分構造(例えば「_に王道_」)は、構文文法のアプローチでは本格的には研究されておらず、構文研究のフロンティアであるように思われる。
このような構文がもつ創発的な意味は、メタファー、メトニミーといった基本的な比喩の意味だけでは十分に説明できない可能性がある。定型表現の比喩的意味は、レトリック研究で注目されてきたが、より包括的な定型表現のコミュニケーション機能の実態を捉えるためには、さらに、定型表現の拡張用法を考察対象とすることが鍵となると言える。
創造的な表現法の1つは、定型表現という「慣習」を上手に利用することである。創造的な表現がゼロから作り出されることは稀である。「創造性は定型性を基盤としている」というテーゼが、本書の探究のテーマになっている。