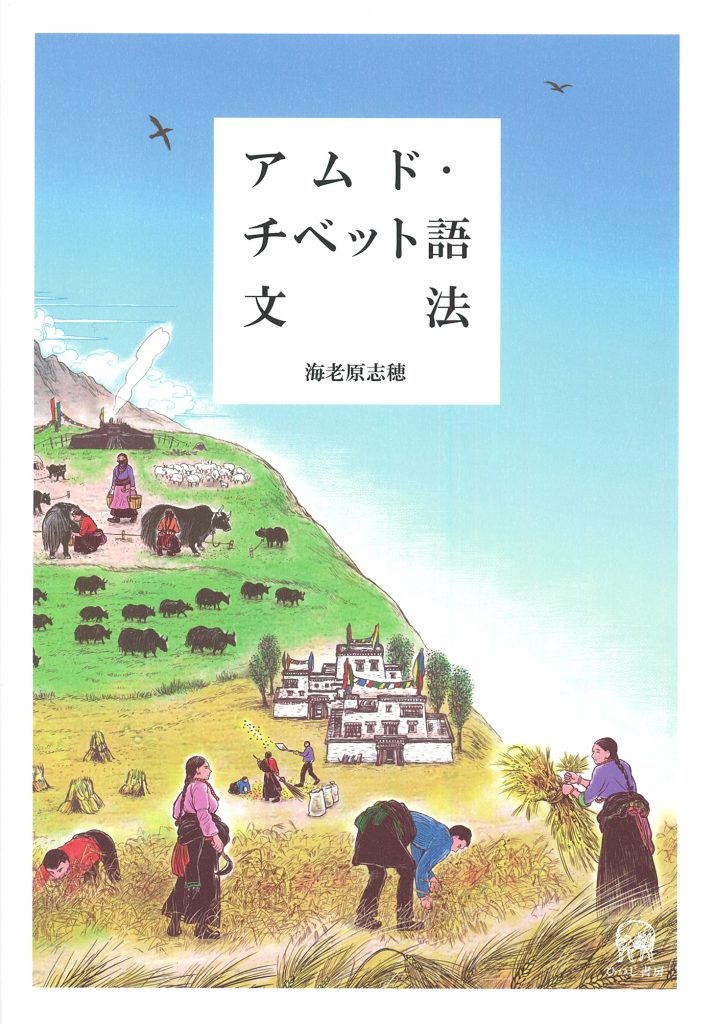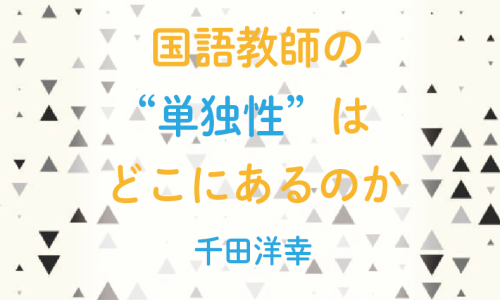鈴木博之
国立民族学博物館
キーワード:チベット系諸言語、アムド、記述言語学、文法範疇
1 本書の概観
本書は日本語による初めてのまとまったアムドチベット語(以下「アムド語1 」)の文法記述である。従前出版された日本語によるチベット系諸言語の記述文法を見渡せば、星(2016) による記述言語学の方法論を応用した古典チベット文語文法があるものの、口語変種に関して見れば、本書が初の本格的な記述文法といえる2 。
本書の内容を概観すれば、先行研究を批判的に検討して文法現象を議論するタイプの学術専門書とは異なることに気づく。計976 の例文3 によって現象を的確に記述し、平易な解説で言語の構造を説いている。本書の例文はすべて母語話者による再度のチェックを経ることで(p.iii)、記述の精度を高めている。第1章はアムド語の概況を簡潔にまとめて提示し、第2章は音韻およびその関連現象を述べ、第3章から第8章まで、語から句、句から文へと、記述の単位を徐々に大きくする配列としている。第9章は敬語の記述であり、そののち3篇の付録と文献・索引が続く。詳細な目次と図表一覧(pp. vii-xvii) は検索にも役立つ。
以上のような構成をとる本書であるが、同時に専門家には物足りないと感じられる部分もある。特に気になったのは、国外で出版されたチベット系諸言語の文法や博士論文にはたいてい存在する、口語音形式とチベット文語形式の体系的な対応関係に触れた部分が、本書には含まれていない点である。Häsler (1999) は、記述研究における音声・音韻の記述には口語形式の体系化とともにチベット文語形式との対比も整理すると述べ、また多くの研究もこの方法に従っている。もちろん、これは共時的な記述研究と直接的にはかかわらない。それゆえ、記述がないこと自体は単に「不親切」であるという印象を抱かせるだけであって、文法記述の質を下げるものではないことは注意しておきたい。むしろ、文語形式を頼らずに共時的現象を記述した著者の方針を肯定的に評価できる。しかし、Aikhenvald (2015:286) が述べるように、歴史的な観点を共時的分析において参考にすることも時として必要となる。
上述のように、本書は文法現象を例示することで著者の分析を支えている。このため、文章による言語現象の検討と分析が簡潔に済まされており、その結果、手軽に言語現象を把握できる一方で、先行研究との立場の異なりや議論すべき問題をめぐり、著者の立場を支持する議論に不足がある。もちろん、簡潔を旨とする著者の論述方針に照らせば、議論の不足自体を否定的にとらえては問題点を見誤ってしまう。
「序」にあるように、著者は博士論文に含まれている一部の内容を割愛して本書を出版した。語彙集とテクスト集を欠くのは、記述文法としては大変惜しい。しかし、著者は本書を「記述文法」や「記述的研究」とは呼ばず、より一般的に「文法」と名づけている。しかし著者は多く文化語彙を収集した経験もあり(海老原2016, 2017、星 主編2018)、手元には数多くの資料があるだろう。CD-ROM などによるデータの添付で出版することはできなかったのだろうか。星 主編(2018) のように、民俗語彙、特に色が問題となる家畜の語彙にあっては、カラー写真をデータ化して提示することが視覚的に有効である4 。電子出版も盛んにおこなわれている昨今、伝統的な紙媒体の出版にも応用できる範囲での工夫があれば、本書の価値をぐっと高めることができたかもしれない。
本書評では、特に著者が重要視する文法現象や、先行研究に言及しつつ議論を展開している点について、読者のために適宜補足し、議論したい。以下、概要、音韻、形態統語に分けて、特に重要な点に絞って評する。
2 概況
本書第1章の記述は、コンパクトなチベット系諸言語とアムド語に関する案内である。著者は最新の研究に注意を払ってはいるものの、博士論文を提出して以降の10 年間の研究成果を正確に跡づけているとは言えない。概況部分は、本体の記述と異なり比較的容易に増補改訂を加えることができる部分であり、学界の最新の研究成果を盛り込めるのではないかと考えると、惜しいことである。
アムド語の分布域として提示された図(p. 2 図1) は、研究史に照らして次のような問題がある。それはアムド語の定義にかかわる重要な方言学上の問題である。まず、甘粛省甘南州の東側と、そこから南に続く四川省阿壩州の東端は、アムド語の分布域から除くべきである。この一帯の言語は、分類に論争があるものの、アムド語ではないチベット系言語であるという見解が主流である(瞿靄堂1962, 1996;共確加措1987;華侃、尕藏他1997;Suzuki 2005, 2008, 2015;鈴木2007, 2012, 2013b, 2015, 2016a;王雙成2012;仁増旺姆2013:4-12;Tournadre 2014;Powell & Suzuki 2017)。確かに、アムド語がリンガ・フランカとして部分的に機能しているのは事実であるが、それは地図に反映させるべきではないだろう。加えて、最新の研究成果に基づいて、書評読者のために補足しておきたい点がある。具体的には、四川省甘孜州中部の部分的な地域がアムド語の分布域として認められる(Suzuki & Sonam Wangmo 2016, 2019; Suzuki 2018)ことである。要するに、アムド語の分布域は、「アムド」というチベットの伝統的地理区分が東西に広いのとは逆に、南北に長くなる5 。
証拠性とウチ/ソトの関係に関して、第1章でこの両者を分けて記述するのが著者の立場であることが表明されている(p. 10)。これをめぐる問題点は、4節で指摘したい。
言語状況について、著者は牧区方言は農区方言と比べて威信が高いと述べているが(p. 3)、それは音韻においてのみ認められているのが現状である。彼らの言語使用全般については、教育の進んだ昨今、威信が高いどころか批判される傾向にある。それは、教育機関における牧畜民の教師が少なく、規範的(normative)言語使用6 において、牧畜民独自の言語表現が往々にして批判されるからである(Tsering Samdrup & Suzuki 2017)。また、昨今流行している「母語純化運動(pha skad gtsang ma)」も少なからず日常の言語使用に影響を与えている(Thurston 2018)。これからの研究においては、これらの点にも目を向けていく必要がある。
3 音韻
第2章は、本書の記述対象の音韻体系の記述と形態音韻論的現象の記述である。本書の言語形式の記述は、音標文字を含む文字セットを用いた音韻表記である。それは国際音声字母(IPA)を踏襲しているように見えるが、そうではない。本文中に明言されていないが、主に中国で使用される音標文字体系を参照したと見える。たとえば、「歯茎/硬口蓋鼻音」(p.18 表1) に/ȵ/ [ȵ] を用いている。これはIPA に含まれておらず、中国で通用する表記であることに注意が必要である7 。評者は、しかしながら、著者のこの音標文字の選択を高く評価する。チベット系諸言語の記述にはIPA には定義されない音標文字が必要となることがある。その際には、朱曉農(2010)などを参考に、厳密に定義された非IPA の使用をためらうべきではない。
一方、中国の記述を参照するあまり、誤解を招く表記を用いているものもある。それは/ɬ/である。これが実際に無声歯茎側面摩擦音であれば正確な音標文字であるが、評者の手元にある複数のチベット系言語のデータ8から判断すると、無声側面音[l̥] である可能性が大いにある。ところが、中国では、[l̥] を用いない「習慣」となっている。この裏事情は張濟川(2009:278-281)が述べているように、「製版上の都合」に過ぎない。我々に[l̥] を用いない理由は存在しない。
著者はアムド語に特徴的な摩擦音を/ç/ [ç͡χ] と、先行研究がなしえなかった本質をついた音声記述をしている(p. 20)。ところが、残念なことに、音韻表記に/ç/を選んでしまった。これは誤解を招く9恐れがあるため、今後は/ɧ/の使用が推奨される(Suzuki et al. 2019)。/u/ [ɯβ~ɯu]について(p. 22) も、著者の記述から推察するに、鈴木(2013a) のいう/v̩/の変種である可能性がある。著者が扱う方言と地理的に近い地域で話される牧民方言を記述するTsering Samdrup & Suzuki (2019) は、/ʋ̩/を用いている。音韻表記における音標文字の選択は、近縁言語の事例を参照するほうが望ましい。また、著者は一貫して声たてを記述していない。母音から始まる音節は[ʔ] を伴うのであろうか。音素として認定するしないにかかわらず、これに関する記述は必要であろう。
音韻分析において、 C1jという分析(pp. 27-28) は再考の余地がある。このわたり音/j/は、実際は後続母音と一体化して、朱曉農(2010:17-21) にある「摩擦化母音」という単一の音素ではないか。この現象については、王雙成(2010) の報告もある。著者の表記する音声の自由変異(p. 28) や制限の多いC1j の出現環境という事実を考えれば、単一音素としての記述が適切であろう。また、この前舌高母音の音特徴について、体系上は著者が後舌高母音の1つとして記述する/u/(評者のいう/v̩/または/ʋ̩/)と共通する点があるのではないだろうか。この点については、今後の研究課題となるであろう。
著者は音調、吸気音、長母音といった周辺的な音声現象にも言及している(pp. 30-32)。いずれの記述も的確であり、こういった記述を含めたことは高い評価に値する。ただし、音調については、Caplow (2016) の記述と異なり、名詞と動詞の音調を区別していない(pp. 30-31)。この点については、著者による究明を期待したい。
4 形態統語
本書第3章以降は、文法の中核となる形態統語の記述である。本書評では、特に重要な問題点のみを指摘しておきたい。
著者は代名詞に双数を記述している(p. 57) が、ギャロン語(長野2018)などと違い、形態統語的に動詞との人称・数の一致を行わないアムド語の場合、双数が特別な形式だと示すには、たとえば「3」という数詞との組み合わせがないことを記述し、双数のみが異質であることを示す必要がある。チベット系諸言語では、特定の数を明示する形式について双数だけが特別の形式をもつ言語10のほか、「不特定の複数」と「数詞と共起して特定数を表す複数」の2系列をもつ言語11 もあるからである。
著者は動詞の範疇で「コピュラ」という用語を使用している(pp. 75-76)。本書では、コピュラ動詞と存在動詞が対立項をなすように記述されている(pp. 75-77)。しかし、特に欧米言語による文献(Tournadre & Sangda Dorje 2003; Zeisler 2004 など)では、著者の言うコピュラ動詞も存在動詞も「コピュラ」として扱われる。Caplow (2000) は、これら2者をまとめてELPA(equative-locative-possessive-attributive) と呼び、一体的に取り扱っている。本書の言うコピュラ動詞は、星(2003, 2016) のように「判断動詞」と呼ぶほうが適切であると、評者の目に映る。
著者は「意思性」という用語を用いて(p. 79) 動詞を分類しているが、それに対応する概念に制御可能性(controllability)があることを注記しておくべきであっただろう。「意志/volitional」という概念を用いている研究にはDeLancey (1986) や星(2003, 2016) があり、「制御可能性/controllability」という概念を用いている研究には、Tournadre (2004) やZeisler (2004) などがある。たとえば、dga’「愛する」やrnyed「見つける」という動詞は意志のある行為を表すが、行為そのものは「制御不可能」である。これらに対する動詞接辞は「非意志動詞」のものが選択される。ここに矛盾が出ることを読者が注意しつつ、本書の記述を読む必要があろう。
語彙動詞の項数による分類は、チベット系諸言語で非常に重要である(pp. 81-85)。特に被動者の標示に必要とされる格標識が何であるのかは、記述の上でも重要になる。この項目の執筆には、たとえ1変種の記述においても、若干の歴史的観点からの配慮があれば当該言語群の専門家に疑問を抱かせずに済む。たとえば、チベット文語にはアムド語にはおそらく対応がないであろう共格(comitative, associative とも;Tournadre 2010 参照;文語ではdang)があり、文語’dra「似ている」など特定の動詞は、被動者の項に対してこの格標示を要請する。これに対応するアムド語の例が知りたくなっても、本書の記述方法では分からないのが難である。
アムド語の動作動詞は語幹の形態変化を伴い、著者もページを割いて記述・分類している(pp.87-91)。しかし、文法書として期待したいのは、付録でもよいから、存在する動作動詞の語幹すべての形態変化を網羅した表である。本書には語彙集が含まれていないため、調べる手段がなく、網羅的な形態変化表を欠くのは大変惜しい。
先に触れた証拠性とウチ/ソトの関係について、著者はこの両者を分けて記述しているが(pp.10, 241-270)、そうではない立場があることにも配慮し、注で解説している(pp. 15, 291)。しかしその記述が釈然としておらず、研究史を正しく把握していないと受け取られる。特に複数の用語の単に並べて言及するだけでは、情報量として不足が多いし誤解も招く。著者は証拠性についてAikhenvald (2004) の立場を追認する形をとっている(p. 259) が、議論されるべきは複数ある立場そのものであろう。どの立場をとるかについての説得力のある議論が本書のどこにも見当たらないのは、立場の違いありきでの記述であり、残念である。ただし、著者が博士論文を提出した時期の研究状況を反映していると考えれば、本書の問題は単に注のつけかたにあると判断できる。その当時は証拠性に関する議論が発展途上であり、最近の10 年間に活発な議論が行われてきたという背景がある。そこで、本書評では、以下にこの点を特に補足して説明を加えておきたい。
チベット系諸言語における証拠性の体系については、source とともにaccess も証拠性の一部であるというように、Aikhenvald (2004) のいう証拠性の定義そのものを変えるべきだと提案したTournadre & LaPolla (2014) を参照するのが望ましい。そのうえで、それを採用するかしないか、そして採用できるかできないかを議論しなければならない。著者はsource として定義するかaccess として定義するかでウチ/ソトを証拠性の一部として認めるかどうかによると述べているが(p. 259)、両者は二者択一ではなく共存するため、誤りである。加えて、Vokurková(2008) は、形態統語上の特徴から、認識性(epistemicity) と証拠性(evidentiality) は不可分であるとし、Oisel (2017) はVokurková (2008) とTournadre & LaPolla (2014) の考えを反映させたラサ方言の証拠性の体系を表形式で提示している。確かに、そこにsource と扱われる伝聞の証拠性を加えていない。それは伝聞標識が形態統語的に異なるふるまいをするからである。著者はTournadre & LaPolla (2014) のいうsensory access(感知;知覚によるアクセス)を「観察知」という用語で証拠性の一部と認定する(p. 24) 一方で、source に直結する「伝聞」については、言及はある(pp. 250-251) が項目を立ててもいないなど、証拠性の枠組みから見れば記述が非常に分かりづらいのは事実である12 。過去にはウチ/ソトを表す用語について論争があり(Tournadre 2008)、用語の適不適はある程度議論する必要があっただろう。現段階の研究では、証拠性とウチ/ソトの取り扱いをめぐって、複数の立場が林立した状態にある。そのことはGawne & Hill eds. (2017) に収録されている論文を通読すれば容易に理解できる。加えて、最近でもZeisler (2018) のような新しい見解が出てきている。いずれの研究についても、どの立場が記述言語学的によりすぐれているかといった議論はない。しかし、一方が他方を正確に理解できていない現状は憂うべきであり、今後より一層の研究が求められる分野である13 。
敬語に関する記述が本書の最終章となる。本章の記述は語形成に関する内容が大部分であるため、第3、第4章に含めるか、それに続く章に配置するほうが配列として適切なように見える。ところが、婉曲表現(p. 334)が含まれているため、単に語の問題ではないことが分かる。なお、アムド語の牧畜民の変種には、大量の謙譲表現があることが最近の研究から明らかとなった(Tsering Samdrup & Suzuki 2019)。今後アムド語の研究にあたっては、この特徴にも留意する必要がある。
5 まとめ
著者は研究開始から本書を上梓するまで15 年以上の年月を費やしている。博士論文の提出から数えても10 年を要している。記述文法を形にするというのは、時間を要する仕事である。著者が本書執筆のために収集した言語資料は膨大な量になるだろう。その資料に基づいて1冊の書物にまとめるのも大変な労力が必要である。その結果として出版された本書は、本書評で述べたような問題点があるとはいえ、アムド語のまとまった文法研究として価値ある1冊であることは疑いない。
著者はまた本書に含まれないデータ集も個別に出版している(Ebihara 2010)。本書評で指摘した問題についても、著者が別途公開すれば、読者はあわせて参照できるようになり、本書の記述を補うものとなるだろう。
注
1 著者は「アムド・チベット語」と中黒を用いているが、評者は中黒を一貫して用いない主義である。以下、冗長になる点も考慮の上、「アムド語」と記す。
2 アムド語のまとまった記述研究としては、ドイツ語で書かれたHaller (2004)、漢語で書かれた周毛草(2003) や邵明園(2018) がある。
3 ただし、p. 24 の(5) は音節構造を述べているため、正確には975 の例文となる。
4 たとえば、Tsering Samdrup & Suzuki (2019:239) は色が問題となる家畜の語彙を挙げているが、やはり写真が添えてあるほうが分かりやすい。
5 詳細な言語分布については、Tournadre & Suzuki (forthcoming) に詳細な地図を付した解説がある。
6 「規範的アムド語」を表題にした教科書(Dpal ldan bkra shis 2017)が出版されていることは特筆に値する。
7 中国で一般に通用する音標文字については、《方言調査字表(修訂本)》(1981:81) などを参照。
8 評者の手元には400 地点を超えるチベット系諸言語のデータがあり、そのうちアムド語にかかわるものは50 種類程度ある。なお、評者が音声記述を行った言語の中には、[ɬ] と[l̥] が対立するものもある(鈴木2012)。
9 チベット系諸言語において、/ç/は[ç] を表す音標文字として用いられている(鈴木2016b)。
10 たとえば、Lhasa 方言(Tournadre & Sangda Dorje 2003)など。
11 たとえば、Sharkhog 方言(評者の調査資料による)など。
12 証拠性を文法体系に組み込むチベット系諸言語にあっては、伝聞というカテゴリーについても慎重にかつ丁寧に記述をする必要がある。また、日常会話と語りにおいては、伝聞標識の現れが異なる、といった研究結果(鈴木、四郎翁姆2019 など)にも今後は注意を払うことが必要であろう。
13 なお、評者は、自身の記述研究を通して、Oisel (2017) の解釈に基づく理解がチベット系諸言語のうち中国に分布する複数の言語の「体系としての証拠性」をもっともよく体現していると考えている。つまり、文法上の体系として機能しているのは、Tournadre & LaPolla (2014) の考えに従った、本書の言う「ウチ/ソト」と「証拠性」、さらには「認識性」までもが不可分のものであるという考えに傾倒している。評者の立場から整理したアムド語(Mabzhi 牧民方言)に関する証拠性の体系は、Tsering Samdrup & Suzuki (2018) で提示している。また、Suzuki et al. (2018) において、評者の立場がアムド語のほかにもカムチベット語にも適用できることを示している。
参考文献
海老原志穂(2016)「チベット人はどのようにヤクを認識しているのか?」Sernya 3: 12-18.
—— (2017)「ヤクの名は。」『Field+ : フィールドプラス』17: 6-7 電子版:http://hdl.handle.net/10108/89784
鈴木博之(2007)「川西民族走廊・チベット語方言研究」京都大学博士論文 電子版:https://doi.org/10.14989/doctor.k12734
—— (2012)「甘粛省甘南州卓尼県のチベット語方言について—蔵文対応形式から見た扎古録[Bragkhoglung] 方言の方言特徴—」『京都大学言語学研究』第31 号1-23 電子版:https://doi.org/10.14989/182195
—— (2013a)「v̩—チベット・ビルマ系諸言語における“唇歯母音”」『地球研言語記述論集』5:17-26 電子版:http://id.nii.ac.jp/1422/00000855/
—— (2013b)「蔵文対応形式から見た舟曲県チベット語拱壩[dGonpa] 方言の特徴—舟曲県チベット語の概説を添えて—」『京都大学言語学研究』第32 号1-35 電子版:https://doi.org/10.14989/182202
—— (2015)「甘南州卓尼・迭部・舟曲3県のチベット系諸言語とその下位分類試論」『ニダバ』第44 号1-9 電子版:http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00045560
—— (2016a)〈藏語方言學研究與語言地圖:如何看待“康方言”〉《民族學刊》第2期1-13+92-94
—— (2016b)「/é/が語る音変化史—カムチベット語香格里拉方言群における硬口蓋系列音素についての覚え書き—」『言語記述論集』8, 91-103 電子版:http://id.nii.ac.jp/1422/00000898/
鈴木博之、四郎翁姆(2019)「カムチベット語塔公[Lhagang] 方言における口承文芸の記録と言語分析」『言語記述論集』11, 17-38 電子版:http://id.nii.ac.jp/1422/00003018/
長野泰彦(2018)『嘉戎語文法研究』汲古書院
星泉(2003)『現代チベット語動詞辞典(ラサ方言)』アジア・アフリカ言語文化研究所
—— (2016)『古典チベット語文法『王統明鏡史』(14 世紀)に基づいて』アジア・アフリカ言語文化研究所
星泉 主編(2018)『チベット牧畜文化辞典(パイロット版)』Version 1.0 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所星研究室 電子版:https://nomadic.aa-ken.jp/
Aikhenvald, Alexandra Y. (2004) Evidentiality. Oxford: Oxford University Press.
—— (2015) The art of grammar: A practical guide. Oxford: Oxford University Press.
Caplow, Nancy J. (2000) The epistemic marking system of émigré in Dokpa Tibetan. Unpublished manuscript.
—— (2016) Reconstructing stress in Proto-Tibetan: Evidence from Balti and Rebkong Amdo. Linguistics of the Tibeto-Burman Area 39.2, 180-221. doi: 10.1075/ltba.39.2.01cap
DeLancey, Scott (1986) Evidentiality and volitionality in Tibetan. In Wallace Chafe & Johanna Nichols (eds.) Evidentiality: The linguistic coding of epistemology, 203-213. Norwood:Ablex.
Ebihara, Shiho (2010) Text from Amdo Tibetan “Little Frog as God’s Son (Zarək ɬasi)”. Asian and African Languages and Linguistics 4, 149-168. Online: http://hdl.handle.net/10108/61390
Gawne, Lauren & Nathan W. Hill (2017) Evidential systems of Tibetan languages. Berlin: De Gruyter.
Haller, Felix (2004) Dialekt und Erzählungen von Themchen : sprachwissenschaftliche Beschreibung eines Nomadendialektes aus Nord-Amdo. Bonn: VGH Wissenschaftsverlag.
Häsler, Katrin (1999) A Grammar of the Tibetan Dege ![]() (Sde dge) Dialect. Zürich: Selbstverlag.
(Sde dge) Dialect. Zürich: Selbstverlag.
Oisel, Guillaume (2017) Re-evaluation of the evidential system of Lhasa Tibetan and its atypical functions. Himalayan Linguistics 16.2, 90-128. doi: 10.5070/H916229119
Dpal ldan bkra shis (2017) Amdo Tibetan language: An introduction to normative oral Amdo. Asian Highlands Perspectives 43, 1-668. Online: http://himalaya.socanth.cam.ac.uk/collections/journals/ahp/pdf/AHP_43.pdf
Powell, Abe & Hiroyuki Suzuki (2017) Phonetic distance and dialect clustering on the Qinghai-Tibet Plateau. Linguistics of the Tibeto-Burman Area 40.2, 161-178. doi: 10.1075/ltba.17004.pow
Suzuki, Hiroyuki (2005) Einige Bemerkungen über den Ursprung des creaky Tons im Tibetischen von Sharkhog [Songpan-Jiuzhaigou]. Kyoto University Linguistic Research 24, 45-57. doi: 10.14989/87857
—— (2008) Nouveau regard sur les dialectes tibétains à l’est d’Aba : phonétique et classification du dialecte de Sharkhog [Songpan-Jiuzhaigou]. Linguistics of the Tibeto-Burman Area 31.1, 85-108. doi: 10.15144/LTBA-31.1.85
—— (2015) New perspective on the suprasegmentals in mBrugchu Tibetan : an introduction to the tonogenesis triggered by breathy voice. Bulletin of Chinese Linguistics 8.1, 117-139. doi: 10.1163/2405478X-00801007
—— (2018) Remarks on ‘rain’ in Tibetans’ languages in Lithang County. Studies in Asian Geolinguistics VIII, 56-61. Online: https://publication.aa-ken.jp/sag8_rain_2018.pdf
Suzuki, Hiroyuki & Sonam Wangmo (2016) Vocabulary of Shingnyag Tibetan: A dialect of Amdo Tibetan spoken in Lhagang, Khams Minyag. Asian and African Languages and Linguistics(AALL) 11, 101-127. Online: http://hdl.handle.net/10108/89211
—— (2019) Migration history of Amdo-speaking pastoralists in Lhagang, Khams Minyag, based on narratives and linguistic evidence. Archiv Orientální Supplementa XI / Ute Wallenböck,Bianca Horlemann, & Jarmila Ptáˇcková (eds.) Mapping Amdo: Dynamics of Power, 241-260.
Suzuki, Hiroyuki, Sonam Wangmo & Tsering Samdrup (2018) Essential evidential framework of Tibetic languages—Data from Khams and Amdo. Unpublished manuscript presented at the 46th meeting of Tibeto-Burman Linguistic Circle (Kobe)
Suzuki, Hiroyuki, Tsering Samdrup, Niangwujia (Nyingbo-Gyal), Jixiancairang (Chaksham Tsering) & Sonam Wangmo (2019) /ɧ/ in Amdo Tibetan: Descriptive and historical approaches. Journal of the Phonetic Society of Japan 23, 76-82. doi: 10.24467/onseikenkyu.23.0_76
Thurston, Timothy (2018) The purist campaign as metadiscursive regime in China’s Tibet. Inner Asia 20.2, 199-218. doi: 10.1163/22105018-12340107
Tournadre, Nicolas (2004) Typologie des aspects verbaux et intégration à une théorie du TAM. Bulletin de la société de linguistique de Paris XCIX (1), 7-68.
—— (2008) Arguments against the concept of ‘conjunct/disjunct’ in Tibetan. In Brigitte Huber, Marianne Volkart & PaulWidmer (hrgb.) Chomolangma, Demawend und Kasbek: Festschrift für Roland Bielmeier zu seinem 65. Geburtstag, 281-308. Bonn: Wissenschaftsverlag.
—— (2010) The Classical Tibetan cases and their transcategoriality: From sacred grammar to modern linguistics. Himalayan Linguistics 9.2, 87-125. doi: 10.5070/H99223480
—— (2014) The Tibetic languages and their classification. In Thomas Owen-Smith & Nathan W. Hill (eds.) Trans-Himalayan linguistics: Historical and descriptive linguistics of the Himalayan area, 105-129. Berlin: Walter de Gruyter.
Tournadre, Nicolas & Randy J. LaPolla (2014) Towards a new approach to evidentiality: Issues and directions to research. Linguistics of the Tibeto-Burman Area 37.2, 240-263. doi:10.1075/ltba.37.2.04tou
Tournadre, Nicolas & Sangda Dorje (2003) Manuel de tibétain standard : langue et civilisation. Deuxième édition. Paris: L’Asiathèque.
Tournadre, Nicolas & Hiroyuki Suzuki (forthcoming) The Tibetic languages: An introduction to the family of languages derived from Old Tibetan (with the collaboration of Xavier Becker and Alain Brucelles for the cartography). Paris: CNRS Éditions.
Tsering Samdrup & Hiroyuki Suzuki (2017) Humilific expressions in Amdo Tibetan and local intellectuals’ attitudes towards them. Unpublished manuscript presented at the workshop of Language Standardisation and Linguistic Variation in Asia from Sociolinguistic Perspectives(University of Nottingham at Ningbo)
—— (2018) Evidential system in Mabzhi Tibetan of Amdo. Proceedings of the 51st International Conference on Sino-Tibetan Languages and Linguistics, 913-925. Online: http://hdl.handle.net/2433/235311
—— (2019) Humilifics in Mabzhi pastoralist speech of Amdo Tibetan. Linguistics of the Tibeto-Burman Area 42.2, 222-259. doi: 10.1075/ltba.17008.sam
Vokurková, Zuzana (2008) Epistemic modalities in Spoken Standard Tibetan. PhD dissertation, Karel University and University of Paris 8.
Zeisler, Bettina (2004) Relative tense and aspectual values in Tibetan languages. Berlin: De Gruyter.
—— (2018) Don’t believe in a paradigm that you haven’t manipulated yourself!— Evidentiality, speaker attitude, and admirativity in Ladakhi. Himalayan Linguistics 17.1, 67-130. doi: 10.5070/H917136797
周毛草[’Brug-mo-mtsho](2003)《瑪曲藏語研究》民族出版社
華侃、尕藏他[sKal-bzang-thar](1997)〈藏語松潘話的音系和語音的歴史演變〉《中国藏學》第2期131-150
共確加措[dKon-mchog rGya-mtsho](1987)〈色繞龍哇藏語初探〉《西藏研究》第2期53-69
瞿靄堂(1962)〈卓尼藏語的聲調與聲韻母的關係〉《中国語文》331-339
—— (1996)《藏族的語言和文字》中国藏学出版社
仁増旺姆[Rig-’dzin dBang-mo](2013)《迭部藏語研究》中央民族大學出版社
邵明園(2018)《河西走廊瀕危藏語東納話研究》中山大學出版社
王雙成(2010)〈安多藏語i 的舌尖化及其類型學意義〉《語言研究》第2期122-127
—— (2012)《藏語安多方言語音研究》中西書局
張濟川(2009)《藏語詞族研究—古代藏族如何豐富發展他們的詞匯》社會科學文獻出版社
中国社會科學院語言研究所(1981)《方言調査字表(修訂本)》商務印書館
朱曉農(2010)《語音學》商務印書館
受理日2020 年4 月14 日
本記事は、『言語記述論集』12(言語記述研究会、2020.4)に掲載されたものを、許可を得て転載したものです。転載に際して、体裁を変更し、一部の文字を画像に置き換えました。元の記事は、統合地球環境学研究所のリポジトリで読むことができます。
鈴木博之(すずき ひろゆき)
1979年兵庫県生まれ。京都大学大学院文学研究科修了。博士(文学)。
国立民族学博物館外来研究員。主要著書に『東方藏區諸語言研究』(四川民族出版社、2015)、100 Linguistic Maps of the Swadesh Word List of Tibetic Languages from Yunnan(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所、2018)がある。