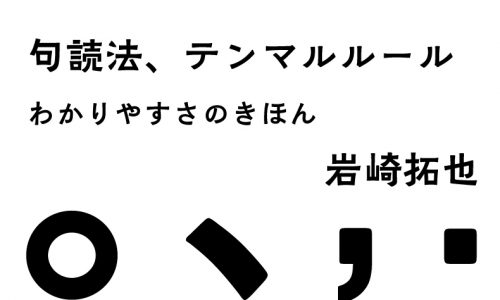渡辺哲司(文部科学省教科書調査官(体育))
1.「学習言語」をよりよく理解できる書
いま日本の教育界に浸透しつつある学習言語(academic language)の語と概念。それをよりよく理解しようとする人にとって、本書は一助となるに違いない。
学習言語とは、評者(渡辺)なりに言えば、学校で生徒のスピーチを聴いたり作文を読んだりした教師が「この子はできる」と思うときに「この子」が使っている言葉の総体である。専門用語というわけではないが、日常生活の言葉とも異なる。がんらいは主に米国で、移民の子たちのなかに日常会話は流暢だがなぜか学業の振るわない子が多くいて、その原因がどうやら学校特有の言葉づかいにある――ということから人々の関心を集めたらしい。さらには、それと基本的に同じ問題とメカニズムが、程度の差こそあれ、移民の子ではない(母語話者である)学業不振児童・生徒たちにも当てはまることがわかってきたと聞く。
学習言語という語を日本の教育界に広めた書としてよく知られるのはバトラー後藤『学習言語とは何か』(2011年)であるが、実は、その書の主要な参考文献となっているのが本書の英語版(原書)The Language of Schooling(2004年)である。その和訳書(本書)が刊行されるまでの13年間に“先を越されて”しまった感はあるが、『学習言語とは何か』が一般向けの書であるのに対して本書は研究書である。よって、学習言語についてより詳しく正確に知りたい向きには本書のほうが好適かもしれない。
2.評者の立場
内容に立ち入る前に、あらかじめ、評者が本書をどのような立場から読んだのかを述べておきたい。
そもそも評者は言語学徒ではなく、日本の言語技術教育に興味をもって“横ざま”の探究を続けるだけのアマチュアである。かつて大学教師であった頃、「書くのが苦手」と自らいう新入生の群れに遭遇し、彼らを教室に集めてねちねちと調べ始めた(『「書くのが苦手」をみきわめる』2010年)。それ以来、教室を離れたいまも無手勝流でやっている。
そうした言葉(言語技術教育)の探究を15年ほど続けてきて、いま確信しているのは、日本の教室における〈書く〉訓練の絶対的な不足である。とりわけ、自分一人の言葉で(聞き手とのやりとりを要せず)正確に、客観的に事実を伝え、明確に、論理的に意見を述べるような訓練が足りない。
そのうえで最近、上記のような〈書く〉訓練をじゅうぶん積むためには国語以外のさまざまな教科の学習時間をも当てる必要がある――と主張するようになった。人員配置や授業時数などの点で他教科と横並びの一教科であるに過ぎぬ国語の時間だけでは、技術の習得に必要な反復訓練をじゅうぶんに行えそうもない。
ところが、そのような確信に基づく主張をほうぼうで述べるうち、一つの壁に突き当たった。その壁とは、日本の学校教師たちがおしなべて教科教育の言語を教えられないこと。まず、国語専門ではない教師たちは、言語を教えるために必要な知識と技術、そして自信を欠いている。そこで同僚の国語教師を〈言葉のプロ〉と見込んで頼るわけだが、実は国語教師たちのほうも他教科の学習・指導で使われる言語をよく知らない(うえに関心も持たない)。これでは、さまざまな教科で言葉の(書く)訓練を――といくら訴えても画餅に帰す。
そうした壁を乗り越えようと模索するなかで出会ったのが、学習言語の語と概念である。学習言語をよく理解することで、日本中にはびこる「書くのが苦手」問題、さらには新井紀子のいう「教科書が読めない」問題(『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』2018年)なども少しは解決に近付くのでは――と評者は感じている。
3.本書の見どころ
上述のような立場をとる評者は、本書によって主に2つの点で刺激を受けた。1点目は、学習言語(学校教育の言語)の特徴をどう捉えるかということ。2点目は、教科教育の言語(教科ごとに異なる言葉づかい)をどのように理解し扱うかということだ。
1点目については、それまでの自身の理解を足元から揺さぶられるように感じた。きっかけは、例えば、第1章の次のくだりである。
—
学習言語を脱文脈性、明示性、複雑性、認知的要求などの概念で特徴付けることは、(中略)社会的経験と言語についての知識の両方を無視している。(p. 25)
—
「学習言語を特徴づけるものは脱文脈性、明示性、複雑性……」といった通り一遍の理解を、評者はこれまで漫然と受け入れてきたが、本書によって、そのような理解は一面的かつ浅薄なものかもしれぬと思い直した。詳しくは本書を読んでほしいが、例えば脱文脈性について言えば、実際に学校で読まれ、書かれ、話されるテクストのなかには本当に「それだけ読めば/聴けばわかる」ような(脱文脈的な)テクストは思いのほか少ないかもしれない。
2点目については、一種の“お悩み解決”的な効果があったと感じる。特に、第5章に埋め込まれた次のくだりが評者の目を惹いた。
—
科学的英語は、科学者たち自身が行った実験についての情報を共有するために、科学的発見の提示の文法的・語彙的手段を発達させる過程で、今あるように進化した。科学者たちがするように世界の過程について語るためには、科学者たちがこれらの過程を名付け、その過程間の関係について語ることを必要とした。(p. 199)
—
このくだりは、科学とそれを語る英語とが相伴って進化(共進化)するという関係を直接的には意味するものだが、それと同じ関係は他でも――科学とそれを語る日本語との間や、歴史など人文科学の場合にも――成り立つ。つまり、各教科にはそれ固有の言語が、あるべくしてあるわけだ。
実際、教科間にある学習言語の微妙な差異をどう理解し扱えばよいかと悩んでいたところ、その悩みの解決へとつながる道がチラリと見えたように評者は感じた。
書籍の見どころを他人に押し付けようとは思わないが、少なくとも上記2つの点は、学校教育全般にわたって言語が果たす決定的な役割に気付いた人にとっては刺激的で、示唆に富むものであると評者は思う。本書から利益を得るに違いない人としては、例えば大学で初年次学生に「アカデミック・ライティング」を教える教師たちや、中・高の各教科で書くことや話すこと(文章・口頭表現)の指導に意欲をもって取り組む教師たちが挙げられるだろう。
4.難点(修正を望む点)
最後に、あえて本書の難点を挙げておきたい。出版そのものは時宜を得た有意義なものだと思うがゆえに、未来の読者のため、できれば増刷・改版などに合わせて修正がなされるよう期待する。
まず、明らかな誤記・誤訳の箇所は十指に余り、疑い例を含めれば倍加する。日本語として誤りはなくとも意味的に「?」と感じた箇所には、たいてい誤訳があった(それらは別して出版社にお伝えする)。
次に、訳語の不統一もいくつかある。なかでも気になったのは[factual]の翻訳としての「事実に基づく」と「事実的」の組みである。前者は第4章に、後者は第5・6章にと分布は章(訳者)ごとにはっきり分かれるが、文脈から推し量られる意味は同一である。この語は本書にとってキーワードの一つであるから、訳語が不統一であってはいけない(ちなみに評者なら、英→和→英の互換性を考えて「事実的」のほうを選ぶ)。
さらに、翻訳書の宿命である難読箇所も稀ではない。その多くは原書に忠実な訳を心がけるがゆえ(訳者たちの誠意の表れ)と評者は見るが、日本の読者のためには、和・英の文法的差異を踏まえ、ときには大胆な書き換え(意訳)も必要であろう。そうした「文法的差異」のなかで最も主要なものの一つが、名詞の修飾を前・後の両方からできる英語と、前からしかできぬ日本語との違いであろう。これにうまく対処しないと、かつて木下是雄が『理科系の作文技術』(1981年)ほかで指摘した“逆茂木型”の難読センテンスが量産されてしまう――ということぐらいは非言語学徒でも具申してよいだろうか。