林良子・定延利之・小林ミナ
キーワード:フィールドインタラクション分析、高梨克也、アナグラのうた、日本科学未来館
Series of Field Interaction Analysis 1
Edited by Katsuya Takanashi (Supervised byKatsuya Takanashi)
Multi-Professional Team Developing New Exhibition: “Songs of ANAGURA” in Miraikan
Tokyo: Hitsuji Shobo, 2018
Ryoko HAYASHI, Toshiyuki SADANOBU,and Mina KOBAYASHI
Keywords: Field Interaction Analysis, Katsuya Takanashi, Anagura, Miraikan
1.タカナシさんと「アナグラ」へ(林良子)
本書は、ひつじ書房による新シリーズ「フィールドインタラクション分析」の第1巻である。232頁というボリュームもさることながら、高梨克也氏のこれまでの研究への取り組み・意気込みの伝わってくる非常に濃い内容となっており、タカナシファン(?)にとっては待望かつ必読の書である。「フィールドインタラクション分析」の「フィールド」とは、「自然な日常生活場面(フィールド)でのインタラクション」を分析するという対象としての側面と、インタラクション分析を「フィールドワークとして行う」という方法論の側面の両方の意味が込められているとしている(p. vii)。「フィールドワークは、参与観察によって、日常生活環境における人々の実践を、妨げることなく自然な姿で捉えるものであり、その対照は人々の活動のあらゆる側面に及ぶ」(p. vi)。そのため、本書で行われるのは、「従来の会話分析やジェスチャー分析などを手法の中心とした、ビデオデータの微視的分析が中心」(p. vii)となっている。
「アナグラのうた」という、この謎に満ちたタイトルを持つ本の秘密を探るため、2019年2月、書評執筆者の3名を含む有志メンバーは、高梨氏とともに本書の舞台となった日本科学未来館の展示「アナグラのうた 消えた博士と残された装置」を実際に訪ねた。
展示は空間情報学をテーマとしており、150平米ほどの展示スペース「アナグラ」の床にはセンサーが張り巡らされ、入場者が足を踏み入れるとその動きや位置や取った行動に応じて様々な映像、音楽が流れ出るものである(注1)。
「アナグラ」には、西暦2011 年に開発された空間情報学の重要な5つの技術(空間情報構築、移動情報解析、生体情報解析、個人情報管理、情報共有と活用)が収められている。これらの技術は、世界に危機が訪れた時、5人の博士が「ナガメ」「イド」「イキトイキ」「ワカラヌ」「シアワセ」という5つの装置に託して残したものである。やがてアナグラには誰もいなくなり、これらの装置だけが残った。それから1000年後(つまり西暦3011年)のいま、入場者はアナグラを訪れ、装置を通じて博士たちの研究の軌跡をたどる、という設定が、この展示には施されている。
映像や音楽の制作には多くのゲームクリエーターも参加し、博士達の世界観を幻想的に物語っている(注2)。そのためか、科学未来館の他の展示に比べても異色を放つ存在である(通好みとも言える)。この展示を見るや否や、単に多職種と言うよりは異職種のスタッフのコラボを経たものであることが実感できる。タカナシさんは、この異職種の集まる制作会議にビデオ・録音機材を持ち込み、その会議の進行をじっと観察してきたのかと思うと頭が下がるというよりも変な感じである。「一体なんのためにそこでそんなことを?」という疑問が誰にでも浮かぶと思うが、それは本書Column 1「「研究プロジェクト」としての側面」(p. 35)および「あとがき」(p. 225)で、「多人数インタラクション理解のための会話分析手法の開発」というJST戦略的想像研究推進事業さきがけによるプロジェクトのための著者と日本科学未来館の共同研究であったことが分かる。ちなみに、著者が「どうやって」分析資料を収集したのかについては、Tips 1(p. 54)、Tips 2(p. 78)に述べられている(ここでタカナシさんがミーティング室にビデオを設置し、その内容を部屋の外からモニタリングしていたことが判明する)。また、私のようなタカナシ初心者にとってはありがたいことに、そこでは、会話分析資料収集や分析のテクニックも簡潔に書かれている。
本書は、第1章は研究目的、第9章は後日談、他の章は3部を成し、第1部の第2・第3章が「アナグラのうた入門」、第2部の第4〜第6章が「多職種ミーティングでの傍参与者の気づき」、第3部の第7・第8章が「身体と環境を使った想像の共有」となっている。展示を実際に体験した者にとっては第9章の後日談が最も面白く読めるが、本書の根幹を成すのは第2部であろう。
第2部では、会話分析における参与役割、順番交代システム、二者間バイアス等の用語整理や解説がなされたうえで、「アナグラのうた」制作のRT(ラウンドテーブル)における参与者間の発話量の偏りについて分析結果を挙げている。このように、発話の分析の方法について詳細に述べられているのは、(特に会話分析やタカナシ初心者にとっては)その後の主張や議論の論拠となるデータ分析の方法を具体的に知る上でやはりありがたい。しかも第4.3節では、RTの参与者間の発話量の比率に安定的傾向があることや、各RT内部ではどのメンバーが中心になってやりとりが展開されているのかが大きく変化していく(p. 68)ことが示されようとするも、【注意】として「これらの点はある意味では当たり前な点を確認しているにすぎないので、これらの点に特に疑いを持たない読者は本節を飛ばしておいていただいてもよい」旨が書かれているのはますます親切であり、余計に読まなければならないという気になってしまう。
音声科学の研究分野においては、主に独話や、多くても2名による対話を音響分析することはあるが、3人以上の大人数が参加するミーティング等での発話などは分析の対象外とすることが多い。しかし、日常生活では、3人以上での意見交換や、更に大人数によるミーティング(例えば教授会)を行う機会は非常に多く、そこでは参与者のうち「いつ誰が何を話すか」が問題となることに改めて気づかせてくれる。本書では、さらに「なぜその人がそこで話すか」までが射程に入れられ、分析が進められていく。教授会等の一般的な会議は、報告事項、審議事項と議事が進められることが多いが、会議の本質とはそう言われて見れば、本書の第5章において取り上げられている「懸念事項の導入」である。単なる報告、質問だけでは会議は全く面白くない。懸念事項の導入があるからこそ場が「ザワめき」、会議が盛り上がる(つまり長引く)。突然に直前まで黙っていた人が発言を始め、参与役割の「ダイナミックな変更」が連鎖していく。著者は、懸念の表明に関し、構文、発話量、ターンの内部構造、ターン連鎖の生起位置、談話区間、メンバーの職能に応じた傍参与者の関与など多角的な分析を鮮やかに展開したうえで、「成員カテゴリー化装置」の観点から体系的に理解することが可能であると論ずる。このように分析された懸念表明―解消連鎖について、さらに著者は第5章第7節においてさらに組織論的な観点からの分析を試みる。
冒頭に記したように、「アナグラ」作成チームは多職種かつ職能の異なるメンバーから成り立っている。ここで著者はチームがRTで繰り返し行ってきた懸念表明―解消の協同問題解決プロセスについて考察した上で、最終的にはリスク管理に関するReason(1997)の「スイスチーズモデル」を参照しながら、問題解決に向けた組織的工夫にも言及し始める。このあたりで私のようなぼんやりとした読者はようやくコトの重要性に気がつく。「アナグラ」チームの会話を分析することは、具体的な「異文化コミュニケーション」を追跡し、その生起原因と紛争解決方法やきっかけ、円滑なコミュニケーションのための工夫について考察することに他ならないのだ。
本書は、理論的背景、仮説、調査とその結果を整然と紹介するのではなく、ミーティングの場におけるあるデキゴトに関して著者の行う多角的な分析を追っていく形式で進んでいくため、一見して研究書には見えない。タカナシさんに「アナグラ」にうっかり引き込まれ、色々なものを見せられてしまったという読後感が最後に残るが、これこそがタカナシワールドの醍醐味なのであろうと思う。この点に関してはタカナシ上級者の定延氏、さらに本書のインパクトについては、タカナシファン(確定)の小林氏に筆を譲る。
2.キャラバンが始まった(定延利之)
高梨克也氏といえば、気鋭にして博識の、インタラクション(評者の用語でいえば「コミュニケーション」だが以下「インタラクション」で通す)の研究者である。研究会の場でも、その発言は(長くわかりにくかったりもするが)、現象の本質、は言い過ぎだとしても、皆に見えていない意外な面をしばしば衝くことで知られている。
その高梨氏が、フィールドインタラクションをテーマにした研究書シリーズの刊行に乗り出し、ほぼ単著に近い形で、シリーズ第1巻を出される。ということで、ひつじ書房のチラシを見た評者は期待していた。その期待を「いかにも高梨氏だなぁ」という形で裏切ってくれたのが本書である。
いやもちろん、本書にも「普通の研究書」らしい部分はある。たとえば、会話分析(サックス)の「カテゴリー付随活動」や、また、ゴッフマンの「従属的関与」とは異なる高梨氏独自の「付随的関与」など、さまざまな概念が紹介され、提案されているところは、多くの読者にとって勉強になるだろう。
だが、本書は基本的に「普通の研究書」ではない。これが本書の最大の特徴である。
2.1 フィールド理解に至る過程
そもそも、フィールド研究は研究である。研究である以上、研究者は「自分がわかったこと」を論じるはずである。逆に言えば、まだフィールドを十分わかっていないと自覚している研究者は、「自分がこのフィールドについて、本や論文を書くなど、おこがましい」と考えるはずである。そして、フィールドについて理解が進み、本や論文を書くに至った段階では「自分がフィールドを十分わからなかったのは、未熟だった自分の問題であって、フィールドの問題ではない。だからそれは書かない」と考えるはずだ、と評者は思う。
だというのに、高梨氏は、本書の冒頭部で次のように宣言されている:
しかし、その一方で、自ずから「徐々に分かるようになっていく」のを待つだけでなく、調査者の側のどのような知識、経験、観点などの変更によってこうした理解が可能になっていくのかという点に自覚的になるのでなければ、フィールドワークという実践自体はいつまでも名人芸の域にとどまり、方法論化されることはないのかもしれない。そこで、本巻では、[中略]調査者自身の思考についても振り返りながら議論を展開することを試みたい。[p. 2]
つまり本書は、「研究者(自分)がフィールドを(以前よりは少し)理解できる(と思える)ようになった過程」にメタ的な観点から堂々と光を当てている。確かに、この過程は、すべてのフィールド研究者が、ド素人の段階からヒトカドの専門家の段階になるために、必ずたどらねばならない道ではある。けれども、それはフィールド研究者が、誰も書かずに済ませてきたものなのだ。まさに、ここまでやっていいんですね、ひつじ書房さんという感じである。
2.2 問題設定をめぐる問い
知らないフィールドにいきなり飛び込んでも、そこに生きる人々の背景知識や文脈を、研究者は知らない。したがって、人々の言動の意味を理解するのは困難を極める。この困難さは、会話を理解する人工知能を開発する分野で「鍵穴認知」と呼ばれているものに似ている。隣の部屋の様子を鍵穴から覗いても、鍵穴は小さく、見える部分は限られている。
人工知能と違って、研究者は、覗かれている人々と同じ人間であり、生物学的レベルで多くのものを共有しているので、覗ける「鍵穴」は多少広いかもしれない。だが、鍵穴は鍵穴であって、人々の言動の意味を完全に理解することはできない。原理的に不可能である。
では、フィールド研究として、さしあたりどのような理解を目指せばよいのだろうか?―よくよく考えてみれば、この問題は「フィールド研究において、人々の言動を、どのような枠組みでとらえるべきか?」という重要な問題と直結する。この問題を高梨氏は「フィールドの特徴や調査の焦点とするに値する問題」(p. 2)と述べている。最初は、自分に何がわかっていないのかさえ、わからない。それがわかってくるのは、この重要な問題が見出される中でのことなのだと、高梨氏は述べている。「どういう問題を設定し、意識し、追究していけば、このフィールドがもっと理解できるのだろう?」という問いを持つことが、フィールド研究においては重要なのである。
2.3 この人は何が気になる人なのか?
日本科学未来館には「アナグラのうた~消えた博士と残された装置」という、これまでに類を見ない、新奇な常設展示がある。この展示を製作するには、ストーリーと世界観を監修する演出家、デジタルコンテンツの開発者、空間デザインの専門家、人物捕捉追跡システムの開発者、製作進行の担当者、製作施工の管理者、そして未来館のスタッフという、さまざまな職種のプロたちが継続的に集まり、会議を開く必要があった。高梨氏のフィールドはこの「多職種会議」である。そして、ここで高梨氏が足がかりとしたのは、「なぜ今この人が発言するのか?」という疑問である。
性格的によくしゃべるわけでもなく、直前まで積極的に発言していたわけでもない会議参加者が、ある時点でなぜか、唐突に話し始める。これが「なぜか」ではなく「もっともなこと」と思えるようになるのが、目指すべき理解のレベルである。「なぜか」と見えるその発言は、その参加者が「その道のプロ、斯界の権威」として、他の職種の人間たちには思いもよらない、何かに引っ掛かったからこその発言、ということなのだ。「気になるのは~」と、1人のプロが懸念を表明し始めると、他の職種のプロたちは一様に緊張し、身構え、場の空気が「ザワザワ」したという。
このフィールドで高梨氏が見つけた「フィールドの特徴や調査の焦点とするに値する問題」とは、つまるところ「この参加者は何が気になる人なのか?」という問題である。高梨氏は言う:
『アナグラのうた』が完成し、フィールド調査も終えた現時点で言えることは、フィールド調査の初期に調査者にとって分からなかった点は、参加者には共有されているが調査者は有していなかった専門知識や背景知識といったものであるというよりも、そのつどの場面において、調査対象者である「彼ら」にとって何が「気になって」いたかであったと表現するのが最もしっくり来ると考えている。逆に、この点をフィールドワークのための方法論のひとつとして事後的に定式化するならば、調査者は「彼らは何が気になる人たちなのか」という点を解明しようと意識することによって、フィールドの特徴やそこに参与している関係者の立場や社会的属性、行われている行為の意味などが徐々に理解できるようになっていく。ということが言えるのではないかと思う。[p. 81]
2.4 食い込みと離脱
指名されたわけでもないのに、ある会議参加者が「なぜか」唐突に発言し始めるという、上で取り上げた現象を、会議の場への「異様」な食い込みと位置づけてみると、その対極には、会議の場からの「異様」な離脱、つまり会議中に参加者が内職にいそしみだすという現象が位置付けられるだろう。
本書では、この現象も取り上げられており、高梨氏は次のように述べている:
…調査を始めて最初に驚いたことのひとつは、毎回平均10名程度の参与者の中で、現行の話し手に視線を向け、あいづちやうなずきなどの聞き手行動を積極的に示している聞き手は案外少なく、一見すると、ある意味では全員が必ずしも熱心に参加しているように見えない、という点であった。そして、こうした聞き手の多くは自身のノートPC や紙の資料などに関与していることも多かった。この状態は少なくとも表層的にはお世辞にも模範的な参加態度とは言いがたいという印象を持った。[p. 127]
プロたちが集まって話し合っているというのに、そこに注意を集中させず、手元のパソコンや書類をいじるとは、一体「なぜ」だろう、どういうことなのだろうか?
ここで高梨氏は、先述の「付随的関与」という概念を用いて謎解きをしている。彼らの「内職」の多くは、会議と直接関わらない純粋な内職(従属的関与)ではなく、会議に関連する情報をネットや議事録で検索したり、会議から導かれた新しい発想を書き留めたりするなど、会議の本流から分かれてはいるが、いつ本流に再合流して貢献をなすとも限らない、支流を走る行為(付随的関与)なのである。これも協調的で目標指向型の、プロどうしの会議なら、何ら問題ないことなのだろう。
「文系」の学会ではまだまだ「お行儀の良い」聴衆ばかりだが、少し「理系」寄りの学会に出ると、講演や発表を聞きながら、聴衆の多くが手元でパソコンをカチャカチャいじっている。これも同じだろう。いや、授業でもそうである。純粋な内職との比率はわからないが。
以上で取り上げた2つの対極的に見える現象の、いずれにおいても、高梨氏のやり方は同じである。まず、ごく常識的な基本(「この局面で次に話すとすればこの人だろう」「他人の話を熱心に聞くとすれば、視線や姿勢はこうなるだろう」)を据え、そこからの逸脱現象に注目し、それを手がかりにして(基本を廃棄するのではなく)フィールドに対する理解を深めている。この点も、フィールド研究において見習うべき点と言える。
2.5 キャラバンが始まった
評者は30年ほど前の学生時代、人工知能や言語情報処理の研究者たちの仕事に、わずかに触れたことがある。彼らは人間と対話する人工知能を開発するために、談話の構造を研究していた。評者のことばで言えば「談話とは、参加者たちが『こんなことを、こんな順番で話そう』と思っている発話プランどうしのすり合わせだ」というような考えのもと、プラン階層型の談話構造モデルが検討されていた。これらは、(現実の談話にはまだまだ程遠いとはいえ)言語学で構想されている「談話」より、はるかにリアルであった。「この人たちは、とにかくシステムを作らなければ、メシの食い上げなのだ。システムを作るために、本気で、談話をわかりたいのだ」と感じさせる迫力があった。
同じ頃、言語学では「談話は文の集まり」と言われていた。今でもそう信じ、そう述べている人は少なくなさそうである。そこから逃れて、リアルな言語インタラクションの世界に飛び込みたいなら、本書は必読の書である。
「フィールドインタラクション分析」という、高梨氏が率いるキャラバンは、始まったばかりである。この隊列についていき、その「体験」を共有し、言語インタラクションについて、高梨氏と一緒に賢くなっていくか。それとも、「談話は文の集まり」の世界に留まるのか。判断は読者に委ねられている。
3.本書が日本語教育に与えるインパクト(注3)(小林ミナ)
本書(本シリーズ)は、言語教育、日本語教育のために編まれた本ではない。それは言わずもがななのだが、本書を読めば読むほど、日本語教育の畑にいる者には、ヒリヒリとした皮膚感覚をもってその内容が迫ってくる。
その理由の1つは、現実に起きているインタラクションが、実に多彩で複雑であることへの畏怖である。もう1つは、現実のインタラクションというものが、それほど多彩で複雑であるにも関わらず、きわめて組織的に美しく構造化されており、かつ、そこには言語が非常に大きく関わっているという事実を、改めて突きつけられた点にある。「いまさら、そこ?」という声が聞こえそうだが、いまの日本語教育界は、このような知見を受け止められる状況にあるだろうか。そのような焦燥感が、上記の皮膚感覚を引き起こしているように思う。
3.1 日本語の教室は「何を」教える場なのか?
本書の冒頭「「シリーズ フィールドインタラクション分析」の狙い」に、次のようにある:
つまり、言語の使用の研究では、これらの文脈や状況の中から言葉だけを切り離して研究することはできず、言語使用を分析の中心に固定してしまうことすら妥当でない場合もある。言語は研究者にとっては「目的」かもしれないが、言語使用者にとっては、日常生活における何らかの活動を行うための「手段」の1つかもしれないという自体を正しく把握する必要がある。[p. v]
日本語教育を開いて言うなら、それは即ち「日本語の教育」である。だから日本語教師は教室で日本語を教える。もちろん、そこに人工物(artifact)や動作(注4)といった日本語以外の要素が持ちこまれることもある。たとえば、飲食店のレジでの会話を練習するときに「これでお願いします[と言いながらクレジットカードを差し出す]」といったように、「これ」を人工物(クレジットカード)や動作[差し出す]と組み合わせたり、料理教室での会話を練習するときに「こうですね?[と言いながら講師と同じように切る動作をしてみせて、野菜の切り方が正しいかどうかを確認する]」といったように、動作を伴いながら練習したりする。しかし、そこでの人工物や動作は、あくまで日本語を練習するために必要だから持ちこまれたものであり、授業の中心には常に日本語がある。
「〜が好き/嫌いです」という文型のためのドリル練習であれば、教師から「どんな飲み物が好きですか」と尋ねられたら、机の上に置いてあるペットボトルのコーラを高く掲げて見せるだけではだめで、「コーラが好きです」と日本語で答えなければならない。
また、図1のイラストのように、学食で空いている1席に座りたいときの発話として「あのー、ここ空いてますか」「すみません、ここ座ってもいいですか」といった表現を練習することはあっても、[空いた席を指さし相手と視線を合わせながら、首を少し傾ける]といった動作を教えたり、練習したりすることはない。
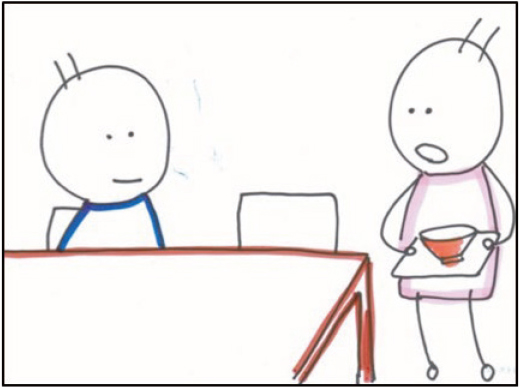
図1:学食で空いている1席に座りたい
しかし、もし高梨氏が言うように「言語使用を分析の中心に固定してしまうことすら妥当でない場合もある」のなら、授業の中心に日本語を据えることが妥当でない可能性があるのではないか。もしそうなら、日本語の教室とは、いったい「何を」教える場なのだろうか。
3.2 文法はどこにあるのか?
本書の第5章「懸念導入表現「気になるのは」と傍参与者」では、多職種ミーティングで、ある参加者が自身の懸念を表明するときの表現が取りあげられる。「懸念表現」と命名されたこの表現は、「気になる」「気にする」という複合的な述語を含み、その多くは「気になるのはXだ」「気にしているのはXだ」といった擬似分裂文として出現するという(p. 83)。第5章では、このような「懸念表現」を含む発話連鎖が丁寧に観察され、表明された懸念が解消されていくプロセスが記述される。
ここで興味深いのは、このような「懸念表現」に高梨氏が行き着いた経緯である。本書では、次のように説明されている:
…そうした際にも、(ノートPCなどで別の仕事を内職している=評者注)筆者の注意をしばしミーティングの場に引き戻す表現があることに徐々に気づいてきた。それが本章で分析する「気になるのは」という表現だった。
この表現が用いられる際、ごく感覚的に言えば、ミーティングの場の空気が多少なりとも「ザワザワ」する。それは、この表現の直後でそれまでは必ずしも熱心に話し手に視線を向けているようには見えなかった傍参与者が俄かに話し手に視線を向け変えたり、また、ある参与者は立ち上がってテーブルの上の共有スペースにある模型や図面を覗き込んだりし始める、といった点にも現れている(第7章も参照)。[p. 82]
「気になるのはXだ」「気にしているのはXだ」といった「懸念表現」は、「(他のことをしていた)筆者の注意が、ミーティングに引き戻された」「ミーティングの場の空気が「ザワザワ」した」といった、その場に居合わせた高梨氏の実感から出発し、それを観察することによって帰納的に導き出されたものである。「人は懸念を表明したいとき、どのように切り出すのか」といった発話機能や、「「気になる」「気にする」という複合辞は、どのような文型で用いられるのか」といった言語構造から出発し、演繹的に導き出されたものではない。
この事実は、何を示しているのか。それは、個別具体のリアルな状況には、発話機能や言語構造から出発したのでは見えてこない、インタラクションのありさまがあるということではないだろうか。
個別具体のリアルな状況は無限に存在する。それにも関わらず、私たちは語や表現や文型を選び出し、動作や表情も駆使して、初めて遭遇する状況を乗り越えている。これは即ち、個別具体の状況は無限であっても、そこでのことばの背後には、有限の社会的合意(=文法)があることを示している。つまり、インタラクションのありさまが、文法そのものだと言うことである。
もしそうであるなら、発話機能や言語構造から出発するのではなく、個別具体の状況に身を委ね、インタラクションのありさまをじっと観察することで、より豊かな文法が発掘される可能性がある。
3.3 どのように日本語授業をデザインするか?
そのような文法が発掘されたとき、日本語教育はどのようにその成果を取り込み、授業をデザインすればよいのか。ここでは、次の2点を指摘したい。
⑴ 「教師が学習項目をすべて事前に準備し、教室をすべてコントロールする」という教師観、授業観を、教師が手放す。
⑵ 「個別具体の状況」から出発し、日本語授業をデザインする。
⑴というのは、たとえば「教師があらかじめ言語モデルを準備しておき、学習者がそれを練習する」といった教室活動を行わないということである。教室で「あのー、ここ空いてますか」「すみません、ここ座ってもいいですか」といった表現を学ぶことがゴールなのであれば、教師がモデルを準備しておき、学習者がリピートするような活動にもさほど違和感はない。しかし、「学食で空いている1席に座りたいときには、どうすればよいか」という状況への対処として、教師が[空いた席を指さし相手と視線を合わせながら、首を少し傾ける]といった動作をモデルとして提示し、学習者にリピートさせるような練習は、どうにも教室活動には馴染まない。
⑵というのは、「発話機能」や「言語構造」から出発して日本語授業をデザインしないということである。たとえば、図2 のように「学食で席が離れて空いている2席しかないが、2人で座りたいときにはどうすればよいか」という状況を考える。このときの行動には、次のような選択肢があり得る。
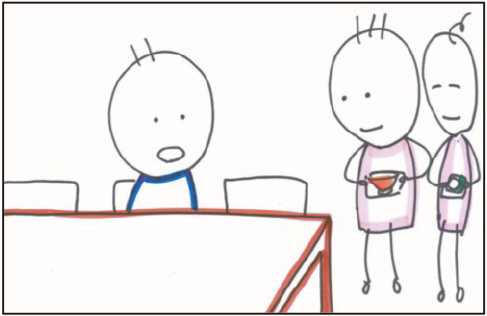
図2:学食で2人で座りたい
⑶ 「あの、2人なんですけど、ちょっと隣に移ってもらってもいいですか」のように丁寧にお願いして、移動してもらう。
⑷ 「あ、失礼します」のように一言断って、両サイドに座る。
⑸ 「席ないねー」と聞こえるように言う。
⑹ 両サイドに座って、食べながら大声でおしゃべりする。
⑺ 後ろで、立ったまま静かに待つ。
⑻ 視界に入るような位置で待つ。
⑼ 他の席を探す。
これらの行動に唯一絶対の正解はなく、「その状況で、自分がどう行動したいのか」を考え、そのようにふるまってよい。そして、その行動のために必要な表現を学べばよい。⑹ – ⑼には、日本語すら不要である。しかし、⑹ – ⑼のような行動を望む学習者にまで一律に、「あの、2人なんですけど、ちょっと隣に移ってもらってもいいですか」「あ、失礼します」という発話(言語構造)を学ぶ必要はあるだろうか。日本語授業を「個別具体の状況」から出発してデザインすると、日本語授業の中心には必ずしも日本語があるとは限らない。日本語の教室は、「日本語を教える場」から「日本語も教える場」へと変容するのではないだろうか。
高梨氏は、次のように述べる:
このように、会話分析やジェスチャー研究においても、言語使用の「現場」である日常生活環境の持つ圧倒的な複雑さと豊かさを十分に捉えきれていたとは言えない。[p. ⅵ]
個別具体のリアルな状況から文法を発掘する作業は、途方もなく長い道のりであろう。しかし、それは発掘作業に取りかからない理由にはならない。「フィールドインタラクション分析」というアプローチとその成果を知ってしまった以上、日本語教育にはそこに対峙する覚悟が求められているように思う。
注
1:日本科学未来館 常設展示「アナグラのうた」 https://www.miraikan.jst.go.jp/sp/anagura/
「アナグラのうた」紹介ビデオ https://www.youtube.com/watch?time_continue=238&v=75jA7F8AXC4&feature=emb_logo (いずれも2019年11月1日閲覧)
2:https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=A0tyn5xOHlc&feature=emb_logo 中村隆之「アナグラのうたのうた」プロモーションビデオ(2019年11月1日閲覧)
3:なお、日本語教育の観点から本書を評したものに、千石・内藤(2019)がある。そこでは、本書が日本語教育に与える示唆として、「「やりとりへの参与」についての新しい視点」「参与者の多面性についての示唆」「言語表現の新しい捉え方」の3点があげられている。
4:本節では、動作や行動を[ ]で括って記す。
参考文献
Reason, J. (1997) Managing the Risk of Organizational Accidents. Ashagate PublishingLimited.
千石昴・内藤香月(2019)「多職種チームで展示をつくる―日本科学未来館『アナグラのうた』ができるまで」『早稲田日本語教育学』20: pp. 139-143.
執筆者
小林 ミナ(早稲田大学大学院日本語教育研究科)
定延 利之(京都大学大学院文学研究科)
林 良子 (神戸大学大学院国際文化学研究科)
『近代』第121号(2020年5月)神戸大学近代発行会刊 pp.1-18より転載
(『近代』ISSN=02872315, NCID=AN00065014)
シリーズ フィールドインタラクション分析1 高梨克也編『多職種チームで展示をつくる—日本科学未来館『アナグラのうた』ができるまで』(ひつじ書房 2018)








