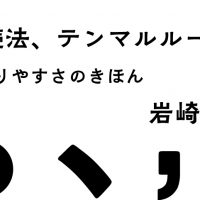現実世界への順応
前回は、柄谷行人『探究Ⅱ』における「単独性」の議論を取り上げ、そこで展開された現実世界と可能世界の質的な異なりが、たとえ論理的に正しいとしても感覚的に納得できるものなのかということを考えていきました。前回の復習となりますが、これがいま・ここでありありと出現している「この私」の「この」性を疑いうると言っているわけではないことに注意してください。そうではなく、他ならぬ「この私」が帰属する現実世界の比類なき唯一性・特権性が、どうしても自明のものとは思えないのではないかという話でした。
もとより「この私」が帰属する時空間のかけがえのなさは、現実世界であろうと並行世界であろうと等価値でしょう。ゆえに、数多の世界のなかで特殊な(各々にとっての)「この現実世界」と、他の可能世界と比較することがそもそも意味をなさない「この現実世界」の唯一性・特権性を、私たちは明晰に区別することができないのではないか。少なくとも僕にとって、この便宜的な傍点によってしか書き表すことができないような差異は、確かにここでこうしている「この私」と「私」一般(各々にとっての「この私」)のあいだには見いだせるけれども、そのような存在が帰属する現実世界と並行世界のあいだにも、それがまったく同じように適合するとは思えません。このズレのようなものは一体何なのかというのが、前回に僕が問題にしたことのまとめでした。
ところで、先に示した柄谷の着想は、並行世界の文化的役割をめぐる議論にも、大きな影響を与えているように思います。たとえば、小泉義之は「複数世界作品とは、別世界への移動可能性を捏造し、別世界を擬似的に体験させることを通じて、現実世界への回帰を促すものであ」り、「別世界との擬似的な比較の後に、現実世界は〈他ならぬこの〉〈かけがえのない〉世界として自由に選択されたかのように教え込むものである」以上、「複数世界作品は本質的に現実の体制に順応的である」と述べています(『あたかも壊れた世界──批評的、リアリズム的』青土社、2019.2)。
その問題意識は柄谷と大きく異なりますが、小泉もまた「複数世界」(並行世界)とは現実世界に「回帰」するための通路であり、ひとえに現実世界の比類なき唯一性・特権性を維持するものでしかないものと捉えています。しかし、「不健全」な私たち(少なくとも僕)は、むしろ自分がいま・ここにいるという生の実感を、作業仮説に過ぎなかったはずの並行世界に置き去りにしてしまうこともあるように思うのです。「この私」の「この」性は疑いえないけれども、「この現実世界」の「この」性は疑いうる(というより、「私」と同じような仕方では「現実世界」に「この」性を抱くことができない)のではないか。何度もいうようにこれは錯覚でしかないのですが、こうした現実世界/並行世界へのリアリティという問題を考えるために、今回は東浩紀『ゲーム的リアリズムの誕生──動物化するポストモダン2』(講談社現代新書、2007.3)を取り上げてみたいと思います。
「ゲーム的リアリズム」とは
柄谷行人から東浩紀へという流れは、多少とも現代日本の批評や思想の歴史に詳しいひとからすれば、「いかにも」で「ありがち」という印象を持たれることでしょう。実際、彼ら2人には特有の思考パターンのようなものがあり、そこにはある種の偏りも少なからず見受けられるのですが、どうにも僕がこれまでの人生で最も影響を受けた書き手がこの2人(と、次回に取り上げるつもりの三浦俊彦と永井均)である以上、「ありがち」であるという批判はいったん脇に置いて、ぜひお付き合いいただければと思います。(以下の考察は、僕の出身研究室の先輩である國部友弘さんから非常にさまざまな教示をいただきました。記して感謝申し上げます。)
『ゲーム的リアリズムの誕生』は、きわめて多岐にわたる論点が展開されており、ここで扱うことができるのはそのなかのごく一部なのですが、柄谷の「単独性」の議論を明確に受け継いでいると思われるところを中心に、その理論的な要諦を抑えておくことにしましょう。東は、まず一般論として「私たちは、一回かぎりの生を、それが一回かぎりではなかったかもしれない、という反実仮想を挟みこむことで、はじめて一回かぎりだと認識することができる」ということを確認します。(それがなぜなのかは、前回の柄谷の議論を思い起こしていただければ明らかなはずなので、ここでは省略します。)もちろん「この感覚は、人間の生の根底に関わるものであり、とくにポストモダン化やオタク化によって生みだされたものではない」ものの、東はそうした「古くからある普遍的な感覚が、新しい表現に生気を注ぎ込むことはありうる」と指摘し、その「新しい表現」のありようを「ゲーム的リアリズム」という術語で呼び表します。周知のように「ゲーム」とは、リセットボタンを押すことで「一回かぎりの生」が何度も反復されるという逆説を備えたメディアであり、たとえばそうした生/死の複数性が、いのちの尊さを軽んじるものとして、かつては批判されたりもしていました。(いまはそのようなナイーブな批判は少ないと信じますが……。)
なぜ「ゲーム」の論理構造に集約されるような「リアリズム」が、「新しい表現」の可能性であると言えるのか。東はここで、桜坂洋の『All You Need Is Kill』(集英社スーパーダッシュ文庫、2004.12)という小説作品の読解を糸口として、その発想の中核に迫ろうとします。『All You〜』は、近未来の地球において、謎の異星人ギタイとの戦闘によって殺されてしまった主人公の兵士キリヤが、ある超越的な力によって何度も自身の意識を戦闘前日の朝に戻され、延々と2日間の時間をループしてしまうという筋立てのSF作品です。キリヤは脱出を試みるなかでトレーニングと実戦を繰り返し、やがてギタイと人類たちの戦場を支配するほどの腕前を持ちはじめますが、その最中リタという女性兵士が、かつての自分と同様に時間のループにとらわれていたことを知ります。そして、キリヤはリタから、ある特定のギタイを特定の方法で倒すことで、時間のループから脱出できると教わるのです。しかし、幾回目かのループのなかでキリヤはその方法を実践しますが、やはり戦闘前日に戻ってしまいます。そして、その次のループにおいて、キリヤはリタから、二人のうちどちらかが死なない限り、ループからは抜け出せないことを告げられます。そしてキリヤは、襲い来るリタと戦い勝利することで、ようやくループから抜け出すことになるのです。(参考までに『All You〜』は、ダグ・リーマン監督、トム・クルーズ主演のハリウッド映画(ワーナー・ブラザース、2014)にもなっているのですが、その設定は原作のものと少し異なっており、ここでは原作版に準拠した説明だと思ってください。)
以上のような物語構成を持つ『All You〜』ですが、東はそのなかで、キリヤやリタが異なる並行世界で複数の人生を経験しながらも、結局はたったひとつの「この」生/死しか選べないという苦悩を味わっていることに注目します。東によれば「桜坂はここで、死の一回性を相対化するメタ物語的な想像力を排除するのではなく、むしろその相対化を活かして、死の重要性を描いている」(傍点原文)というのです。そして、「そのような逆転が可能になったのは、彼がこの小説で、キャラクターのレベルとプレイヤーのレベルを区別して描いたうえで、死の残酷さが感じられる場所を、すなわち読者がその痛みに感情移入する場所を、物語=キャラクターのレベルからメタ物語=プレイヤーのレベルへと移動させたからである」と指摘します。
東は、この感情移入の特徴を理解するための参照軸として、大塚英志という、これもまた非常に有名な批評家の「死は一回的であり、したがって死の描写には物語の一回性が必要だ」という物語観を対比的に導入します。死のかけがえのなさ(一回性)は、それが帰属する物語世界のかけがえのなさ(一回性)が必要なのだとする大塚の論旨に対して、東は『All You〜』においては「死が一回的だとすれば、その一回性を感じるためにこそ、むしろ複数の物語が、つまりプレイヤーの視点が必要だと考え」られていると主張します。つまり、「前者では読者は、一回かぎりの生を生きるしかないキャラクターの無力さに感情移入し、後者では読者は、複数の生を横断しつつも、結局はキャラクターに一回かぎりの生しか与えられないプレイヤーの無力さに感情移入している」というのです(✳)。ここから、「キャラクターのレベルとプレイヤーのレベルの二層の区別を導入し、人間や世界を描きだす」ような新しい表現様式として、「ゲーム的リアリズム」という概念の必要性が強調されていくことになります。(ここには、「コミュニケーション志向メディアの台頭(メディアの環境の変化)」という、もうひとつの重要な要素が備わっていると東は述べているのですが、論点が拡散してしまうため割愛させてください。)ゆえに『All You〜』は、「選択の残酷さを前にして逡巡してはならない、メタ物語的な宙づりは放棄してひとつの物語を選ぶべきだ、という強い主題」を持つ小説作品であり、「ここには、現在の日本において、物語を語ることがいかに困難であるか、はっきりと自覚した作家の姿が窺える」というのです。
(✳)ちなみに、単行本『ゲーム的リアリズムの誕生』のもとになった連載で、東はこの点について「まんが・アニメ的リアリズムが主題としている(と大塚が述べる)死の一回性、反復不可能な物語に対する単独的な経験から、ゲーム的リアリズムが主題とするはずの生の一回性、反復可能な物語のあいだを横断する経験そのものの単独性への視点の転換」が起こっていると説明しています(「メタリアル・フィクションの誕生」『文学環境論集──東浩紀コレクションL』講談社、2007.4、傍点原文)。ここでは、あるひとつの物語に「この」性が付与されるにあたって、数多の物語を横断する「経験」がどのような意味を持つのかという非常に重要な問いが提示されています。単行本版では削除されたこの問いが、後々の本連載にとって大きなポイントになってくる(と思う)ので、ぜひとも頭の片隅に入れておいていただけたらありがたいです。
並行世界への想念
続く論述で、東は「2000年代の前半にオタクを惹きつけた二つの物語メディア、キャラクター小説と美少女ゲーム」が、「表面的にはそれぞれ異なった主題を追い、異なった物語を語っていたとしても、構造的には、メタ物語的な読者/プレイヤーをいかにして物語のなかに引きこむかというひとつの課題への回答として、共通の視点で分析することができる」ことを明らかにします。その具体的な作品考察は、またも紙幅の都合で省略せざるをえないのですが、要するにキャラクターというのは、ありえたかもしれない別の物語世界への可能性を必然的に作り出してしまうのであり、そのような特有のキャラクターへの情念に対応した表現様式として、2000年代(ゼロ年代)には「ゲーム的リアリズム」の手法を備えた文化コンテンツが求められていたというのです。
これが、前回に見た固有名の議論と合わせ鏡のような関係になっていることは明らかでしょう。「この私」と「こうではなかったかもしれない私」の区分が、ここでは概ね物語/メタ物語の区分に対応しており、柄谷が「こうではなかったかもしれない私」という反実仮想を経由することで「この私」へと帰着する理路を重視していた一方で、東はむしろメタ物語の視点(プレイヤー)が不可避的に物語(キャラクター)の複数性を招き寄せ、そこに事後的なかたちで「この」性を喚起させてしまうことを強調しています。ただ、ともに並行世界への想念を挟み込むことによって、人びとは現実世界の「こうでしかなさ」に確かなリアリティを感じることになるという趣旨は一致しているのではないでしょうか。こうした現実世界の「こうでしかなさ」が仮に正当なものであったとしても、どの程度まで経験的に人びとを納得させるものであるのかというのが、僕が問いたい最大の焦点となります。
さて、ここで同時に重要なのは、東の論旨に従うならば、「この私」の生を実感するために「こうではなかったかもしれない」という反実仮想を介在させようとする人びとの感性が、まさに切迫したものとして受け止められはじめたのがゼロ年代だったということです。しばしば指摘されるように、この時期の物語文化のなかでは、純文学・サブカルチャーを問わず、並行世界を扱った作品群がさまざまに量産されていきました(千田洋幸『ポップカルチャーの思想圏──文学との接続可能性あるいは不可能性』おうふう、2013.4)。こうした並行世界への興味・関心の高まりは、先ほど東の論述を跡づけていきながら確認したような、「この私」のかけがえのなさを理解するための作業仮説であった「こうではなかったかもしれない私」に対するまなざしが、特有の価値を帯びはじめたことに支えられているでしょう。その理由となる時代状況のあり方については、さまざまに社会学的な意味づけが可能でしょうが、とにかく強調しておきたいのは、今日における「ゲーム的リアリズム」という表現様式の台頭は、もとより「現実の体制」に奉仕するものでしかなかったはずの並行世界への想念が、ある別様の〝現実感〟を伴っていたことの証ではないかということです。もちろん、その淵源をたどっていけば、ゼロ年代よりも以前の物語文化のなかに、こうした想念の痕跡は無数に見いだせるでしょう。しかし、以上のような少なからぬ人びとの感性の変化によって、並行世界に思いを馳せる文学的主題の射程もまた大きく拡張していったことは確かだと思われます。
前回の最後で、並行世界というのは、現実世界でうまく(正しく)やっていけず、どうしてもいま・ここに生きていることの実感を抱くことができないひとたちのための楽園のようなものではないかという話をしました。「一回かぎりの生」を感じるために、並行世界における複数の物語経験を逆説的に必要とする「ゲーム的リアリズム」の理念は、こうした屈託を的確に掬い上げているようにも思えます。しかし、どれだけの並行世界を航行したとしても、いま・ここの「一回かぎりの生」をどうしても感じることができないとしたら? 頭では現実世界の特別さを理解できたとしても、そこに備わっているはずの「この」性をどうしても感覚的に受け止められなかったとしたら? それは理性的でない人びとの単なる「病理」でしかなく、もしかしたら一周まわってナイーブな議論になっているのかもしれません。しかし、ここにこそ広義の並行世界を扱い、かつ現実世界の唯一性・特権性を失効させてしまうような作品群が、現代日本の物語文化の領域で相次いで現れはじめたことの最大の鍵があるように思えるのです。
では、それはどのようなものなのか。その具体的なありようを、以下で考察していきたい……と思うのですが、その前にもうひとつ、柄谷・東の思考ラインと重なりつつも、並行世界をめぐる思考の枠組みにまた別の文脈から多大な影響を与えた学問の潮流として、次回は分析哲学の領域における可能世界論の隆盛と、分析哲学的な手法に寄り添いつつも、そこからなお独創的な思考を展開した永井均という哲学者の議論の輪郭を跡づけておきたいと思います。