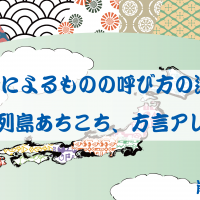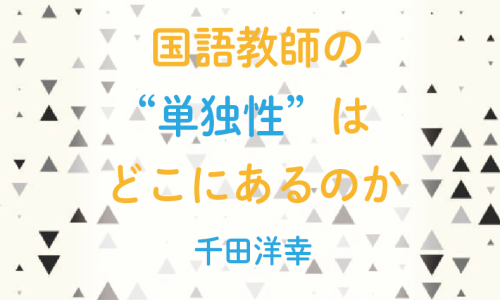| 本連載が書籍になりました。連載の内容に大幅な加筆をしての書籍化です。ぜひご覧ください。
並行世界の存在論 現代日本文学への招待 |
ただ端的にある並行世界
冒頭から奇妙なことを言うようですが、僕は中学生か高校生くらいの頃から、並行世界というものが実際に存在するということを強く確信していました。別に、たとえば僕に瓜ふたつの人間がそこで生活しているというような、ある特定の具体的なドラマが仕立て上げられた時空間のことを想像していたわけではないのですが、とにかく世界がこのひとつだけであるとは単純にどうしても信じられなかったのです。僕にとって、それは科学的な証明とも哲学的な思弁とも一切関係なく、ただ端的にありのまま疑いえない真実でした。(同じようなことで、人びとの見えている色や感じている痛みなどは、それぞれに少しずつ異なっているに違いないとも昔から思っているのですが、話がややこしくなるのでここでは割愛します。)
もとより根拠も何もあったものではなく、およそ他人を納得させるような説明ができるわけでもありません。したがって、なぜそう思うんだと理詰めで問われても、なぜかわからないが直観的にそうなのだと言うほかないでしょう。しかし、少なくとも僕には、そのような並行世界に対する独特な情熱とでもいうべきものがあり、そこに論理的な妥当性はなくとも、何かしらのかたちで同調してくれるひとは多少ともいるのではないか……と思っています。事実、これから検討していくように、並行世界に対する想念は、今日の文学的主題の重要な一角を占めるものであり、また現代思想の分野においても繰り返し考察の対象となってきました。こうした時代精神(?)のありように、僕自身が抱えていた並行世界への執着をそのまま重ね合わせてよいのかどうかは分かりませんが、そこにある種の共鳴があることを信じつつ、これからしばらくのあいだ、並行世界と文学に関わるいくつかの論考めいたものを書いていくことにしました。
連載にあたって
皆さんはじめまして、加藤夢三と申します。昨年11月、ひつじ書房から『合理的なものの詩学』という研究書を刊行しまして、その縁でこの度、こちらのウェブマガジンでしばらくのあいだ連載を担当させていただけることになりました。研究者としての僕の専門分野は、昭和初期の文壇・論壇における理論物理学の受容と展開という、さほど多くのひとが興味を持つとも思えない地味なテーマを扱っているのですが、そのテーマを選んだ理由のひとつは、もともと大学院で並行世界をめぐる文学的な想像力の可能性を取り上げたいと思っていたことがあります。なぜ(少なくともある特定の)ひとは並行世界というものに強く惹きつけられるのか、並行世界に思いを馳せるとはどういうことなのか、並行世界とはそもそも何なのか……そういった問題を、哲学でも心理学でもなく文学の領域で考えてみたいと思っていたのです。
もっとも、文学の研究というのはどうしても作家や作品単位でなされることが多いため、当時の僕の研究テーマは完全に浮いていました。いくつかの具体的な小説作品を論じることで、修士論文は何とか出すことができたのですが、博士課程に進学し、本格的に学術誌に論文を投稿することを考えたとき、どうにも壁にぶつかってしまったのです。結果として、博士論文の研究テーマはやり方を大きく変更し、修士論文で並行世界を導く科学的な仕掛けを扱ったことから、先に示したような領域を新しく選びなおすことにしました。その道筋は長くなるので省略しますが、要するに僕は、並行世界の仕組みを支える要素としての科学理論(量子コンピュータや多元宇宙仮説といったもの)への関心から、次第に時代を遡っていくことによって、結果的に黎明期の現代物理学に多大な影響を受けた昭和初期の文化思潮へと、自分の研究対象を移していったのです。
もちろん、昭和初期の言論空間にはまだまだ重要な思想的課題が眠っており、そのあたりの検討は今後も続けていきたいと思っているのですが、同時に著作を出版したことをひとつの区切りとして、学術的な価値があるかどうかはともかく、今度こそもともと自分が考えていた最初の問いに改めて忠実に取り組んでみたいとも感じていました。なので、今回そういった思考を自由に発揮して文章を書けることは大きな歓びであり、そのような貴重な場を与えていただいたひつじ書房の皆さまに、まずはお礼を申し上げたいと思います。
柄谷行人の「単独性」
では、上で示したような問いはどのように考えればよいのでしょうか。僕も現時点で全体の構想がしっかり描けているわけではないのですが、この連載ではまず、現代日本で名の知られた(広義の)並行世界に関わるいくつかの理論的な枠組みの検討を通じて、僕が抱いている問いの輪郭を少しずつはっきりさせていこうと思います。第1回となる今回は、柄谷行人『探究Ⅱ』(講談社学術文庫、1994.4)の第1章に登場する「単独性」の議論についてです。
柄谷行人は、現代日本を代表する思想家のひとりで、彼の提唱した数々の独創的な概念は、学問分野を超えて人文系の研究者たちに多大な影響を与えました。特に、それまでの思索を総合しつつ『探究Ⅱ』で展開された「単独性」の概念は、とてもパワフルなもので、さまざまな批判を受けつつも、柄谷と同じような問題意識を抱える多くの読者たちを圧倒的に魅了したのです。僕はリアルタイムでその影響の高まりに触れたわけではないのですが、それでも「私は十代に哲学的な書物を読みはじめたころから、いつもそこに「この私」が抜けていると感じてきた」という印象的なフレーズで始まる『探究Ⅱ』の冒頭数ページは、僕がそれまで漠然と不思議に思いながらもクリアに言葉にする術を持っていなかった〝自分という存在の不思議さ〟について、周りの誰よりも明晰な説明を施してくれるものでした。それはどのようなものだったのでしょうか(以下、鉤括弧のなかは原則として著作からの引用を示します)。
柄谷は、「私」という存在のあり方について、「一般性からみられた個体性」としての「特殊性」と、「もはや一般性に所属しようがない個体性」としての「単独性」に分けて考えることを提案しました。(なお、以降の論理展開は「私」に限らずあらゆる事柄に当てはまるものですが、ここでは「私」に関わる議論に特別な意味を持たせています。その理由は、追って本論のなかで展開していくつもりです。)人称概念としての「私」は、それを辞書的な意味どおりにとらえるならば、詰まるところ「人間」という一般的なカテゴリのなかのひとつの具体的な事例に過ぎず、この世界に無数に存在する「誰か」を指すものでしかありません。先の分別で言うところの「特殊性」は、このような「私」観に相当します。
しかし一方で、実際問題として「私」というのは、世界のなかのたったひとりだけ(=実際にいま・ここでこうしている「この私」)だけに当てはまる特別な指標であり、そもそも他の「私」たちとのあいだに比較する尺度自体が存在しないような、根本的に隔絶した存在でもあります。こちらが、先の分別で言うところの「単独性」です。もちろん、それを誰にでも当てはまる普遍的なテーゼとして差し出した瞬間に、すべての「私」は「この私」となる資格を持ちうるわけなので、なおそこから根本的に隔絶した「この「この私」」という特権的な指標が必要になり、あとは際限のない堂々めぐりが続いていくことになるでしょう。その点で単独的な「私」というのは、何かしらの積極的な定義を施せるものではなく、単にただこうであるとしか説明できないものだと言えます。
ここで重要なのは、「私」全般と「この私」の差異は「同一性(一般性)からみられた差異」ではない以上、「この私」の「この」という指示語は、特定の何かではなく「たんに私と他者の差異(非対称性)を指示する」だけの空疎な表現にすぎないということです。したがって、あらゆる「単独性」は、本質的に「他なるものを根本的に前提し他なるものとの関係において見出される」ことになります。これが、数多の人間たちと自分自身のアイデンティティ(=自分らしさ)の比較を意味しているわけではないことに注意してください。あくまでも「この私」は普通の意味での「私」たちから根本的に隔絶しているわけで、そのアイデンティティが他人と比べて特別であるかというのはどうでもよいことです。仮に自分にそっくりの記憶や人格を共有する分身(ドッペルゲンガー)が眼の前に現れたとしても、「私」のアイデンティティはもちろん重大な危機に直面することになるでしょうが、しかしそんなこととは少しも関係なく、実際にここでこうしている「この私」のかけがえのなさは欠片も揺らぎえないでしょう。そういうことではなく、「この」という指示のあり方そのものが、言わば「他なるもの」という内的な分裂を抱え込むかたちでしか意味を持たないフィクショナルな産物であるということなのです。ただし、その指示対象としての「私」が〝いる〟というのは、もとより疑うこと自体ができないという意味で自明の事実なので、単に幻想だと切って捨てることができないところが厄介なのですが。
そして上記のような「単独性」の仕組みは、何より固有名によって誰か/何かを呼びかけることと非常に深く結びついています。なぜなら固有名こそ、その指示対象の唯一無二性を支える絶対的な条件として、「他なるもの」(「こうではなかったかもしれない」という視点)が不可欠の要素となっているからです。どういうことでしょうか。
固有名の論理
柄谷は、「なぜ私はここにいて、あそこにいないのか」というパスカルの言葉を引用し、そこに「偶然性と切り離しえない」ような「現実性」のありようを読み取ります。「「ここにいる」という現実性は、あそこ(ここより他の場所)にいるかもしれないという可能性のなかではじめて在る」というのです。それは固有名の問題でも同じことです。固有名とは、この世界にたったひとつしかないもの(「他ならぬこれ」)を指示する名称のことですが、ここで「「他ならぬ」というとき、すでに、他(あるいは多)が前提されている」ことに注意してください。それは、とりわけ言語哲学の領域で繰り返し問われていたことでした。
固有名に関する非常に有名な哲学的議論として、B・ラッセルとS・クリプキのものがあります。ラッセルは、固有名を確定記述の集積として理解していました。この確定記述という概念の専門的な定義は非常に難しいのですが、ここではざっくりと、ある固有名に対して経験的に整合するような属性のことだと考えてください(加藤夢三は男性である、加藤夢三は学校の教員であるといった傍線部(述語)のことです)。ラッセルは、確定記述を無限に寄せ集めることによって、その束のようなものは、最終的に固有名そのものが指し示す対象と一致すると主張しました。しかし、クリプキはそれでは反実仮想的に固有名をとらえることがそもそも不可能になってしまうのではないかと反論します。加藤夢三は男性でなくてもよかった、加藤夢三は学校の教員でなくてもよかった、加藤夢三は〇〇でなくてもよかった……。こうした現実世界では起こらなかった想像上の可能性について考え、あらゆる現実世界の属性と食い違う加藤夢三という存在を想起したとしても、なお加藤夢三という固有名の加藤夢三性は揺らがないはずである。ゆえに、固有名を確定記述の束に置き換えることはできず、むしろ反実仮想の適用可能性こそが固有名の固有名たる所以を条件づけているのだというのが、クリプキの主張の骨格でした。
柄谷は、これを「固有名がすでに可能世界をはらむ現実性にかかわるということを意味する」と解釈します。確定記述は、可能世界(起こりうる事物の組み合わせによって成り立つ世界の総称のこと)のなかではどのようにでも変動するにもかかわらず、固有名の指示対象がただひとつのものとして同定されるのは、「他=多なる可能性において、多=他ならぬ一者として指示される」からだというのです。したがって、この「現実性」というのは、現実世界の内側で閉鎖的に完結しているわけではなく、逆にこうではなかったかもしれないという可能性こそが、固有名のかけがえのなさを条件づけていることになります。この発想の転換から、柄谷は先述の「単独性」をめぐる議論の足場を構築していこうとするのです。(こうした固有名の論理を導きの糸として、以降の『探究Ⅱ』では超越・交通・外部といった主題をめぐる重厚な思索が展開されるのですが、ここではそれを扱えません。ぜひ『探究Ⅱ』の原本に当たっていただきたいと思います。)
「不健全」な感性
どうでしょうか。僕の説明の仕方が上手いものであったかは自信がありませんが、僕はこの一連の論述の流れに、本当に震えるほど大きな感銘を受けました。哲学や科学の議論、あるいは自己啓発や宗教でもよいのですが、それらはいずれも一般的な人間のありようを何らかの仕方で描き出しており、その仮説や教義は「誰か」の救済にはなりうるのかもしれないけれども、他ならぬ「このひと」のことは何もわからないし、まして「このおれ」のためのものではありえないのではないか……ここまで綺麗にまとめられるほど達観していたわけではないものの、僕は昔から漠然とそんなふうに思っていました。たとえるなら、あらゆる人間全体に向けられた神の祝福よりも、いま・ここで他の誰でもない「このおれ」に発せられた恋人からの愛の承認こそが、真の意味での救済となりえると言えばわかりやすいでしょうか。(ただ、この例だと「特殊性」の承認と「単独性」の承認という二通りの解釈ができ、余計な勘違いをさせてしまうかもしれないのですが、そのことは後で述べます。)
だからこそ、「この私」という根本的に隔絶した存在のあり方を何とかして捕まえようとする柄谷の思考に、とても強い憧れを抱いたのです。そして、少なくとも柄谷行人という名前が、今日の代表的な思想家のひとりとして近代日本批評史に刻まれている以上、同じような思いを抱いたひとは少なくなったのではないかと推察します。(もっとも本来であれば、そこで扱われている事柄の本質からして、他ならぬ「この私」という存在のあり方に一般的な共感を示すということ自体が、ある意味で問題の核心を取り逃がしているとも言えるのですが。)
一方で、そのしなやかな論理と断定的な物言いに対して畏敬の念を抱きつつも、また同時にその明快さに対する小さな違和感のようなものが、ひそかに僕のなかにはありました。それは、柄谷にとって可能世界や並行世界は、結局のところ現実世界の存在に奉仕するだけの作業仮説でしかないのではないかという疑念でした。つまり、柄谷の「単独性」をめぐる議論は、つねに現実世界のかけがえのなさが思考の始点と終点に据えられており、その唯一性や特権性がまったく疑われていないという点で、ある種の偏向が忍び込んでいるようにも思われたのです。いや、偏向というのは不誠実な表現でしょう。実際問題として、僕たちにとってこの現実世界が唯一の特権的ないま・ここであることは自明であり──もちろん並行世界の住人たちは、いずれも自分たちの住む現実世界こそが唯一の特権的ないま・ここであると主張するでしょうが──、その前提がなければ上で示したような思考自体がそもそも成り立たないものだからです。思考の前提が思考によって疑いうるというのは、言うまでもなく錯覚にほかありません。
しかし、一方で現実世界の唯一性・特権性が疑いなく明らかであったとしても、なおある種の人間たちは、どこか別の並行世界にこそ、かけがえのない唯一性・特権性を感じてしまうのではないでしょうか。少なくとも、僕にとって文学とはそのようなものです。文学という営みが、良くも悪くも現実世界からの逸脱(逃避?)によって成り立つ側面を持つ以上、僕にはこうした逸脱や逃避を肯定したいという思いがずっとあるのです。間違っていてもいい。矛盾していてもいい。そのような錯覚が許されるというのが文学の強みであり、現実世界の明らかな唯一性・特権性を引き受ける必要がないというのが、ある種の救いになりうるように思うのです(実際、優れた物語に対して現実世界の出来事は驚くほど無力ではないでしょうか!)。
念のため、僕はいま・ここの現実世界が決して嫌いなわけではありません。なんだかんだ何十年か過ごしてきたこともあり、この時空間の拡がりに対して一般的な意味での愛着を抱いているし、特別な親近感を持っているとも思います。しかし、しつこいようですがそれは、単独的な「この」性とは何ひとつ無関係なのです。つまり、現実世界の唯一性・特権性というのは二重の意味を帯びており、それこそ内実や属性の特別さ、あるいは経験の蓄積などを他の可能世界と比較することで示される唯一性・特権性(こちらが柄谷の用語で言うところの「特殊性」にあたります)と、そのような特別さとは根底から隔絶した、比類なき「この」としか呼び表しようがない唯一性・特権性(こちらが柄谷の用語で言うところの「単独性」にあたります)を分けて考えねばならないのです。僕がうまく感じられないと言っているのは後者のほうであり、この違いこそが、以降の僕のほぼすべての論述の最も重要な前提になるところなので、何とぞ注意していただければありがたく思います。
その違和感は、柄谷のようには考えられない自分の屈託に拠るものなのかもしれませんが、事実として、こうした「不健全」な感性を承認することこそが、僕にとって文学という営みに向き合ううえで最大のモチベーションとなっています。その意味で、並行世界というのは、現実世界でどうにもうまく(正しく)やっていけないひとたちのための楽園のようなものなのかもしれません。
ただ、こうまとめてしまうと、結局は異なる並行世界で起こりえた可能性を夢想することで、現実世界の「こうでしかなさ」を相対化し、場合によってはその不満を書き換えてしまおうという、なんとも穏当な話のようにも誤解されてしまうのですが、僕はそういうことを言いたいわけではありません。もしそのような主張だとすれば、たとえば「並行世界」を「こうではなかったかもしれない私」に、「現実世界」を「この私」に置き換えてもまったく同じことが言えるでしょう。しかし、「こうではなかったかもしれない私」を夢想することで「この私」の「こうでしかなさ」を相対化しようというのは、繰り返しになりますが「単独性」と「特殊性」の概念を根本的に取り違えています。「この私」の比類なき唯一性・特権性は、原理的に明らかであり経験的にも疑いえないけれども、そのような存在が帰属する現実世界に比類なき唯一性・特権性があるということは、原理的には明らかであっても経験的には疑いうるどころか、むしろきわめて疑わしいと思ってしまうというのが、冒頭で僕が示した問題意識のポイントなのです。
次回はこの点について、もう少し別の角度から考えてみることにしましょう。