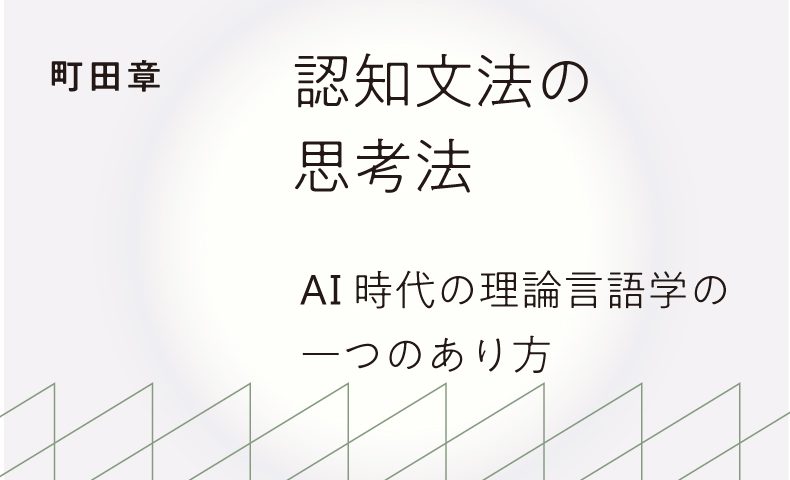はじめに
前回、有限の知識から無限の表現を生み出す最もポピュラーな方法として言語をある種の記号演算操作と見なせばよいということを紹介しました。そして、この考え方は、長い間、生成文法をはじめとする多くの言語理論に採用されてきた最も有力な考え方でした。しかしながら、前回簡単に触れておきましたが、残念ながら、認知文法はそのような考え方をとりません。もっと言うと、言語を記号演算操作と見なすことは認知文法では禁じられているのです。では、なぜ、言語を記号演算操作と見なしてはいけないのか。今回は、この問題について考えてみましょう。
何でもありは、何にもなし
よく、認知文法に対して「あーあの何でもありの理論でしょ」なんて批判を受けることがあります。たしかに、認知文法は、絵を描いたり、あいまいな説明を許したり、しまいには、話し手の捉え方次第です、なんて言い出したりしますから、傍から見れば、何でもありに映っても仕方ありません。もちろん、僕らからしてみれば、それぞれ理由あってのことなんですが、とにかく、認知文法は部外者には“何でもあり”に映ってしまうようです。そして、何でもありの理論は、何にも説明していないのと同じことになりますので、冷ややかな視線を受けることになるわけです。
もちろん、認知文法は“何でもあり”の理論というわけではありません。それどころか、認知文法は“何でもあり”には程遠い非常に自制的で自己抑制的な理論であると言ってもよいでしょう。なぜそのように言えるのかというと、認知文法は、内容要件(content requirement)と呼ばれる厳しい制約を自らの理論に課しているからです。そして、この内容要件があるために、認知文法では、言語を記号演算操作と見なすことができないのです。言語を記号演算操作と見なせないということは、有限の知識から無限の表現を生み出すための便利な豊饒の角(Cornucopia)に自ら封印してしまうことになるわけですから、かなり険しい道のりを自らに強いることになります。それでは、そこまでして守らなければならない内容要件とはいったいどのような制約なのでしょうか。
経験から得られる知識
内容要件とは、言語学者が言語現象を記述する際に認められるのは、以下の3つの要素だけであるというものです。逆に言うと、この3つの要素以外を用いて言語を記述することは厳しく禁じられているということになります(cf. Langacker 2008: 24-25)。
(ⅰ) 意味構造と音韻構造、そしてそれらを結び付けた記号構造
(ⅱ) (ⅰ)の要素をスキーマ化した構造
(ⅲ) (ⅰ)と(ⅱ)の構造間で成立するカテゴリー化の関係
一見するとちょっと難しそうですが、背後にある考え方を理解すればごく当然のことを言っているだけですので心配はいりません。それでは、一つずつ見ていきましょう。(ⅰ)は認知文法のもっとも基本となる考え方に従ったものです。まず、ことばは音で意味を表す記号であるという基本的な考えについて確認しておきましょう。例えば、「いぬ」という音は、僕らが知っているあの動物を意味として表す記号です。このため、「いぬ」はことばだと言えます。一方、「ぬい」という音は何の意味も喚起しません。そのため、「ぬい」は記号とは言えず、ことばとはみなされないことになります。このように、ことばは、音で意味を喚起する、または意味で音を喚起する記号であるというわけです。注意しておきたいのは、ここで述べている「記号」とは、記号演算操作における「記号」とは全く異なるということです。記号演算操作における「記号」とは意味を伴わない単なる符号(label)のことを指します。例えば、記号演算操作に用いられるNやVやCPなどは、意味を伴っておらず、演算操作のために用いられる便宜的な符号にすぎません。それに対して、認知文法が「記号」と呼んでいるものは、音と意味がペアになったもの(form-meaning pairing)だけです。
そして、日々のことばのやり取りの中で実際に生じているのは、音と意味と記号の3つだけです。そのため、人間がことばとして習得するのは、音、意味、そしてそれらを結び付けた記号だけであり、人間がことばとして使うのも、音、意味、記号だけであるということになります。このように考えると、例えば、生成文法で提案されている空範疇のような音を伴わない意味だけの要素や、ある要素を元の場所から別の場所に移すような移動操作などは、言語知識の中には存在しないことになります。なぜなら、これらの要素は、演算操作上の必要性に迫られて便宜上導入されたものにすぎず、言語使用の現場において直接観察されたものではないからです。直接観察されないこれらの要素は習得されず、結果として、言語知識を構成する要素にはならないと考えられます。
(ⅱ)は上記の考え方を補足するものだと考えてよいでしょう。スキーマとは、ある事物の中に内在する抽象的な構造のことですが、このスキーマがはっきり意識されるのは、複数の事物を比較した場合です。例えば、えんぴつとロープがあったとします。僕らは、両者が似ていると直感的に思う部分がありますが、それは、両者の間に「細長い」という抽象的な構造(=スキーマ)を見ているからです。よく複数の事物間の共通点がスキーマであるという説明のされ方をしますが、それは厳密ではありません。厳密には、ロープと比較される以前に、えんぴつという物体の中にすでに「細長い」という抽象的な構造(=スキーマ)は内在しているのです。比較されることによって共通点としてのスキーマがより意識されやすくなるだけです。ですので、先ほど、音と意味、そしてそれらを結び付けた記号は直接観察されると述べたわけですが、スキーマはそれらの要素に付随して、いわば無意識のうちに、間接的に観察されているわけです。そのため、直接観察される事物から引き出されたスキーマも僕らが習得する言語知識の一部であり、僕らはことばを使用する際にこのスキーマも利用すると考えてよいでしょう。
最後に、カテゴリー化に関する(ⅲ)についてですが、上記のように直接または間接的に観察された事象がバラバラの知識として脳内に収納されているわけではありません。僕らはそれらをグループ(=カテゴリー)にまとめながら、つまり、それぞれの知識を関係づけながら知識の構造を作り上げていきます。そして、そのようなことを行うカテゴリー化もことばを習得したり使いこなしたりするためには、なくてはならない認知メカニズムということになります。
要するに、この内容要件は、言語知識は実際の言語使用の現場で直接観察される要素とそこから得られる要素だけからできているはずなので、それらだけを用いて言語知識を記述しなさいということなのです。そして、これら以外の体験を伴わない要素をいくら仮定しても、それらの要素が言語知識として脳内に実在する保証はありません。分析や説明をするうえで便利だからというだけの理由で、意味を伴わない記号(=符号)や記号操作を仮定することは理論言語学ではよくあることですが、認知文法では、そのような意味を伴わない記号演算操作を禁止することで、実在性の疑わしい要素を多用することに歯止めをかけているのです。
大切なことは、目に見えない
もちろん、この内容要件に関しては批判もあります。直接観察されるものしか認めないなんて、学問的な態度としていかがなものか、というものです。学術の発展は、ある意味、それまで一般には知覚されてこなかったものを発見してゆく過程であるとも言えます。ブラックホールであれ、ヒッグス粒子であれ、まずは直接観察されないものを思考の目で見るのが学者の仕事であり資質でもあるわけです。その意味では、直接観察されるものしか信じないという態度はあまりにも浅はかすぎるというのです。実際、サン=テグジュペリだって「いちばんたいせつなことは、目に見えない」(『星の王子さま』)と言っていますし、どの言語理論でも、ことばの表面だけを見るのではなく、その背後に隠された見えない何かを明らかにすることが求められるわけです。
しかしながら、実は、このような批判は認知文法には当てはまりません。認知文法の研究者だって、当然、物事の背後に潜んだ目に見えない何かを明らかにしようとしているからです。そして、その点では、認知文法の学問的態度は他の理論となんら変わりがないのです。ただ、ことばを習得し用いている話者にとっては事情が異なります。直接観察されない事物は、話者には体験されず、習得もされないからです。少なくとも、ことばは誰にでも習得できるようにできている以上、観察されるものがすべてなのです。学習者フレンドリー、使用者フレンドリーであることが言語のあるべき姿だとすると、観察されない要素が言語知識の中で生き延びる余地はないのです(cf. 本連載第5回)。
実は、認知文法をやっている人の中にも、なぜ言語を記号演算操作と見なしてはいけないのかを明確に説明できる人はあまりいないかもしれません。お題目のように、「記号演算操作は内容要件に反するから」などと唱えていても、それは何にも説明したことにはならないからです。その意味で、内容要件という概念は、思考停止を誘発する恐ろしさも持ち合わせています。そこで、なぜ内容要件に従う必要があるのかを、ここではもう少し掘り下げて考えてみましょう。
記号接地問題
実は、言語を記号演算操作と見なしてはならないことは、長年AI研究を苦しめてきた記号接地問題もしくはシンボル・グラウンディング問題(symbol grounding problem)と深く関係しています。記号接地問題とは、簡単に言ってしまえば、コンピュータが行う記号演算操作に用いられる記号(=符号)は意味と結び付けられないという問題です(cf. 松尾2015:105-107)。よく引き合いに出されるシマウマを例に考えてみましょう。例えば、人間の場合、シマウマを見たことがない人でも、「シマウマとは縞模様をした馬です」と説明してあげれば、大概、イメージしてもらえるはずですが、これは、馬の意味と縞模様の意味がその人に理解されているからこそできることです。ところが、馬や縞模様の意味を理解していないAIマシーンにシマウマについて上記のように説明したとします。そして、別の機会にそのAIマシーンに向かって「シマウマって何ですか?」と聞いたとします。すると、そのAIマシーンは、当然「シマウマは縞模様をした馬です」と答えてくれるので、僕らは「ああ、このAIマシーンはシマウマとは何かを知っているんだな」と判断することになります。ところが、実は、このAIマシーンは全くシマウマとは何かを理解していません。ただ無意味な記号(=符号)を用いてシマウマとは何かを表現しただけなのです。僕らは馬や縞模様の意味を既に知っているため、無意識のうちに、AIマシーンも僕らと同じようにこの説明が意味するところを理解していると思い込んでしまいます。ところが実際は、意味を学習していないAIマシーンのことばには意味が込められていないのです。そして、このことが意味しているのは、コンピュータ上の記号演算操作によって生成された言語表現は、意味と結び付けられない限り、閉じた記号体系の中をぐるぐると回るだけの空虚な記号列にすぎず、何ら現実世界とのかかわりを持てないということなのです。このことは、AI研究の観点から言うと、究極的には、AIに身体を持たせ、外的世界と相互作用をさせることにより、記号(=符号)の意味を習得させなければならないということを示しています。真にことばを理解できるAIを作るためには、AIに実体験を与えて音と意味の対応関係を構築しなければならないということなのです。
このAI研究における記号接地問題は、理論言語学においても重要な示唆を与えてくれます。なぜなら、意味の問題を先送りにして、記号演算操作だけを追求していっても、最後には必ず記号接地問題という厄介な問題が待っていることになるからです。AI研究における記号接地問題は、言語を記号演算操作とみなす言語理論に早くから根本的な問題を突き付けてきました。それにもかかわらず、多くの理論言語学者たちは、言語知識(linguistic knowledge)とそれ以外の一般的な知識(extralinguistic knowledge)とを区別するというできもしない言い訳を盾に、この記号接地問題を棚上げにしてきました。その結果、将来、正しい表現だけを生成できる記号演算操作にたどり着くことが仮にできたとしても、その次に待っているのは、記号接地問題という泥沼なのです。
実は、このAI研究の記号接地問題は、ディープラーニングの登場により、一気に様変わりしています。大量の実例を学習することにより知識を獲得していくディープラーニングの設計思想は、まさに、AIマシーンに経験を積ませることだったからです。もちろん、身体を持たない現在のAIマシーンに完全な身体経験を積ませることは不可能ですが、それでも、ディープラーニングの登場により、AIマシーンに「意味」を習得させる道筋が見え始めたのは確かです。これにより、最も解決が困難だった記号接地問題に突破口が開かれることになったのです。
まとめ
さて、このように考えてくると、なぜ言語学者が内容要件に従わなければならないのかがはっきりと分かるようになります。要するに、僕ら人間は地に足の着いた直接的な身体経験を通して学んだ知識を用いてことばを操っているというとなのです。そしてこれは、経験基盤主義(experientialism)(cf. Lakoff and Johnson 1987)や本連載で何度も言及している用法基盤主義と呼ばれる考え方にも通じています。人間は、経験から学ぶんですね。ですので、経験を伴わない記号演算操作は、われわれに何の意味ももたらさないということになります。このように、内容要件とは、徹底した経験基盤主義・用法基盤主義を認知文法に課すことを通して、理論を健全な発展に導く仕掛けなのです。
そして、AI研究が僕たちに示してくれた最も重要なことは、記号接地問題が始めから起こらないように理論を設計しなさいという指針です。そして、このことを念頭に置きながら、次回以降、音と意味の対応関係に関して深く掘り下げていくことにしましょう。