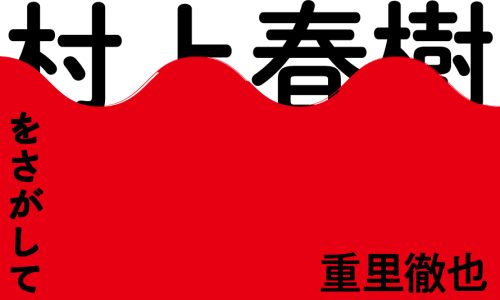情況は二極化している
助川 先日、私はある温泉に旅行してきました。特急の停まる駅で列車を降りて、そこから何十分かバスに揺られてめざす温泉にたどり着いたのですが、乗り継ぎ駅周辺のシャッター商店街化がすさまじかったです。飲食店と理髪店だけが営業していて、「通販や買いだめで代替できない店だけが生き残るんだ」とあらためて感じました。そして歩いているのが、高齢者の方ばかり。岐阜は田舎だと思っていましたが、高校生や大学生がたくさん街なかにいて、こういう状況とはかけ離れています。
重里 東京の週末の盛り場を眺めたら、「日本が衰退している」という実感をそれほど持たないと思うのです。若者はたくさんいるし、外国人の姿も多い。老若男女、活気がないわけではない。それが首都圏の外へ行くと、いろいろな問題が目に入ってきます。
助川 この対談で以前、佐伯一麦と絲山秋子の話をしました。二人とも地方の街に住んで、そこを舞台に印象深い作品を書いています。「地方にいたほうが、時代の最先端の問題をつかまえられる」という一面が現代日本にある。そのことを、彼らの小説は教えてくれる気がします。
重里 芥川賞の受賞作を見ても、はっきり二つの路線がある印象ですね。一つは、都市生活(東京での生活)を描いて、そのなかから日本の新しい状況や現象、衰退や高齢化をあぶり出す。平成最後の芥川賞作品である上田岳弘の『ニムロッド』は、この路線でかなり面白い小説になっていると思います。『コンビニ人間』もここに入るでしょうか。もうひとつのタイプは、地方を舞台に設定して、人間の生々しい実相を浮き彫りにする。以前に受賞した高橋弘希『送り火』や沼田真祐『影裏』はこのタイプですね。
助川 平成最後の芥川賞では、社会学者の古市憲寿が書いた『平成くん、さようなら』が候補作になって話題になりました。主人公はあきらかに作者自身をモデルにしているのに、ヘンなヤツでありながら魅力的に映るようにえがかれていて、すごい自己洞察力だと思いました。文章も、初長編とは信じられないほど巧みです。ただ、「都会の先端風俗を出せば、時代の姿をつかまえられる」というコンセプトで書かれているところが、やや古いかなという印象もうけました。
重里 田中康夫の『なんとなく、クリスタル』は、消費文化が本格的に浸透し始めたころの作品です。田中がいちはやくそれをつかまえたのが興味深かった。しかし、時代の風向きは変わって、キラキラとした消費に、関心を示さない若者が増えてきた。
助川 むしろ私ぐらいの年齢のバブル世代のほうが、キラキラした消費にいまだにあきらめきれず、各種ブランドやメーカーのターゲットにされています(笑)。
そういえば、絲山秋子は私より一歳年上で、バブル世代です。なのに、最新作の『夢も見ずに眠った。』もそうですが、就職氷河期世代の、八〇年代前半ぐらいに生まれた、あまり冴えない人物に焦点をあてる傾向があります。キラキラした消費なんか、最初から夢みることもできない主人公をえがくことで、就職氷河期世代や、さらに若い二十代の読者から共感をあつめているわけです。
『夢も見ずに眠った。』では、三十代後半のカップルがあちこち旅をしてまわります。そのふたりの、行く先ざきの土地とのかかわりかたがすばらしいのです。鋭敏で、土地の本質を一瞬で見抜くような人物を登場させる文学は多いと思いますが、『夢も見ずに眠った。』の主人公たちはちがいます。特別なセンサーがないからこそ、ていねいに旅先の自然や人間とかかわっていく。土地の神さまの声を一瞬で聴きとれないから、一生懸命耳をすませている感じなんです。そういう姿勢のかけがえのなさが、この作品を読むと心にきざまれます。
重里 おっしゃったような特質は、『薄情』でも『ばかもの』でも、絲山作品では一貫しているのではないでしょうか。
助川 古市の平成くんより、絲山の登場人物に若い世代の共感があつまるのが、平成後期の現状なんだとおもうんです。絲山は、「風俗の最先端」をあえて出さないことで、かえって時代のうごきをつかまえている。そういう観点から、私は絲山の『薄情』を自分の「十選」に入れました。
日本近代文学における「地方」
重里 これは助川さんとはよくお話することなのですが、日本の近現代文学において、「東京出身者は大成しない」という鉄則があるように思うのです。この呪縛から逃れるためには「みそぎ」を受けないといけない。「みそぎ」とはしばらく地方で暮らすか、海外に滞在するか、ということです。「地方経験のある東京人と地方出身者が、日本の近現代文学をつくった」というのが私の見つけた法則です。
東京で生まれた作家は、谷崎潤一郎みたいに関西に亡命するもよし。海外留学もよし。地方に長期滞在するもよし。そうすることで、ほんとうに大切な作品を書くのです。
助川 夏目漱石なんかは、ロンドンへの留学が決定的に重要です。これも一種の「地方移住」ですよね。
重里 彼は松山も、熊本も知っていますしね。
どうしてこういうことになるのか、考えてみたことがあるのです。つまり、文学を書く、あるいは真剣にそれを読む、という営み自体が、日本の近代においては「地方に住む」ということを意味するのではないか、という結論にたどりつきました。
「東京が配電盤みたいになって、どんどん文明を全国に流す。それが日本の近代だ」というのは司馬遼太郎が示した印象的な形容です。この百五十年つづいたシステムを距離を置いて考えることが、日本の近現代においては文学にかかわるということだったのではないかと思うわけです。
助川 村上春樹も、関西に生まれ、大学入学と同時に上京しました。彼も関西弁と標準語の二重言語生活者というわけです。
重里 この経験は、彼の小説の懐の深さになっていると思います。
助川 カズオ・イシグロなんて、物ごころがついたあとで習得した英語で書いています。イシグロの文体は、作品ごとにカメレオンのように変わるのですが、彼にとってはことばが完全に「他なるもの」だから、生理や体質と密着した「自分の文体」という感覚がないのでしょう。そのことがイシグロを、類例のない作家にしています。
イシグロの例なんかを見ると、「生得言語の自明性」みたいなものを疑ったり、違和感を覚えたりするところから、ほんとうの文学言語は生まれる気がしてくるのです。東京にだけずっと住んでいると、そういう部分に気づきにくいのだとおもいます。
重里 芥川龍之介も、一度、地方の学校の教師にでもなって、何年か東京の外で生活していれば、あんなふうに自滅しないですんだのではないでしょうか。
助川 芥川には最晩年に、九州大学の英文科に呼ばれる話があったのです。フリーランサーは、人気や売れゆきに一喜一憂することを強いられます。芥川は神経の細い人だったので、大学で教えながら好きなものを書くほうが向いていたかもしれません。
重里 吉本隆明が描き出した図式を思い出します。芥川は「下町の庶民として生まれたことに由来する土着性」(下町の悪ガキとしての自分)と「首都に生きる最先端の秀才文学者」(近代のエリートとしての自分)がうまく調和がとれている間、虚構を書くことができた。両者が統合できずに分裂すると、虚構が破れた。そういう図式です。「下町」も「首都」もおなじ「東京」なので、かえってその二重性を整理しにくかったのでしょうか。地理的な距離というのは意外な恵みをもたらすものです。
助川 九州に行けば、自分のなかの土着性を「首都でもてはやされるエリート」としての顔とどのように関連づければいいか、一瞬にしてわかった可能性がありますよね。
重里 だいたい、「九州に落ちのびて復活する」というのは、日本史のなかでくり返されてきたパターンです。古くは足利尊氏とか。文学者なら石川淳も一時期、旧制の福岡高校でフランス語を教えていました。西鉄ライオンズを率いた三原脩とか。
助川 王貞治も、巨人を追いだされて福岡に行ってから、「天下の名監督」になりました(笑)。
重里 三島由紀夫はどうだったのだろうとか、考えてしまいますね。「地方でしばらく暮らした三島」を想像することは、私には楽しい試みです。
助川 三島は、東京に生まれてそこから離れなかった作家のなかでは、珍しく大成したひとりです。それでもたとえば、二・二六事件にあれだけこだわりながら、あのとき決起した将校の大半が東北出身で、故郷の農村の荒廃が彼らをうごかしていたことにほとんど目を向けていません。社会人経験がとぼしいまま作家になったので、世俗のことについて、体感的にわかっていない部分があったのだとおもいます。
九州あたりで何年か暮らしていれば、東京にいては関わりになるはずもないものと、いろいろ触れあう機会ができたはずです。そうなっていれば、作品にもべつの魅力がくわわったことでしょうし、『金閣寺』以降の人生航路もちがっていたかもしれません。
重里 三島は「大成」したのかどうか。私には、にわかに判断できません。でも、九州で何年か暮らすような経験をしていたら、違う形の「大成」があったのではと考えたくなりますね。
沖縄を引き受ける「負荷」
助川 重里さんもそういえば、毎日新聞の西部本社(九州、山口、沖縄を管轄)にいらっしゃったことがおありです。そのころ、沖縄の文学をずいぶん取材しておられます。
重里 沖縄というのは、「東京から文明が送電されてくる」という図式を激しく揺さぶる土地です。そんななかで大城立裕が長年がんばって、すぐれた作品を書き続けてきました。しかし、そういう環境で表現をし続けると、非常に負荷もかかります。
助川 沖縄の小説家をみると、琉球大学を出て、地元の公務員になったり、教員になったりというような人が多いですよね。沖縄のなかでは、エリートに近い立場にいるというか。
重里 そういう経歴をたどると、沖縄社会全体を背負って書くという立場になりがちなのでしょうか。そのことが負荷にもなっているのかもしれません。
さきほど、平成最後の芥川賞の話が出ましたが、平成最後の直木賞は、真藤順丈の『宝島』という作品で、沖縄の話です。真藤は沖縄の出身者ではないので、外側からこの土地を書いています。そのことが、地元出身の作家の手になる沖縄小説とはまた違う面白さや発見につながっているのではないでしょうか。これからの沖縄文学のあたらしい可能性が、そこに示されているように思います。ただし一方で、『宝島』から感じとれる自在さや軽快さから、沖縄作家が引き受けざるをえない負荷の重さも改めて考えたりもしました。
助川 私は子どものころから『ウルトラセブン』が好きで、生まれて初めて自分から進んで書いた文章は、『ウルトラセブン』のシナリオでした(笑)。
それで、『セブン』の脚本をいちばん中心になって書いていたのは、沖縄出身の金城哲夫です。その金城が『セブン』のために書いたシナリオに、「ノンマルトの使者」という作品があります。「地球には、人間より先にノンマルトという先住民族がいた」というストーリーなので、「金城は、琉球人の思いをノンマルトに仮託して書いた」としばしば評されます。ところが、金城の後輩で、おなじ沖縄出身の脚本家である上原正三は、その説を否定するんです。「金城は七歳で沖縄戦に巻きこまれて、母親が目のまえで負傷している。そういう体験をした人間が、簡単に何かに仮託して沖縄問題を語れるわけがない」というんですね。
重里さんがおっしゃる「沖縄作家にかかる負荷」という言葉から、そんなことを思い出しました。金城は『セブン』のあと、『怪奇大作戦』というテレビシリーズに参加します。このとき、「対馬丸事件を題材に脚本を書け」とプロデューサーにいわれてスランプにおちいり、その影響もあって沖縄に帰りました。上原のいうとおり沖縄問題は、金城にとって簡単に作品化できるものではなかったのでしょう。
沖縄にもどってからも、一九七五年の海洋博にかかわったりしましたし、金城は本土と沖縄の関係を考えるうえで無視できない作家です。重里さんが先ほど名前をあげられた大城立裕も、金城についてのエッセイを何本も書いています。
「近代批判」とカラ兄ブーム
重里 「近代を相対化する場所」といえば、たとえば水俣もそうです。石牟礼道子は、たいへん評価が高い作家ですが、それだけの功績はある人でしょう。『苦界浄土』一冊で、日本の高度経済成長を相対化してしまった。中央が推し進める近代化のゆがみは、つねに地方を通して表れてくることが、あの作品を読むとほんとうによくわかります。
私は戦後の経済成長を肯定したい立場の人間です。飢えて死ぬ子供がほとんどいなくなったことや平均寿命が飛躍的に伸びたことを肯定したいと思っています。「物質的な豊かさ」は素晴らしいことだと考えています。しかし、水俣病ひとつで、そんな肯定にひびが入ります。石牟礼というのはそういう重みのある存在ですね。
助川 原発にしても、問題の本質はそこですよね。
このごろ泉鏡花とか、折口信夫とかに注目が集まるのも、近代によって切りすてられた土着的な要素にフォーカスしているからではないでしょうか。平成も終わりに近づいてきて、「東京から文明が送信されてくる」みたいな構図の限界を、これまで以上に肌で感じている人が増えている気がします。
重里 中沢新一や南方熊楠がよく読まれているのもおなじ文脈でしょう。
助川 もっといえば、「土着をもって近代を撃つ」という構えで創作をつづけた最大の書き手は、ドストエフスキーだとおもいます。
重里 二〇〇〇年代に、『カラマーゾフの兄弟』のブームがありました。亀山郁夫の優れた新訳が出たのがきっかけです。このことは二つの意味で非常に印象的でした。
一つは、こんなにも近代に疑問をもち、飽き飽きしている人が多いのだということ。もう一つは、この対談ですでに申しあげたことですが、日本人はほんとうに文学が好きで、その読み書きの能力の高い国民なのだということ。何せ、『カラマーゾフ』みたいに長くて、読みやすいとはいえない小説が、新鮮な翻訳が出たとはいえ、ベストセラーになるのですから。
ともあれ、この「カラ兄ブーム」が起きたのは平成の前期と後期の境目といってもいい時期でした。平成に入ったころから、近代への違和感がじわじわと広がっていたのでしょう。いや、こういえばいいでしょうか。平成後期の近代への決定的な違和感を先取りするようにして、平成の半ばに「カラ兄ブーム」が起こった。
私は福島第一原発の建屋が吹っ飛んだ映像を見た時に、「ああ、ドストエフスキーはこのことを知っていたのだ」と思いました。私より上の世代の人は、連合赤軍事件が起こった時に、同じことを思ったようですね。オウム真理教による地下鉄サリン事件でも、9・11のアメリカ同時多発テロでも、私はドストエフスキーが予想していたような思いにかられました。いよいよそれが背筋の寒くなるような迫真性をもって感じられたのが原発事故だったのです。きっとドストエフスキーは原発事故のことを知っていました。
助川 これもこの対談ですでに話題にしたことですが、一九九〇年代は「書くことをめぐって書く」ポストモダン小説が盛んだった時期です。インテリだけが面白がるようなその種の小説への反発も、「カラ兄ブーム」を支えていたのではないでしょうか。
ドストエフスキーは、「骨まで浸透してしまった西洋近代」と、「それでも捨てられない土着の伝統」の対立を、豊かな物語性をもって描いた作家です。これに対し、九〇年代に流行ったタイプのポストモダン小説は、西洋近代を極限まで研ぎすませることで、近代を乗りこえようとしていました。
重里 ドストエフスキーの小説にインテリが出てくると、だいたい馬鹿にされる役なのです。嘲笑の対象なのです。本質的なことは何もわかっていないくせに、ドイツやフランスから仕入れた理屈をこねまわす。外国語を交えて薄っぺらな理想を語る。
助川 大事なことをわかっているのは、「白痴」であるムイシュキンだったり、家族のために体を売っているソーニャだったり。
重里 「いちばん苦しんでいる者が、最も豊かな知恵を持っている」というのが、ドストエフスキーの世界ですね。障害者が出てくると、その言葉の重みに注意する必要があります。酔っぱらいや狂信者が、ほんとうのことを言います。
「県庁のない二十五万都市」の解放感
重里 「地方」という問題とからめて、あと二人、語りたい作家がいます。
ひとりは佐藤正午です。この人は長崎県の佐世保市に生まれて、大学は北海道大学に行ったのですが中退しました。それからずっと、佐世保に住んでいます。彼の小説は佐世保を思わせる街を舞台にしていることが多いのですが、そこに描かれた「地方都市の生活実感」に魅力を感じることがあります。仕事の帰りにふらっと立ちよったバーで、偶然、高校の同級生に遭う確率がけっこうあったりする。こういう日常の出来事は、人口が二十万、三十万の規模の都市だから起こることで、東京ではあまりないでしょう。
佐世保の街になぜ解放感があるかといえば、県庁がないからです。このことが、街を自由にしている。佐藤の小説を読んでいると、そんなことまで考えてしまうのですね。
助川 地方だと、「地元でトップの高校を出て、地元の国立大学に行って、県庁に就職する」みたいなのが、いちばんの勝ち組だったりしますよね。県庁の権威はものすごいです。
重里 県庁が江戸時代のお城の跡にある場合もありますね。為政者の威圧感というか、窮屈な印象をあたえます。そういうものが存在しない都市のほうが、風通しがいいのです。私は、下関(山口県)という街をよく知っているのですが、ここも県庁がなくて人口が三十万ぐらい。この街も独特な解放感の漂う街ですね。なんていうか、光がまぶしくて、闇が深いのも、佐世保と下関に共通しているように思います。
人口は少し多いですが、絲山秋子が住んでいる高崎市(群馬県)も、「県庁のない街」ですね。八戸市(青森県)、いわき市(福島県)、倉敷市(岡山県)、唐津市(佐賀県)。人口の多い少ないはありますが、県庁のない街には魅力を感じます。
助川 佐世保は村上龍が生まれたところでもあります。大きな港があって、米軍基地も置かれていますよね。下関も港街で、日清戦争の講話条約はここで締結されました。
重里 軍港と漁港の違いはあると思いますが。
助川 「県庁のあるなし」にプラスして、港があったりして「よそもの」に対し寛容度があることも、街の魅力を左右する気がします。
そういえば、村上春樹は兵庫県の阪神間で成長しました。神戸港に寄港した外国の船員さんが、船のなかで読んだ本を古本屋に売りとばすので、春樹の高校時代はドルが高かったのに、こづかいで英語の本をいくらでも買えたらしいです(ペーパーブックが、古本屋で十円とか二十円だったとか)。それで高校生の春樹は、英語のSFとかミステリーを大量に読んだ。このことは彼が独自の文学を形成するうえで、大きく影響しているとおもいます。
重里 春樹の初期作品では、「ジェイズバー」という名の、中国人が経営するバーが、重要な役割を果たします。そういう店は、どこの都市にでもあるとは限らないでしょうね。また、中国人ということでいえば、「中国行きのスロウ・ボート」というのも、忘れがたい短編ですね。(笑)。
ストレンジャーの視点
重里 もうひとり、土地の問題とかかわらせて論じておきたい作家は、『その街の今は』の柴崎友香です。この作品は大阪を舞台にしているのですが、あの街の魅力を実にうまく表現しているように思いました。
大阪という都市はよく誤解にさらされていると思います。大阪は、さまざまな記憶の層が何重にも折りかさなって今日のような「庶民の街」になっている。一面だけから語ることが難しい街だと思うのです。そこのところが、『その街の今は』では非常にうまくとらえられている。
助川 たしかに、大阪のなかのいろんな場所が出てきて、そのそれぞれの表情が生き生きとつたわってくる小説だとおもいます。
大阪出身の作家は多いとおもうのですが、そのなかで柴崎が、こういう「さまざまな顔をもつ大阪」を描くことができたのはどうしてでしょうか?
重里 柴崎本人に話を聞いたことがあります。そのとき印象的だったのは、自分は大阪生まれの大阪育ちだけれど、親はそうではないという話でした。母が話す言葉は大阪弁ではなかったというのですね。そういうことから、かえって大阪の街をリアルに書けたのではないでしょうか。
助川 名古屋に生まれて、「こんな街、都会じゃない!」とか、地元に不満をいだいて上京したひとのほうが、東京生まれの人間より、都心のかっこいいスポットに詳しかったりします。
重里 でも、そういうタイプは、東京の生活に疲れると、名古屋の共同体的なところが懐かしくなったりするわけです。
助川 「故郷」と「あとから住んだ土地」が両方あると、それぞれの特徴をよく理解できるということですね。「東京とそれ以外のどちらにも住んだことのある作家が、いい小説を書く」というさっきの話ともつながってきます。
重里 私は二十代の前半を下関ですごしました。地元の人間で、気のきいたことをいうヤツは、だいたい東京の大学にいって帰ってきた人間でした。
助川 自分が属している環境に対し「部外者」の意識をもつ、というのは、文学や思想にとって大切なのかもしれません。
重里 ストレンジャーとして生きるのは、つらいこともあるでしょう。でも、そういう経験を通して深まるのが、文学や思想というものなのでしょうね。