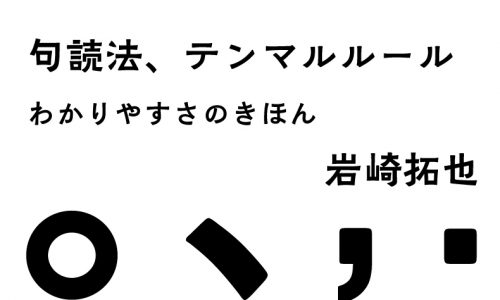朝日新聞の漱石連載
助川幸逸郎 これまでは、平成時代に書かれた文学作品そのものをテーマにしてきました。少し切り口を変えて、「文学をめぐるメディア状況」について話せたらと思います。
重里徹也 朝日新聞が夏目漱石の小説を次々に連載したのも平成の出来事でした。この現象をどう思われますか?
助川 この対談で何度も話題になっているように、作家を新しい段階にステップアップさせるうえで、新聞小説は大きな役割を果たしてきました。ところが、「亡くなった巨匠」の作品で紙面を使っている。あれだけの権威と伝統のある朝日新聞のやることかな、という気がします。
重里 朝刊も夕刊もこれまで通り連載小説を掲載したうえで漱石の連載をしたわけで、連載小説が減ったわけではないですね。でも、漱石を扱うのなら、現代の作家に漱石作品の続編を書かせるとか、漱石の研究者に新しい知見をもとに対談をやってもらうとか、やり方はあるように思います。漱石の小説は各種の文庫で簡単に読めるので、そのまま載せることにどこまで意義があるのでしょう。
助川 ネットで青空文庫にアクセスすれば、漱石の作品は大半が無料で読めます。
重里 漱石は朝日新聞の社員だったので、それを宣伝したい気持ちはわかります。でも、もう少し、やりようがあったように思いました。朝日新聞はいろいろあって自信が揺らいだので、とっておきの遺産に頼ったような印象を受けました。
話が少し飛躍した印象を与えるかもしれませんが、しかし、決して飛躍していないと思うのでいいます。「朝日新聞的なもの」の地位が下がったのを平成年間の特徴に挙げてもいいのではないかということです。この三十年間はいわゆる朝日・岩波的なリベラリズムがさらに力を失う過程でした。
最近、井伏鱒二『黒い雨』を読み返す機会がありました。この小説の中で主人公が「いわゆる正義の戦争よりも不正義の平和の方がいい」と考える場面があります。戦後、とても説得力のある言葉だったのだと思います。そして今も庶民はそう考えているように感じます。私自身の政治的な立場でもあります。戦後日本の経済的繁栄は、この精神のうえに築かれてきたのです。
助川 「戦争放棄」の憲法を掲げながら、実際は米軍の軍事力に守られてきたわけです。
重里 ところが、日本の「リベラル知識人」といわれる人々は、現実を直視せず、「正義の日本」を求め過ぎたのではないでしょうか。そんなきれいごとを代弁するメディアが朝日新聞でした。一方で、国民はそんな理想主義だけでは現実の政治が動かないことを意識的にか無意識にか、よく知っていた。長く続く保守政権を支えてきたのはそんな政治感覚だったのだと思います。
ところが、平成の三十年間を通じて、いよいよきれいごとの化けの皮がはがれてきた。民主党政権の失敗もその理由の一つでしょう。「自称リベラル」の言論人は居場所を失いつつあるような気がします。彼らの指摘の中には現実に即したものもあるのでしょうが。
助川 私は、戦後のリベラル派も、平和の背後に不正義があることはわかっていたと思うんです。わかったうえで「正義」を提唱することで、アメリカからの「人や金をアメリカの軍事行動にもっと供出しろ」というリクエストを、為政者たちがことわりやすい状況をつくっていたのだとおもいます。
私の父親なんて、士官学校出のバリバリの右派ですが、「適度にリベラルが騒いでくれて、アメリカにあんまりお付きあいしないで済むほうが、日本にとってはいいかもしれない」といっていました。
重里 そういう「ごまかしの構造」によって、戦後社会は支えられてきました。でも、その枠組ではいつまでもやっていけないことがはっきりしてきた。
助川 冷戦時代のパワーバランスが、日本の特権的な経済成長を保証してきました。でも、もう東側陣営が崩壊して三十年になります。リベラル派は、それ以降の時代の変化に対応しきれていないのかもしれません。
重里 保守の方が、まだしも柔軟ですね。現実的な選択肢からマシな政策をしようとしている。
助川 平和を維持するためには、どうしてもグレー・ゾーンが必要です。正しさに固執しすぎると、「正しさと正しさの戦い」が生まれ、テロや戦争を阻止できません。
ただ、現在の政権は、じぶんたちの「正義」にかなりこだわっているように見えます。田舎の自民党支持者は、「行きがかり上、いまさら野党は支持できないが、おかしな理想に燃えないで、昔の健全な保守政党にもどってほしい」といっているそうです(笑)
偉大な批評家たちの「幅」
助川 もうひとつ、平成になってからの、文学をとりまく状況として無視できないのは、文芸批評の地位が凋落したことです。
重里 八〇年代ぐらいまでは、文芸批評集がよく出ていた印象がありますね。
助川 今は、「村上春樹論」なら出版にこぎつけられるかもしれませんが、いろんな作家を論じた評論を一冊にまとめて出すのはかなり難しい状況です。ところが、アニメとかゲームを論じた文章は、けっこう本になるし、売れるんです。
重里 なるほど。
助川 どうして仮面ライダーやガンダムを論じた本は読まれるのに、文芸批評集にニーズがないのか。しかも、小林秀雄とか吉本隆明とか、かつての文芸評論家の本は、いまでも読まれていて、人気があるわけでしょう。
重里 江藤淳も含めてください。小林、吉本、江藤の書いたものは、たしかに現在でも価値を失っていないと私も思います。小説を読んだ後で、江藤淳はどのように評していただろうと、よく『全文芸時評』で調べたりします。
なぜ、彼らの評論は面白いのか。この問題を考えていて、今年亡くなった梅原猛のことを思い起こしました。毀誉褒貶の激しい人ですが、私は独特な魅力を感じます。日本列島数千年の歴史をたどりながらものごとを解釈していくとか、インド以来の仏教の流れのなかで日本の思想を語るとか、清濁併せ呑んで政治を考えるとか。ともかく視野が広い。こういう知識人は今、どれだけいるでしょうか。私は中沢新一にも魅力を感じていますが。中沢も毀誉褒貶が激しい人でしょう。
助川 小林秀雄も、「音楽の知識はあやしい」とか批判もされていますが、いろんな方面についてそれなりに興味深いことをいっています。吉本隆明も、社会や文学のことだけでなく、生活上のこまごましたことまでたくさん論じている。「全共闘世代は、ゆりかごから墓場まで、吉本隆明の教えにみちびかれた」と私はよく冗談をいうんです(笑)。
重里 私は生身の吉本を知っていますが、こちらが質問したことに何でもきちんと答えてくださる人でした。「司馬遼太郎をどう思うか」と尋ねるとわざわざ『空海の風景』を読んで論じてくださいました。「関東の笑いと関西の笑いはどのようにちがうのか」と聞くと、吉本新喜劇の島木譲二を例に挙げて解説してくださった。親鸞について何か質問すると話が止まらなくなった(笑)。こちらが興味に任せて何を話題にしても、じっくりと答えてくださりました。
小林や吉本は、森羅万象に関心があったのだとおもいます。梅原にも、それと共通するものがあったのでしょう。そういう幅の広さを文芸評論には求めてしまいます。
助川 小林や吉本と会って話したら、絶対面白そうですよね。そんな文芸評論家が今、どれだけいるか。
重里 昭和ひと桁ぐらいまでに生まれた人と、戦後の知識人では、関心の持ち方の幅が違うような気がします。これは何でしょうか。
助川 旧制高校の教育を受けたかどうかの影響が大きい気がします。
戦前に高等教育を受けられたのは、ほんとうにひとにぎりの人間です。それだけに「自分たちが日本の社会を支える」という使命感があった。それが知的な関心の広さにつながっていたのではないでしょうか。「自分のキャリアアップだけを考えていてもいけない」という感覚があったというか。
重里 それを聞いて、思い出したことがあります。開高健が亡くなったとき、大江健三郎にコメントをもらうために会いにいったのです。大江は「開高健さんは旧制高校的な教養を持っていた」と評しました。
当時それを聞いて、「大江は開高に対し、批評的な含みがあってこういうことをいうのだろうか」と感じました。今、助川さんの話をきいて、大江は正しく開高の一面を言い当てたのかもしれないと考えていました。
もう一つ。戦争を体験しているかどうか、というのは大きい気がします。戦争というものはものごとを根底から考え直させる力を持っているのでしょう。保守とか革新とか、思想的な立ち位置がどうであれ、戦争をくぐり抜けたまともな人間は、何かを考えるときに根底的に降りていく習性が身についたのではないでしょうか。戦後生まれは、そこが弱いような気がします。頭のいい優秀な人は多いと思いますが。
助川 焼け跡を見てしまうと、国家とか体制とかの虚構性を実感するんだと思うんです。それが開高の問題であり、私の十選にもあげた古井由吉が、なぜ毎回、空襲で廃墟になった東京を描くのか、ということともつながっているのではないでしょうか。
重里 そういう徹底したニヒリズムは井上靖を読んでいても、感じることがあります。戦後生まれの知識人も、国家が共同幻想にすぎないということを頭ではわかっているのでしょう。でも、骨の髄でそれをとらえているのかどうか。
助川 戦後しか知らない人間は、いまあるシステムを本気で信じてしまう部分があります。だからどうしても、現行の「ゲームの規則」のなかで効率よく評価をあげることに入れあげることになりがちです。源氏物語の研究者なら、余計な本など読まないで、源氏物語とそれに関連した論文に集中していたほうが、たくさん研究業績も残せて評価も上がる、という方向に傾くわけです。
そうやって効率重視で生きたとしても、とりあえず授業もできるし、専門領域の論文を書くこともできます。でも、そんな具合に生きている人が、小林や吉本や、あるいは開高や古井のように、他人の心を動かす言葉をつづるのはむずかしいでしょう。
国際的評価の陥穽
重里 助川さんが、十選に挙げておられた古井作品は『聖耳』でしたね。平成に入ってからの古井を、どのように評価なさっているのでしょうか?
助川 日本の古典と外国文学の両方に真摯に向き合って、現代日本語散文の可能性の極限を追求していると思います。とても大事な仕事をしている作家であることはまちがいないのですが、古井のやっていることの神髄は、おそらく翻訳ではなかなか伝わりません。
スポーツだったら、国内リーグでチャンピオンになったら海外に出るのは、まちがいなく正しい選択です。けれども、海外で評価されている作家にくらべ、文章語としての日本語に何ができるかを、徹底して追いつめている古井のような書き手の価値は低いのか、私は疑問に思います。
たとえば、安部公房がすばらしい作家であることはまちがいありませんが、大江健三郎より重要な小説家でしょうか?
重里 個人的には、『砂の女』より『洪水はわが魂に及び』により惹かれます。両方とも屈指の名作と呼びたいですが。
助川 大江については、この対談でも以前問題にしましたが、「日本の土着」と「外からやってきた近代」――「四国の山奥」と「欧米の先端文学理論」――を一身に引き受けた大変な作家です。これに対し安部公房は、「近代産業社会における人間疎外」とか「革命思想の挫折」とか、多くの表現者が問題にしていることがらを、もっともわかりやすく絵ときして見せた人、という風に私には映ります。
しかし欧米では、安部のほうが大江より評価は高かったのですね。大江がノーベル賞をとったときも、安部が生きていれば安部が受賞したろうといわれています。
重里 どうして安部は、欧米でそこまで買われているのでしょう。わかりやすいからでしょうか。
助川 安部の小説の多くはSF仕立てです。欧米人はアジアの作家に、自分たちの社会に見当たらないものを見せてくれることを期待します。アジアに固有な土着的風景を見せるか、そうでなかったら未来の光景を見せてくれるか。
重里 エキゾチシズムを求めるということでしょうか。
助川 知り合いのフランス人が面白いことをいっていました。テレビの戦隊モノの格闘場面は、しばしば郊外の住宅造成地で撮影されます。そういう光景は日本ではありふれていますが、フランスでは宅地造成などあまりやらないので、フランス人には「超未来都市」に見えるのだそうです。
大江の小説はふつうのリアリズム小説として読めてしまうものが大半ですから、アジアの作家に欧米人が期待する「未来感覚」みたいなものは、安部の作品ほど与えてくれないということでしょう。
重里 海外の評価だけで作家の値うちは決まらない、というのはわかる気がします。
助川 古井由吉はたぶん、ノーベル文学賞をとったりしないでしょう。だからといって「メジャーリーグで成功できなかった野球選手」みたいに扱うのはまちがいです。そのことをはっきりさせるのは、文芸評論家や文学研究者の使命だとおもいます。
書店員という書評家
重里 文芸評論家の発言力が低下していくのと軌を一にして、書店員の声が注目を集めるようになりました。
助川 一九八〇年代に、雑誌はメーカーとタイアップして広告収入をあつめ、経営を安定させるシステムを確立させました。極端な話、雑誌が一冊も売れなくても、黒字になるケースが出てきたわけです。
そうなると、雑誌に載っている記事の「公正さ」とか「信頼度」はゆらぎます。服飾メーカーから広告を出してもらっているファッション雑誌は、そこのメーカーの製品について、批判的なことは書けません。
こうした「雑誌の宣伝媒体化」は、平成になると、純文学雑誌にも波及しました。純文学雑誌に掲載される批評が、自社が推したい作家や作品のPRと結びつくようになったのです。その作品をどう受けとめたかについて率直に語った記事は、近年の純文学雑誌には載りにくくなっています。
重里 書店員は、自分が売りたい本を推奨します。読者からすると、そっちの方が、雑誌の書評よりあてになるというわけですね。
助川 ゲームとかアニメとかは、コンテンツをつくっているところと資金的に切れた媒体で批評が展開されています。これらのジャンルで評論が比較的元気なのは、そのことも関係しているはずです。
重里 かつては吉本隆明や北川透、今では東浩紀や宇野常寛が自前のメディアを立ちあげていますね。
ただ、書店員の評がチヤホヤされることにも、危うさはありますね。一人一人の書店員が自分の言葉にどれだけ責任を持っているのか。それは問われるでしょうね。新聞記者や編集者も同じことですが。
ところで、一部の書店が近年、批評的機能を持ち始めています。雑誌を出したり、本を出した人のトークショーや朗読会を企画してみたり、個性的な活動をするところが少しずつ増えてきました。書店の数は減っている反面、平成になってから、街の文化センターみたいな性格をもつ本屋さんが出てきているというのは、期待したい動きです。
助川 ネットでいろんなことができるようになったぶん、「リアルでなければやれないこと」もはっきりしてきています。
たとえばクラシック音楽は、いまではいろんな音源をYouTubeで聴くことできます。その影響で、生きている演奏家は、CDを買うよりライブを聴くことを優先するひとが増えました。それで、昔の有名演奏家の音盤は、CDじゃなくてオリジナルのLPやSPの状態のいいやつを探して聴く。
重里 村上春樹も、昔のジャズのLPを中古レコード店で漁るといっていましたね。膨大なコレクションがあるようです。
重み増す文学賞
重里 先ほど、近年の文芸誌から、批判的な記事が少なくなったという話題が出ましたが、そうしたタブーとほとんど関係ないのが新人賞や登竜門的な文学賞の選評です。芥川賞、直木賞の場合は、『文藝春秋』や『オール読物』みたいに一般にも読まれるメディアに、厳しい批評が載せられます。
私は芥川賞や直木賞の意義を重くみる立場です。取材をしても、かなり公正に選考がおこなわれていると感じました。候補作品の事前の発表、受賞作決定後の記者会見、選考委員全員の選評と、その選考経過が包みかくさず公表されるというのは、小説の世界を健全にしているとおもいます。透明性こそ、公平性ですから。
助川 先日、私の市民講座に出てくれている方から、面白い質問をうけました。「将来有望な同業者があらわれたら、はやめにつぶすのが経営の原則です。ということは、小説の賞の選考を、小説家がやるのはマズいのではないでしょうか?」とその人はいうのです。
でも、ビールだったら、エビスをやめてスーパードライを呑むようになる、みたいなことが起こりますが、小説の読者はそうではありません。ものすごく魅力的な若手が芥川賞をとって、多くの読者を得たとしても、その読者は宮本輝や川上弘美も引きつづき読むわけです。
重里 芥川賞・直木賞のシステムはまず、菊池寛がつくり、代々の文藝春秋の人たちが改良を加えていって現在の形になりました。先輩作家が後輩作家を選ぶというシステムも、うまく機能していると思います。頭でっかちにならず、作品の手触りを大事にする批評がされているように思うのです。自分が純粋にいいと思う小説を推す、という基本原則を、選考委員の作家たちはおおむね守っているのではないでしょうか。その結果、文壇の人事システムとして機能する理由にもなっているわけですが。
助川 実作者たちは、いい小説を書いたら報われるシステムを守りたいのだと思います。「話題性だけで売れたとしても、売れたら勝ち」みたいな業界に文学の世界がなったら、自分たちがやりきれないのでしょう。
重里 もちろん、芥川賞や直木賞の選考が常に万人を納得させるものになるとは限りません。それに対しては、芥川賞・直木賞を相対化するような、別の文学賞をつくればいいと思います。それが建設的な考え方でしょう。
たとえば、本屋大賞は、直木賞に対する批判から生まれた賞です。東野圭吾や宮部みゆきが多くの読者に支持される作品を書いているのに、なかなか直木賞をとれない。それに対する書店員の反発が本屋大賞のできた背景にありました。
ところが、東野も宮部もその後、直木賞を受賞し、今では選考委員です。ここに直木賞を運営している人たち(文藝春秋の社員)のしたたかさを見る思いがします。
魅力的な評論とは
助川 書籍の売れゆきは落ちていますが、出版点数そのものは昭和のころより増えています。すべての新刊に目を通すことなど、おそらく誰にも不可能です。「本の水先案内人」が必要とされているのはまちがいありません。
書店員の活動と文学賞の選評だけで、ナビゲーターが足りているのかというと……。
重里 文芸評論の活躍する場所は現在でも大いにあるはずです。
ただし、「肉声」で語らない評論を見抜くだけの知恵を、一般読者の側がすでに持っています。出版社の意図を忖度して、その作品に対する本音を隠しているような書評は、そのうち相手にされなくなるでしょう。また、作品に何かの図式(たとえば、政治的正しさの主張とか)をあてはめるだけの批評も、小説好きの読者はその欺瞞や薄っぺらさに気づくでしょう。
最後に少し差しさわりのあることをいいましょう。個人的な意見です。社会学者とか、精神科医とか、政治学者とか、とても頭はいいのだけれど、「別に文学がなくても生きていける気の利いた人」が、小説について語るケースが目立ちます。そういう人の文章には確かに知的な面白さがあります。けれども一方で、文学が何よりも好きで、文学以外に興味がないという人の、いわば命がけの文芸評論(笑)も読みたいと思います。古今東西の小説をのめり込むように読んで、身体で書いているような評論ですね。
助川 先ほど挙げた古井由吉の例でいえば、古井がどれほど外国文学にも、日本の古典にも真剣に向き合っているか、きちんとわかっている人の解説も必要ですね。
重里 小川国夫の文体に接したら、問答無用にほめる人の評論も私は読みたいです(笑)。恥を忍んで打ち明けますが、私は学生時代の一時期、胃痛に苦しみました。精神に起因するもので、薬はなかなか効かない。その時に小川国夫の作品を、写経するように紙に写していると胃痛が和らいだのです(笑)。
知識もとても大切ですが、文学を切実に求めている人間の言葉でないと、ディープな小説読者の心は動かせないでしょう。外国語ができるからといって、小説が読めるとは限りませんからね。特定の誰かのことを言っているのではないですよ(笑)。
助川 江藤淳なんか、いっぱいまちがったこともいっています。でも、まちがい方も含めてこの人なんだという気にさせられるんです。「文学を通してしか、社会とかかわれない人間なのだな」と思わせる何かが、江藤にはたしかにあります。
重里 彼はまさに、「肉声」で語っていたのです。そういう「本気で小説と向き合う言説」は、これからますます必要とされていくのではないでしょうか。優れた小説家は本気で小説と向き合っています。同じ本気さで小説と向き合う批評家が求められているのだと思います。