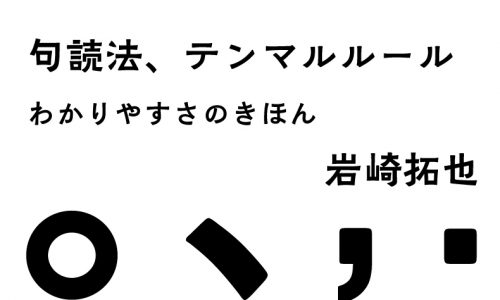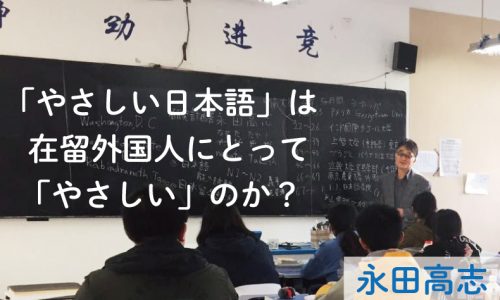お好み焼きのリアリティー
助川 宮本輝の『流転の海』なんかも、お好み焼きの豚玉が出現した、みたいなところから、戦後日本がゆたかになっていく転換点があざやかに見えてくる書きかたになっています。
重里 お好み焼きは豚玉に限ります(笑)。
助川 こういう「手でさわれる細部」みたいな点を通してしか、「戦後史」だとか「地方と中央の格差」みたいな大きな問題は語りにくい時代になっているのかもしれません。
重里 宮本の場合も、戦後の日本人の歴史を書きたい、という意欲はあるのでしょう。ただ、それを作品化するときに、自分の父親という身近な存在を通して描く。
助川 『流転の海』の主人公は、宮本さんのお父さんをモデルにしているわけですが、おもしろい人物ではあるけれど、別に国会議員とか、大企業の社長とかではありませんよね。
重里 市井の人、といえばいいでしょうか。
助川 その、市井の人の生きざまを通して、「戦後史」という大きな問題が語られていく。
バブルのころから平成前期にかけては、平均的な日本人が、「自分ひとりの力でやれる範囲」をかなり大きく見つもっていました。それだけに「特別な資質をもった人間」や「何ものかになろうとする人間」が軸となる物語に共感があつまった。それが平成後期になると、大きな問題を語る場合にも、誰もがアクセスできるような体験をなかだちにするほうが支持されやすくなった。
重里 お好み焼きはだれでも食べますからね。
助川 『流転の海』は八〇年代から書きつがれていますし、黒井千次は六〇年代から活躍している作家です。けれども、宮本や黒井に、平成後期になってもアクチュアリティーがあるのは、「凡事」のなかから大きな問題をつかみ出す力があるからだと思います。
重里 これは実際に本を開くと一目瞭然なのですが、小川国夫にせよ佐伯一麦にせよ、一つ一つの章が短い。断片の積み重ねで作品ができているのです。
これが実にリアリティーを感じさせるというか、生活実感に合っているというか。先ほどもお話したように、物事を上から大づかみにするのではなく、手で触れる出来事や人物の描写があつまって現実が語られていく書き方に合っている。読者に寄りそってくれる作品という印象も受けます。
そうやって作者と歩調をあわせながら、佐伯さんの場合であれば「理想の家族とは何か」とか、「人が老いるとはどういうことか」とか、「大震災をどう生き抜くか」といった問題を、読者はじっくり考えることになる。
小川も、はっきりとは書かないのですが、超越的な光というか、そういうものが存在するかどうかという問いをつねに抱えているのです。ただしそれを遠まわりに、「男女の関係とは何か」「病気とは何か」「働くとはどういうことか」「なぜ、人は賭博をするのか」みたいなことを問いながら、じっくりと追い求めていく。そのジグザグな歩みに強い確かさを感じるのです。
物語は「人の視点」で語られる
助川 佐伯や小川のそういう書きかたというのは、先ほどからお話ししているとおり、平成後期の今だからこそ説得力を感じさせる、というのもたしかにあります。ただ、もうすこし長いスパンで見ると、日本語散文における視点の問題、というのとかかわりがあるような気がするんです。
簡単に言ってしまうと、西洋語や中国語には、三人称客観視点をとるうえでの拠りどころがあります。欧米の場合だと、三人称客観描写は、一神教の神のまなさざしから世界を見ることとつながっているわけです。
それから中国では、一つの王朝が滅びると、それにとって代わったつぎの王朝が、前の王朝の歴史を総括する。このとき、あたらしく支配権をにぎった王朝は、天命をうけて前の王朝と交代したという建前になります。この「前王朝を総括する新王朝の視点」は、三人称客観描写の拠点になりえます。
しかし日本には、キリスト教の神もいなければ、天命によって前王朝の功罪を裁く歴史家も存在しません。
重里 日本には王朝の交代は基本的になかったとされています。
助川 ですから、日本語で三人称客観描写をやろうとすると、かなりの力技が必要になります。純粋な和文を三人称で書こうとしてもなかなか難しくて、どうしても和文は「特定のだれかの視点からの語り」になりがちです。『源氏物語』なんかも、現代語訳で読むと三人称客観描写みたいに見えてしまいますが、あれは作中世界に生きているさまざま女房の語りを集積したものです。
重里 『源氏物語』の語り手はけっこうあちこちで、個人的な感想をもらしますものね。
助川 そういう「語り手の個人的な感想」がのべられた部分を、『源氏物語』研究では草子地と呼んでいます。
それで、「特定のだれかの視点からの語り」を積み重ねていって、ひとつの全体像を形成する。日本の多くの古典が打ち出したそういうやりかたを、「平凡な私」のまなざしから見た断片をいくつも書いていくという、小川の書き方は踏襲しているのではないでしょうか。
和文が宿命的に抱えている問題と向きあっていることが、佐伯や小川の作品の力になっているのではないか。重里さんのお話を聴いて、そんなことを私は考えました。
重里 小川の遺作については、いろいろと考えるところがあります。小川はカトリック信仰を持っているわけです。神の視点から、三人称の客観描写をするという方法も考えられるかもしれません。最後の長編でそれをやらなかったのが、小川の文学的態度ですね。そこには、重要なポイントがあると思います。
『弱い神』には何度か、ドストエフスキーの『悪霊』が象徴的な意味合いをもって出てきます。私は『悪霊』について、学生時代から長年、疑問に思ってきたことがありました。語り手の存在なのです。「アントン・ラヴレンチエヴィチ・G」という人物ですね。この人は一体、何なのか。ドストエフスキーはなぜ、こんな語り手を必要としたのか。
先日、助川さんと話していて、この疑問が私の中では氷解しました。つまり、神が存在するかどうかを問いかける小説なのだから、神の視点から書くのはアンフェアなのですね。地上の人間の視点から書く必要がある。
小川はこれを踏まえたのではないでしょうか。『弱い神』は会話体で進行するのです。いつも誰かの語りで描かれていくのです。歴史も、性愛も、暴力も、信仰も、経済行為も、人間の営みのすべてが「誰かによって語られるもの」として提示されています。そのようにして、必死でまさぐるように、神の存在を問いかけているわけです。
助川 三人称客観描写を採用しない、というところに、「日本人がキリスト教を受け入れられるか」を真剣に問おうという小川の誠実さを感じますね。
重里 小川国夫のキリスト教との向きあい方は、生涯を賭けたもので、ほんとうに地に足がついている感じがします。優れた作家が、最後にたどりついた地点ということで、『弱い神』は平成文学を考える時に決してはずすことができませんでした。
助川 私小説作家が老いると、文体が妙に安定してえらそうになることがあります。それを称して古井由吉が「説教がはまる」みたいな言いかたをしていましたが、『方丈記』や『徒然草』以来の伝統なのかもしれません。この国ではしばしばし、「世俗の秩序を離れた爺さん」のポジションが、「批評家の特等席」になるわけです。
『弱い神』は、いっけん稚拙にも映る語りことばで書かれています。「説教がはまる」文体を意識的に拒否しているんですね。そこに小川国夫の誠実さを感じます。
私小説作家としての大江健三郎
助川 ここまで話題に出ませんでしたが、大江健三郎もじつは、非常にユニークな私小説作家ですよね。
重里 興味深い私小説作家です。
助川 大江は、エッセイでも小説でも書いているように、四国の山奥の出身です。それこそ宮古島のシャーマンたちに通じるような、「その土地の神」みたいなものと結びついて成長してきたひとです。そういう人物が、大学生になって東京に行き、現代フランス文学を勉強した。日本のハイパーローカルとヨーロッパ近代の最先端が、大江の中で出あってしまったんです。そこから来る混乱を誠実に引きうけているところが、大江の魅力だと私は考えます。
そして、大江の抱えこんだ揺らぎを表現するには、鳥瞰的な三人称客観描写ではなく、私小説的な「個人に固有の視点」から語ることがおそらくマストでしょう。
重里 丸谷才一が井上ひさしを追悼する会でおもしろいことを話していました。平野謙が昭和初期の文学を評して「三派鼎立」ということをいっています。つまり、プロレタリア文学、私小説、モダニズム小説(当時だと、新感覚派)の鼎立ですね。
丸谷はこの図式が現代でもいえるというのです。そして、プロレタリア文学をよみがえらせたのが井上ひさし、私小説の進化形が大江健三郎、モダニズムの最先端が村上春樹というわけです。魅力的な見立てだと感じました。
助川 丸谷の批評眼はさすがですよね。大江健三郎は、先ほど申しあげた「地方に生まれた人間が、何ものかになろうとして上京する」という「私小説の基本フォーマット」に完璧にあてはまりますよね。
彼は「四国の山奥に育った前近代人」と、「東大でフランス文学を学んだ現代インテリ」の二股に引きさかれている作家です。
大江が書いたエッセイには、「政治音痴」とか「さっぱりものが見えていない」とかいう評価がつきまといます。けれども彼のエッセイは、二股に引き裂かれたいっぽうだけ、「フランス文学をまなんだ現代人」の側から書かれているんです。
私小説というのは、日本の風土にしっかり根をおろしていて、これを短絡的に批判してもしょうがない。そのことを、平成時代に書かれた私小説は物語っている気がします。