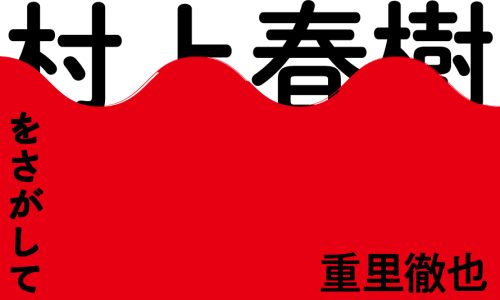歴史と大衆
重里徹也 村上春樹は、昭和期にデビューした作家ですが、チャレンジを続けて、平成期になってもうひとまわり深化し、スケールアップもしました。リアルタイムで全作品を読んできましたが、日本文学のエースの地位を不動にしたと思います。ノーベル文学賞の受賞も、私は素直に期待しています。
助川幸逸郎 『ねじまき鳥クロニクル』は、最初「新潮」に連載されました。この連載が始まったのが一九九二年(平成四年)で、第一部の単行本が刊行されたのが一九九四年(平成六年)です。
昭和のころの村上の作風は、「鼠と僕」が主軸になる四部作にしても、『ノルウェイの森』にしても、個人の心情に焦点をあてる抒情的なものでした。それが『ねじまき鳥』で国家や歴史を問うようになった。
重里 初期作品が好きだったファンのなかには、『ねじまき鳥』で離れていった人もいましたね。『羊をめぐる冒険』や『ノルウェイの森』が好きという村上愛読者は少なくないと思います。そういう人にとって『ねじまき鳥』はとっつきにくいかもしれません。
助川 でも私は、春樹の長編小説から一作選ぶとすれば『ねじまき鳥』だと思います。ノモンハン事件とか、戦前の日本の歴史ともアクセスして、それまでの春樹作品には見られない広がりがここにはあります
重里 ヨーロッパで評価が高い作品と聞いたことがあります。私は春樹の長編では『海辺のカフカ』を最も高く評価したいのですが、『ねじまき鳥』もすぐれた作品だというのには異存ありません。この作品から、近代史を作品に本格的に取り込みました。それは見事に成功していると思います。
助川 『海辺のカフカ』も、春樹にとって大きくターニングポイントになった小説です。
それまでの春樹は、しばしば指摘されるように「英語圏のポップカルチャー」を作品に登場する小道具として上手に使ってきました。音楽はジャズか英国のロックで、登場人物の服のブランドもブルックスブラザーズとかで。
ところが『カフカ』から、ヨーロッパ大陸の文化が大きく取りあげられるようになった。
重里 クラシック音楽が衒いなく使われていますね。
助川 ベートーヴェンとかシューベルトを星野青年が聴いていましたよね。あと、トリフォーの映画を観たりとか。
私が二〇〇〇年(平成十二年)にパリにいったとき、本屋に寄ったら日本人の小説家のなかでいちばん広く書棚を占拠していたのは村上龍でした。九〇年代末に、『トパーズ』が村上龍当人の監督で映画化されて、ヨーロッパでも公開された影響です。
春樹はそのころ、アメリカではすでに知られていましたが、ヨーロッパでの評価はさほどではなかった。『カフカ』は二〇〇二年(平成十四年)に刊行されますが、ここでヨーロッパ文化に焦点を合わせたのは、欧州進出を意識した戦略だと私はとらえています。
それが見事にあたり、二〇〇六年(平成十八年)にパリに行ったときには、日本人作家でいちばんポピュラーなのは春樹になっていました。私は昨年(二〇一八年)もフランスに行きましたが、状況は同じでした。
重里 『カフカ』についていえば、星野青年やナカタさんのような人物は、それまで春樹の小説には出てこなかったように思うのです。
星野青年は、春樹自身やそのまわりにいる人間とはぜんぜんちがって、元自衛隊員のちょっとやんちゃな好青年ですね。気の優しいヤンキーみたいな雰囲気もある。一方、ナカタさんは人生で苦労を重ねてきた「不思議な感じのするおじいさん」です。春樹は「僕」という一人称をやめると同時に、こういった人物たちを小説に登場させました。それが作品の深みになっています。
これは以前にも指摘したことなのですが、オウム真理教による地下鉄サリン事件を題材にしたノンフィクション『アンダーグラウンド』『約束された場所で』を書くにあたり、春樹は多くの人間にインタビューしました。そのことを通して「生身の大衆」に触れたのではないでしょうか。それで、それまで書けなかったような登場人物を小説に出すようになって、春樹は『カフカ』でさらなる飛躍を遂げたと思うんです。唐突で大それた比較ですが、ドストエフスキーのシベリア体験に対応するのが、村上のオウム真理教取材体験だったのではないかと思います。
助川 『アンダーグラウンド』は一九九七年(平成九年)、『約束された場所で』は一九九八年(平成十年)の作品です。
重里 これは吉本隆明から我流で学んだことですが、私は「作家」と「大衆」の関係をついつい考えてしまいます。どのようにして大衆に接しているか、いかにして大衆の心の底の願望を作品の中に繰り込んでいるか、時代の無意識を体現しているか。文学作品の成否を占う指標の一つだと考えます。大衆から遊離すると作品は生気を失ってしまう。さらに進むと作家は自滅する。
吉田修一や高村薫、平野啓一郎がジャンプした背景には、新聞や週刊誌、漫画雑誌に連載小説を書くという経験があるように考えています。随分と図式的ですが、新聞や週刊誌を読む「大衆」を意識する経験を重ねることで、作家がひと皮むけていったといえばいいでしょうか。大衆の目にさらされることによって、鍛えられたといえばいいでしょうか。元・新聞記者がこんなことをいうと、我田引水の批判は免れないでしょうが(笑)。小川国夫や佐伯一麦にさえ、新聞連載小説の経験が彼らにもたらしたものを検証したくなってきます。
村上春樹の場合、『カフカ』の後の『1Q84』も実にチャレンジングな小説で、今でも私はどのように評価したらいいのか、よくわからないでいます。でも、肯定的に批評したい思いはいっぱいです。新興宗教をあれだけ深く書けたのも、オウム関連の取材の成果があるのだと思いますが。
助川 前回申しあげたことですが、一九九五年(平成七年)が、本当の意味で平成が始まった年だと私は思っています。村上春樹は、この時点で起きた変化に見事に適合した。
関西出身ということもありますが、阪神淡路大震災のあとには、「デタッチメントからコミットメントへ」と称して、チャリティー朗読会なんかをやっています。
重里 オウム真理教への対応、阪神大震災の咀嚼。一九九五年をどう受けとめるかにおいて、春樹は日本文学のなかで「ひとり勝ち」でした。その春樹が、平成の前期と後期を画す、東日本大震災と原発事故にどのように対処したかというと……。
助川 あまりうまくいっていると思えませんね。
重里 『1Q84』については、どう評価なさいますか?
助川 率直にいって、『1Q84』を全面的には肯定できないと感じています。知りあいの編集者には、「あれはライトノベルだ」といっている人もいて、あながちそれが「暴論」といえない部分もある。登場人物が類型的というか、リアリティに乏しいというか。
とはいえ、野心作なのはたしかでしょう。「神話」や「寓話」といった「近代小説成立以前の文学」は、「ほんとうにいそうな人物」ではなく、「ある概念を象徴するキャラ」を描くことで「この世の摂理」を啓示する。『1Q84』は、そういう文学の方法をとりいれている感触があります。三島由紀夫の『鏡子の家』や中上健次の『地の果て 至上の時』のような、作者の志を汲んで批評されるべき作品といえるでしょうか。
重里 なるほど。ところが、『騎士団長殺し』となると、そうもいっていられなくなる。
助川 「欠点もあるけれど、野心を買う」という評価をすれば、『1Q84』なら救えるのですが、『騎士団長』はそれもできない感触があります。
エースの失点
重里 『騎士団長殺し』は、野球にたとえるとこういう印象なんです。村上は日本文学のエースですね。もう、二百勝はしているでしょう(笑)。そのエースがローテーションを守って先発した。七回途中まで三点ぐらいで押さえて試合はつくった。そういう感じなんですね。勝ったか負けたかは、味方がどれだけ得点したかで決まります(笑)。ローテーションの中心を担う役割は果たした。でも、初めから飛ばしていった割には、随分とヒットを打たれて、失点しまったなあ、という感じなんです。
助川 そこそこ読める作品ではあるけれど、春樹に期待する水準ではないという感じですよね。
重里 長編小説でいえば、二〇一三年(平成二十五年)に出た『色彩のない多崎つくると、彼の巡礼の年』もとっつきやすい作品でしたが、少し物足りない思いがしました。期待が大き過ぎるのかもしれませんが。エースが失点するのは、少し調子がよくないためか、そうではなくてもっと別の理由なのか。気になるところです。
助川 でも短編のほうは、最近の作品でも読めるのではないですか?
重里 二〇一四年(平成二十六年)に出た『女のいない男たち』も面白かったし、昨年「文學界」に載った短編も、魅力的だったですね。
助川 先に『1Q84』はラノベだ、といった編集者の話をしましたが、その編集者は「春樹の本質は短編作家だ」という説を唱えています。だとすると、加齢によって地金が露わになったということでしょうか。
それと、前回も話題に出た、平成前期と平成後期の話でいうと、平成前期には春樹は適合的だったと思うのです。しかし平成後期と春樹の相性はイマイチだった。だからもともと向いている短編しか書けなくなった。
重里 うーん。
助川 個人のトラウマとか不満の側から、「社会制度=システム」を撃つ。そういう構図が、平成前期にはひろく受け入れられていました。この状況は、「壁」と「卵」を対比させ、「卵」の側に味方するという春樹の思想にマッチします。けれども、個人と個人が連帯して敵に当たるという平成後期のヴィジョンは、「壁」と「卵」の理論ではとらえきれません。
重里 弱いけれどピュアな「個」と、その「個」を押さえつける「壁」。この二項対立にこだわっているかぎり、「個」の連帯は描きにくいということでしょうか。
助川 「壁」と「卵」の対比がそんなに単純なものでないことは、実は春樹自身もわかっているのです。たとえば『アンダーグラウンド』に、サリンの被害にあった直後に、会社に行ってラジオ体操したおじさんが出てきますよね。
あのおじさんは、絶対に悪人ではないんです。当人のつもりとしては、良心や道徳心が人一倍あって、だからこそサリンにやられても会社に行き、体操をしたのでしょう。ただ、強権的なシステムというのは、無理をしてでもそれに従うひとがいるから生きのびるんです。
重里 サリンをまかれてもラジオ体操するような社員は、ブラック企業で働かされても、投げ出さないでがんばりそうですね。
助川 そういう「がんばっていうこと聞く社員」がいなければ、ブラック企業も存続できません。
重里 「卵」は実は「壁」に支えられているということですか。そういう面も確かにありますね。「壁」は卵がつくる。オウム教団を構成していたのも、悩める「卵」たちだったのでしょう。
助川 『女のいない男たち』に収録された『木野』という短編でも、春樹はこの問題をあつかっています。人間はまちがったことをしないだけではダメで、怒るべきときに怒らないと魂をなくしてしまう、というのが『木野』のテーマです。
重里 さっきの図式でいうと、ブラック企業に酷使を強いられたら、怒りの声をあげないと、ブラック企業が生きのびてしまうということですね。
助川 「卵」が「壁」を維持させる可能性に春樹は気づいているのに、どうして長編になると「暴力的な壁」と「脆弱な卵」の対比に固執するのでしょうか。
重里 あくまで自分は良心的な「卵」でいるつもりだ。ところが、結果としては「壁」の暴走に加担してしまう。そして自分がその壁に押しつぶされてしまう。これは、「大衆」にとっては身につまされるストーリーでしょう。
先にも申しあげたように、春樹は『アンダーグラウンド』の取材を通じて、そういう市井の人々の実像に触れた。ところが月日が経つにつれて、社会、大衆とのつながりが希薄化していったという部分があったのかもしれません。
助川 春樹はお坊ちゃん育ちだし、会社で上司に仕えた経験もない。意識的に努力しないと、「外」に向かって開かれて行きにくいタイプなのはたしかです。