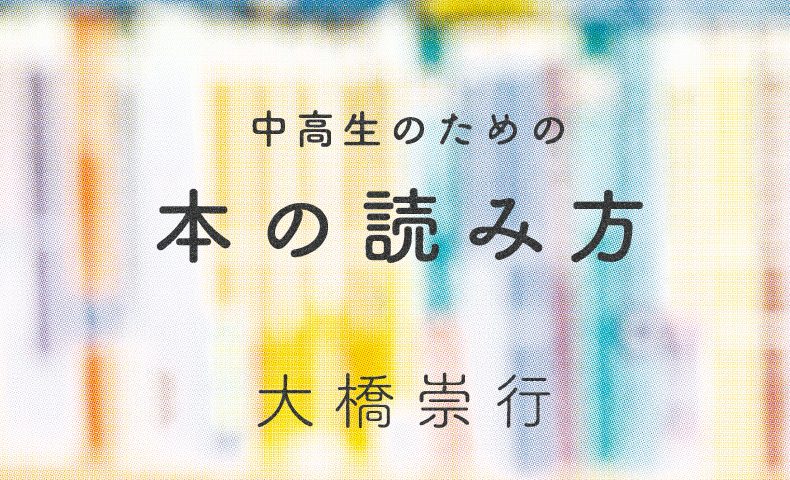バッタ博士の憂鬱
7月13日(金)から、東京の上野にある国立科学博物館で特別展「昆虫」が開催されています。
首都圏にお住まいの方は、Eテレで不定期に放送されている「香川照之の昆虫すごいぜ!」で「カマキリ先生」がすっかり定着した香川照之さんがイメージキャラクターを務められているポスターを見かけることも多いでしょう。
この企画展では、模型や標本の展示のほか、3D画像で昆虫の生態を見たり、昆虫採集のテクニックについても学んだりすることができます。特に土日はとても混んでいるようですが、10月8日(月)まで展示は続いているとのことですので、まずはぜひHPをご覧になってください。(http://www.konchuten.jp)
昆虫に関する本というとまず思い浮かぶのは、『ファーブル昆虫記』(岩波少年文庫、2000年。他多数)。小学生のときに読んだという人も多いと思います。
一方で、日本ほど昆虫好きが多いというのは世界的に見ても珍しいことで、どちらかというと昆虫は、穀物などに被害を与える害虫としてのイメージのほうが強いのだそうです。
そんな中、バッタについて研究し、西アフリカにあるモーリタニアという国に渡った若い研究者が、自身の奮闘ぶりを書いているのが、前野ウルド浩太郎『バッタを倒しにアフリカへ』(光文社新書、2017年)です。
著者自身がバッタの恰好をした表紙カバーは非常にインパクトがあるので、書店や図書館で見かけたのを覚えている人も多いでしょう。非常に話題になっている本ですが、たしかに新書版の本、しかもルポルタージュで、これほどおもしろいものを読んだのは久しぶりのように思います。
前野さんが昆虫学者をめざすきっかけになったのも、『ファーブル昆虫記』だそうです。けれども小学生のとき、科学雑誌でバッタの大群に巻き込まれた女性観光客が緑色の服を食べられてしまったという記事を読み、「バッタに食べられたい」という夢を抱くことに。この時点で、すでに意味がわかりません。
しかも、毎日のようにバッタに触り続けたために、バッタに触ると体がかゆくなるバッタアレルギーに。バッタ研究者としては、どう考えても致命的です。
それでも昆虫学者をめざして努力を続けますが、日本ではバッタ研究の需要がありませんでした。バッタ研究が必要とされるのはバッタの被害に遭っている土地であり、日本ではそういうことが起こらないからです。
バッタ博士になるだけでは収入が得られないので、生活をし、研究を続けられる昆虫学者になるためには、それでも研究を理解してバッタ博士を雇ってくれる大学や研究機関を探して就職し、給料をもらわなくてはいけません。けれども大学や研究機関に就職をするためには、学術論文を発表し続ける必要があります。それなのに、まだ就職できていないので、研究費は入ってこない。だから、研究がなかなか進まない。
こうした状況は、今の博士、研究者と呼ばれる人たちのあいだで、非常によく起こっていることです。
仮説から観察・実験・データ収集へ
そんな前野さんは、昆虫学者になる夢をかなえ、しかもアフリカの人々をバッタ被害から救うという二つの目標を達成するために、1つの賭けに出ました。それが、バッタの大群による被害に遭っているモーリタニアに行くことだったそうです。
けれども、モーリタニアでの研究は、困難の連続。
捕まえたバッタを入れておくはずだった飼育ケージ(檻(おり))は海からの潮風でダメになり、子どもたちにお金をあげてバッタを捕まえようとしたところ大混乱に。バッタ発生のガセネタに振り回され、限られた研究費から現地のドライバーとして雇ったティジャニさんはこっそりと1人で2人分の給料を要求し、研究をするためには出現してもらわないといけない肝心のバッタの大群は一向に現れません。そのうち、とうとう前野さんは無収入に陥ってしまいます。
このように紹介すると、現代の研究者がどれだけ大変かということを書いた本のように思われるかもしれません(実際、そういう側面も少なからずある本なのですが)。けれども、このように追い込まれて必死になっている状況を、前野さんがむしろユーモラスな語り口で書いているところが、この本の魅力の1つになっています。
一方で、この本のいちばんのおもしろさは、やはり、前野さんがモーリタニアの生活を書いていく中でときどき見せる、科学者としてのものの見方にあると思います。
研究とは、単に自分はこういうこと考えているのだという主張を展開するだけのものではありません。
誰も調べたことがない未知の領域や、主観や思い込み、ごく狭い範囲から集められた情報によって語られて信じられていること、異なるデータの取り方で導かれた先行研究に対して、新たな問題を探し、テーマを設定し、新しいデータをとり、そこからより現実に近い事実を導きだしていこうとする営みです。
仮説を作り、その仮説を証明するための実験設備を作り、周囲の状況を考えて実験計画を立て、それにしたがって対象を観察する。実験を繰り返しながら観察によって集めていったデータをまとめて整理し、研究の全体像をデザインして論文としてまとめていく。分野や、文系や理系といった枠組みを問わず、研究はこうした地味な作業を何度も繰り返していくことでできあがっていきます。
たとえば、私自身は日本の明治文学が専門ですが、研究の進め方としては基本的に同じものになります。ただ、仮説を立てた後の「実験」の方法が違っていて、図書館にこもったり本を買ったりして、過去に書かれた文献を無数に調べていくという作業を行うことが、研究データを収集していくことになるわけです。
また、もう一つ前野さんの研究の特徴として、実験室を飛び出し、未知の世界に足を踏み出したことが挙げられます。
手元で得られるデータだけでも論文は書けますが、前野さんは「生物を研究する本来の目的は自然を理解するため」だという原則にしたがおうという発想から、研究成果が得られるかどうかも定かでないアフリカでの野外観察に出ています。このように、どんなに大変な状況にあっても、科学にとっていちばん大切なことは何かという視点を見失わなかったことが、前野さんが持っている世界の見方を、とても魅力的なものにしているのだと思います。
マンボウ博士の研究
昆虫ではなく海の生物になりますが、若手の生物研究者がもう少し具体的な研究の進め方と内容について詳しく書いているのが、澤井悦郎『マンボウのひみつ』(岩波ジュニア新書、2017年)です。
「はじめに」に「Ⅰ~Ⅱ章は専門的な言葉も多いので、もし難しいと感じたら、Ⅲ章から読んでみてください」とあるのですが、Ⅲ章は前野さんの本の後で読むと、重なる部分も多いと思います。今の若手研究者は安定した職を得るまでが本当に大変なので、研究書ではなく一般向けの本を書くとなると、どうしてもこの部分に触れたくなるのでしょう。
むしろ、中高生のみなさんが読みやすいのは、Ⅳ章の「バイオロギングが暴く生態の謎」でしょうか。というのも、光村図書が発行している中学2年生向けの国語教科書『国語2』に佐藤克文さんの「生物が記録する科学 バイオロギングの可能性」が掲載されているので、多くの人が中学生のときにバイオロギングという研究方法に触れているからです。
バイオロギングとは、生き物に機器を取り付け、その生き物がどこで、どのように動いたのかを計測したデータによって生態を明らかにしようとする研究方法です。教科書に載っている「生物が記録する科学」ではペンギンに機器をつけていましたが、同じ方法は生き物であれば人間も含めたあらゆる研究対象で採用することができ、それをマンボウで行う可能性について触れています。
その上で澤井さんが特に述べているのが、マンボウは「鰾(うきぶくろ)がないのにどうやって浮力を得ているのか?」「尾鰭(おびれ)がないのにどうやって泳いでいるのか」「遊泳スピードはどのくらいか?」といったように、目の前にある対象に対して疑問を持つことの大切さです。
たとえばマンボウはゆっくり海を漂うように泳いでいるというイメージがありますが、国立極地研究所の渡辺佑基さんの研究によると、実際の平均遊泳スピードは時速2.2キロ。これは、魚類の中でも比較的早いほうの部類に属します。しかも最高では時速八キロ以上出したマンボウもおり、これは人間の競泳選手と同じくらいの早さになるそうです。
また澤井さんは、マンボウについてインターネット上で広まった「寄生虫を落とすためのジャンプの着水の衝撃で死ぬ」、「ほぼ直線でしか泳げない」ために「岩に激突死」する、「仲間が死亡したショックで死亡」するといった情報がデマであることについて述べています。研究にとっていちばん大切なことは、観察や実験によって得られた事実に基づいて、ものごとを考えることなのです。
世界を観察する小説
これまでご紹介してきた本で触れられているような科学的なものの見方、考え方を、非常によく小説の中に取り込んだ作品があります。8月17日から劇場版のアニメーション映画も公開されている、森見登美彦『ペンギン・ハイウェイ』(角川文庫、文庫版は2012年。ほか)です。
主人公は、毎日たくさんの本を読んで、身の回りにあるたくさんのことを観察し、それをノートに書いて記録している小学四年生の「ぼく」(アオヤマ君)。
ある日、アオヤマ君が住んでいる街に、突然ペンギンが現れるという不思議な現象が起こります。どうやらそのペンギンの発生には、アオヤマ君が憧れている歯科医院の「お姉さん」が持っているペンギンを生み出す不思議な力が関わっているだけでなく、クラスメートの女の子・ハマモトさんが森の奥にある草原のような場所で観察を続けている〈海〉という水のような奇妙な物体とも関係しているようです。
そこでアオヤマ君は、ハマモトさんや、友だちのウチダ君、お姉さんとともに、この街で起きているさまざまな現象について「研究」を進めていきます。そのうち、これらの現象が起こっている原因が明らかになって……。
このように、小学生のアオヤマ君の視点から身の回りの世界で起きているさまざまな現象が観察されていくことで、その中に潜んでいる秘密が明らかになっていくというストーリーです。
お姉さんはなぜペンギンを出すことができるのか。
ペンギンたちと〈海〉にはどういう関係があるのか。
〈海〉とはいったい何なのか。
なぜ、遺伝子によって決められたお姉さんの顔と、お姉さんのおっぱいに「ぼく」は引かれるのか。
アオヤマ君は周囲にあるさまざまなことについて数多くの疑問を持ち、それに対して仮説を立て、観察をしてデータをとり、ノートに記録し、自分自身を取り巻いている世界そのものに触れていくことになります。
もちろん、街にペンギンが現れたり、そのペンギンたちをお姉さんが出したりすることができるという部分は、あくまでファンタジーとして作られています。けれども、子どもの視点で考えてみれば、世界はあまりにも不思議な現象やモノであふれているのです。
1人の小学生がそうした未知の世界に触れてしまう瞬間。このときの驚きや期待感、発見、衝撃、感動は、誰でも子どものときに持っていたものでしょう。この小説では、そうした未知の領域をファンタジーに置き換えることで、子どものときに持っていたはずの未知の世界を、読者が追体験できるように書かれています。
そして、目の前で起こったできごとに疑問を持つこと。それを観察し、仮説を立て、検証すること。そうした、私たちが世界を見るときに必要なものの見方、考え方を、この小説は思い出させてくれます。
最後に、この作品のラストシーンでアオヤマ君は、大人になるまでのあいだに「世界の果て」へと続く「ペンギン・ハイウェイ」をたどっていくことを決意するのですが、1つだけ、アニメーション映画と小説とで、決定的に違っていることがあります。
ネタバレになってしまうので詳しくは触れませんが、なぜそこが違っているのかを考えると、アニメーションやマンガ、実写映画といった図像・映像で作られている作品を見ることと、文章で書かれた小説で読むこととのあいだにある、とても大きな違いが見えてくるように思います。
劇場版『ペンギン・ハイウェイ』は、ここ数年のアニメーション映画の中でも、傑作の1つだと思います。この作品はぜひ、小説と映画版とを合わせて見てください。