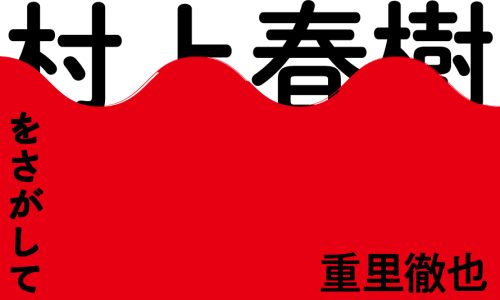地方には仕事がない。文化がない。
それにより、どんどん若者が東京または東京近郊に出てきます。
いまや、それは学生などの若者に限りません。30代や40代でも仕事のために東京に出てきます。ぼく自身も、活動拠点を東京にするべく30で移り住みました。
『東京アレルギー』
これはボクが作った芝居のタイトルです。
ある事情で青森から上京してきた30代半ばの女性、観音林まりあ。彼女は東京でティッシュ配りのアルバイトをしながら暮らしています。ですが、あまり素直じゃない性格も手伝い、まわりからどんどん孤立していき、居場所がなくなっていきます。そして最終的に死に至ります。
だいぶはしょりましたがストーリー自体はこういった、なんの救いもないお話です。ですがこの作品で、それまでもこの先もやってない、特殊な点が一つあります。
それは、方言と標準語の入れ替えです。
舞台は、東京の新宿歌舞伎町と地元青森を行き来するのですが、そこに出てくる人たちは全員津軽弁を話します。津軽の老人が話すような濃厚な津軽弁です。
新宿歌舞伎町のキャバクラ。華やかで刹那的なキャバ嬢や黒服の男たちの、殺伐として享楽的な会話が、津軽弁により温もりとおかしみにあふれてきます。
一方まりあが、青森に暮らしている両親と会話をすると、両親とも標準語で話します。
近所のうわさ話から始まり、主人公まりあの心配をしているような会話が交されます。ですが観客は、歌舞伎町での濃厚な津軽弁に耳が慣れていたので「東京=殺伐、青森(田舎)=温もり」というイメージが覆され、よりどころのなくなった状態で観劇することになります。そしてそのまま、主人公まりあが孤独の道を突き進み死に至るまでの道のりを、ともに体験することになります。
いわば方言によるダークなファンタジーでした。
なぜ、こういうことを思いついたのかというと、ある観劇がキッカケになりました。その演目の場所設定が地方だったのですが、会話は標準語でした。実際、そこの地方には方言があまり残ってなかったのかもしれません。ですが、それを当たり前のようにやっていることと、観客も普通に受け入れていることに違和感を感じてしまいました。そこでボクは「地方なのに標準語が普通に受け入れられるなら、東京なのに方言の演劇をつくってもいいんじゃないか」と考えました。「こういう形の演劇はみたことないぞ。そして方言芝居をやってるボクだからそれができるぞ」と、どんどん妄想が膨らみとまらなくなったので『東京アレルギー』をやることになりました。
各地の方言を聞くと、ユーモラスに感じたりキツく感じたりと、それぞれ受ける印象が違います。なので、この仕掛けを別の方言でやった場合は、また違った味わいになるのではないでしょうか。
方言には標準語では訳せない、そこの土地独特のニュアンス、感情、言い回しなどがあります。これはどこの土地でも大抵一つか二つはあるものです。その言い回しが、との土地独特の風土や人の性質などから生まれたものだと考えると、とても貴重だし、自分の感覚にないものを得られる感覚というのは、わざわざ外国に行かずとも日本のなかで味わえるものだと思います。
実際、東京で活動するようになってから分かったのですが、東京の周り、埼玉、千葉、神奈川から首都圏に通っている人っていうのは結構な数の方がいます。
埼玉生まれの知り合いが以前、埼玉は青森ほど強烈な田舎感がない。取り立てて主張するものがなにもないと、コンプレックスを抱えていました。
そして東京生まれ、東京育ち、東京在住の人は「自分には田舎というものがない。方言がないから、田舎がある人に憧れる」と言っていました。
「それぞれが自分にないものを求めていながらも、集まってくる東京というものはいったい何なんだろう?」と『東京アレルギー』を作っている最中、そんな考えが生まれてきました。自分自身、なぜこんなに東京で演劇をやりたいのかと思いました。
でも青森にいたら『東京アレルギー』のような発想は絶対に生まれてこなかったと思います。人生を通して演劇をやっていくためには、人との出会いや多くの経験が必要だと思い、出てきたのだと思います。
そして方言を使った、また新たな演劇を模索していきたいと思っています。