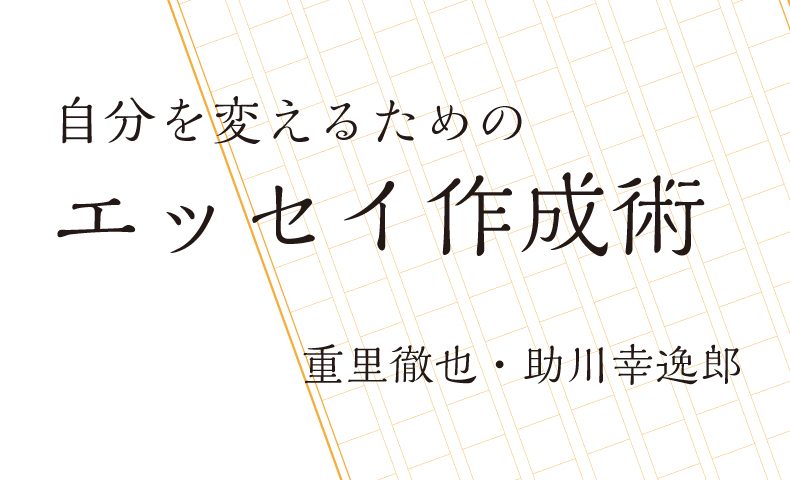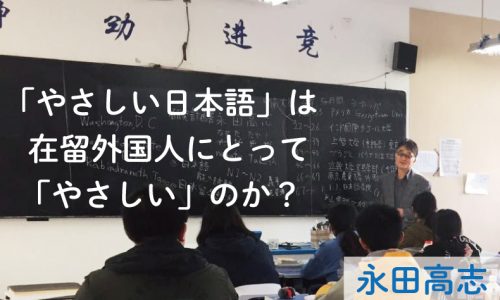今回は、連載を締めくくる対談の後編。前回の重里徹也のおススメ3冊に続き、助川幸逸郎が推薦するエッセイ3冊について、2人が語りあいます。
今回俎上に載るのは、次の3冊です。
五味康祐『音楽巡礼』(新潮文庫)
徳大寺有恒『ダンディー・トーク』(草思社文庫)
スコット・フィッツジェラルド『マイ・ロスト・シティー』(村上春樹訳、中公文庫)
五味康祐『音楽巡礼』
助川幸逸郎 これは、音楽エッセイというより、私小説的な面白さのある作品だと思います。
重里徹也 同感です。このエッセイにはつねに、「死」というものが影を投げかけています。2つの「死」ですね。1つは、太平洋戦争で犠牲になった、おびただしい人々の「死」。もう1つは、五味が加害者になって交通事故で死なせてしまった被害者の「死」。これらの「死」と向き合いながら、五味は音楽を聴いています。
助川 五味の描く剣豪には、芥川賞受賞作の『喪神』の主人公もそうですが、虚無的なタイプが目立ちます。小説でもエッセイでも、五味は「死」や「虚無」と対峙している。
重里 「見てはいけないもの」を見る体験が、五味の根底にあったということでしょうか。
助川 開高健は、ベトナムに行って「人間の力の及ばないものの猛威」を初めて知ったわけではありません。ずっと以前から感知していた「それ」をたしかに見るために、彼はベトナムに行った。
五味も偶然、自動車事故を起こしたわけではなかったと思います。もともと、この人は運転が茶苦茶なので有名だった。「生活者」として壊れていた人ではないでしょうか。だからこそ五味は、「日常性」の底が割れた下を目にしてしまった。
重里 陸軍二等兵として中国大陸で戦った経験も、大きかったのでしょうか。戦死した友人がベートーヴェンを聞いていたエピソードが書かれていますが、印象的でした。
おそらく五味は、戦争が終わってから、ベートーヴェンの音楽の意味を、根底から考えたはずです。戦っていた自分たちを、どうしてベートーヴェンは支えてくれたのか。
ところが、戦後になって生きのびた五味の拠りどころになったのも、やっぱりベートーヴェンだった。戦中の自分と戦後の自分。そのいずれもがベートーヴェンを頼みにしているところが印象的です。
助川 なるほど。その視点は私にはありませんでした。
重里 それから、この『音楽巡礼』は、非常に口語体的なエッセイで、そこが魅力になっています。「ベートーヴェンは、文体でいえば『ねばならぬ』で、バッハは『である』だ」なんていう指摘は、私のようなクラシック音楽に疎い人間にも響いてくる。
助川 作曲家を論じるときの筆致も、小説家的というか、具体的です。
重里 シューベルトの音楽は、梅毒で死ぬ男が書く音楽だと言っていますね。シベリウスにしてもモーツァルトにしても、五味は彼らの人生を通してそれぞれの音楽を論じています。
助川 「死」や「虚無」に直面しても、それに呑みこまれない強さを持つ人を、五味は高く買っています。たとえば、ベートーヴェンとかマーラーとか。これに対しシューベルトは、強さを欠いているから梅毒になったという評価です。
五味には、ベートーヴェン的な強靭さが不足していたように私には映ります。自分が死ぬとか他人をあやめるとかの瀬戸際になると、たいていの人間は、本能的にリミッターがはたらくのです。五味は生存本能みたいなものが壊れていて、そういうかたちでの危機回避ができなかった。それで、交通事故の加害者になってしまった。
重里 五味は、自分にないものを持つ芸術家にひかれていたということでしょうか。
助川 シューマンは、ライン川に投身したときだけまともだったとこの本でいっています。シューマンは死に馬のような弱い存在で、そういう自分を投身することで裁いたのだと。そして、自分とシューマンは同類だとも書いています。強靭さの不足を、五味は自覚していました。
重里 そうした欠落感から、真剣に音楽を求めたのかもしれません。音楽評論というと、吉田秀和がいますが、彼をどう評価しますか?
助川 片山杜秀が、「吉田秀和は〈市民〉の代表だ」といっています。これは名言ではないでしょうか。知識があって文章もうまい。しかし、「日常性」が割れた底みたいなところには、吉田秀和は触れません。
徳大寺有恒『ダンディー・トーク』
重里 これも本当に面白く読みました。自動車を語って、こんなに魅力的な言葉が紡げるのは驚きです。20代から30代にかけて、仕事上の必要で相当な距離を運転していました。でも、自動車というものに大して魅力を感じませんでした。
ところが、この本を読んで、自動車の運転には確かに魅力があり、徳大寺の言葉を借りるなら「官能的」なものなのだな、ということを感じさせてくれました。
助川 とにかく徳大寺は、状況や体験を物語化するのがうまい。比喩もたくみです。
重里 そのせいでしょうか、時代状況や民族性といった大きな話題に触れるときにも、大上段に振りかぶった感じにならず、親しみやすい。難しいカタカナ言葉をあまり使わないところがいいですね(笑)。自動車業界全体にとって、徳大寺のような評論家がいたことは幸運だったと思います。
助川 徳大寺は、なるべく多くのクルマを、自費で購入して乗るようにしていたようです。自分の財布をいためないと、そのクルマの価値を実感できないと考えていたとか。まっとうな姿勢だと私は思います。
重里 映画や本も、レストランやホテルも、同じでしょうね。自腹を切らないと正しく評価できません。興味深いのは、徳大寺はイギリスとイタリアが好きなのですね。
助川 特にドイツの負の部分に関しては、徳大寺は的確にとらえているという印象です。
メルセデスのことを例に出して、ドイツ製品は精密でよくできていると称賛する一方で、ドイツ人には、高性能の戦車をつくることを、戦争に勝つより重んじるみたいなところがあるとも書いています。だから、「道具は人間が使うもの」と割り切ることのできる英国に、ドイツは戦争で勝てなかったのだと。
いま、EUでドイツは独り勝ちのようになっています。しかし内情は、効率重視が行きすぎたせいで切り捨てられる層が生まれ、いいことばかりでもないようです。ドイツの国民性が抱えるそうした問題点を、徳大寺は巧みに描きだしています。
重里 ファッションについても、わかりやすいですね。
助川 モノに対するかかわり方がイギリス的というか、「自分の生活になじんだもの」を大切にして、そういうものについてだけ語っている印象です。
重里 「上から目線」ではなく、低いところから発想している感じがします。
助川 おそらくそれは、エッセイを書くときに忘れてはならない重要ポイントです。よそから聞きかじった知識をひけらかして、ドヤ顔で物事を語っても、他人の心には響きません。イチゴを食べた、甘くておいしい。そういう当たり前の経験を当たり前の言葉で記しても、そこに実感がこもっていれば読者の共感を呼ぶことは可能です。
徳大寺も五味も、あくまで自分の言葉で語っています。権威にはまったく頼っていません。
重里 肉声で語るのは、今回の対談で取りあげている6人全員に共通しています。それにしても、あらゆる分野に、こういう人がいてくれればいいと思います。たとえば建築でも、家電でも、家具でも。この人のようにざっくばらんに語ってくれる存在がどれだけいるでしょうか。
助川 建築の評論家は、自分のかっこよさを競っている人が多いという印象があります。
重里 アカデミズムの専門家が多いからでしょうか。
助川 だいたい「名建築」というのは、設計する側の意図が暴走して使い勝手がわるいというのが相場のようです。今の東京国際フォーラムがある場所に建っていた旧都庁は、丹下健三の設計で、歴史的名建築といわれていました。しかし、そこで働く職員にとっては不便なことだらけ。一刻も早く移転すればいいとみんな願っていたそうです。
重里 建築を語る魅力というのは、その内部に自分の肉体を置くことができるところにあります。もっと身体と感性を使った建築エッセイの書き手はいないものでしょうか。
助川 その点、徳大寺はホテル批評も秀逸です。伊豆の高級ホテルで、7000円のロブスター・カレーがメニューに載っているのを見て、「カレーというのは庶民的な食いモノなんだぞ!」と文句をいったそうです。フェラーリに何千万円も出すひとなのだから、たんなるケチではありません。コスト意識をどこまでも大事にしている。
重里 そういう身体実感というか、生活実感というか、そういうものを大切にして、エッセイを書ける人が、さまざまなジャンルでもっとほしいですね。
スコット・フィッツジェラルド『マイ・ロスト・シティー』(村上春樹訳)
重里 村上春樹の翻訳した小説は、村上の小説ほど面白くない。数十年来の実感です。
助川 実は私も、今日はその点についてお話しようと思っていました。
ある種の小説家は、小説よりもエッセイで「自分の問題」を端的に表現する場合があります。フィツジェラルドの根源的なテーマは「喪失」です。かけがえのない何かが失われる悲しみ。短編でも長編でも、フィッツジェラルドはそれをくり返し書いていく。そして、それがもっとも圧縮されたかたちで書かれているのがこの本です。
重里 「喪失」ですか。
助川 この本には、とても印象的なくだりがあります。人生の絶頂期に、摩天楼の谷間をクルマで走りながら、「もう、これ以上幸せにはなれないんだ」と突然気づいて涙が溢れてきたというんです。フィッツジェラルドのものの感じ方がよくあらわれた一節だと思います。
けれども、春樹はフィッツジェラルドとちがって、「喪失」を哀惜するのみの作家ではありません。もしそれだけの作家だったなら、春樹は『ノルウェイの森』までしか書けなかったでしょう。
重里 デビュー当時、村上は彼の世代の抱える「喪失感」を叙情的に描く作家と見られていました。
助川 初期小説には、「大事なことは終わってしまったムード」が漂っています。それは、学生運動の挫折体験に由来するのだというのが、80年代には定評でした。けれども、『ねじまき鳥クロニクル』あたりから、それだけでは片づけられない小説を書くようになった。よりスケールの大きい、深い作家として認められていったのが、春樹の90年代です。
こういう言いかたをすると語弊があるかもしれませんが、村上春樹の作品世界は、フィッツジェラルドより多様なのです。フィッツジェラルドは、たいへん魅力的な書き手ではあるけれども、春樹にくらべて限られた問題しか扱っていません。
重里 村上は「喪失感」を書く作家から、脱皮したということでしょうか。ずっと疑問に思っているのは、フィッツジェラルドの小説では、ストーリーに偶然が多いことです。
助川 私はあまり気になりませんが。
重里 急な病気とか、困った事故とか、予期せぬアクシデントに頼りすぎていませんか?
助川 たぶん、フィッツジェラルドを好きな読者は、そこは気に留めないのでしょう。プロットに必然性がなくても、ある「喪失」が叙情的に語られていれば納得する。フィッツジェラルドは、学校を出てすぐにスター作家になりました。あまり人生経験が豊富ではないんです。彼は「喪失」を描く達人ですが、逆にいうとそれぐらいしか書くことがない。
重里 それだと、長く一線で書きつづけるのは厳しいでしょうね。
助川 一方、村上春樹は、フィッツジェラルドを読んで「喪失」の描きかたを学ぶ。次にはチャンドラーに取り組んで、「孤独な魂のふれあい」を扱う方法を習得する。そうやって「書きうる対象」を広げていくので、フィッツジェラルドよりもチャンドラーよりも、春樹のほうが引き出しは多くなる。
重里 それで、村上の小説のほうが、彼の訳した小説よりも面白いわけですか。そもそも、齢を重ねることで得るものもあるでしょう。いつまでも青春に執着していないで、大人になったらいい。でも、それでは、フィッツジェラルドのよい読者にはなれませんね。
助川 重里さんの発想は、非常にイギリス的だと思います。
アメリカは、イギリスから逃げてきたひとたちによって建てられました。イギリスとはちがう思想を持つことが、合衆国の国是なのです。イギリス人は、「年相応」を重んじる。だからアメリカ人はそれとは反対に、「青春の理想」を一生大切にする。フィッツジェラルドがアメリカで国民的作家になった背景には、そうした精神風土があると私は見ています。
終わりに
重里 これで、私たちの薦める6冊のエッセイについての対談もおしまいです。連載もゴールにこぎつけました。
助川 今日は、小説や評論の話も相当出ました。エッセイというのは、いろんな文芸ジャンルの要素が入り混じっていて、ものを書く原点みたいな分野です。言葉による表現を志しているひとは、どんどんエッセイに挑戦していってもらいたいと思います。
重里 日本人に向いているジャンルではないでしょうか。『枕草子』や『徒然草』以来、エッセイを抜きに日本文学は語れません。
八百万の神々がいる日本では、いろいろなもののよさをさまざまな角度から眺めていく風土がある。エッセイは、多くの要素を混ぜこみながら、自由に話題を渡り歩く分野です。体験や実感から出発する普段着の発想も含めて、日本人の思考や感性を発揮しやすい表現形式だと思います。
助川 構えず気どらず、どんどんエッセイにトライしていって欲しいですね。