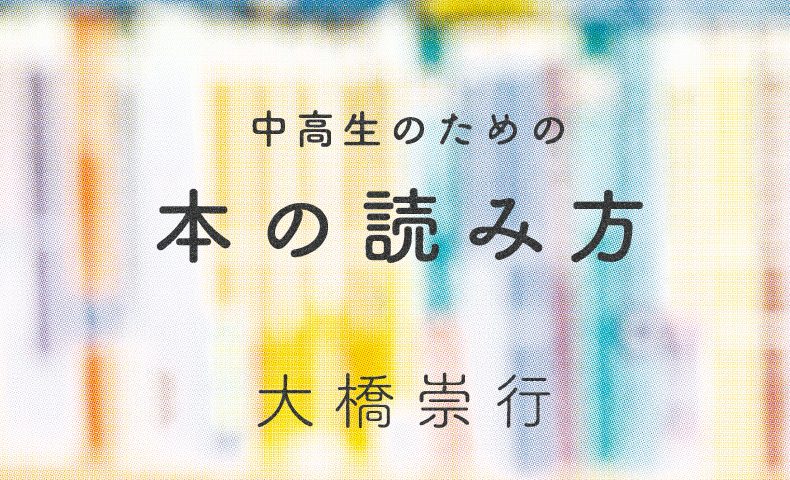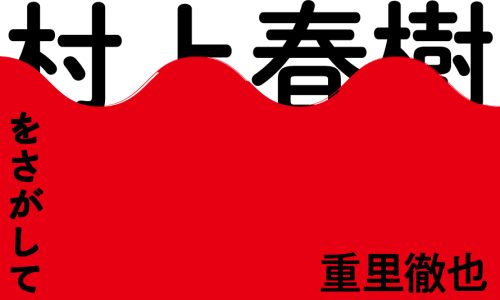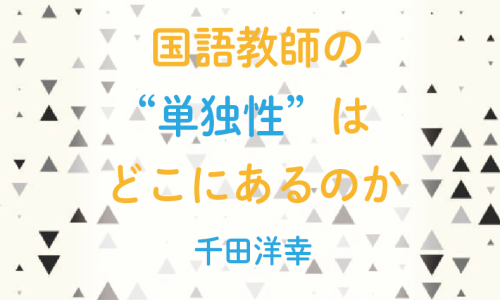人工知能と職業
2015年に日本語版が刊行されたマーティン・フォード著・松本剛史訳『ロボットの脅威 人の仕事がなくなる日』(日本経済新聞社、2015年)は、人工知能(AI)やロボットの進化は新しい技術として人類に幸福をもたらすものでは必ずしもなく、人間が機械につぎつぎと仕事を奪われていくことによって、将来的には経済の成長が見込めなくなっていくという警鐘を鳴らしました。
この直前、2014年秋にオックスフォード大学のマイケル・A・オズボーン博士が発表した論文で、人工知能などの発達によってあと10年で「なくなる仕事」がどういう職業かが論じられたこともあり、この本の内容は衝撃をもって受け止められました。
これらを受けて、井上智洋『人工知能と経済の未来 2030年来雇用崩壊』(文春新書(文藝春秋)、2016年)、小林雅一『AIが人間を殺す日 車、医療、兵器に組みこまれる人工知能』(集英社新書(集英社)、2017年)などをはじめ、特に大人のビジネスマンに向けた本では、人工知能の恐怖を論じるものが数多く出版されています。
たしかに、たとえばお店が自動化されれば、買い物をする私たち客の視点からすれば便利でしょう。一方で、そこで働く人がいらなくなったり、人数が減らされたりすることはあるかもしれません。
こうした話は、中学3年の公民の授業、あるいは高校の倫理や現代社会の授業などで、聞いている人も多いと思います。
けれども、これまでも人類は歴史的に、たとえ何かの仕事がなくなったとしても、新しい仕事をつぎつぎに作り出して発展してきました。
この点はオズボーン博士の論文でも、今後は特に人工知能が苦手な創造性が求められる領域で、人間が活躍していくことが求められる点を強調しています。今ある仕事がなくなるからといって、いたずらに不安をあおる必要はないでしょう。
一方で、たとえば将棋やチェスで人工知能が人間に勝ったという話がニュースなどで流れてくると、人工知能とはどういうふうに作られているのか、今の時点で人工知能はどういうことができる(できない)のかということは、とても気になります。
けれどもこうした内容を説明した本は、これまでに挙げてきたものも含めて非常に難しいものが多く、中高生のみなさんに読んでもらえそうなものが多くないのが現状です。
ゲームの中の人工知能
そんな中でぜひおすすめしたいのが、三宅陽一郎・山本貴光『高校生のための ゲームで考える人工知能』(ちくまプリマー新書(筑摩書房)、2018年)です。
この本は、デジタルゲームで使われている人工知能の研究・開発をされている三宅さんと、プランナーとしてゲームの企画やデザインをされている山本さんのお二人が、ゲームで使われる人工知能がどのような仕組みでできているのかを、楽しみながら学べるように書かれたものです。
主人公の勇者が魔物を倒す西洋ファンタジー風RPG(ロールプレイングゲーム)をプレイするとすれば、ゲームをする主人公を中高生のみなさんが操ることになるので、人工知能を与えられてみなさんと戦うのは魔物となります。
そのためこの本では、勇者を倒そうとする敵の知能をどのように作っていけば良いのかという視点から、人工知能の設計のしかたについて説明されています。
たとえば「第一章 キャラクターに知能を与えよう」では、敵となる「ゴブリン」にどのような「命令」をコンピューター上で行えば、その「ゴブリン」がまるで生きているかのように主人公と戦ってくれるかがまとめられています。
その「命令」が自動的に行われるようにプログラムを組み、「ゴブリン」自身が「意志決定」し、「運動」しているかのように見せる。そのことができれば、私たちにはデジタル画面上に作られた一体の人工生物が、「知能」を持って動いている、もっと言えばまるで生きているように見えてしまうわけです。
このような作業は、具体的には、「ゴブリン」の「視覚」や「聴覚」といった感覚をコンピューター上で数学的に作り出し、ある一定の範囲に主人公がいるときに「ゴブリン」が反応して動作するようにさせ、そのルールにしたがって運動させるというものになるそうです。
こうしたプログラムを組むときに中学から高校にかけて勉強した数学がどのように使われるのか、数学が人工知能を考える上でどうして必要になるのかを、図やイラストを使いながらわかりやすく説明していている点も、この本の特徴として挙げられます。そのため、なぜ数学を勉強するのかわからないという人にも、おすすめしたい1冊です。
さらに「第二章 環境の中で人工知能を動かそう」「第三章 メタAIでよき遊び相手を目指す」では、より高い知能を持って動いているように見せるためにはどうすれば良いのか、よりプレイヤーが楽しめるようにするにはどのようにキャラクターを動かしていけば良いのかと、解説が展開します。
この本の中で特に強調されているのは、人工知能が人間から仕事を奪うと論じられるような「人間から見た人工知能」という視点ではなく、「人工知能から見た人間」という立場にこだわることの重要性です。
こうした視点を持ち、人工知能に私たち人間をどのように見せたいのかを設計し、プログラミングしていくことで、人工知能は人間に恐怖を与える存在ではなく、人間にとって有益になり、人間を楽しませるものとなり得る。この点は、とても重要な指摘だと思います。
人工知能というと、とても難しいものに思えるかもしれません。けれども具体的な説明を読むことで、一見わかりにくいものでも、そのことについて考えることができるようになります。
人工知能のことに限らず、学校の授業でも、ちょっとこの話は難しいな……と思ったら、この本のように具体的に説明が書かれている本を探すと、きっと理解しやすくなると思います。
SFの想像力と人工知能
新しい科学技術は、私たち人間の想像力を大きく刺激します。そのためSF(サイエンス・フィクション)の世界では古くから、そうした想像力を駆使した作品が書かれてきました。
もちろん人工知能についても、例外ではありません。
その中でも黒野伸一『AI(アイ)のある家族計画』(早川書房、2018年)は、中高生のみなさんでも手に取りやすく、面白く読める1冊だと思います。
かつて自動車保険の営業をしていた杉山健司。自動車の自動運転が普及したことによって勤めていた会社は業績不振に陥り、ロボット製造販売会社最大手の「Jロボテクス」社に買い取られてしまいます。その結果、健司はロボットのレンタル販売の営業をすることになり、今までやったこともない仕事はなかなかうまくいきません。
しかも、新たに営業所の所長としてやってきた上司の山下富士夫は、人間のような名前を持ってはいるものの、人工知能を搭載したドローン。もはや人型のアンドロイドですらない上、ハエのようにブンブンと飛びながら社員たちを管理する強引なやり方に不満が出て、健司は自分の部下たちと所長とのあいだを調整することで四苦八苦することになります。
また健司は私生活でも、年老いた両親と二人の子どもの世話で手一杯でした。特に、母親のマサは痴呆の症状が出ており、娘の瑠璃は難しいお年頃。イケメン男性と良い関係になりはじめますが、どうやらその彼もアンドロイドのようです。
そんな健司が家に連れてきたのが、恵という名前の、家族とは縁もゆかりもない女性。彼女は家事を一手に引き受け、マサの面倒も見ることになります。
一方、健司が住んでいる場所の近くにあるマンションでは、一件の殺人事件が起きていました。やがて、その殺人事件の犯人として、恵が疑われていくことに……。
あらすじをご紹介すればすぐにおわかりのように、この小説では、最初に挙げたマーティン・フォードの著作などをもとに、人工知能を持つアンドロイドが人間社会に進出して多くの人間の仕事を奪ってしまった、少し先の未来の世界を想像して描いています。
人工知能がどのように人間から仕事を奪うのか、それによって仕事が奪われたり、人工知能の下で働くことになったりした人間がどうなるのか。
そうしたテーマを、健司の家族との生き方についての問題や、殺人事件をめぐるミステリを織り交ぜながら、読者が楽しめるストーリーの中で扱っているのです。
人工知能の人間らしさ
マンガ作品では、山田胡瓜『AIの遺電子』(少年チャンピオン・コミックス、2015~2017年。続編の『AIの遺電子 RED QUEEN』が2017年~)が、人工知能の問題を扱っています。『週刊少年チャンピオン』の連載なので、知っている人も多いかもしれません。
国民のおよそ1割を、人口の体に人工知能を搭載したヒューマノイドが占めている近未来の世界。そこで、人工知能の専門医である須藤が、さまざまなヒューマノイドを治療していきます。第84話から最終の第87話までの「旅立ち」は4回連続で一つの物語を描いていますが、それ以外の回は16ページの短い読み切りを連ねた、オムニバス形式になっています。
この作品の特徴は、ヒューマノイドを人間と同じように生活し、食事をし、感情を持ち、人権を持っている存在として描いている点にあります。
たとえば「第2話 かけそば」は、落語家として活動しているヒューマノイドが、師匠から「お前の食う蕎麦はまずそうだねぇ……」と言われ、そばを人間と同じように食べる感覚が得られれば美味しそうに食べる演技ができるのではないかと体を改造したところ、「ヤブ」の医者に引っかかって体を壊してしまい、須藤がそれを修復するという物語。
ヒューマノイドが事故に遭って体を入れ替えたところおかしな現象が起こってしまう「第15話 ファントムボディ」や、ラーメン屋の店主をしているヒューマノイドが味を繊細に感じ取れるように舌を修復したところ、ラーメンの味が変わってしまったという「第26話 味音痴」など、この作品ではヒューマノイドが身体を比較的簡単に入れ替えられるために、感情にしたがってそれを行ってしまうことで、逆にさまざまな問題が起きてしまうという物語が多く繰り返されています。
こうした人工知能の感情をめぐる問題は、先ほどご紹介した『AI(アイ)のある家族計画』でも、重要な位置を占めています。このことは、とても興味深い問題を示しているように思います。
三宅陽一郎さん、山本貴光さんの本では、現実の世界にある今の人工知能は、あくまでプログラムの中で周囲の世界を認識し、判断し、運動するという役割を持っていました。そのため人工知能が感情を持つというのは、もちろんあくまでフィクションの世界でのできごとです。
けれども、もしかしたら本当にそういうことがあるかもしれない。そう読者に思わせるところが、SFで発揮される想像力の力だと言うことができるでしょう。
また、もうひとつ指摘するならば、こうした感情は現時点で、フィクションでしか人工知能に与えられません。言い換えれば、そうした感情にこそ人間と人工知能とのあいだの違いがあることが、浮き彫りになっているのです。
SF作品で科学の問題を扱い、人工知能というテーマに焦点を当てることで、むしろ現在を生きる私たち人間が人間らしく生きるとはどういうことなのか、現実の社会で人間がどのように生きているのかが見えてくる。そうした点にこそ、SFにおける想像力の面白さの一つがあると言えるように思います。