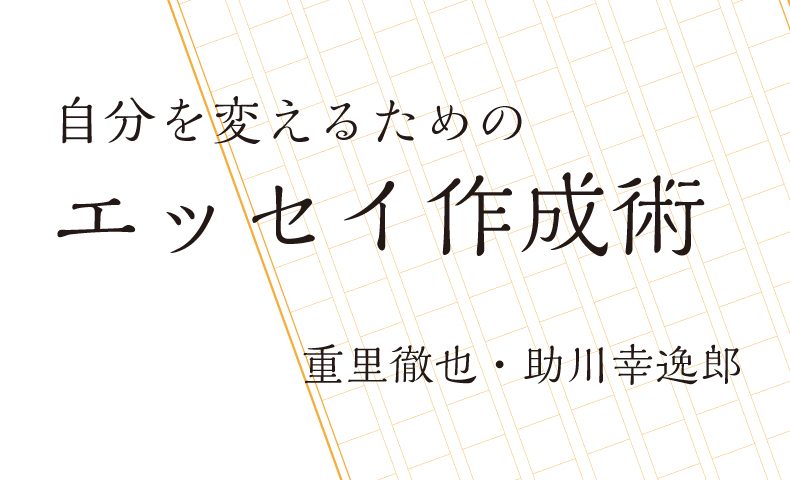前回まで、様々な角度から「魅力的なエッセイの書き方」について考えてきました。
それでは、2人の著者がイメージする「心ひかれるエッセイ」とは、具体的にどのようなものなのか。今回と次回の2回にわたり、対談形式でお話してみようと思います。
今回、論じ合う「重里徹也のおすすめエッセイ ベスト3」は次の通り。
織田作之助『二流文楽論』(岩波文庫『六白金星・可能性の文学』所収)
『吉行淳之介ベスト・エッセイ』(ちくま文庫)
開高健『人とこの世界』(ちくま文庫)
織田作之助『二流文楽論』
重里徹也 私はエッセイの魅力として、読者にある「場所」を提供するということを考えます。世の流れとは違うところで、読者に「考える場所」「思いを深める場所」を提供している点で、3冊は共通しているのではないでしょうか。
助川幸逸郎 どの作からも、イデオロギーにとらわれず、人間を眺める視点を感じます。3作とも、そういう視点に立つからこそ生まれる「つまらないコダワリや欲望を愛おしむ精神」にあふれている。
重里 「二流」というのは織田独特のレトリックです。「一流になろうとしている限り、一流にはなれない。二流でいいのだと思うと一流への道が開けてくる」という逆説があるのですね。3人とも「二流」の意気を骨髄に持っている人たちですね。それは「地べたから物事を考えよう」という志向ともいえるように思います。織田は「地べたに密着した思考法」を「大阪的」と呼びました。この場合の「大阪」は、実在の大阪とはそのまま重なりません。世の中を支配する側の「上から目線」を、相対化する視座が織田の「大阪」です。
助川 この連載の6回目に、重里さんは「エッセイを魅力的にするのは、『一見、関係ない要素』だ」とお書きになっています。
「一見、関係ない要素」を入れると、「いかにもな因果関係」に亀裂が走る。その結果、書き手の心に「その瞬間のリアルな知覚」がよみがえる。読者もその部分を見て、それと似たような体験をしたとき、何を感じていたかをありありと思いおこす。
たとえば、こんな例を考えればどうでしょう。授業中に窓の外を見ていて先生に注意された。この時、「授業が難しくてさっぱりわからなかったからです」というと、先生は反省して許してくれるかもしれない。でも本当は「ケーキを焼く匂い」を無意識に感知して、それが気になっていたのが真相だったりします。
「いかにもな理由」は類型に陥る。逆に「一見、関係のない要素」は、生の実感のようなものをみずみずしくよみがえらせる。織田のいう「一流」とか「二流」は、おそらくそうした問題と関係しています。「通りのいい因果関係」は「マジョリティ=一流」を目指す構えに通じます。そこからは生きた文章は生まれません。「ケーキの匂い」みたいな「いわく言いがたいリアル」に目を向けると、「二流の(=冴えない)自分」に直面させられることもある。けれど、本当に生きたことばというのは、そういうところから立ちあがるものです。
重里 「二流」にこだわると「オンリーワンの自分」を表現することができる。魅力的なエッセイを書く秘訣も、文学にしか出来ないことがどこにあるのかも、「マイナーな自分」に目をやることが出発点です。だから、エッセイを書こうという人は自分の真相をさらけ出すことを怖がらないで、果敢に裸になって欲しい。
さらに、「二流」であることを織田の視点に即していうと、「さんざん、戦争でひどい目に遭ったのに、エスタブリッシュメントはまだ懲りないのか」という感覚とつながっています。体制のそういう部分を批判する拠点として、織田は「大阪」を持ち出す。実在の土地としての大阪を特権化し過ぎるのは危険です。でも、中央のエスタブリッシュメントから身を離す方法として、「大阪」を仮構するのは「あり」ではないか。
助川 将棋の初手というのは、原則的にツーパターンしかない。それなのに坂田三吉は、生涯を賭けた大勝負で、そのツーパターンのどちらでもない手を指して負けました。『二流文楽論』では、坂田のそんな「阿呆さ」が評価されています。
重里 将棋と同様に文楽も、もともと大衆に根を張った芸能でした。生で聞けばわかることですが、文楽の世界は地べたからの声に溢れています。三味線も太夫も、洗練というのとは少し異なる野太い響きです。そこで展開される物語は「情」の世界です。将棋と文楽を通して文学を語ろうとする織田は、「人々の肉声」に身を置いています。
『吉行淳之介ベスト・エッセイ』
助川 吉行淳之介はある意味、織田とは対照的ともいえる文体の持ち主です。
重里 織田は非常に饒舌で、歌い続けるようなリズムがある。文楽のようだとも評されます。
助川 文章には、書き手がつづっているときと、読者が読んでいるときのあいだに、時間的ずれがある。この二つのどちらを重んじるか。織田は、書いてるさなかの生理的リズムを、そのまま文章に乗せていくタイプです。
重里 「いま・ここ」のリアリズムより大切なものはない、という思想の表れでしょうか。
助川 吉行淳之介の文体については、村上春樹が『若い読者のための短編案内』の中で面白い指摘をしています。一般的なイメージとは反対に、吉行はどちらかといえば不器用な作家だというんです。これは、非常に鋭い。
吉行の文章は、不自然なぐらい明快で論理的です。小説家だった父親への反発もあり、吉行は、十代の後半になるまで文学書に近づかなかったそうです。幼少期に文学言語に親しまなかったため、外国語をあやつるような感覚でしか言葉をつづれなかったのかもしれません。
重里 いうまでもないことですが、第三の新人と呼ばれた人々の作品には戦争体験が決定的な影響を及ぼしています。敗戦によって、それまで存在して当然と思っていたものが瓦解した。「もう、何も信じられない」という思いが、第三の新人には共通してありました。助川さんがおっしゃる吉行の文体の特質も、そうしたことと関連している気がします。
助川 吉行の場合、あらゆる対象との間に距離がある。そうやって突き放して見ているからこそ、どんな物事も裁かず、「醒めた肯定の目」で見る。そういう姿勢が、日本語ネイティヴとは思えないような「不自然に明晰な文体」と独特の仕方でマッチしているのが、吉行の魅力です。そういう書き手の根底に、「敗戦を体験したことによるニヒリズム」があるというご指摘は、明察だと思います。
重里 場所の比喩でいうと、吉行は、「隠れ家」を示してくれるのですね。それは女との性愛であったりするわけですが、必ず最後には壊れます。『驟雨』のラストがその典型です。それでも人間はそのような、社会の表からずれた「場所」を求めてしまう。路地裏が人生の支えになる。そのことを実感させてくれます。
助川 吉行は自分のことを「マイナー・ポエット」だといっているんです。主流から外れた、マイナーな「場所」を書いているという自覚は、吉行当人にもあったと思います。
重里 けれどもそうした「場所」は、一部の人間のためだけにあるわけではありません。おそらくは全ての人間が心のどこかで、そうした「場所」を求めている。吉行が取りあげたテーマは、誰もが抱えている普遍的な問題です。
助川 時代の流れのど真ん中を歩いているように見える人々だって、ほとんどが「世界に対する違和感」を抱えています。誰もが共有できるテーマを吉行が描いた、というご意見には賛成です。吉行のいう「マイナー」は、少数者にしかわからないという意味ではなく、パーソナルで微妙な領域に触れていることを指していたのでしょう。
重里 吉行の描く「場所」は、村上春樹の作品に出てくる「阿美寮的なもの」と共通性があります。阿美寮というのは、『ノルウェイの森』に出てくる山の療養施設です。日常世界の中には存立しえない、ユートピア的な共同体を象徴しています。この阿美寮と同じような機能を担う組織や領分が、村上の小説にはくり返し現れる。吉行と村上にそういう共通性があることに、私は非常に興味をひかれるのです。
開高健『人とこの世界』
助川 吉行淳之介が、「弱いように見えて強い人」だったとすると、『人とこの世界』を書いた開高健は、見るからに体力があって、タフな人物です。
重里 それでいて、人間にはどうにもできない「この世を超えたもの」に、初期の頃から取りつかれています。
助川 『パニック』のネズミとか、『流亡記』の匈奴とか。
重里 開高の有名な言葉に「人間は一本の管に過ぎない」というのがあります。食べ物を口から取り入れて、残りカスを排泄する。大きな視野で人間存在を見ると、そういう姿が浮かびあがってくる。「この世を超えたもの」の側から、人間を観察しているわけです。
助川 『人とこの世界』で取りあげられているのは、みんなネズミや匈奴に精通してしまった人間です。大岡昇平、武田泰淳、金子光晴……。その結果彼らは、人間を「一本の管」として見る視点を抱えこんでしまった。人類をサルと並べて観察する今西錦司はその代表でしょうね。私がつくづく感じるのは、「この人たちが生きていたら、福島の原発事故をどう考えたか」ということでした。文明史全体、人類史全体を視野に入れて、考えを述べてくれるように思います。
重里 開高と吉行の価値観には、共通するものがあったでしょう。人間や社会をマクロでとらえるからこそ、ミクロな情の世界を裁かず、ありのまま肯定する。
助川 ただ、吉行と違って、開高は普通の意味で名文家。高度な技巧を繰り出しつつ、滑らかな文章を綴る人です。
重里 それなのに、いざ小説を書くとなると、物語ることを拒絶する。開高は物語を信じない作家です。途中からその傾向が濃厚になります。その根底には徹底したニヒリズムがあるのでしょう。『人とこの世界』では、一人一人の人物を描く中で、開高のそういう認識が凝縮されていく。それぞれの人物のスケッチが、開高の価値観の結晶物になっている。
助川 名文家であることが、ある意味、開高にとって不幸だったように思えます。織田のような、破綻もいとわず書き手のライヴ感覚を伝えるようとする文体。吉行の、対象との距離感を意識させるギクシャクした書き方。それにくらべて、開高のスタイルは端正すぎる。開高が書きたかった「ネズミや匈奴が人間を蹂躙する光景」は、織田や吉行の文体の方がリアルに語れた気がします。
重里 うーん、どうでしょうか。開高はおそらく、自分の文体が手ごたえを感じるものを求めて、さまざまな対象に挑戦し続けたのでしょう。それが人間だと『人とこの世界』になり、土地だと『オーパ』などの紀行文になる。
もう一つ、開高が晩年、司馬遼太郎と親しかったことは見逃せません。
助川 司馬の歴史観は俯瞰的だ、とよくいわれます。開高の「この世を超えたもの」の側から人間を見るところに、自分と似たものを感じて、司馬は共鳴したのでしょうか?
重里 開高には確かに、大きく距離を置いて人間を眺めるような部分があります。そのくせ、地べたを這いずりまわるのです。ベトナム戦争の前線に赴いたりとか、世界中を釣りして回ったりとか。司馬は決してそういう真似はやりません。司馬の目から見た開高は、「俺と同じ光景を見ているはずなのに、やってることは無茶苦茶違う。おもろいヤツやな」といったところだったでしょう。
助川 共有する部分がありながら、それが対照的なカタチで言動に現われる二人であった。だから、司馬と開高はたがいに惹かれあった。
重里 三島由紀夫ふうにいえば、乱暴ないい方ですが、開高が行動者で司馬が認識者。つまり、開高がボケで、司馬がツッコミ。二人はコンビとして理想的な組み合わせだったと私は感じています。あと5年、開高が生きていてくれて、二人の対談本がもっと残されていたらと思うと、残念でなりません。