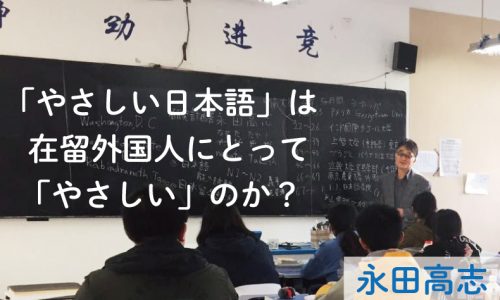言葉で紡ぐ音楽
マンガであれば絵をともなっているので、読者はその絵のとおりに作中人物がピアノを演奏している場面を想い描くことができます。
これに対して小説には、ほとんどの場合、絵がありません。一方で、作中人物の心の中で起きたことや、そのときの状況については、言葉によってマンガよりもずっと具体的に描くことができます。そこから、どのように読者のイメージを作っていくかが問題になるわけです。
それでは、音の出せない小説で音楽を表現しようとするとき、何を、どのように描けば良いのか。この点でとてもおもしろい試みをしているのが、2017年に第156回直木賞と、書店員の投票で選ばれる本屋大賞とをダブル受賞した、恩田陸『蜜蜂と遠雷』(幻冬舎、2016年)です。
単行本を手に取ると分厚さに驚く人もいるかもしれませんが、とてもおもしろいので、それを気にせず一気に読めると思います。
この小説は、3年ごとに開催される「芳ヶ江国際ピアノコンクール」を舞台に、そこで起きたできごととコンクールに出場したピアニストたちを描いています。
養蜂家の子どもで、世界中の音楽家から尊敬を集めていたピアニストのユウジ・フォン=ホフマンが、亡くなる直前にコンクールへと送り込んだ少年・風間塵。母親が亡くなってしまってからピアノが弾けなくなってしまった、かつての天才少女・栄伝亜夜と、その友人の浜崎奏。亜夜の幼なじみで、ずばぬけた演奏技術を持つ優勝候補のマサル・C・レヴィ・アナトール。ピアノから離れてサラリーマン生活をしていたものの、28歳の年齢制限ギリギリの年に出場を決めた高島明石と、彼を取材することになった仁科雅美。そして、コンクールの審査をするピアニストたち。
このように特定の主人公を決めず、さまざまな人物の立場でピアノコンクールに対するそれぞれの思いをたどった、群像劇になっています。
この作品では、ピアニストたちがピアノを演奏している場面を、とても丁寧に、読者がイメージとして把握できるように表現しています。
凄い情報量だ。
やはり亜夜のラフマニノフに圧倒されつつも、明石はそんなことを考えていた。
プロとアマの音の違いは、そこに含まれる情報量の差だ。
一音一音にぎっしりと哲学や世界観のようなものが詰めこまれ、なおかつみずみずしい。それらは固まっているのではなく、常に音の水面下ではマグマのように熱く流動的な想念が鼓舞している。音楽それ自体が有機体のように「生きて」いる。
彼女の演奏を聴いていると、遥かな高みから睥睨する高次の存在を感じてしまう。彼女自身がピアノを媒体とした、巫女か、依代のようなのだ。彼女を使って誰かが「弾いて」いる―そんな気すらしてくる。
コンテストの第二次予選、最後の演奏者である栄伝亜夜のステージは、マサル、明石、奏、塵、審査員の嵯峨三枝子とナサニエル・シルヴァーバーグ、そして亜夜自身というそれぞれの視点から描かれます。
引用は明石の視点。亜夜がラフマニノフ『「音の絵」作品39、アッパーショナート変ホ短調』を弾いているところです。一音一音が奏でる音の質や、そこで表現される演奏者の情念、演奏から聴衆の一人である明石が抱いたイメージと、つぎつぎに音が言葉として置き換わっていきます。
また、他の人物たちは、亜夜の演奏に驚きながらも、それぞれに違った聴き方をしています。マサルは亜夜の演奏が「城」のように確立していくことを感じ、亜夜自身は母親と自分との関係を曲から思い起こす、それを感じとった奏は大地に包まれるような安心感、安堵感を感じる。
このように、群像劇が複数人物の視点から描けることを最大限に利用して、さまざまな角度からピアノの音を言葉で描き出そうとしています。
音を探求する物語
ピアノと向き合う人たちの人生を、ピアニストとは違った立場から描いているのが、宮下奈都『羊と鋼の森』(文春文庫(文藝春秋)、文庫版は2018年)です。この作品は、『蜜蜂と遠雷』の前年に本屋大賞を受賞し、2018年6月には映画版が公開されることになっています。
ストーリーは、ピアノの弦を調整して、音や響きを作り出す調律師を描いたもの。主人公の外村は、高校生だったときに体育館にあるピアノを調律する板鳥の仕事に感動して自身も調律師を目指すようになり、晴れて板鳥が勤めている「江藤楽器」に調律師として入社します。同僚となった柳や秋野、由仁と和音の双子の姉妹をはじめ、客として調律を依頼してくる人たちと触れあうことを通して、外村が調律師として成長していく姿を描いています。
これまでご紹介してきた2つの作品がドラマチックなストーリーで読者をドキドキさせるものでしたが、『羊と鋼の森』は、「僕」(外村)による静かな語り口で、ピアノの音を探求していきます。
まずは、鍵盤の高さの調節からだ。鍵盤の奥につながるクッションが摩耗してしまっている。ここに、ごく薄い紙を敷いて高さを調節する。もともとの鍵盤の可動範囲は十ミリしかない。〇・五ミリでも違っていたら、弾きにくくてたまらないだろう。
高さの次は、深さだ。一つずつ叩いて、ハンマーが弦に当たる位置を確かめる。
そしてやっと調律に入る。前に、柳さんと話したことがあった。目を瞑って音を決めろ、と。あれは比喩ではなかったのだと思う。目を瞑り、耳を澄ませ、音のイメージが湧いてきたのをしっかりつかまえて、チューニングピンをまわす。
物語の終盤、外村は、柳の結婚披露パーティで和音が弾くことになっているピアノの音を調律することになります。
ピアノは、鍵盤を叩くと、その反動で動いたハンマーが中にある弦を叩くことで音を出しますが、その鍵盤のわずかなズレや、ハンマーによる弦の叩き方を調整し、そこから生まれる一つ一つの音を作り出していきます。
タイトルにある「羊」はハンマーを覆う羊毛のフェルト。「鋼」は一本一本の弦。そこから生まれる音を、外村が心の中に持っているイメージとしての「森」と重ねていく。そうして音を探求していく姿が、外村が調律師として成長していく物語そのものとして紡ぎ出されているのです。
表現と物語
これまで、「ピアノにまつわる物語」ということで、3つの人気作を読んできました。
もちろん『蜜蜂と遠雷』の中心は、コンクールをめぐって展開される人間模様や、それぞれの人物がコンクールにかける思い、そしてその中でピアニストとして成長していく物語にあります。また、『四月は君の嘘』では、公生とかをりとの恋愛関係も、とても重要な要素を占めています。
その中で今回は、そうした物語の部分に加えて、3つの作品がピアノの「音」をマンガや小説といった音のないメディアでどうやって描いていたかという、表現の部分にこだわって読んでみました。
このように言葉では本来表現できないはずのものを、どのように表現するのか、それらが物語とどのように関係しているのか、そしてそれらが作品ごとやメディアごとに、どのような工夫によって行われているのか。もちろんこうした表現の仕方にはあるていど様式化されたパターンになっているものもあるのですが、一方で、創り手の側ではさまざまな試みを行っています。
こうした視点から読み返してみると、きっと、作品の違った側面が見えてくるのではないかと思います。